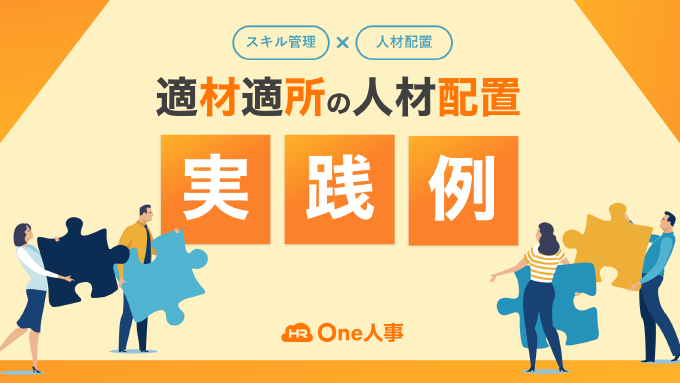部署異動とは|実施理由と必要な手続き、拒否され場合の対応と従業員がストレスなく進める注意点とポイント

部署異動とは、企業内で従業員を現在所属している部署から別の部署へ配置替えをすることです。 キャリアアップの機会になると前向きに考える方もいれば、異動先の業務や人間関係に不安を感じる方もいるでしょう。
本記事では、部署異動の実施理由や必要な手続き、メリット・デメリットを解説します。また、人事担当者向けに従業員が異動を拒否した場合の対応策や、異動のストレスを軽減しながら進めるポイントも紹介しています。
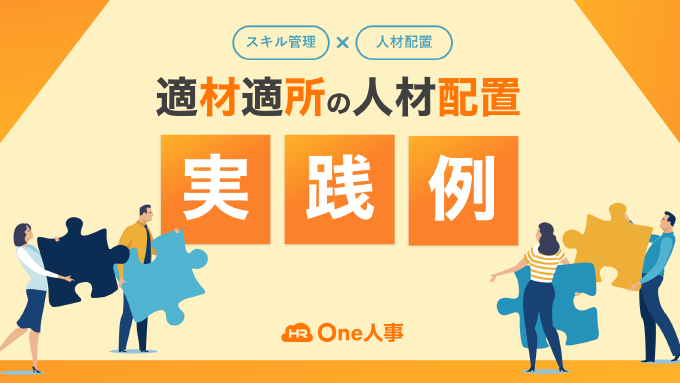
 目次[表示]
目次[表示]
部署異動とは
部署異動とは、会社のなかで働く配置を変えることです。従業員を現在所属している部署から別の部署へ配置転換します。
たとえば、営業部から人事部へ、製造部から総務部へ移るケースです。
部署異動は、それぞれの部署の需要に応じて実施し、目的は従業員のスキルアップや適材適所の配置、成長を促すことです。正しく実行できれば、社内の風通しが改善するとともに、個人の視野が広がって本人のキャリア形成にも役立ちます。
部署異動は人事異動の一種であり、多くの企業では一定のルールが決められています。部署異動を実行する際は、従業員への配慮と明確な目的を持つことが大切です。
部署異動が実施される理由・目的
企業が部署異動を実施する背景には、組織運営や人材活用において戦略的な意図がある場合と必要に迫られた場合があります。
| 企業が部署異動を行う主な目的 | |
|---|---|
| 欠員補充 | 業務の滞りを防ぐため、迅速に人材を配置 |
| 人材育成・スキルアップ | 個人の成長と将来のキャリア形成を支援 |
| 不正防止 | 業務の透明性を確保し、組織の健全性を維持 |
| 新規配置の立ち上げ | 適任者を配置し、新規事業の成功へ |
感覚的で目的のはっきりしない部署異動にならないよう、詳しい目的を確認していきましょう。
欠員を補充するため
退職や休職による欠員補充の手段として、必要に迫られて部署異動が行われることがあります。新規採用には時間とコストがかかるため、即戦力が求められる場合、社内人材を異動させるほうが、業務の滞りを防げるからです。
しかし、欠員補充を目的とした部署移動は時間が限られ、玉突き人事のような結果になりがちです。時間の制約があるなかでも、部署全体のバランスや適材適所の配置を意識する必要があります。
部署異動の前にシミュレーションを実施していますか。
欠員補充のような必要に迫られた異動であっても、最適な配置を検討することが重要です。
タレントマネジメントシステムを活用すれば、従業員の過去の評価やスキル、キャリア志向をもとに事前シミュレーションを行い、最適な異動計画を立てることが可能になります。
タレントマネジメントシステムを活用した具体的なシミュレーション方法は【こちら】
人材育成・スキルアップのため
部署異動は、従業員の成長を意識し、スキルアップに取り組むための戦略的な手段です。従業員は異なる業務に取り組むことで、新たな知識やスキルを習得し、視野を広げられます。
たとえば、営業から経理への異動により、財務やコスト管理への理解が深まり、経営視点を養えるでしょう。将来の管理職候補者を育てたい場合も、複数の部署を経験させることで、組織全体の仕組みがわかりやすくなり、リーダーとしての資質を磨く機会となります。
不正を防止するため
経理や購買部門など現金を扱う業務では、不正の温床となりやすいため、定期的に部署異動を行うことが重要です。
部署異動により、業務の透明性を確保し、組織全体のコンプライアンス強化につながります。新しい担当者が業務プロセスを見直すことで、非効率な業務フローを改善するきっかけとなるでしょう。
新規部署を立ち上げるため
新規事業や新部署の立ち上げには、関連する知識や経験を持つ人材が必要です。既存部署から適切な適任者を選び部署異動させると、事業の立ち上げをスムーズに進められます。
新規プロジェクトは、新しい挑戦に前向きな人材や、幅広い経験を持つ従業員が選ばれることが多く、将来的に企業の成長に貢献できるような環境が整備できます。
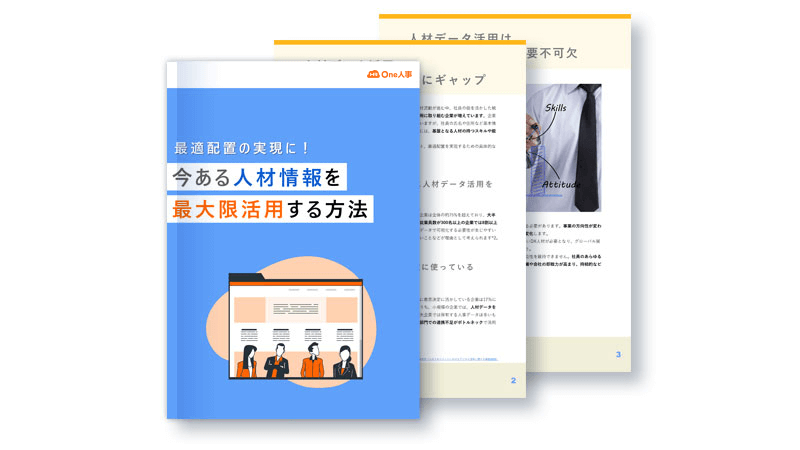
部署異動を実施するメリット
部署異動が企業の成長戦略の一環として行われる場合、組織と従業員の双方にとって多くのメリットがあります。
- 人材配置の最適化
- 従業員のモチベーションアップ
- 業務の属人化解消
- 組織の活性化
部署異動を成長の手段として活かすためにも、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
人材配置を最適化する
部署異動を通じて適材適所の人材配置を実現し、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出せるのはメリットです。本人のスキルや適性に合った業務を担当させることで、パフォーマンスが向上し、組織全体の生産性アップにつながります。
たとえば、営業経験のある従業員をマーケティング部に異動させることで、顧客視点を取り入れた戦略立案に活かせるでしょう。
各従業員のスキルや適性を正確に把握し、最適な配置を実現することが企業の成長にとっても重要です。
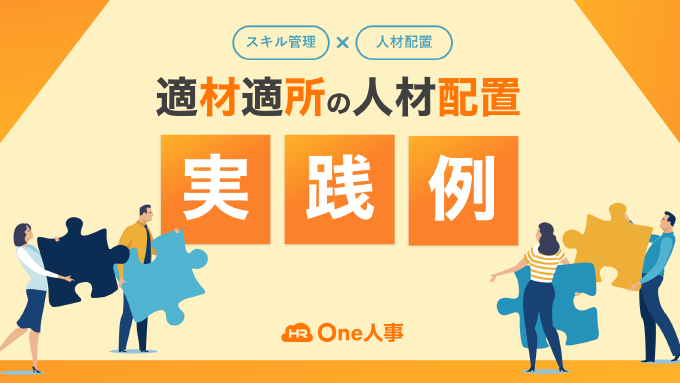
従業員のモチベーション向上につながる
新しい環境での業務は、従業員にとって刺激となり、成長の機会となります。自身の希望や適性に合った部署で働くことで、仕事への意欲・モチベーションが高まり、より積極的に業務に取り組めるようになるでしょう。
また、新たな役割に挑戦できることで、キャリアの幅が広がり、将来の選択肢も増えます。
部署異動を通じて、従業員の会社に対する満足度を高められると、離職率の低下にもつながります。長期的に企業と従業員の双方にとってメリットのある環境を整備できるのは大きなメリットです。
業務の属人化を防止する
特定の業務を特定の従業員のみが担当する状態が続くと、担当者が不在になった際に業務が滞るリスクがあります。部署異動を実施することで、複数の従業員が業務を理解し、遂行できる体制を構築できます。急な休職や退職があっても業務の継続性が保たれるでしょう。
属人化の解消はリスクマネジメントになるため、長期的な視点で考ると、部署異動はメリットのある重要な取り組みといえます。
組織全体が活性化する
部署異動は新しい視点やアイデアを生み出すきっかけとなります。配置内のメンバーが固定されるとマンネリ化し、新しい発想が生まれにくくなるのが課題となりがちです。
新しいメンバーの参加により、業務の進め方が見直されたり、新たな知恵が取り入れられたりすることで、イノベーションの創出につながるでしょう。
また、部門間の交流が活発化し、情報共有がスムーズになるため、組織全体の風通しもよくなります。
部署異動を実施するデメリット・課題
部署異動には戦略的に実行できればメリットがある一方で、適切に実施しないとデメリットや課題が生じます。
人事担当者としてはとくに、異動後のストレス、教育コストの増加、適性の見極め不足が注意したいポイントです。
- 一時的なストレス増加
- 教育・育成コストの発生
- 適性を見極める必要性
注意しないと、どのようなことが起こるのか一つずつ確認していきます。
一時的に従業員がストレスを感じる
新しい業務に慣れるまでの期間、従業員が抱えるストレスに対して異動前後のフォローが大切です。。
異動者は、業務内容の変化に加え、新しい人間関係を構築する必要があるため精神的な負担が増し、一時的に生産性が落ちることが考えられます。
未経験の業務に配属される場合 | 業務をゼロから覚える必要があり、慣れるまでの負担が大きい。 |
| 対人関係が大きく変わる場合 | 慣れ親しんだ同僚と別れ、新しい環境で人間関係を築く必要がある。 |
| 本人の希望と異なる異動の場合 | 自分のキャリアプランに合わない異動だと、モチベーションの低下につながる。 |
業務パフォーマンスに影響を与えないよう、異動先の上司・同僚と連携して、適応しやすい環境づくりが欠かせません。
教育・育成コストが発生する
部署異動した従業員が新しい業務を習得するまでには、相応の時間と労力がかかりデメリットです。即戦力として活躍するまでには時間がかかるため、企業は育成のためのリソースを確保する必要があります。
課題を減らすには、事前の研修やマニュアルの整備、OJTの計画的な実施が有用です。異動前に必要なスキルを身につける機会を設けると、異動後の適応がよりスムーズになるでしょう。
適性を見極める必要がある
適性を考慮しない部署異動は、従業員のモチベーション低下や業務効率の悪化を招きます。とくに本人のキャリア志向と異なる異動が行われると不満が蓄積し、最悪のケースでは離職や休職となるため、慎重に見極めなければなりません。
| 本人の適性に合わない業務に配属される | ストレス増加・パフォーマンス低下 |
| キャリアプランと異なる異動 | 成長機会がないと感じ、転職を検討 |
| 本人の希望と異なる異動の場合 | 部署内の業務が停滞し、周囲の負担が増加 |
デメリットを最小限に抑えるためには、異動の目的を明確にしたうえで、異動前に本人の適性を評価し、全体とのバランスを見て決定することが重要です。
しかし、個人の意向や適性と、全体とのバランスをとるのは非常に難しい問題ですよね。
1つ欠かせないのは、日頃から従業員一人ひとりの適性を評価しておくことです。異動の前にあわてて人物を評価するのは、場当たり的な対応になりおすすめできません。本人のキャリアプランと組織の成長戦略をすり合わせた異動にするには、タレントマネジメントシステムの活用もおすすめです。
→タレントマネジメントが基礎からわかる入門ガイド|無料ダウンロードはこちら

また本人への伝え方も重要なポイントになりますので、以下の記事もあわせてご確認ください。
部署異動の基本の進め方・手順
部署異動を円滑に進めるためには、計画的な手順に沿って実施する必要があります。以下のステップを参考に、スムーズな部署異動を進めましょう。
- 欠員・不足・補強したい部署を調べる
- 異動部署に必要なスキルを明確にする
- 候補者を複数出す
- 内示後に辞令を出す
- 異動後、定期的にフォローアップする
計画的な異動により、場当たり的な人事施策とならないよう、各ステップで対応することを紹介していきます。
1.欠員・不足・補強したい部署を調べる
まず各部署の責任者へのヒアリングを通じて、人材が不足している部署や補強が必要な部署を特定します。
このステップでは、どのようなスキルを持った人材が求められているかを明確にしなければなりません。以下の視点で確認していきます。
- 業務の負担が大きくなっている部署はあるか?
- 新規プロジェクトや事業拡大にともない、補強が必要な部署はどこか?
- 長期間欠員が出ている部署はあるか?
- 特定のスキル・経験を持つ人材が不足している部署はどこか?
現場の従業員からも情報を収集し、組織全体の人材ニーズを正確に把握しましょう。組織の現状を把握することで、異動計画を立案しやすくなります。
2.異動部署に必要なスキルを明確にする
次に、異動先の部署で必要とされる具体的なスキルや経験、知識などを明確にします。具体的な人材要件を設定し、経営戦略との整合性を確認しながら、関係者間での認識を統一させましょう。
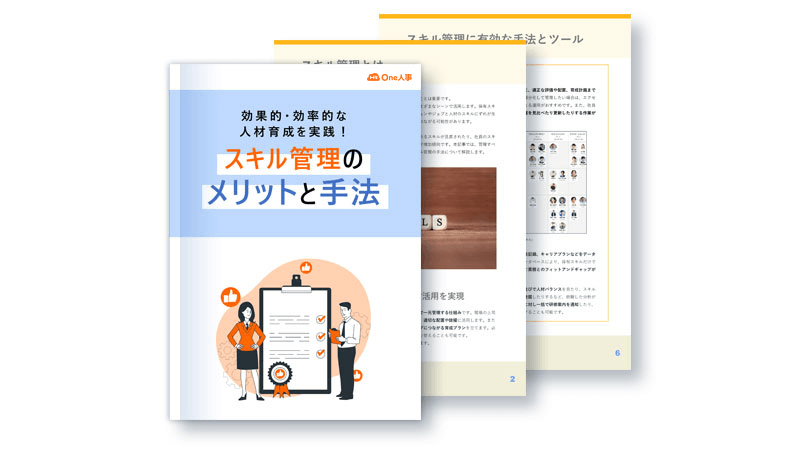
部署異動で考慮される要素
ある調査によると、異動人材の選定において、各社が考慮している要素は以下のとおり多岐にわたります。
- 職務遂行能力(スキル・資格など)
- 能力(適応力・柔軟性など)
- キャリアの状況(過去の職務経験・移動歴)
- 本人の希望
- 適性
- 年齢・勤続年数
- 過去の人事評価(業績評価)
以上のような要素を総合的に評価し、組織の成長戦略や人材育成、受け入れ部署の体制なども考慮する必要があるでしょう。
参考:『人事異動・配置転換に関するアンケート』労政時報 第4075号(2024年4月12日発行)(P.23)
3.候補者を複数出す
従業員のキャリア希望や適性、スキルを考慮しながら、複数の候補者をリストアップします。組織全体のバランスが崩れないよう、異動シミュレーションをしたうえで最適な人材配置を検討します。
4.内示後に辞令を出す
候補者が決定したら、部署異動の内示を行ったあと、少し時間を置いて正式な辞令を発行します。内示から辞令までの期間は、業務の引継ぎや準備に必要な時間を十分に確保することが重要です。
異動における内示のポイントは以下の記事でもご確認いただけます。
内示と辞令は何が違うの? と思ったら以下の記事でご確認ください。
5.異動後、定期的にフォローアップをする
異動後は、新しい業務環境に適応できるよう継続的なフォローアップを実施します。
【フォローアップ施策】
- 定期的な面談
- 研修の提供
- メンター制度
- OJT
その他一般的なフォローアップ施策は以下の記事でご確認ください。
異動直後は不安やストレスを感じやすいため、適切なフォローを行い、従業員のモチベーション維持に努めましょう。
部署異動の注意点・ポイント
部署異動を成功させるためには、慎重な計画と従業員への配慮が欠かせません。適切に進めることで、異動後のパフォーマンス低下やモチベーションの低下、離職リスクを減らせます。
部署異動をスムーズに進めるための注意点・重要なポイントについて解説します。
対象者に理由をていねいに説明する
部署異動を実施する際、対象者に対して異動の目的や期待される役割を明確に伝えることが非常に重要です。理由が納得できないまま異動を命じられると、従業員は不安を感じ、前向きな姿勢で臨めません。
異動の背景として、本人のキャリア成長につながる点や、組織全体にとってのメリットをしっかり説明しましょう。異動後にどのようなサポートが用意されているのかも説明することで、従業員の不安を軽減できます。
事前に異動をシミュレーションする
異動先部署の状況を十分に把握し、異動後の業務がスムーズに回るかどうかをシミュレーションすることもポイントです。
異動対象者のスキルが新しい業務に適しているかだけでなく、異動元部署の業績やチームワークが悪化することも考えられます。
後任の育成状況や、引き継ぎ対象者の有無など、異動元・異動先の双方にどのような影響が出るかも検討しましょう。
適切なシミュレーションを行うことで、異動後のパフォーマンス低下やミスマッチを未然に防げます。
異動シミュレーションの方法は【こちら】
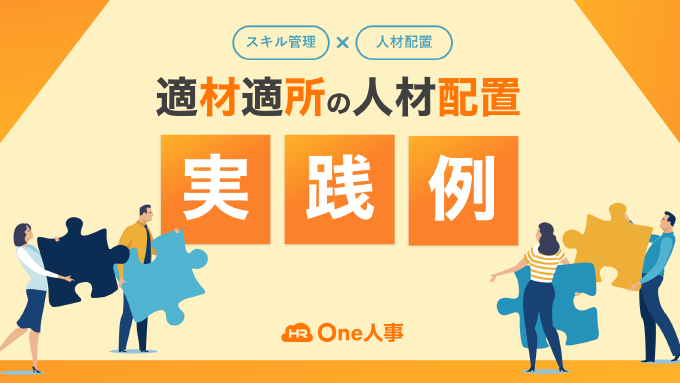
部署異動に必要な手続き
部署異動が決定したら、従業員と人事労務担当者のそれぞれがやるべきことがあります。引継ぎや新しい環境への適応を円滑にするため、計画的に準備しましょう。
従業員
異動が決定したら、まず担当業務の棚卸しを行い、後任者にスムーズに引き継ぐよう準備します。業務内容や作業手順、注意点をまとめた引継ぎ資料を作成し、後任者が円滑に業務を開始できるようサポートしましょう。日常業務の進め方や、取引先とのやり取りのポイントなど、経験者だからこそ知っているノウハウも記載すると、より実践的な資料になります。
取引先や社内関係者への挨拶も重要な手続きです。可能であれば、直接訪問して異動の報告を行うのが望ましいですが、距離や時間の制約がある場合は、メールや電話での対応でも構いません。
最終日までには、使用していたデスクやファイルの整理を済ませ、後任者が気持ちよく業務を始められる環境を整えます。また、部署内の上司や同僚へのあいさつも忘れずに行い、異動後も良好な関係を維持できるよう努めましょう。
人事労務担当者
人事労務担当者は、部署異動に関する社内手続きや各種書類の準備を担当します。
とくに転勤をともなう異動では、社会保険や雇用保険の変更、住所変更にともなう住民税の手続きなどが発生します。
異動初日から問題なく業務を開始できるよう、職場環境の整備も欠かせません。具体的には、デスクや備品の手配、業務に必要なソフトウェアのインストール、社内システムのアクセス権限設定、名刺発注の設定などです。
異動後は定期的な面談を実施し、業務の習熟度や心理的な不安がないかを確認します。必要に応じて研修を実施したり、上司と連携をはかったり、異動者が新しい環境に早く適応できるようサポートしましょう。
部署異動を拒否されたらどうする? 解雇はできる?
人事異動の拒否に対しては、法的観点と人道的な配慮の両面から、適切な対応が求められます。部署異動は会社の人事権に基づく業務命令であり、原則として従業員には拒否する権利はありません。ただし、ある調査によると約7割の企業が育児・介護や健康上の理由などによる拒否を認めているのが実態です。
人事労務担当者としては、まず拒否の理由を確認し、育児・介護などのやむを得ない事情がある場合は柔軟な対応を検討します。
一方、正当な理由なく拒否が続く場合は、就業規則に基づく業務命令違反として懲戒処分の対象となる可能性を説明する必要があります。ただし、合理的な理由なく給与を減額したり即時解雇したりするなどの極端な処分は避け、段階的な対応を心がけることが重要です。
参考:『人事異動・配置転換に関するアンケート』労政時報 第4075号(2024年4月12日発行)(P.29)
そもそも、やむを得ない事情がある従業員に対して部署異動を命令しないのが基本です。正当な理由もなく部署異動を拒否する従業員を発生させないことにも目を向けましょう。
普段から会社の方針や期待などを伝える機会として、1on1ミーティングを定期的に実施し、従業員一人ひとりの状況を把握する「仕組み」を整えることも対策の一つです。
部署異動を従業員がストレスなく進めるには?
部署異動は、新しい業務や人間関係の変化に直面するため、従業員にとって大きなストレス要因となります。スムーズな適応を促すためには、サポート体制を整えることが重要です。
異動後、従業員は業務内容の変更、新しい職場のルールへの適応、キャリアプランの見直しを迫られます。人事労務担当者としては、まず本人の心理状態を把握することから始めましょう。
そして所属上司との定期的な1on1ミーティングを実施し、業務の習熟度や人間関係の状況を確認するとともに、悩みや不安を気軽に相談できる環境を整えます。チーム全体で支える体制を構築することも大切です。
とくに異動直後の数か月間は手厚いフォローが求められます。必要に応じて研修の機会提供や業務量の調整を行い、無理なく新しい環境に適応できるよう配慮しましょう。細やかなサポートを継続することで、ストレスを軽減し、異動後のパフォーマンス向上につなげられます。
従業員のスキルを把握して適切な部署異動を(まとめ)
部署異動は、組織と従業員の双方にとって戦略的な人事施策です。大切なのは、従業員一人ひとりの適性を見極め、異動によって本人の成長と組織の活性化の両方を実現することです。
そのためには、まず異動先の部署で必要とされる人材要件を明確にし、候補者とのマッチングを慎重に検討する必要があります。また、異動による影響を事前にシミュレーションし、引継ぎやチームのバランスを考慮した対策を立てておくことでスムーズな異動につながります。
部署異動が成功すると、従業員のキャリア形成を支援でき、組織全体の成長にもつながります。異動シミュレーションをはじめ準備と実施後のフォローアップを通じて、双方が納得できる適材適所の配置を実現しましょう。
適材適所の人材配置を実現|One人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、従業員一人ひとりのスキルや経験をクラウド上で集約して可視化し、適材適所の人材配置に役立てるタレントマネジメントシステムです。
従業員の顔とスキルなどを見ながら、画面上の組織図で直感的に部署異動をシミュレーションできます。
One人事[タレントマネジメント]は、自社の課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけます。多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、無料トライアルも提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。