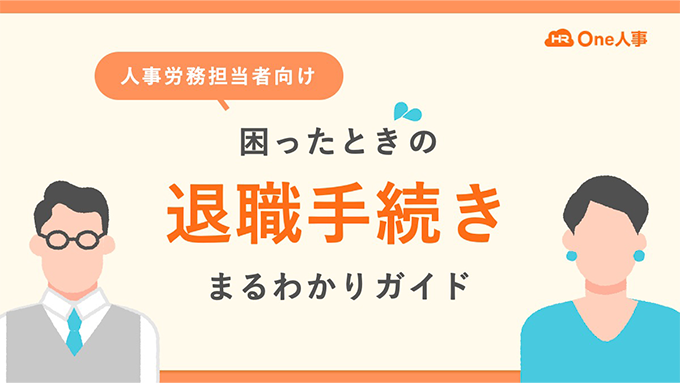離職票はアルバイト・パートでも交付するのか|必要・不要な場合をそれぞれ解説

雇用保険の失業手当の受給手続きの際、ハローワークに提出を求められる「離職票」。正社員が退職する際、離職票を求められるケースは少なくありませんが、アルバイトやパートに対しても発行する必要はあるのでしょうか。
本記事では、アルバイトやパートが退職する際の手続きについてご紹介します。パートタイム労働者が退職する際の手続きについてお悩みの担当者の方はぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
離職票とはどのような書類?
まずは、離職票の概要や構成書類について解説します。
離職票は失業給付の受給手続きのために必要
離職票は、当該者が失業状態であることを公的に証明するものです。正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険の失業手当の受給申請を行う際に提出を求められます。
離職票は「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚で構成されており、それぞれ以下のような役割があります。
雇用保険被保険者離職票-1
ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出後、確認が完了することで発行される書類です。退職者が離職票を希望した場合は「雇用保険被保険者離職票-1」が「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」としての役割を持ちます。
| 雇用保険被保険者離職票-1の記載内容 |
|---|
| ・離職者の氏名・性別・生年月日 ・被保険者番号 ・振込先口座情報 ・マイナンバー など |
雇用保険被保険者離職票-2
離職票の発行申請では「雇用保険被保険者資格喪失届」とともに「離職証明書」を提出しなければなりません。離職証明書は複写式の3枚ひとつづりで構成されており、そのうちの1枚が「雇用保険被保険者離職票-2」として使用されます。
離職証明書に記載される項目は、おおむね以下のとおりです。
| 雇用保険被保険者離職票-2の記載内容 |
|---|
| ・離職者の情報 ・事業所の情報 ・賃金 ・退職理由 など |
このように、失業手当の受給期間や金額を決定するための重要な情報が記載されています。
アルバイト・パートで離職票が必要なケース
正社員だけでなく、アルバイトやパートなどのパートタイム従業員の退職時にも必要になるケースがあります。
アルバイト・パートが雇用保険に加入している場合
パートタイム従業員の退職時に離職票の発行・交付が必要になり得るのは、当該者が雇用保険に加入していた場合です。雇用保険に加入している従業員は、失業手当を受給する権利が存在する場合があります。
原則として、以下の条件を満たす場合、企業はアルバイトやパートを正社員と同様に雇用保険に加入させなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の継続雇用が見込まれる
雇用保険の加入要件の詳細については、厚生労働省のページをご確認ください。
退職者が59歳以上の場合
退職時の年齢が59歳以上の場合は、高年齢雇用継続給付の金額を決定するために離職票が必要です。この場合は、本人が希望するか否かにかかわらず、企業は離職票を発行する義務があります。
なお、アルバイトやパートに限らず、正社員が退職する場合も同様です。手続きや高年齢雇用継続給付の詳細は、厚生労働省のサイトでご確認ください。
参照:『第5章 被保険者についての諸手続』
参照:『Q&A~高年齢雇用継続給付~』厚生労働省
アルバイト・パートの離職票が不必要なケース
雇用保険の加入要件を満たすアルバイトやパートが退職する際、なかには離職票が必要ないケースもあります。
退職者が離職票を希望しない場合
退職者が59歳未満かつ離職票の受け取りを希望しない場合、企業が手続きを行う必要はありません。
たとえば、再就職先が決まっている場合は失業手当を受給しないため、離職票が必要になるタイミングはほとんどないでしょう。ただし、退職後しばらく経ってから離職票の発行を希望されるケースもあるため、注意が必要です。
学生の場合
昼間に学校へ通う学生は、労働時間などの要件を満たしていても雇用保険に加入できません。
ただし、夜間や定時制、通信教育課程の学生、卒業後も継続して働くことが内定している学生などは、雇用保険の加入対象となるため注意が必要です。
離職票を交付する流れ
退職者本人に発行の意思を確認するところから、離職票が本人の手に渡るところまで、離職票交付のおおまかな流れを解説します。
1.アルバイト・パートの退職者に離職票交付の希望を確認する
アルバイトやパートから退職の申し出があったら、離職票の希望についてヒアリングします。退職者が59歳未満で離職票の交付を希望しない場合は、これ以降のステップは不要です。
2.離職証明書の内容をアルバイト・パートの退職者と確認する
離職証明書の記載内容については、退職者の同意をとる必要があります。
内容に誤りがないか、退職者と一緒に確認しましょう。とくに、離職証明書に記載する離職理由については注意が必要。失業手当の給付日数を決定するうえで重要な項目なので、退職者の署名を別途受けなければなりません。
3.所轄のハローワークに必要な書類を提出する
雇用保険法施行規則7条において、離職証明書の提出期限は「退職日の翌々日から10日以内」と定められています。雇用保険被保険者資格喪失届とあわせて、期限内に所轄のハローワークに提出しましょう。
ハローワークの確認が完了すると、離職票は退職者ではなく、企業宛に送付されてきます。受け取った離職票は、退職者の自宅まで郵送するケースが一般的です。
アルバイト・パートを掛け持ちしている場合の注意点
退職するアルバイトやパートが仕事を掛け持ちしている場合は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
雇用保険は一つのアルバイト・パート先でのみ加入できる
原則的に、雇用保険に加入できるのは1社のみです。アルバイトやパート先が複数ある場合、それぞれの勤め先で雇用保険に加入することはできません。
通常は、掛け持ちしている企業のうち、もっとも給与が高い勤め先で雇用保険に加入するのが一般的です。アルバイトやパートが雇用保険の加入要件を満たしている場合は、掛け持ちの有無や主たる勤め先について確認しておきましょう。
複数のアルバイト・パートの時間合算は不可
1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、企業は当該労働者を雇用保険に加入させる必要があります。ただし、加入要件の算定に用いられるのは、あくまでそれぞれの企業における労働時間です。
たとえば「A社で週4日3時間勤務、B社で週5日2時間勤務」という勤務スタイルで働いている場合、それぞれの企業における労働時間は週20時間を超えておらず、雇用保険の加入要件を満たせません。
ただし、65歳以上の労働者の場合には、2つ以上の勤務先の合計労働時間が20時間以上である場合には、特例として雇用保険の加入対象となることが可能です。アルバイトやパートに尋ねられた場合は、明確に説明できるようにしておきましょう。
ハローワークはアルバイト・パート掛け持ちを把握している
雇用保険の加入者には、1人につき1つ「雇用保険番号」が割り振られています。ハローワークはアルバイトやパートの掛け持ちを把握できるため、雇用保険の重複加入はできない仕組みになっているのです。
退職するアルバイトやパートが雇用保険の加入要件を満たしていても、すでにほかの企業で雇用保険に加入している可能性があるため、十分に確認しておきましょう。
離職票を発行・交付しないと受ける罰則
退職者から「離職票を発行してほしい」と申し出を受けた場合、企業は所定の手続きを行う義務があります。では、もしも企業が離職票の発行・交付を拒んだ場合、ペナルティはあるのでしょうか。
離職票発行・交付は企業の義務
離職票の発行・交付は、雇用保険法第76条3項で定められた企業の義務です。従業員から離職票の発行申請を受けた場合、企業は速やかに応じる必要があります。
正当な理由なく離職票の発行・交付を拒むと、雇用保険法第83条の規定に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。雇用保険法の条文を確認したい方は、下記をご参照ください。
離職票は再発行が可能
離職票の発行回数に制限はなく、何度でも再発行が可能です。
企業・退職者のどちらでも手続きできる
紛失などにより退職者から「離職票を再発行したい」と相談された場合は、まずハローワークのホームページにアクセスしましょう。「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」をダウンロードしたら、初回の発行時と同様にハローワークへ提出して手続き完了です。
なお、一度発行された離職票はシステム上に履歴が残されているため、退職者が自分で申請することもできます。退職者自身がハローワークで直接申請すれば、企業を介した場合と比べてスピーディな再発行が可能です。再発行を急いでいる様子なら、自分で手続き可能なことを伝えてあげてください。
離職票と離職証明書・退職証明書の違い
離職票と混同されがちな書類に、離職証明書や退職証明書があります。名称は似ていますが用途や役割が異なるので、事前に把握しておきましょう。
離職票と離職証明書の違い
離職証明書は、離職票の発行手続きにおける提出書類の1つです。正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。退職者から離職票の発行を求められたら、企業は当該者の離職証明書を作成し、ハローワークに提出しなければなりません。
離職証明書は複写式の3枚つづりとなっており、3枚目の本人控えが「雇用保険被保険者離職票-2」として退職者に返却されます。
離職証明書の記載項目
離職証明書には、以下の内容をはじめとした計16の項目があります。
- 退職者の氏名
- 離職年月日
- 事業所名・住所
- 事業主氏名
- 離職理由
- 被保険者期間算定対象期間
- 賃金支払対象期間 など
なかでも重要なのが「離職理由」の項目です。離職理由は失業手当の給付期間を決定する情報なので、退職者本人に内容を確認してもらったうえで、署名を受けなければなりません。
あとのトラブルを避けるため、退職者とともに念入りに確認しましょう。離職証明書の詳細や記載例、作成上の注意点などは、厚生労働省のページでご確認ください。
参照:『雇用保険被保険者離職証明書についての注意』厚生労働省
離職票と退職証明書の違い
離職証明書が「離職したこと」を証明する書類なのに対し、退職証明書は「退職したこと」を証明する書類です。非常に似通っていますが、退職証明書は公的な書類ではありません。
退職証明書は、国民健康保険や国民年金の手続きにおいて離職票の代わりに使えるほか、転職活動で使用されるケースもあります。決められたフォーマットはなく、記載内容についても「離職理由は伏せてほしい」といった退職者の要望に応じて変更可能です。
労働基準法第22条により、退職から2年間は、企業は退職者からの要望に応じて退職証明書を発行する義務があります。
退職証明書に記載する項目
退職証明書の記載内容は退職者の要望に応じて変更可能ですが、ある程度の雛形は決まっており、おおむね以下のような項目が記載されます。
- 退職年月日
- 在職期間
- 在職中の業務内容
- 在職中の賃金
- 退職理由
なお、退職者が望まない項目を記載することは、労働基準法第22条3項の違反です。たとえば、退職者から「退職理由を記載したくない」と申し出があった場合、退職証明書に当該項目を記載することは認められません。
退職証明書の用途
退職証明書は公的な書類ではないものの、公的手続きの代替書類として利用できる場合があります。
たとえば、国民健康保険への加入や国民年金の種別変更手続きなどには離職票が必要ですが、紛失や発行の遅延などの理由から用意できない場合は退職証明書を代わりに提出可能です。
また「退職の証明」は「過去の在籍の証明」でもあるため、転職活動において退職証明書が必要になるケースもあります。
アルバイトやパートにも離職票は必要
アルバイトやパートの従業員が雇用保険に加入している場合、企業は退職者の求めに応じて離職票を発行する義務があります。なお、正社員と同様、退職者の年齢が59歳以上の場合は、本人の意思とは関係なく離職票を発行しなければなりません。
離職票の発行は、雇用保険法で定められた企業の義務です。アルバイトやパートが退職する際に速やかに対応できるよう、業務フローを整えておきましょう。
「One人事」は人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。電子申請や年末調整、マイナンバー管理など幅広い業務の効率化を助け、担当者の手間を軽減。費用や気になる使い心地について、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。