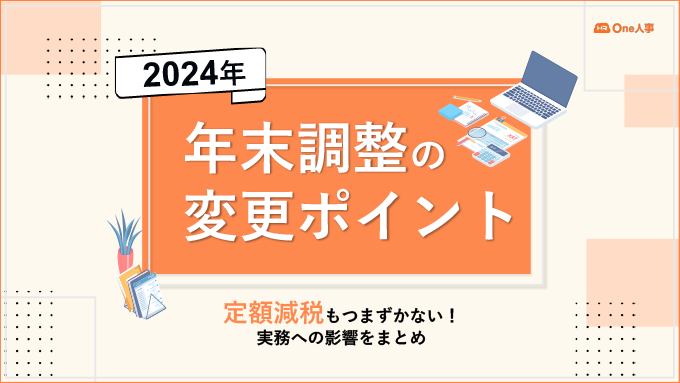積立NISAは年末調整が必要なのか|企業が知っておくべきことや対応策を解説

企業では毎年、年末調整をする必要がありますが、積立NISAについても企業で年末調整が必要なのか疑問を抱く担当者もいるのではないでしょうか。結論からいうと、積立NISAは年末調整する必要はありません。
ただし、場合によっては従業員に確定申告をしてもらう必要があるため、どのようなケースが確定申告の対象か把握しておくことが大切です。
本記事では、積立NISAの概要と、積立NISAにおける年末調整の必要性などについて解説します。

 目次
目次
積立NISAとは
積立NISAとは2018年からスタートした、長期的な資産形成を支援する制度です。2024年1月からは新制度が始まっているため、あらためて積立NISAについて理解しておく必要があります。
NISAは少額投資非課税制度
NISAとは「少額投資非課税制度」を指し、投資で得た利益や配当が非課税、つまり税金がかからない制度です。通常は投資信託や株式などで得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAを利用すると投資利益の一定範囲が非課税になります。
たとえば、50万円を投資して3万円の利益を得られたとすると、通常であれば6,094円の税金が引かれ、利益は23,906円です。しかし、NISAを利用すると利益に税金はかからないため、3万円をそのまま利益として受け取れます。
NISAは日本国内に住んでいる人であれば誰でも利用可能で、20歳以上(2023年からは18歳以上)を対象とする「一般NISA」「積立NISA」と、未成年を対象とする「ジュニアNISA」があります。ジュニアNISAの新規の口座開設受付は2023年末までで、2024年以降は新規で購入できなくなりました。
参考:『NISAとは?』金融庁
2024年1月から新NISAが導入
2022年12月に『令和5年度与党税制改正大網』が発表され、「資産所得倍増プラン」の具体的な手段として、新しいNISAが導入されることが決まりました。以前の積立NISAは2023年末で新規買付が終了し、2024年1月からは新しいNISAがスタートしました。
以前のNISAと新しいNISAで異なるポイントは以下のとおりです。
- つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができる
- 非課税保有期間が無期限になる
- 口座開設期間の恒久化される
- 年間投資枠が最大360万円に拡大される
(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円) - 非課税保有限度額が全体で1,800万円になる(成長投資枠は1,200万円)
以前のNISAは年間投資枠が一般NISAで120万円、積立NISAで40万円でした。
2024年からはつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、併用することで年間最大360万円まで投資枠が拡大されています。非課税保有期間も無期限になり、より長期的な資産形成がしやすくなったといえるでしょう。
参考:『新しいNISAのポイント』金融庁
参考:『令和5(2023)年度税制改正について』金融庁
積立NISAの概要
積立NISAは少額からの長期分散投資を支援する制度として2018年にスタートしました。正式名称を「つみたてNISA(以下、積立NISA)」といいます。
積立NISAはNISAと同様に、一定の投資信託による分配金や譲渡益は非課税になります。新規投資額は年間40万円が上限で、非課税保有期間は最長20年です。投資方法は文字どおり「積み立て」に限られ、毎月決まった日に一定金額を投資できます。
一般NISAの概要
一般NISAとは、2014年にスタートした少額投資非課税制度です。株式や投資信託で得られた配当金や分配金、譲渡金は非課税となり、新規投資額の上限は積立NISAより多い年間120万円とされています。
一般NISAは投資枠の範囲内であれば、対象の金融商品を複数購入することが可能です。非課税保有期間は最長5年間、トータル600万円までの投資で得られた利益が非課税となります。
参考:『NISAとは?』金融庁
年末調整や確定申告とは
積立NISAは非課税のため、投資から利益が得られても、年末調整や確定申告をする必要はありません。
そもそも年末調整は会社員を対象にした、源泉徴収票された所得税の過不足を調整する手続きです。毎年11月ごろから翌年1月にかけて、1年間の収入や社会保険料などの控除、源泉徴収した分の所得税額などを会社がまとめて計算し、過不足金を調整する仕組みです。
一方、確定申告とは1年間の収入から経費や控除を差し引いて、所得税の税額を確定するための手続きです。主に自営業や個人事業主、フリーランスを対象としています。毎年2月〜3月に、前年の1月〜12月までの所得税などの税金を申告します。
参考:『【確定申告・還付申告】』国税庁
参考:『年末調整がよくわかるページ(令和4年分)』国税庁

証券口座の種類による違い
基本的に積立NISAで得られた利益は非課税ですが、口座の種類によっては確定申告が必要なケースがあります。
- NISA口座
- 特定口座(源泉徴収なし)
- 特定口座(源泉徴収あり)
- 一般口座
NISA口座
NISAには一般NISAとつみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります(ジュニアNISAは新規の口座開設受付が2023年末までのため、2024年以降は新規購入できません)。原則としてどのNISAも利益は非課税であるため、確定申告や年末調整をする必要はありません。
ただし、非課税となる利益には上限があり、NISA口座では毎年120万円までの非課税投資が可能です。仮に120万円を超えた分で得た利益は課税対象になり、確定申告をする必要があります。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座とは、投資商品を保有するために使用する口座です。証券会社が本人に代わって保有する投資商品の譲渡損益を計算し、年間取引報告書を作成してくれるのが特徴です。
特定口座(源泉徴収なし)では、口座内で株式の譲渡損益が出ても源泉徴収されないため、納税者本人で、証券会社が発行した「特定口座年間取引報告書」をもとに確定申告をする必要があります。ただし、年間の利益が20万円以下なら確定申告は不要です。
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座は「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」の2種類があり、「源泉徴収あり」を選ぶこともできます。「源泉徴収なし」の特定口座との違いは、利益が確定した時点で証券会社が源泉徴収(納税)してくれることです。したがって、「源泉徴収あり」の特定口座では、確定申告をする必要はありません。
ただし、複数の証券口座で損益通算する場合は、確定申告をする必要があります。同じ証券会社の場合は自動で損益通算されますが、ほかの金融機関では自動で損益通算は行われないので注意しましょう。
一般口座
一般口座とは、NISA口座や特定口座以外の口座を指します。一般口座で利益がでた場合は、証券会社が作成した年間取引報告書を参考に、1年間の譲渡損益計算をすべて自分で行わなければなりません。また、特定口座のように源泉徴収の有無を選択できないので、確定申告が必要です。
ただし、以下の条件にすべて当てはまる場合は、原則として確定申告が不要です。
- 給与の支払いが1か所のみ
- 年収2,000万円以下
- 譲渡益と配当金をあわせた利益が20万円以下
積立NISAは年末調整の対象なのか
積立NISAやNISAで得られた利益は、基本的に税金が発生しないので、年末調整の対象にはなりません。そもそも年末調整は会社員を対象にした、給与から源泉徴収票された所得税の過不足を調整する手続きのことです。
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、確定申告の必要があります。積立NISAをしている従業員には、確定申告の必要があることを事前に周知しておきましょう。
積立NISAで確定申告が必要なケース
積立NISAは基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、以下の条件に該当する場合は忘れずに確定申告を行いましょう。
確定申告が必要な条件
積立NISAで確定申告が必要となる条件は、給与所得以外の所得が20万円を超え、かつ以下に該当する場合です。
| 上場株式の配当金などの受け取り方法に「株式数比例配分方式」以外を選択している |
|---|
| 「登録配当金受領口座方式」や「従来方式(配当金領収証方式)」は課税の対象になるため、積立NISAであっても確定申告をしなければなりません。 |
| 外国株の売却によって為替差益が発生している |
|---|
| 為替差益とは、為替レートの変動によって生じた損益のことです。たとえば、預け入れたときは100万円でも、円安が進んで満期到来時に110万円になっていたら10万円の為替差益が発生したことになります。この場合、為替差益は雑所得として課税対象になるため、確定申告が必要です。 |
| 積立NISAの非課税保有期間である最長20年が終了した |
|---|
| 積立NISAの非課税保有期間である最長20年が終了したあとに、引き続き運用したい場合は一般口座や特定口座へ払い出しする必要があります。この際に、源泉徴収票ありの特定口座なら引き続き確定申告をする必要はありません。 しかし、一般口座や源泉徴収なしの特定口座へ払い出しした場合は、新しい取得価格になるため、値上がりに応じて確定申告が必要です。 |
課税については従業員が総合課税と申告分離課税のどちらかを選ぶことができます。
総合課税の概要
総合課税は利益(配当金や分配金)を、ほかの所得と合算して税金を計算する課税方法です。対象となる以下の所得をすべて合算し、その合計額を累進課税によって課税します。
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
- 一時所得
- 雑所得
- 譲渡所得 など
総合課税を選択するメリットは、確定申告をした場合に配当控除を受けられることです。
また、総合課税は所得が多ければ多いほど税率が上がる累進課税を採用しているため、言い換えれば所得が低ければ税率も低くなります。課税所得の合計額が900万円以下の場合は、所得税の税率は源泉徴収されるよりも低くなるので、総合課税を選ぶことで節税になる場合もあります。
申告分離課税の概要
申告分離課税は総合課税とは異なり、利益と所得を合算せず別に計算する課税方法をいいます。そのため、所得の種類ごとに税率が異なり、配当金や分配金にかかる税率は源泉徴収の税率と同じです。
申告分離課税を選択するメリットは、複数の証券口座でそれぞれ別に利益と損失が発生している場合に損益通算ができることです。売却損があった場合は、利益と損失を相殺できれば配当所得が低くなり、減った分の税額が還付され節税につながる場合もあります。
会社が積立NISAに関して対応すべきこと
基本的に積立NISAは年末調整する必要はありませんが、場合によっては確定申告が必要です。従業員が積立NISAをしている場合は、年末調整や確定申告について事前に周知しておくようにしましょう。
- 積立NISAは年末調整の必要がないことを周知する
- 積立NISAの確定申告について周知する
積立NISAは年末調整の必要がないことを周知する
従業員側から年末調整における、積立NISAの扱いについて問い合わせがあることも考えられます。積立NISAを利用していても基本的に年末調整する必要はありません。そのため、会社側は積立NISAをしている従業員に、あらかじめ年末調整する必要がない旨を知らせておきましょう。
ただし、確定申告が必要なケースもあるので、該当する場合は確定申告を促してください。
積立NISAの確定申告について周知する
基本的に、積立NISAは年末調整や確定申告をする必要はありません。しかし、一定の条件を満たすと、確定申告と納税をする必要があります。
従業員が確定申告が必要であることを知らず、申告漏れが生じないように担当者は理解を促しましょう。確定申告は会社で行うものではなく、従業員本人が行わなければならないため、事前に周知することが大切です。
まとめ
積立NISAは少額から投資を始めることができる、長期的な資産形成に役立つ制度です。毎月一定額を積み立てていく比較的かんたんな投資方法なので、積立NISAをしている会社員も増えてきています。
一方、積立NISAにおいては得た利益が非課税のため、基本的に会社側で年末調整する必要はありません。ただし、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要になるので、申告漏れのないよう従業員に周知しておくことが大切です。
年末調整担当者はどのようなケースで確定申告が必要になるのか、積立NISAのルールを把握しておきましょう。
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。従業員の入退社手続きや年末調整の効率化を実現し、担当者の負担を軽減することで、人材活用の基盤をつくります。気になる費用や操作性は、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |