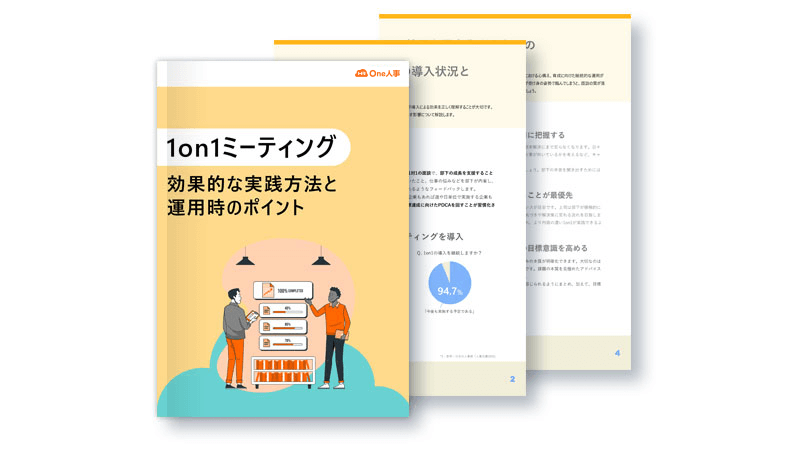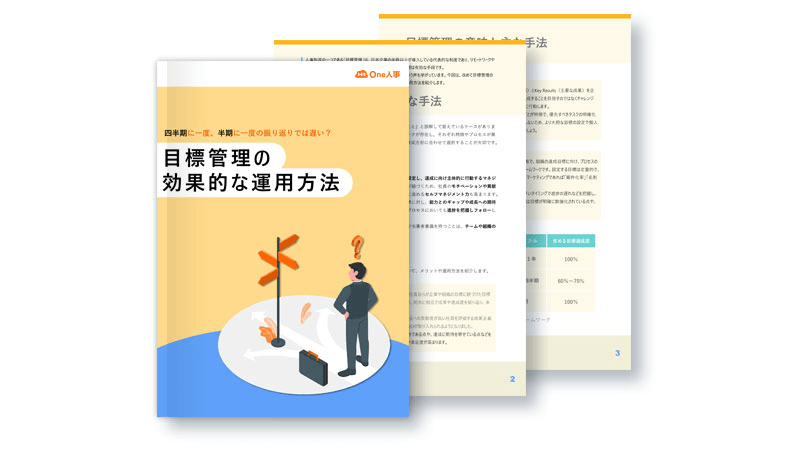1on1ミーティングと評価面談の違い|人事評価に活用するコツも解説

1on1ミーティングと、人事評価面談はまったく別のものです。違いがわからないまま、なんとなく実施していませんか。
本記事では、1on1ミーティングと人事評価面談の違いを明確にし、1on1ミーティングを人事評価に活用するコツを紹介します。
→1on1の質を高めるには? 運用ガイドBooKを無料ダウンロード
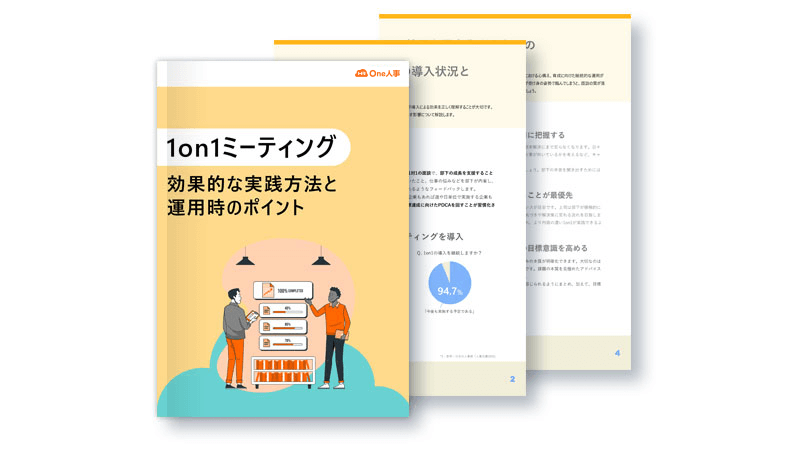
 目次[表示]
目次[表示]
1on1ミーティングと人事評価面談の違い
1on1ミーティングは、従業員の成長を支援し、信頼関係づくりを目的とした、上司と部下の定期的な対話の場です。
一方で、評価面談は文字どおり「評価」が主軸。目的も内容も、じつは大きく異なります。
両者の主な違いは以下のとおりです。
| 1on1ミーティング | 人事評価面談 | |
|---|---|---|
| 実施目的 | 成長促進・信頼関係の構築 | 業績評価・フィードバック |
| 管轄 | 管理職 | 人事部 |
| 実施頻度 | 週1回~月1回程度 | 四半期または半期に1回 |
| 実施時間 | 15分~30分程度 | 30分~1時間程度 |
| 対話のテーマ | ・KPIや業務の進捗 ・仕事の悩み ・キャリア ・(プライベート) | ・目標達成度 ・評価結果 ・次期目標設定 |
▼より深く1on1ミーティングの内容や実施目的を知るには、以下の記事もご確認ください。
実施目的
1on1ミーティングの主な目的は、人材育成にあります。日々の業務を支えながら、部下の成長を継続的に促すマネジメント手法です。定期的な対話を通じて課題や悩みを把握し、早期にフォローできる関係を築きます。会話を積み重ねることで信頼関係が生まれ、結果としてエンゲージメントの向上にもつながるメリットがあります。
一方、人事評価面談は、前期の振り返りと次期の目標設定が主な目的です。一定期間の実績や行動をもとに、昇給・昇進を見極める評価を行う場とされています。評価者である上司が主導し、やや一方的な進行になりやすいといえます。
▼1on1はうまくいっていますか。1on1ミーティングの実施に課題がある方は、以下の資料をご活用ください。
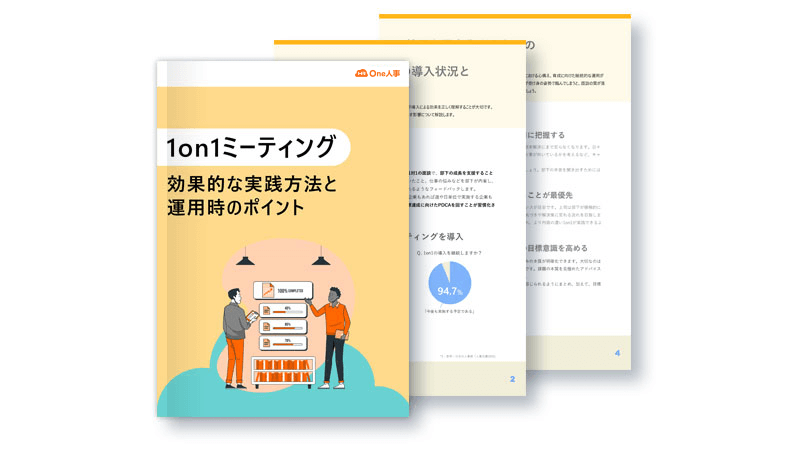
実施頻度
1on1ミーティングは月1回や隔週、週1回など、比較的短いサイクルで継続的に実施します。小さな変化にも気づきやすく、タイムリーな承認やアドバイスが可能です。
対して評価面談は、四半期や半期に一度と頻度が高くありません。期間が空くぶん、上司と部下で認識に相違が生まれやすいという課題があります。
日ごろから1on1で目標の進み具合をすりあわせておくと、評価時の行き違いが少なくなり、従業員の納得感につながります。
▼最近では評価頻度を高める目標管理の方法も注目されています。目標管理を運用するコツは、以下の資料からご確認ください。
実施時間
1on1ミーティングの所要時間は15〜30分ほどが一般的です。短い時間でも十分に効果を出すには、アジェンダの準備やテーマ設定が重要です。
評価面談は、評価内容の説明や目標のすり合わせを行うため、30分〜1時間程度かけて実施されることが多くなります。
対話のテーマ
1on1ミーティングでは、仕事の進捗や悩みだけでなく、キャリアや働き方、ときにはプライベートにかかわる話題まで自由に話すことができます。あくまでも主役は部下で、今上司に伝えたいことを話す場です。
一方で評価面談は、目標の達成度や評価フィードバック、次の目標設定など、業績に直結した内容が中心です。評価者が話す比率も高く、形式的な対話になりやすい特徴があります。
▼1on1で話すネタに困っていませんか。テーマの例は以下の記事よりご確認ください。
1on1ミーティングによって人事評価の納得度が高まる理由
1on1ミーティングと評価面談は役割が異なるものの、上手に運用すれば評価の納得度を高められる可能性があります。
1on1がどのように人事評価を支えるのか、3つの視点から紹介していきます。
- 評価の根拠を得られる
- 評価軸を明確化できる
- すり合わせの機会を設けられる
評価の根拠を得られる
1on1ミーティングを継続的に実施、記録を残しておくことで、評価に活用できるエピソードや事実が自然と蓄積されます。
日々の業務や成果、工夫のプロセスなど、上司が逐一把握できるため、期末により具体的な評価が可能です。
たとえば「プロジェクトを予定より早く完了した」「トラブル対応が的確だった」など、日常で見落としがちな貢献も評価材料として1on1の場で拾えるかもしれません。
評価に至る過程も見ていたことを伝えられると、部下の評価に対する納得感は高まるでしょう。
評価軸を明確化できる
1on1の場は、部下に対して、どのような行動や成果が評価されるのかを伝えるチャンスでもあります。
評価制度や求められる役割、期待している行動を定期的に共有することで、部下は何を目指せばよいのかが明確になります。
たとえば「このポジションでは主体性を重視している」「こうした成果が高く評価される」と伝えることで、評価軸のすり合わせが可能です。
目標の進捗を一緒に確認しながら、課題への対応を考える機会を設けることで、評価基準への理解を深められるでしょう。
すり合わせの機会を設けられる
評価面談で「思っていたより低い評価だった」と不満を持たれた経験はありませんか。1on1を通じて日常的にすり合わせをしておくことで、上司と部下のズレを防げるかもしれません。
たとえば、部下が順調だと思っていた案件に対して、上司は改善の余地を感じていたというギャップはよくある話です。
1on1ミーティングで、認識のズレを早めに調整し、フィードバックを重ねることで、評価時に「すでに改善済み」として前向きな対話につながります。
1on1は、評価をめぐるすれ違いをなくすための土台となるのです。
1on1ミーティングを人事評価に活用するポイント
1on1ミーティングは直接的に評価する場ではありませんが、話した内容は評価を支えるものとなります。ここでは、1on1を人事評価にうまく活用するためのポイントを紹介します。
目的を周知する
まず大前提として、1on1と評価面談は目的が異なることを部下に伝える必要があります。「1on1は評価ではなく、あなたの成長を促す対話の場」と伝えることで、部下は安心して本音を話しやすくなるでしょう。
そのうえで、「話してくれた内容は評価に直結するわけではないが、必要に応じて参考にすることもある」と補足しておくと、警戒心を和らげられます。率直な対話があってこそ、1on1の効果は最大化されるはずです。
ミーティングの記録を残す
1on1で話した内容は、可能な範囲で記録しておくことが大切です。評価の際に具体的なエピソードを思い出しやすくなり、納得感のあるフィードバックがしやすくなります。
1on1の記録はシンプルで構いません。「話した内容」「合意事項」「次回の確認ポイント」などを簡潔にまとめましょう。専用の1on1ツールや1on1を支援する機能があるタレントマネジメントシステムの導入もおすすめです。
→1on1を支援する機能があるタレントマネジメントシステムの特長はこちら

ただし、個人のプライバシーに配慮し、必要に応じて記録対象は事前に合意を得るように注意しましょう。
部下の本音を引き出す工夫をする
評価に役立つ情報を得るには、部下の本音を引き出す工夫が欠かせません。そのためには、上司が聞き役に徹し、安心して話せる雰囲気をつくることが大切です。
質問はオープンな形で投げかけ、部下の言葉をさえぎらずに耳を傾けましょう。沈黙の時間も、部下が考えを整理するきっかけになります。「ちゃんと聞いてくれている」と感じてもらえる接し方が、信頼関係の構築につながるでしょう。
話す内容を決めておく
1on1ミーティングを実のある時間にするには、あらかじめテーマを決めておくことが必要です。アジェンダを用意しておかないと、雑談だけで終わってしまい、評価にも活かせる情報を聞き出せません。
たとえば「最近の進捗で悩んでいること」「成長したと感じる場面」などを事前に提示しておくと、部下も準備しやすくなります。
| 話すことの例 |
|---|
| ・現在の進捗状況 ・業務課題と解決の方法 ・目標達成に向けた取り組みや障害 ・今後のキャリア開発や成長に関する希望 ・チームメンバーとの関係性や協力体制 ・仕事のモチベーションや満足度 ・プライベートでの悩みや健康状態(業務に影響する範囲で) ・会社の方針や制度に対する疑問や提案 |
「最近うまくいったことは?」「困っていることはある?」といった問いかけから始めると、自然な対話のきっかけになるかもしれません。
▼1on1で話すネタに困っていませんか。テーマの例は以下の記事よりご確認ください。
1on1ミーティングを人事評価に活用する際の注意点
1on1ミーティングは評価の納得感を高める手段ともいえますが、運用を誤ると逆効果になりかねません。ここでは、人事評価に活用するうえで意識したい注意点を3つ紹介します。
- 信頼関係の構築には時間がかかる
- 上司側に一定のスキルが求められる
- 現場に負担がかからないよう配慮する
信頼関係の構築には時間がかかる
1on1を実施するだけで、上司と部下の信頼関係を築くのは難しいです。日頃のコミュニケーションが足りなければ、部下は「評価に影響するかもしれない」と本音で意見を話すのをためらいます。
1on1の効果を発揮するには、普段から気軽に話せる関係性を構築しておかなければなりません。部下が安心して話せる土台があってこそ、成長支援や評価の参考になる対話が成り立ちます。
1on1は信頼を深める手段の一つであり、それだけで完結するものではないと理解しておきましょう。
上司側に一定のスキルが求められる
1on1を評価に活かすには、上司側に一定のスキルが必要です。とくに重要なのは、傾聴力・質問力・フィードバック力の3つです。
相手の話にしっかり耳を傾け、気持ちや意図をくみ取ることが傾聴力。質問力は、部下が自分の考えに気づく手助けができる問いかけができるかどうか。そして、タイムリーで具体的なフィードバックは、部下の行動変容につながります。
スキルが十分でない場合、1on1がただの報告や雑談になり、評価にも育成にもつながりません。
▼傾聴力を伸ばしたいとお考えなら、以下の記事もご確認ください。
現場に負担がかからないよう配慮する
定期的な1on1の実施は、上司・部下の双方に時間的な負担がかかります。たとえば10人の部下と毎週30分ずつ1on1を実施すれば、それだけで週5時間を要します。
全員と均等に実施するのが難しい場合は、重点的に支援が必要なメンバーに絞る運用も効果的です。たとえば、新入社員や異動者、パフォーマンスに課題を抱える人などが優先対象になります。
また、1on1ツールの活用もおすすめです。スケジュール管理や記録、振り返りが効率化されるでしょう。形式にとらわれすぎず、現場の実情に合わせて柔軟に設計することが大切です。
まとめ|1on1ミーティングの実施で人事評価に納得感を
1on1ミーティングと人事評価面談は、それぞれ目的が異なるものです。前者は部下の成長支援と信頼関係の構築、後者は業績評価とフィードバックを目的とした、制度上の対話の場です。
とはいえ、1on1を定期的に実施することで、評価面談の場で生じがちなギャップは減らせる可能性があります。
日々の対話を通じて、評価の根拠を蓄積し、評価軸や期待値を共有しておくと、納得感のある評価につながるでしょう。
もちろん、信頼関係の構築には時間がかかり、上司側にもスキルや配慮が求められます。運用には負担をともないますが、課題を上回る価値があるのが1on1ミーティングです。
人事評価の透明性と公平性を高める手段として、1on1ミーティングを上手に活用していきましょう。社員の納得感が高まれば、結果的に組織全体のパフォーマンス向上や離職の防止にもつながります。
1on1ミーティングの効果を最大化|One人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、1on1ミーティングの運用を効率化し、効果を最大化するための機能を備えたタレントマネジメントシステムです。
1on1ミーティングは継続的な実施で効果を発揮しますが、運用負担には課題を抱える企業も少なくありません。結果的に形骸化してしまい、「失敗した」「意味がない」と感じられる人もいるでしょう。
One人事[タレントマネジメント]を活用すると、テーマ設定や次回までの目標アクションの記録を、評価履歴と紐づけて一元管理できます。
意味のある1on1ミーティングにするために、ツールでの管理も検討してみてはいかがでしょうか。
気になる初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントに役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |