人事の年間スケジュールとは? 業務の種類や計画を立てる際のポイントを解説

人事担当者は、年間を通じてさまざまな業務に追われていませんか。年度末や繁忙期には、複数の手続きを同時進行しなければならず、負担を感じることも多いでしょう。
手続きの漏れや遅れが起きないよう、年間スケジュールを整理しておくと安心できます。
本記事では、人事の年間スケジュールと人事担当者が月ごとにやるべきこと、進め方のポイントを紹介します。

 目次[表示]
目次[表示]
人事・労務担当者の主な業務
人事の年間スケジュールを紹介する前に、まずは人事労務の主な業務内容を整理しておきましょう。
人事・労務の業務は、大きく分けると「人事管理業務」と「労務管理業務」の2つに分けられます。
人事管理業務は、採用や人材育成など、社員と直接かかわる仕事が中心です。一方、労務管理業務は、給与計算や社会保険の手続きなど、社員を支える間接的な仕事が主になります。
それぞれの業務がどのような内容か、次に詳しく見ていきましょう。
主な人事管理業務
人事管理業務は、採用や人材育成など、社員と直接かかわる仕事が中心です。
| 人事管理の主な仕事 |
|---|
| ・入社オンボーディング/退社オフボーディング ・採用活動 ・人事評価 ・人事異動 ・研修 ・教育活動 ・キャリア開発支援 |
たとえば、採用では新卒・中途それぞれの計画立案や選考、インターンシップの運営、採用イベントの企画を実施します。
評価制度の運用や目標管理、面談を通じて、キャリア形成を支援するのも重要な役割です。
さらに、昇進や異動の調整、人材配置の計画も人事担当の大切な仕事です。教育・研修活動や自己啓発支援など、従業員の成長を促す取り組みも欠かせません。
主な労務管理業務
労務管理業務は、社員を支える間接的な業務が中心です。
| 労務管理の主な仕事 |
|---|
| ・給与・賞与計算 ・勤怠管理 ・社会保険手続き ・安全衛生管理 ・年末調整 |
たとえば、給与計算では毎月の基本給や各種手当、退職金などを正しく計算し、期日までに支給します。
勤怠管理では、残業や休日出勤の把握、年次有給休暇などの休暇管理を行います。
入退社にともなう加入・喪失などの社会保険手続きや年末調整では、法律で定められた業務を期限内に進めることが必要です。
また、安全衛生管理を通じて、従業員の健康維持や安心して働ける職場環境づくりも担います。

人事の年間スケジュールで押さえたい業務
人事の年間スケジュールは、大きく「採用業務」「給与・労務」「人材開発・人材育成」の3つに分けて整理できます。
ここでは、それぞれの業務が年間を通してどのように進むのか、人事の年間スケジュールのポイントを紹介します。
採用業務
採用業務は企業の成長を支える重要な機能です。必要な人材を適切なタイミングで確保するためには、採用活動を計画的に進めなければなりません。
採用業務は大きく「新卒採用」と「中途採用」の2つに分かれます。それぞれ採用のプロセスやスケジュールが異なるため、別々に計画を立てる必要があります。
新卒採用
多くの企業と学生は日本経済団体連合会(経団連)による就活ルールにしたがうため、ルールを踏まえて採用スケジュールを検討する必要があります。
新卒採用の年間スケジュールは、おおむね以下のような流れです。
- 3月〜6月頃:採用計画の立案
- 6月〜9月頃:広報活動・母集団形成
- 10月〜12月頃:選考プロセスの実施
- 1月〜3月頃:内定通知とフォロー
- 入社前〜4月:入社準備とオンボーディング
採用計画では、翌年度に向けた採用人数や求める人物像、予算を決め、採用サイトや説明会の準備を進めます。
広報活動は、エントリー受付やインターンシップを実施し、本選考への応募を促します。とくにインターンシップは、優秀な学生と接点を持つ大事な機会です。
本選考では、エントリーシートの確認、筆記試験や面接を行い、内定者を決定します。内定式や入社準備も並行して進めるのが一般的です。
内定通知後は、懇親会や入社前研修を実施し、内定辞退を防ぐためのフォローを行います。
中途採用
中途採用は基本的に通年の採用のため、企業の状況によってスケジュールが異なります。とくに年度の切り替えや賞与の支給後は、転職希望者が増える傾向があります。
中途採用の活発な時期は、次のとおりです。
- 1月〜4月:年度替わりに合わせて転職を検討する人が多い時期
- 7月〜8月:夏のボーナス支給後に動き出す求職者が増える時期
- 10月〜12月: 年内の転職を目指す人や、冬のボーナス後の退職を検討する人が多い時期
中途採用は新卒に比べて選考期間が短いため、迅速な書類選考や面接対応が必要です。
また、条件調整や入社準備も並行して進め、入社後のフォローをしっかり行うことが定着と即戦力化につながります。
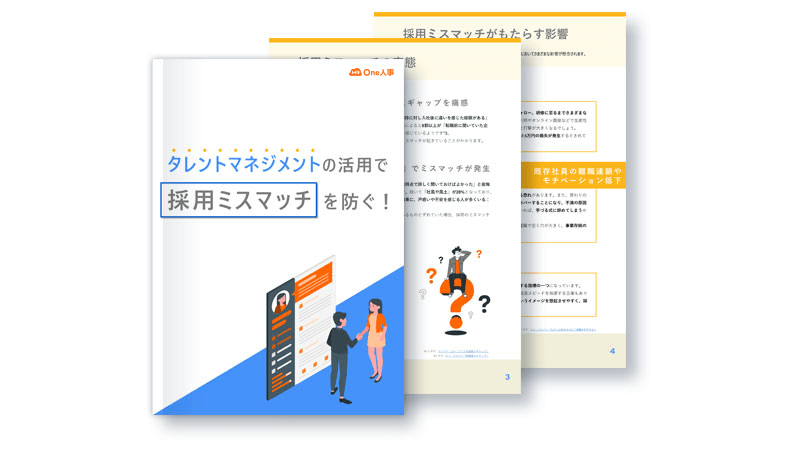
給与・労務
給与・労務は、給与の支払いや社会保険・税金に関する各種手続き、就業規則・労使協定の運用を担う部門です。法定期限を守る対応が欠かせないため、年間スケジュール管理がとくに重要です。
年間のおもな流れは以下のとおりです。
- 4月〜6月:新入社員の社会保険加入、給与改定、住民税の変更、算定基礎届の準備、労働保険の年度更新
- 7月〜9月:社会保険算定基礎届の提出、労働保険の年度更新、夏季賞与の支給
- 10月〜12月:年末調整の準備・実施、冬季賞与の支給
- 1月〜3月:源泉徴収票と法定調書の提出、住民税更新、給与改定の準備
年末調整は11月から12月にかけて精算を行い、翌年1月31日までに源泉徴収票と法定調書を提出し、従業員の所得税を確定させます。算定基礎届は7月10日が期限で、労働保険の年度更新も毎年6月1日から7月10日までのため、同時期に対応が必要です。

人材開発・人材育成
人材開発・人材育成は、新入社員研修や階層別教育を通じて組織の成長を支える業務です。
年間を通じて中長期的な視点で、計画的に取り組むことが求められます。
年間の一般的な流れは以下のとおりですが、企業によって大きく異なります。
- 4月〜6月:新入社員研修の実施、評価制度説明会、目標設定面談
- 7月〜9月:中堅・管理職向け階層別研修、上半期評価面談の準備
- 10月〜12月:評価結果のフィードバック、下半期の目標設定、次年度研修計画の検討
- 1月〜3月:年間評価のまとめ、昇格・昇進検討、次年度の育成計画策定、新入社員受け入れ準備
年間を通じて計画的に進めることで、従業員の成長と組織の活性化につなげられるでしょう。
【採用】人事の年間スケジュール
採用業務は「新卒採用」と「中途採用」に分かれ、異なるスケジュールで進行します。限られた人数で多くの対応をこなす必要があり、スケジュール調整に悩む方もいるでしょう。
ここでは、新卒採用と中途採用の年間スケジュールを具体的に紹介します。
新卒採用
新卒採用は、4月入社を前提とした長期的なスケジュールで進めます。新卒採用担当者は、当年度の採用活動を行いながら、翌年度の採用計画も並行して策定しなければなりません。
新卒採用業務における月別の年間スケジュールの一例を以下に紹介します。
| 月 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 4月 | ・新入社員の受け入れと研修の実施 ・前年度の採用活動の振り返りと課題抽出 ・次年度の採用計画の策定開始(採用人数、予算、スケジュール等) |
| 5月 | ・採用計画の確定(各部門との調整) ・採用サイトの更新準備 ・インターンシッププログラムの企画 |
| 6月 | ・採用サイトのオープン ・夏季インターンシップの募集開始 ・会社説明会の準備(資料作成、会場手配等) |
| 7月 | ・夏季インターンシップの実施 ・採用広報活動の本格化(SNS、採用媒体等) ・会社説明会の開催(オンライン/オフライン) |
| 8月 | ・夏季インターンシップの実施継続 ・インターンシップ参加者のフォロー ・選考プロセスの最終確認 |
| 9月 | ・秋季インターンシップの準備と実施 ・会社説明会の継続開催 ・エントリーシートの受付開始 |
| 10月 | ・本選考の開始(エントリーシート選考、筆記試験等) ・面接官トレーニングの実施 ・内定式の準備 |
| 11月 | ・面接選考の実施(一次面接、二次面接等) ・内々定の通知 ・内定者フォローの計画策定 |
| 12月 | ・最終選考と内々定の通知 ・内定式の開催 ・内定者フォロープログラムの開始 |
| 1月 | ・追加選考の実施(必要に応じて) ・内定者フォローの継続(懇親会、情報提供等) ・次年度の採用活動の準備開始 |
| 2月 | ・内定者の入社前研修の準備 ・内定辞退防止策の実施 ・次年度の採用戦略の見直し |
| 3月 | ・入社前研修の実施 ・入社手続きの案内と準備 ・新年度の受け入れ体制の最終確認 |
無理なく進められるよう、年間計画を部署内で共有し、こまめに進捗を確認しましょう。
中途採用
中途採用は通年で行われることが多く、事業の状況や人材ニーズに応じて計画やスケジュールが柔軟に変わります。
以下は、中途採用業務における一般的な月別の年間スケジュールです。ただし、採用時期によって業務内容は随時変動します。
| 月 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 4月 | ・新年度の採用計画の確認と調整 ・採用媒体の選定と契約 ・職務記述書の作成と更新 ・年度始めの転職希望者向け採用活動の強化 |
| 5月 | ・求人広告の出稿 ・応募者の選考(書類選考、面接等) ・採用ブランディング施策の実施 ・入社手続きと受け入れ準備 |
| 6月 | ・選考活動の継続 ・内定者のフォローと入社日調整 ・夏のボーナス支給後を見据えた採用戦略の準備 ・採用実績の中間レビュー |
| 7月 | ・夏のボーナス支給後の転職市場活性化に合わせた採用活動の強化 ・採用媒体の効果検証と見直し ・選考プロセスの効率化検討 ・内定者の受け入れと研修 |
| 8月 | ・選考活動の継続 ・採用担当者の夏季休暇を考慮したスケジュール調整 ・採用実績の分析と戦略の微調整 ・リファラル採用(社員紹介制度)の促進 |
| 9月 | ・下半期の採用計画の見直しと調整 ・採用チャネルの多様化検討(エージェント、SNS等) ・選考活動の継続・内定者の受け入れと研修 |
| 10月 | ・年末年始の入社を見据えた採用活動の強化 ・採用イベントへの参加(転職フェア等) ・選考活動の継続 ・採用実績の分析と戦略の微調整 |
| 11月 | ・年内入社希望者向けの採用活動の最終調整 ・次年度の採用予算の策定 ・選考活動の継続 ・内定者の受け入れ準備 |
| 12月 | ・年末の入社手続きと受け入れ ・年末年始の採用活動の調整(面接日程等) ・次年度の採用計画の策定 ・採用実績の年間レビュー |
| 1月 | ・新年度の採用戦略の確定 ・年始の転職市場活性化に合わせた採用活動の強化 ・採用媒体の契約更新と見直し ・選考活動の継続 |
| 2月 | ・春の転職シーズンに向けた採用活動の強化 ・採用プロセスの改善施策の実施 ・選考活動の継続・内定者の受け入れ準備 |
| 3月 | ・年度末の入社手続きと受け入れ ・次年度の採用活動の準備完了 ・採用実績の最終レビューと課題抽出 ・新年度の採用担当者への引き継ぎ |
【給与・労務】人事の年間スケジュール
給与・労務業務は、毎月発生する定例業務と、年度を通じて特定の時期に集中する業務があります。
ここでは、給与・労務担当者がおさえておきたい月別の業務を、年間スケジュールとして整理し紹介します。
| 月 | 主な給与・労務業務 |
|---|---|
| 1月 | ・源泉徴収票の発行 ・住民税特別徴収額の通知書対応 |
| 2月 | ・給与計算・支給 ・社会保険手続き(入退社発生時) |
| 3月 | ・給与計算・支給 ・年度末の各種確認(異動・昇給・手当等) |
| 4月 | ・新入社員の入社手続き(雇用契約書、労働条件通知書など) ・新入社員の社会保険資格取得届の提出 ・給与計算・支給 ・社会保険定時決定の準備開始 |
| 5月 | ・給与計算・支給 ・社会保険定時決定の準備 ・賞与支給の準備(夏季賞与の場合) |
| 6月 | ・給与計算・支給 ・社会保険定時決定(算定基礎届の作成・提出) ・労働保険年度更新(確定・概算保険料の申告納付)・賞与支給(会社規定による) |
| 7月 | ・給与計算・支給 ・社会保険定時決定(算定基礎届の提出期限:7月10日) ・労働保険年度更新(納付期限:7月10日) ・賞与支給(会社規定による) |
| 8月 | ・給与計算・支給 ・社会保険料の改定(7月提出分反映) ・賞与支給(会社規定による) |
| 9月 | ・給与計算・支給 ・社会保険料の改定確認(定時決定による確認) |
| 10月 | ・給与計算・支給 ・新入社員や異動者の手続き ・社会保険料の改定(9月分の給与より新標準報酬月額適用) ・賞与支給(会社規定による) |
| 11月 | ・給与計算・支給 ・年末調整の準備(扶養控除申告書等の回収) ・賞与支給(会社規定による) |
| 12月 | ・給与計算・支給 ・年末調整の実施 ・源泉徴収票の作成準備 ・賞与支給(冬季賞与の場合) |

【毎月】入社
毎月、新入社員や中途採用者がいる場合は、雇用契約書や労働条件通知書の準備が必要です。4月や10月は入社が多く、給与・労務担当者にとって繁忙期となります。
入社手続きでは、社会保険や雇用保険の資格取得届の提出が欠かせません。入社後の給与計算や勤怠管理の初期設定も重要な業務です。
【毎月、4月~6月】社会保険定時改定
社会保険定時改定は、4月から6月の3か月間の報酬月額をもとに、標準報酬月額を決定する手続きです。7月1日に在籍している従業員について、算定基礎届を作成し提出しましょう。
10月(9月分給与)には7月の算定基礎届に基づき、各従業員の社会保険料が改定され、新しい標準報酬月額が適用されます。
【6月〜7月】労働保険料
労働保険料の処理は、毎年一度の更新業務です。前年度の労働保険料を精算し、確定保険料を申告・納付します。
同時に新年度の概算保険料も申告・納付する必要があります。手続きは6月から7月に集中し、期限を守って正確に対応しなければなりません。
【会社の規定による】賞与
賞与の支払いは法定で義務化されていませんが、就業規則に記載がある場合は支払いが必要です。
多くの企業では夏季賞与と冬季賞与を支給しています。賞与を決定するためには、人事評価制度に基づく人事考課が必要です。
賞与支給月は会社ごとに異なりますが、一般的には6月〜8月と12月に支給されます。
【12月】年末調整
年末調整は毎年12月に実施する、年間の所得税を確定させる重要な業務です。従業員から扶養控除等(異動)申告書などを回収し、1年間の所得税を再計算します。
調整後は結果を給与に反映し、翌年1月までに源泉徴収票を作成して従業員に交付しなければなりません。年末調整はミスが許されない業務の一つです。スケジュールを立てて、慌てず準備を進めれば、スムーズに対応できます。
【人材開発・人材育成】人事の年間スケジュール
人材開発・人材育成も、年間を通じて多様なプログラムを進めるため、計画的に運用する必要があります。
ここでは、人材開発・人材育成担当者がおさえておきたい月別の業務を、年間スケジュールとして整理し紹介します。
| 月 | 主な人材開発・人材育成業務 |
|---|---|
| 1月 | ・次年度の人材育成計画の策定 ・新入社員研修の準備(カリキュラム、教材、講師の手配等) ・年間の研修効果の分析と改善点の抽出 |
| 2月 | ・新入社員研修の準備継続 ・階層別研修の年間計画策定 ・昇格者研修の準備 |
| 3月 | ・新入社員研修の最終準備 ・昇格者研修の実施(4月昇格者向け) ・年度末の研修実績のまとめ |
| 4月 | ・新入社員研修の実施 ・新任管理職研修の実施 ・年度始めの目標設定面談の支援 |
| 5月 | ・新入社員研修の継続(OJT含む) ・新入社員のフォローアップ面談 ・中途入社社員の教育プログラム実施 |
| 6月 | ・新入社員研修の評価と振り返り ・階層別研修の準備(中堅社員向け等) ・中途入社社員の教育プログラム継続 |
| 7月 | ・階層別研修の実施(中堅社員向け等) ・上半期の研修効果の中間評価 ・中途入社社員の教育プログラム継続 |
| 8月 | ・階層別研修の継続 ・次年度の研修予算の検討開始 ・中途入社社員の教育プログラム継続 |
| 9月 | ・上半期の研修効果の分析 ・下半期の研修計画の見直し ・昇格者研修の準備(10月昇格者向け) |
| 10月 | ・昇格者研修の実施(10月昇格者向け) ・階層別研修の実施(管理職向け等) ・次年度の研修計画の骨子作成 |
| 11月 | ・階層別研修の継続 ・年間の研修効果の測定準備 ・次年度の研修計画の詳細検討 |
| 12月 | ・年間の研修実績のまとめと効果測定 ・次年度の研修計画の確定 ・新入社員研修の基本設計 |
新入社員教育
新入社員教育は、1週間から2〜3か月程にわたって実施する研修です。会社の理念やルール、ビジネスマナー、業務知識などを体系的に教育します。
研修スケジュールは業務や行事と調整し、部署内の共有ツールで可視化すると計画的に進めやすくなるでしょう。
準備は入社の2〜3か月前から始め、カリキュラム策定、教材準備、講師手配を進めます。
配属後も定期面談や追加研修を行い、早期離職を防ぐため職場適応を支援します。研修の効果測定を行い、次年度の改善に活かすことも大切です。
中途社員教育
中途社員教育は、即戦力として活躍してもらうために行います。
中途入社者は職務経験がある一方で、自社文化や業務の理解が浅い場合も多いため、独自にカリキュラムを策定しなければなりません。
入社後3か月が定着のポイントで、この期間に十分なサポートを提供できるとよいでしょう。
本人の経歴やスキルを尊重しつつ、自社の業務フローや専門用語、ルールを重点的に学んでもらいます。
メンター制度やOJTを活用し、実務を通じて習得を促すと、早期戦力化と離職防止につながります。
階層別教育
階層別研修は、新入社員、中堅社員、管理職など役職やスキルに応じて必要な能力を育てる研修です。
実施の2〜3か月前から外部委託先やカリキュラムを検討し、教材や講師の準備を進めます。
階層別教育の主な内容例は、以下のとおりです。
- 新入社員向け:ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、業務基礎知識
- 中堅社員向け:リーダーシップ、問題解決力、プロジェクト管理
- 管理職向け:マネジメントスキル、評価者研修、戦略立案
階層別教育は、定期的に内容を見直し、組織の変化や課題に合わせて更新することが大切です。
昇格者教育
昇格者教育は、新たに役職に就いたリーダーやマネージャーが役割や責任を理解し、スムーズに移行できるよう支援する研修です。
多くの企業では4月や10月の昇格にあわせて実施します。昇格決定後に準備を進め、早期に研修を設定するとよいでしょう。
昇格者研修の主な内容例は、以下のとおりです。
- 新任リーダー向け:チームマネジメント、コーチング、フィードバック手法
- 新任管理職向け:部下育成、評価者研修、組織マネジメント
- 新任経営層向け:経営戦略、リスクマネジメント、変革リーダーシップ
研修後の面談や実践課題、先輩によるメンタリングを通じて、学びを実務に定着させることが重要です。
人事年間スケジュールを改善させるポイント
人事の年間スケジュールは、採用や労務管理、研修など幅広い業務を滞りなく進めるために必要です。
しかし、急な人員の入退社や法改正、組織変更など、予期せぬ変化に対応しながらスケジュールを整えるのは簡単ではありません。
多くの人事担当者が「いつも目の前の対応で手一杯」「計画どおりに進まない」と悩むこともあるでしょう。
ここでは、そんな状況を少しずつ改善するため、3つのポイントを解説します。
- スケジュール作成をする際の基準を設定する
- 柔軟に対応できるスケジューリングシステムを導入する
- 従業員への理解を高めてコミュニケーションの強化をはかる
スケジュール作成をする際の基準を設定する
人事の年間スケジュールを立てる際は、業務の優先順位や負荷を判断する基準を明確にすることが重要です。
まず、月次業務や年末調整、社会保険の算定基礎届など、定例業務と繁忙期を洗い出し、1年の流れを可視化します。
そのうえで、各業務の標準工数や担当者の負担を把握し、負荷が集中しないよう調整します。
業務の優先度や法改正などの基準を考慮し、あらかじめ余裕を持った無理のない年間スケジュールを立てましょう。
柔軟に対応できるスケジューリングシステムを導入する
人事スケジュールは一度作成すれば終わりではなく、法改正や経営方針の変化、予期せぬ人員の異動に応じて更新が必要です。
変化に対応するためには、情報を常に収集し、タイムリーに反映できる体制が求められます。システムの活用も効果的です。
クラウド型のスケジューリングツールや人事管理システムを導入すれば、データを一元管理し、変更履歴を共有できます。
従業員への理解を高めてコミュニケーションの強化をはかる
人事の年間スケジュールを円滑に運用するには、従業員が内容を理解し、自分の役割を正しく認識することが欠かせません。
スケジュールを共有するだけでなく、わかりやすい資料や説明会を通じて理解を促すことが大切です。
さらに、定期的な面談やミーティングで意見や疑問を吸い上げ、改善に反映する仕組みを整備しましょう。
スケジュール変更時は影響範囲や理由を明確に伝え、透明性を高めることで信頼関係が構築されていきます。双方向のコミュニケーションが、働きやすい環境づくりにつながります。
まとめ|人事の年間スケジュールを把握して計画的に業務遂行
人事年間スケジュールは、採用、給与計算、社会保険手続き、人材育成など多岐にわたる業務を計画的に進めるために重要です。
とくに法定期限のある手続きは、期限を守らなければ罰則を受けるケースもあります。
業務を効率的に進めるためには、年間を通じた全体像を把握し、計画を立てて管理しなければなりません。
人事の年間スケジュールを適切に管理することで、業務の平準化や抜け漏れの防止、関係部署との円滑な連携が可能です。
作成したスケジュールは継続的に見直して改善することで、業務効率化が進み、より柔軟な人事運営が実現できるでしょう。
人事労務の効率化を支援するシステム「One人事」
人事業務の効率化と高度化を実現するには、適切なシステムの活用をおすすめします。
「One人事」は、労務管理・勤怠管理・給与計算・タレントマネジメントまで、人事業務をワンストップで支援する人事労務システムです。
多くの企業が人事DXを進めるなか、人事情報を複数のシステムで管理しており、データの分散や連携が課題となっています。
「One人事」はこうした課題を解消し、人事情報の一元化と業務の効率化を実現します。
作成した人事の年間スケジュールを確実にやりきるためにも、システムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
詳しい活用例は当サイトより、お気軽にご相談ください。専任スタッフが課題の整理からお手伝いします。
当サイトでは、人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。人事労務をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
