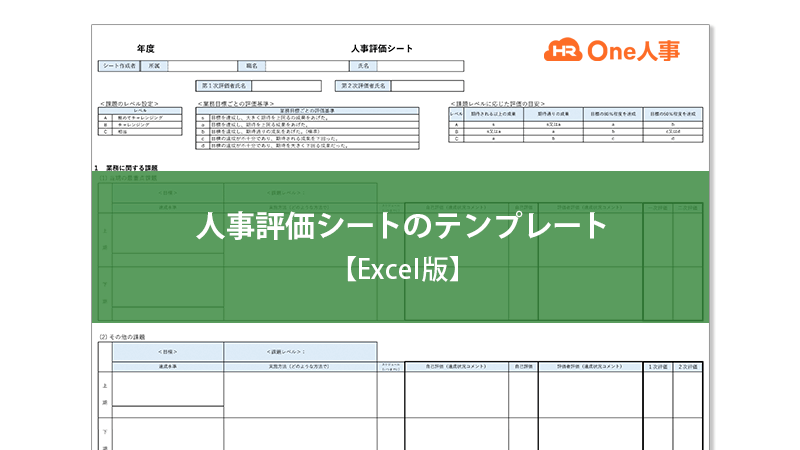人事評価制度の事例【5選】|トレンドや運用方法、不服申し立ても解説

人事評価制度の納得感が低ければ、モチベーションが下がり、優秀な人材ほど早く離れていってしまいます。
本記事では、人事評価制度の事例や主な人事評価制度の概要を紹介します。他社の成功事例を参考に、自社の人事評価制度の導入や見直しにお役立てください。
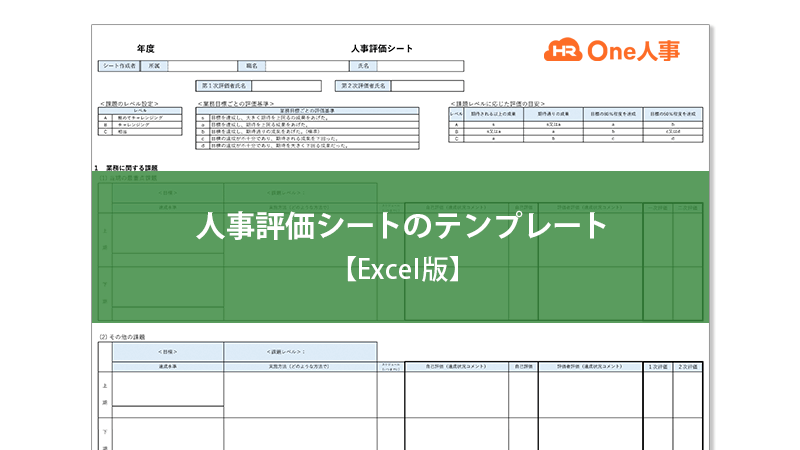
 目次[表示]
目次[表示]
人事評価制度の事例
人事評価制度を見直したい・導入したいと考えるご担当者に向けて、他社が成功した制度の導入事例を5つご紹介します。
人事評価制度は、業種や規模によって適切な設計や運用方法が異なるものです。ここでは、制度の設計意図・工夫・社内での浸透方法に注目して紹介していきます。
カゴメ株式会社
カゴメ株式会社では、人事評価に目標管理制度を取り入れています。期初に上司と部下が話し合って目標を設定し、達成度を期末に評価する仕組みです。単に成果を確認するだけでなく、達成度をもとに次に取り組む課題や、今後の育成方針についても対話を重ねるのが特徴です。
さらに同社は、人事評価の運用実態を調査し、結果を社内に公開しています。すべての社員が他部署の目標を閲覧できるなど、制度の透明性が高く、組織全体の方向性を理解しやすくなっています。また従業員が自分のキャリアの参考にすることも可能です。
株式会社富士通
株式会社富士通は、企業や個人のパーパス(存在意義)、および自社の行動規範である「Fujitsu Way」の実現を目指しています。取り組みの一環として、パーパスと連動した新たな人事評価制度「Connect」の運用を開始しました。
「Connect」は、企業や個人それぞれのパーパスを結びつけ、一貫性を重視した評価制度です。同制度では、パーパスを起点として、会社への貢献度や成長度を評価する仕組みが特徴となっています。
参照:『Financial Well-being』株式会社富士通
参照:『共感・信頼をベースとしたマネジメントへ、富士通が実践する新たな評価制度とは – フジトラニュース』株式会社富士通
株式会社丸井グループ
株式会社丸井グループでは、複数の制度を組み合わせて人事評価を運用しています。中心となるのは、「パフォーマンス評価」と「バリュー評価」の2つです。
パフォーマンス評価はチーム単位の実績を対象とし、バリュー評価は経営理念に基づいた主体的な行動や成長を促進するために採用されています。バリュー評価では、チーム内の360度評価の結果を踏まえたうえで評価会議を実施し、最終的な個人の評価が決定されます。
また、すべての社員の成長を支える取り組みとして、四半期ごとの進捗確認と、半期ごとのフィードバックを上司との対話で実施。全社的に対話を重ね、課題を明確にし、気づきや学びにつなげています。
株式会社花王
株式会社花王は、人事評価制度として独自のOKR評価を運用しています。同社のOKRは、夢や理想に近づくために、あえて高い目標を設定するのが特徴です。
従業員がそれぞれ職種や業務に応じた目標のもと、プロセスや成果を設定します。ありたい姿を思い描きながら挑戦的な目標を立てるため、たとえ達成率が6割にとどまっても、評価では問題とされません。
さらに同社では新たな評価制度として「チャレンジ評価制度」も取り入れました。従業員が、自分の理想に向けて努力した内容や、プロセスなどを評価するものです。チャレンジ評価制度は、個人だけでなく、組織全体の成長を促す制度として期待されています。
KDDI株式会社
KDDI株式会社では、ジョブ型人事制度のもと、人事評価を「成果の最大化」と「個人の能力開発」の両面から運用しています。評価制度は目的に応じて複数組み合わせており、以下の3つが中心です。
| 評価制度 | 目的 | 手法 |
|---|---|---|
| 成果・挑戦評価 | 過去の結果や挑戦する姿勢を評価 | グレード標準に対する評価 |
| 能力評価 | 現在の能力に対する評価(課題解決・コミュニケーション・専門性) | 360度評価と上司評価 |
| 人財レビュー | 未来への期待を予測するための評価 | 成果・挑戦評価と能力評価の掛け合わせ |
成果・挑戦評価と能力評価の結果は、自動的にグラフ化され、可視化されています。同社の特徴は、評価目的に応じた制度を柔軟に組み合わせて活用している点にあります。
参照:『環境・制度を知る KDDI版ジョブ型人事制度』KDDI株式会社
多くの企業で導入されている人事評価制度
ここまで各社の独自性ある人事評価事例を紹介してきました。では「自社に導入するには、どの制度をベースにすべきか」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
そこで主な人事評価制度を一覧表で紹介します。特徴を理解し、制度の目的や評価したい観点に照らして比較してみてください。
| 人事評価制度の種類 | 特徴 |
|---|---|
| MBO(目標管理制度) | ・企業が設定した目標に基づき、従業員がみずからの目標を設定 ・目標に対する達成度や成果を1年の終わりに評価 |
| 360度評価 | ・被評価者の上司や部下、同僚などが評価 ・多角的な角度から評価が可能 |
| コンピテンシー評価 | ・成果を出している従業員や理想像(コンピテンシーモデル)に基づいて評価 ・評価基準の明確化が可能 |
| バリュー評価 | ・企業の「価値観や行動基準(=バリュー)」を実践できているか評価 ・「成果」「能力」「情意」の3軸が基準 |
| OKR | ・定性目標であるO(Objectives)と定量目標のKR(Key Results)を設定・高い頻度で進捗確認と評価を実施。 ・60〜70%の達成を目指す |
人事評価制度には、企業規模や組織風土に応じて合う・合わないがあります。まずは代表的な評価制度の種類と特徴を整理し、自社にマッチする評価軸を見極めることが重要です。
人事評価制度の運用方法
評価事例を参考に制度を設計しても、どのように運用すればよいかわからないという担当者もいるのではないでしょうか。人事評価を新たに導入した場合、現場に浸透せず、従業員の納得が得られなかったという失敗例も少なくありません。
基本的な人事評価制度の運用方法を紹介します。
- 最適な人事評価制度の検討と導入
- 目的や目標の確認
- 評価基準の決定
- 評価手法の決定
- 社内周知
制度を形骸化させないためには、「制度をどう使い、どう改善し続けるか」という視点が欠かせません。以下では、制度の導入から実運用までの流れと、それぞれの段階で注意したいポイントを解説します。
最適な人事評価制度の検討と導入
まず自社にとって最適な最適な制度を検討することから始めます。人事評価制度の導入は、人事部だけで進めず、経営層とも連携しながら進めましょう。また、一度に全社導入するのではなく、導入の初期段階では、初めは一部の部署や小さな単位から試験的に運用を始めることをおすすめします。
目的の明確化と確認
新たな人事評価制度の導入目的を明確にします。大きな目的を設定したうえで、具体的な課題や目的を細かく分解していきます。大きな目的から段階的に整理することで、制度設計の軸がぶれることなく、目的を共有しやすくなります。
評価基準の決定
評価基準は、一律で設定するのではなく、役職や職種ごとに決定しましょう。評価の公平性を保つためには、細やかな評価基準を設定することが大切です。
また、評価と報酬(給与や賞与など)を連動させることで、従業員の納得感とモチベーションを高められます。形だけの制度に終わらせないために、評価と処遇の関係性はていねいに設計しましょう。
評価手法の決定
評価基準を定めたあとは、それをどのような手法で評価するかを検討する必要があります。評価手法は大きく「能力」「業績(成果)」「行動」の3つに分類されます。人事評価制度の導入目的をふまえ、自社がどの価値観を重視して運用するのかを明確にしましょう。評価手法は、企業の人材観や組織文化が反映されやすい要素であるため、慎重に決定することが大切です。
社内周知
人事評価制度の運用準備が整ったら、社内全体に対して周知し、理解を促します。運用開始後も、実際の運用状況を見ながら定期的に振り返り、改善して徐々に制度を構築していきましょう。
人事評価制度に対する不服申し立て
人事評価に対する納得感が低いと、従業員から不服申し立てを受ける可能性があります。とくに以下のようなケースは、不服申し立ての原因となりやすいため注意が必要です。
- 公平な評価が行われていない
- 評価に納得感がない
- 評価と給与が見合っていない
以下では、実際に起こりがちなケースとあわせて、企業側が改善したい点について解説します。
公平な評価が行われていない
人事評価に対する不服申し立ては、従業員が「公平な評価が行われていない」と感じることで起こる可能性があります。
たとえば、男性と女性で評価を変える、飲み会への参加率など業務と無関係な点を評価に反映させるといったケースです。
評価者に差別意識が働いていたり、業務とは無関係な要素が加味されていたりすることが明白であれば、すぐに是正したいところです。人事評価の不公正さは、不服申し立てにつながる大きな要因になることを企業は理解しておく必要があります。
評価に納得感がない
従業員の成果に対する評価が不当に低い場合も、トラブルにつながるおそれがあります。
たとえば、目標を達成していたり、同僚よりも明らかに成果を上げていたりするにもかかわらず、評価が低い場合です。
企業は、人事評価制度の評価基準の周知を徹底するとともに、従業員への評価について、いつでも説明できるようにしておきましょう。
評価と給与が見合っていない
人事評価で高評価を受けているのに給与が変わらない場合、従業員が不満を抱き、不服申し立てにつながる可能性があります。
一般的に給与は社内のルールに基づいて決まります。人事評価と給与の関係性については、あらかじめ従業員に説明しておくと不満の原因になりにくいです。
もし評価と給与が連動する制度であるにもかかわらず、正当な給与が支払われていないと判明した場合は、企業は迅速に対応しなければなりません。
注目されているトレンドの評価制度
人事評価制度は多様化しており、従来の枠組みにとらわれない新しい評価にも注目が集まっています。
人事評価の課題背景には、制度そのものの設計思想が今の働き方や価値観にそぐわなくなっている可能性があります。場合によっては新たな発想や切り口によるものが必要です。
ここでは、課題に向き合う企業が取り入れている、注目のトレンド評価制度を紹介します。評価に対する柔軟なアプローチとして、自社にも活かせるヒントがあるかもしれません。
ノーレイティング
ノーレイティングとは、一般的な人事評価制度の等級のようなランクづけをしない制度です。半期一度の評価面談の代わりに、日々の1on1や目標設定をとおして従業員を評価します。
上司と部下が密にコミュニケーションを取ることで、本人に適した目標が設定しやすくなり、評価に対する納得感も高まりやすいとされています。従業員の主体性や成長を引き出せる点もメリットといえるでしょう。
チェックイン
チェックインとは、従業員と管理職である上司が、頻繁に面談を重ねるなかで評価を行う人事制度です。
面談の都度、上司は部下にフィードバックを行うため、従業員は課題の認識やモチベーションの向上につなげることができます。双方向によるコミュニケーションの機会は、上司と部下の信頼関係を深める効果も期待できます。
パフォーマンス・デベロップメント
パフォーマンス・デベロップメントは、従業員の成長度に着目して評価する制度です。 業績や成果ではなく、どれだけ成長しているかに評価の軸を置く点が特徴です。
評価する上司は、成果の有無ではなく、本人の成長を支援するマネジメントの姿勢が求められます。ただし、あくまでも成長度のみを評価するパフォーマンス・デベロップメントは、成果や業績にはつながりにくい点がデメリットです。ほかの評価制度と組み合わせて導入するのがよいでしょう。
まとめ
人事評価制度は、企業が目指す方向性や価値観にあったものを選ぶことが重要です。制度を見直すときは、他社の事例を参考にしながら、自社に最適な仕組みを考えていきましょう。
本記事で紹介した事例にもあるように、企業によっては複数の評価制度を組みあわせて運用しています。注目されている新しい評価制度にも目を向けて視野を広げ、まずは自社にふさわしい制度を見つけていきましょう。
人事評価制度の運用に|One人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、従業員一人ひとりの基本情報と、過去の評価歴や1on1ミーティングの記録などを紐づけて一元管理するタレントマネジメントシステムです。
自社の評価制度の運用にもお役立ていただけるため、評価業務の効率化も実現できます。
システムを活用し、人事評価を透明性高く運用することで、納得感のある運用につなげられるでしょう。振り返りを促す仕組みをつくれるため、人材育成にも効果が期待できます。
One人事[タレントマネジメント]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事評価の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。人事評価をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |