育児休業給付金は延長できる? 2025年4月〜厳格化した手続きのポイントと必要書類も解説
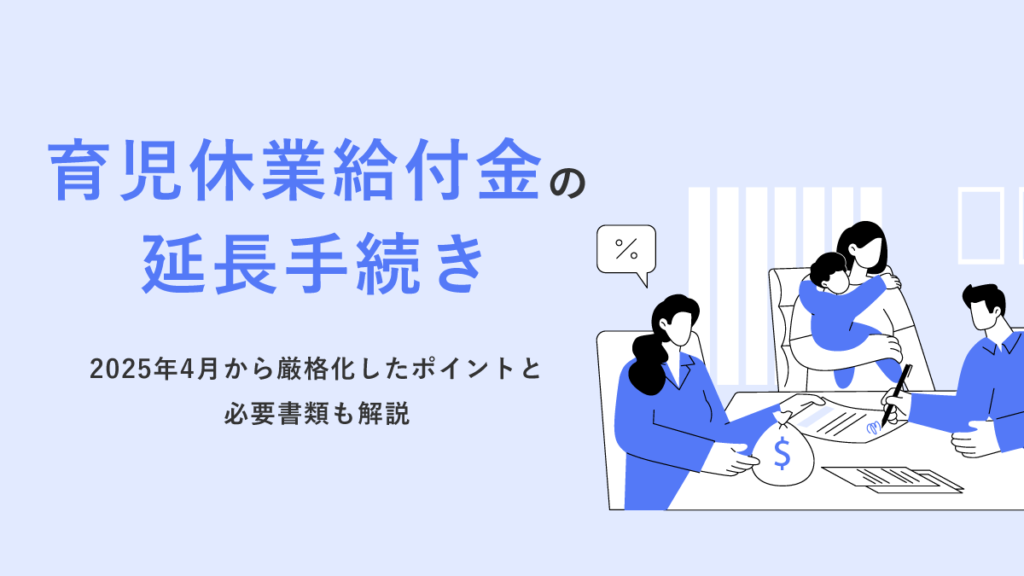
育児休業を延長する従業員は、一定の条件を満たせば 育児休業給付金の延長受給が可能です。しかし、厳格化により今までと同じ方法では認められないケースが出てくる可能性があります。
企業の人事労務担当者は、 育児休業給付金の延長条件や、厳格化される手続きを従業員に正しく案内する必要があります。
本記事では、 育児休業給付金の延長要件や手続きの流れ、2025年4月からの変更点と必要書類について詳しく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
育児休業給付金の受給期間は延長できる
育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまで(※)支給されます。ただし、一定の条件を満たせば最長2歳まで延長が認められます。
そもそも育児休業とは、子どもが1歳になるまで仕事を休める制度です。そして育児休業給付金とは、育休中の収入減少を補う目的で国が支給する手当です。
つまり、育児休業を延長するのであれば、育児休業給付金の受給期間も延長されます。
延長の理由によって必要書類は異なり、申請時に適切な手続きを行う必要があります。
(※)誕生日の前々日まで

2025年4月以降、育児休業給付金の延長基準が厳格化
2025年4月から、育児休業給付金の延長申請には、より厳格な審査が求められることになりました。
具体的には、「保育所等に入園できないこと」を理由とする延長申請に対して、新たな提出書類が追加されています。
以前の延長手続き
育児休業を延長する場合、以前は自治体が発行する「入所保留通知書」のみで、入所・入園できないことの確認をしていました。
延長基準厳格化の背景として、保育所に入る意思がないのに申し込むケースや、入園決定に対するクレームが問題があります。
また、育児休業の取得者のなかには、本心では「子どもを家庭で養育する期間を延ばしたい」 という理由から延長を希望するケースもありました。
「入所保留通知書」のみでは、本当に保育所の受け入れができなかったのかを判断しにくいという課題があったのです。
2025年4月以降の延長手続き
以前の課題に対応するため、2025年4月以降、保育所等に入園できないことを理由とする育児休業給付金の延長には、新たな書類の提出が必要となりました。
新たに加わった書類は以下のとおりです。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の申し込みを行った際の申込書のコピー
また、保育所の利用申し込みの際に、「入所保留」を希望する意思表示がないことも、審査の対象となります。
2つの書類が提出されることで、実際に保育所へ申し込んでいたにもかかわらず、入園できなかったことの確実な証明になります。

育児休業給付金を延長できる条件と期間
育児休業の延長は、特別な事情がなければ認められません。
人事労務担当者は、従業員から相談を受けた際に、延長条件や必要な書類について適切に説明できるようにしておく必要があります。
育児休業給付金を延長できる条件と期間について解説します。
休業延長が認められる特別な事情
育児休業の延長が認められるのは、まず大前提として、子どもの1歳の誕生日の前日に、労働者本人または配偶者が育児休業を利用して休んでいることが条件です。
そのうえで、以下のような特別な事情がある場合に延長が認められます。
| 保育所に入所できなかった場合 | 保育所の申請に落ちてしまった |
|---|---|
| 配偶者が育児を担当できなくなった場合 | 配偶者の病気・死亡・負傷・離婚などで育児ができない |
| 育児休業中に次の子どもを妊娠・出産した場合 | 継続して育児が必要 |
以上のような理由がある場合に、育児休業が1歳6か月または2歳まで延長が可能です。
延長手続きの必要書類
育児休業給付金の延長手続きでは、まず育児休業給付金支給申請書を準備します。そして延長理由に応じて以下の書類を提出する必要があります。
保育所に入所できなかった場合
- 市町村発行の「入所保留通知書」(当面保育ができないことを証明)
- 市区町村の保育所申し込み時の申込書コピー(申し込みを行った証明)
配偶者が育児を担当できなくなった場合
- 世帯全員の住民票の写し
- 医師の診断書・死亡診断書・離婚証明書など(状況を証明できる書類)
育児休業中に次の子どもを妊娠・出産した場合
- 母子健康手帳の写し(出産予定日・出産後の状況を証明)
提出書類はケースによって異なるため、不安な場合は事前にハローワークに問い合わせてみましょう。
育児休業給付金を延長できる期間
育児休業給付金の延長期間は、通常の育児休業の延長と 「パパ・ママ育休プラス」制度を利用した延長の2つの方法が考えられます。
| 育児休業給付金の延長を行うパターン | 時期 |
|---|---|
| 通常の育児休業を延長する場合 | 子どもが1歳6か月(または2歳)になるまで |
| パパ・ママ育休プラスにより延長する場合 | 子どもが1歳2か月になるまで |
パパ・ママ育休プラスは、育児休業取得率の向上を目的として、子どもが1歳2か月になるまで育児休業を取得できる制度です。子どもの母親と父親の両方が育児休業を取得することなどを条件とし、あとから育児休業を取得した方が制度を利用できます。
注意したい点は、パパ・ママ育休プラスでは、あくまでも育児休業の取得期限を延長するための制度であることです。
育児休業の取得期間は原則として1年間であり、パパ・ママ育休プラスを利用したとしても1年間という期間は超えられません。
育児休業の延長が認められないケース
育児休業の延長は、すべての申請が認められるわけではありません。
たとえば「育児休業の延長が必要であることを証明する書類」を、期限内に提出できない場合は当然ながら許可がおりないでしょう。
また、保育所へ入園できなかったとしても、以下のような場合は育児休業の延長は認められません。
- 無認可保育所のみに申し込んでいる
- 保育所の入園申込日が1歳の誕生日以降である
- 保育所の利用開始日が1歳の誕生日の翌日以降である
- 保育所等の入園を申し込んでいない
保育所の種類には、大きく分けて無認可保育所と認可保育所の2種類があります。無認可保育所のみに入所申し込みをしただけの状態では、認可保育所に入れた可能性もあるため、育児休業の延長は認められません。
また、保育園等に入所できる可能性が低くても、保育所の利用には申し込む必要があります。
育児休業を延長したい従業員は、市区町村の担当者などから「途中入園は難しい」「今後も入園できない可能性が高い」と言われたとしても、申し込みだけは行いましょう。
育児休業給付金の受給を延長した際の計算方法
育児休業給付金の受給期間を延長した場合も、金額の計算方法は通常と同様です。
| 育児休業給付金=休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%(給付率) |
育児休業給付金の延長時において注意したい点は、給付率です。
育児休業給付金は、育児休業取得開始日からの経過日数によって給付率が異なります。
本来、育児休業取得開始から180日目までは67%、181日目以降は50%の給付率で計算しなければなりません。
「給付金が減額された」などと誤解されないように、経過期間によって、給付率が変わることについて説明しておきましょう。
育児休業給付金の延長に関するデータ
育児休業給付金の延長について、厚生労働省の『令和5年雇用均等基本調査』のデータを紹介します。
本調査では、令和5年度において実際に1年以上の育児休業を取得した人の割合が、男女別に以下のように報告されています。
| 女性 | 男性 | |
|---|---|---|
| 12か月から18か月未満 | 32.7% | 1.4% |
| 18か月から24か月未満 | 9.3% | 0.2% |
| 24か月から36か月未満 | 3.0% | 0.0% |
女性の4割以上が、本来の育児休業期間である1年を超えて取得している結果です。一方で、男性の育児休業取得は1年以上になるケースがほとんどないことも特徴です。
4割という数字から、1年以上の期間で育児休業を取得している人は決して少なくないことがわかります。
育児休業延長における基準厳格化にともない、育児休業の延長手続きが少し複雑になります。担当者は従業員から質問や相談を受ける可能性を踏まえ、制度を正しく理解しておきましょう。
参照:『「令和5年度雇用均等基本調査」の結果概要』厚生労働省
まとめ
育児休業給付金は、保育所に入れない場合や、配偶者の病気・死亡などの特別な事情がある場合に限り、最長2歳まで延長が可能です。
2025年4月以降の延長審査において、保育所等に入園できない理由による申請では、審査基準が厳格化されます。
追加の提出書類が必要になるため、最新情報を確認したうえで、適切な対応を心がけましょう。
育児休業における労務管理も効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、企業における人事労務業務を効率化できるクラウドシステムです。育児休業に関する各種手続きや管理業務の効率化にお役立ていただけます。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
