雇用契約書と労働条件通知書の違い【比較表】兼用できる? 必要なのはどちら? 何のため?
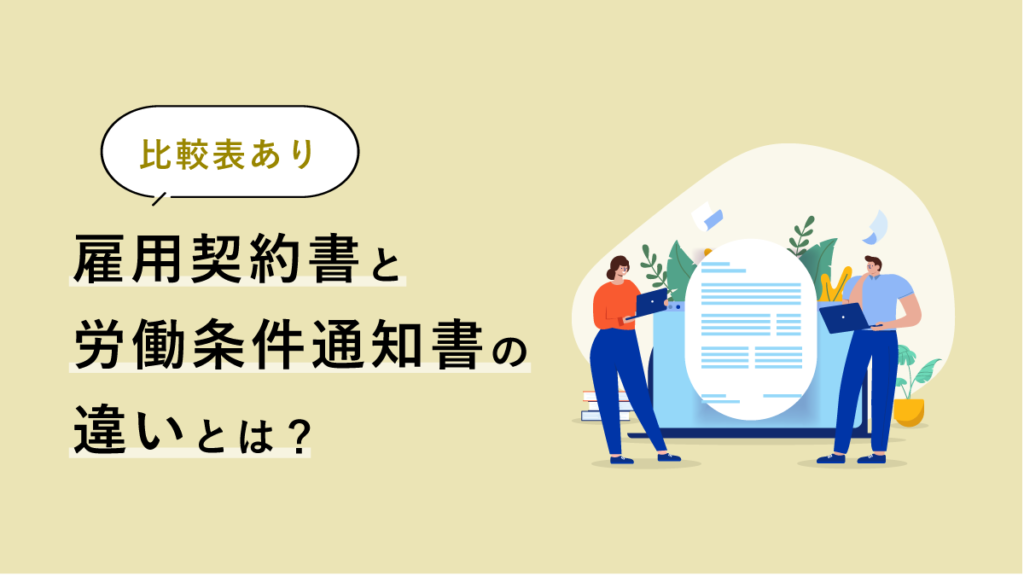
雇用契約書と労働条件通知書は、使用者と労働者が雇用契約を結ぶうえで重要な文書です。両者は記載内容が似通っており混同されやすいですが、それぞれ役割や作成目的が異なります。
本記事では、雇用契約書と労働条件通知書の違いや必要性、兼用について解説します。人事労務に携わる担当者は、ぜひお役立てください。
 目次[表示]
目次[表示]
雇用契約書と労働条件通知書について
まずは雇用契約書と労働条件通知書が、それぞれどのような書類なのかを解説します。
雇用契約書の作成は任意
雇用契約書とは、使用者(企業)側と労働者(従業員)側が、労働条件に合意したことを証明する書類です。賃金や業務内容、就業場所などの労働条件にまつわる重要事項を明記し、企業と従業員がそれぞれ記載された内容について合意したことを証明します。
雇用契約書は、雇用後のトラブルを防ぐために重要な書類ですが、法的な作成義務はありません。そのため、企業によっては作成しない場合もあるでしょう。
労働条件通知書の作成は義務
労働条件通知書とは、賃金や就業場所といった労働条件の重要事項を、企業から従業員に通知する書類です。労働基準法第15条1項によって、企業は労働契約を結ぶ際、従業員に対して労働条件を明示しなければならないと定められています。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
引用:『労働基準法 第15条』e-Gov法令検索
第15条1項の規定に基づいて作成を義務づけられているのが、労働条件通知書です。企業は、正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、雇用するすべての従業員に労働条件通知書を発行しなければなりません。
雇用契約書と労働条件通知書の違い【比較表】
雇用契約書と労働条件通知書の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 雇用契約書 | 労働条件通知書 | |
|---|---|---|
| 適用される法律 | 民法 | ・労働基準法 ・パートタイム労働法 |
| 法的な作成義務 | なし | あり(労働基準法第15条1項) |
| 記載内容のルール | 法的な定めはない | 法的な定めがある |
| 締結・交付の方法 | 企業と従業員の合意により締結 | 企業から従業員に対して 一方的に交付 |
| 署名・捺印 | 双方で署名・捺印することが一般的 | 企業の署名・捺印があっても、従業員の署名・捺印はないことが一般的 |
締結・交付の | 法的なルールはない。内定日や入社日などが一般的 | 法律で「雇用契約を締結するとき」と定められている(内定日が一般的) |
雇用契約書と労働条件通知書のもっとも大きな違いは、法的な作成義務の有無です。雇用契約書には法的な作成義務がないのに対し、労働条件通知書は労働基準法で作成が義務づけられています。
また、労働条件通知書は記載内容についても一定のルールがあり、交付のタイミングも「雇用契約を締結するとき」と定められています。
雇用契約書の作成は任意ではあるものの、労働条件に関する合意を証明する大切な書類です。そのため、書類には署名・捺印欄を設け、企業と従業員双方が署名捺印することが一般的です。
任意でも雇用契約書の作成が勧められる理由
雇用契約書の作成は任意ですが、基本的には作成する方が無難といえます。
労働条件通知書は企業から従業員へ一方的に交付されるのに対し、雇用契約書は企業と従業員がそれぞれ内容を確認して、合意のうえで作成されます。
そのため、従業員と労働条件についてトラブルになった際、労働条件通知書だけでは「そんな条件は聞いていない」と言い張られてしまう可能性も否定できません。雇用契約書があれば双方が労働条件に合意したことを証明できます。
双方が合意した内容を書面に残すことで「言った・言わない」の水掛け論を防げます。トラブルを回避するためにも、雇用契約書は労働条件通知書とあわせて作成するとよいでしょう。
雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる
雇用契約書と労働条件通知書は共通する記載項目が多く、兼用することも可能です。2つの文書を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」として発行すると、作成の手間を軽減できます。
ただし、多くの記載項目を1つの書類にまとめようとすると、文書量が多くなりすぎてしまうこともあるでしょう。多くの内容を盛り込む必要がある場合は、それぞれ分けて作成するのも一つの方法です。
「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行するタイミング
「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行するタイミングは、労働基準法で定められている労働条件通知書のルールに従う必要があります。
労働基準法第15条1項では「労働条件の通知は、労働契約の締結に際して行う」と定められています。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
引用:『労働基準法 第15条』e-Gov法令検索
「際し」という表現には「するにあたって」という意味合いが含まれているため、実際に契約を締結するよりも前に交付するのが一般的です。
多くの企業では、求職者に内定を出す際に労働条件を通知し、内容を確認してもらってから雇用契約を結ぶという流れになるようです。
「労働条件通知書兼雇用契約書」の記載内容
「労働条件通知書兼雇用契約書」には、法律で定められた「絶対的明示事項」と、企業が制度として定めている場合に必要な「相対的明示事項」の2種類があります。
それぞれの項目は以下のとおりです。
| 絶対的明示事項 | ・労働契約期間 ・労働契約期間の定めがある場合、更新の方法や基準に関する事項 ・就業場所に関する事項 ・業務内容に関する事項 ・始業・終業時刻 ・所定労働時間を超える労働の有無 ・休憩時間 ・休日や休暇に関する事項 ・シフト制を導入する場合、就業時転換に関する事項 ・賃金の決定方法や支払い方法 ・時期などに関する事項 ・退職に関する事項(解雇の事由含む) ・昇給に関する事項 ・就業場所や業務内容について変更される可能性のある範囲※ ・契約期間や更新回数の上限の有無と理由※ ・無期雇用転換申込権に関する説明と、転換後の労働条件※ |
|---|---|
| 相対的明示事項 | ・退職手当に関する事項 ・臨時に支払われる賃金や賞与、各種手当、最低賃金額に関する事項 ・安全衛生に関する事項 ・職業訓練に関する事項 ・災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項 ・表彰や制裁に関する事項 ・休職に関する事項 |
(※)2024年4月の労働基準法改正により追加
昇給に関する事項や相対的明示事項については口頭で伝えても問題ないとされていますが、トラブルを回避するために、なるべく書面で通知するとよいでしょう。
パート・アルバイトは4項目多い
パートやアルバイトの従業員に対しては、上記の項目に加えて以下の4つの事項を明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職手当の有無
- 相談窓口
参考:『2024年4月からの労働条件明示ルールの変更 備えは大丈夫ですか?』厚生労働省
参考:『令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます』厚生労働省
参考:『労働基準法の基礎知識』厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:『パートタイム労働法のあらまし』厚生労働省
雇用契約書と労働条件通知書を兼用する場合の注意点
雇用契約書と労働条件通知書を兼用する場合は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
- 明示事項を不足なく記載する
- 雇用形態に応じて記載事項を追加する
- 電子通知には条件がある
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
明示事項を不足なく記載する
雇用契約書や労働条件通知書には、労働者に明示すべき事項をもれなく記載することが大切です。必ず記載が必要な絶対的明示事項はもちろんのこと、自社の制度に合わせて必要な相対的明示事項も網羅する必要があります。
明示事項の抜けもれが心配なら、信頼できる発行元が公開するテンプレートを活用するとよいでしょう。たとえば、厚生労働省の公式ホームページでは、労働条件通知書のテンプレートが公開されています。
参照:『一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型)』厚生労働省
雇用形態に応じて記載事項を追加する
従業員に対して明示すべき事項は、雇用形態によっても異なります。たとえば、パートやアルバイトに対しては、基本事項に加えて昇給や賞与の有無、相談窓口などを明示しなければなりません。
また、法律上の定めはなくとも、雇用形態ごとの就業実態に応じた事項を盛り込むことが大切です。たとえば、正社員に転勤を命じることがあるなら、転勤の有無についても記載します。
電子化には条件がある
2019年より、労働条件通知書や「労働条件通知書兼雇用契約書」を、電子的方法で通知することが認められるようになりました。
ただし、2つの書類を電子化するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 従業員が電子的方法による通知を希望している
- 従業員本人のみが確認できる状態で交付する
- プリントアウトできる形式で交付する
雇用契約書と労働条件通知書を兼用によりトラブル回避を
雇用契約書と労働条件通知書の大きな違いは、適用法や作成義務の有無です。
雇用契約書の作成は任意、労働条件通知書の作成は義務ですが、1つにまとめて「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付することもできます。兼用により、書類の作成にかかる手間やコストを抑えつつ、従業員とのトラブルに備えられます。
法律で定められた絶対的明示事項や、会社ごとの相対的明示事項を不足なく記載し、労働条件に関するトラブルを未然に防ぎましょう。
雇用契約書や労働条件通知書を電子化するなら?
労働基準法施行規則の改正により、2019年4月以降は電子的方法による労働条件の明示が認められています。メールやFAXのほか、SNSを使った労働条件の明示も可能です。
雇用契約書については、もともと法的な定めはないため、インターネットを使ってオンライン契約を締結しても問題ありません。
紙面での明示から電子的方法に切り替えれば、印刷代や用紙代、郵送代などのコスト削減につながります。契約締結や書類交付をオンライン上で進められるため、業務の効率化も目指せるでしょう。発行した書類は電子データとして残り、交付後の管理や見直しも容易です。
雇用契約書や労働条件通知書を電子化するなら、雇用手続きに対応したシステムの導入をおすすめします。雇用手続きに関する情報を一元管理したり、対象者に書類を一括で交付したりできるため、業務負担の軽減につながります。
「雇用手続きの電子化を進め、手続きを簡略化したい」という方は、検討してみてはいかがでしょうか。
雇用手続きの電子化に|One人事[労務]
One人事[労務]は、煩雑な労務管理をクラウド上で完結させる労務管理システムです。
- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い
- 【年末調整】記入もれ・修正の対応に追われている
- 【退職手続き】離職証明書の作成が面倒
という悩みがある担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
