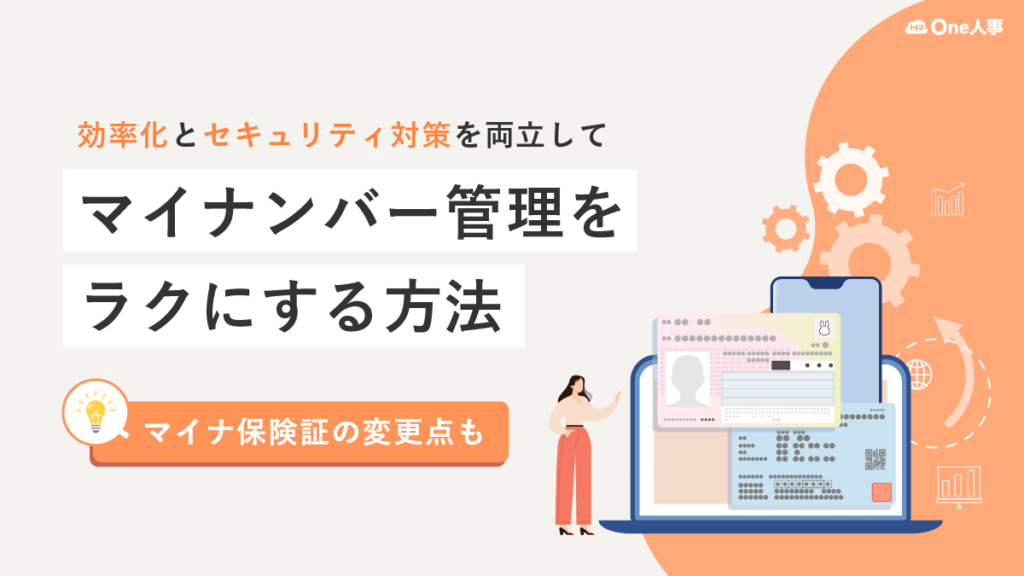マイナンバーをクラウドで安全に管理するには? 委託リスクと注意点、サービスの選び方を解説

マイナンバー管理のクラウド化が注目される理由
マイナンバーの管理は、従業員のマイナンバーを収集・保管・利用・破棄までの一連の業務です。
個人情報であるマイナンバーは情報が外部に漏れたり、不適切に使用されたりしないように厳重な管理が求められています。情報漏えいが起こると、法的な罰則を受けるおそれがあり、社会的な信用も低下しかねません。
マイナンバー管理をクラウド上で行う場合、十分な安全性が確保できるのか、不安に感じる方もいますよね。一方で、紙の管理では、次のような課題がありました。
- 物理的な保管場所が必要で、管理コストがかかる
- アクセス管理が難しく、情報漏えいのリスクが高い
- 制度改正時に運用を変更するのが大変
以上の課題を解決する手段として、クラウド管理が注目されています。はじめに企業がマイナンバー管理においてクラウドを選択する理由を紹介します。
業務効率化につながるため
マイナンバー管理をクラウド化するメリットの1つに、業務効率化が挙げられます。
紙やファイルなどでマイナンバーを管理する場合は、印刷や保管の手間がかかるだけでなく、人的ミスも発生しやすくなるでしょう。クラウド上であれば、従業員情報の収集はもちろん、保管や利用、退職者の情報破棄までまとめて管理できます。
また、自動バックアップにより手間なくデータ保全ができ、クラウド上でメッセージを送受信することも可能です。給与管理システムと連携することで、源泉徴収票へのマイナンバー表示もスムーズに行えます。
マイナンバーのクラウド化は、人事担当者の業務効率を大きく向上させるでしょう。
安全管理の負担を減らせるため
情報漏えいやデータ紛失を防ぐため、マイナンバーのクラウド管理には「安全対策」が標準で装備されているのも大きなメリットです。
紙媒体で管理する場合は、アクセス制限やログ管理といった対策が難しく、外部に持ち運びやすいため、常に不正持ち出しや紛失のリスクがあります。
しかし、クラウド上でマイナンバーを管理すれば、アクセス権限を細かく設定したり、誰がいつアクセスしたかを記録できたり、セキュリティを強化できます。
「クラウドは不安」と思う方もいるかもしれませんが、適切なサービスを選べば、じつはアナログな管理方法よりも安全に運用できるのです。
法改正への対応が早いため
マイナンバーの使用範囲は年々広がり、身分証や健康保険証として、あるいは公的な証明書を取得するために活用されています。今後も幅広い活用方法が見込まれていますが、制度や法律の改正があれば、そのたびに新たなルールに応じて対応を変えなければなりません。
クラウドでマイナンバーを管理するシステムを導入すれば、自動的にアップデートが行われることが多く、法改正にも素早く対応が可能です。
参照:『マイナンバーカードでできること』マイナンバーカード総合サイト
低コストで運用できるため
クラウドでマイナンバーを管理するシステムは、低コストで運用できる点も大きなメリットです。管理システムには、自社でサーバーを管理するオンプレミス型と、オンライン上で管理するクラウド型の2タイプがあります。
オンプレミス型のメリットは、自社の業務フローや設備、人材に応じたレベルのITインフラや情報システムを構築できる点です。一方で、膨大な初期費用がかかり、メンテナンスやトラブル対応もすべて自社で行わなければなりません。従業員の人数が少ない場合は、オーバースペックになるおそれもあるでしょう。
クラウド型の場合は、サーバーを設置する必要がないため、初期費用をあまりかけず、すぐに運用を始められます。毎月定額で利用できるシステムも多くあるため、維持管理にかかる費用も最小限に抑えられるでしょう。
→効率的なマイナンバー管理も実現「One人事」サービス資料を無料ダウンロード

マイナンバー管理をクラウド化するリスク
マイナンバー管理のクラウド化には数多くのメリットがある一方で、次のような懸念もあります。マイナンバーを管理する担当者は、自社に最適なサービスを選んだうえで正しく運用できなければ、重大なリスクを招くことを事前に理解しておきましょう。
| 情報の漏えいや流出 | 不正アクセスやウイルス感染により、マイナンバーが外部に漏れる |
| 法的罰則 | マイナンバーを不正に提供・盗用すると、3年以下の懲役または150万円以下の罰金 |
| 社会的信用の低下 | マイナンバー流出が発覚すると、企業イメージが悪化し、取引先や顧客の信頼を失う |
セキュリティ対策が必要
クラウド管理であってもセキュリティ対策は必須です。インターネット接続時に不正アクセスやウイルス感染などによって情報漏えいが起こるおそれがあります。アクセス制限がされていない環境では、不正コピーや外部からの閲覧のリスクもまったくないとは言い切れません。
法的罰則が厳格
マイナンバーの取り扱いを誤ってしまうと、通常の個人情報保護法よりも厳しい法的罰則を受けます。たとえば、不正に利益を得ようとする目的で従業員の個人番号を提供したり盗用したりした場合は、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
社会的信用の低下
マイナンバーの情報漏えいは、企業としての社会的信用の低下にもつながるでしょう。顧客や取引先からのイメージダウンのほか、積み重なると経営が悪化して莫大な損害が生じることも考えられます。
マイナンバー管理をクラウドに移行しても、運用が不十分であれば、紙の管理方法と同様のリスクが発生します。リスクに対して、安全・安心に管理できる仕組みづくりをしていきましょう。
マイナンバーをクラウドで管理する際の注意点・法律上の義務
企業がクラウド上でマイナンバーを管理する場合も、マイナンバー法(正式名称:『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』)に基づき、厳重な管理が求められます。
とくに以下の2つのポイントに注意が必要です。
- クラウド管理でも、企業が管理責任を負う
- 安全管理措置の実施が必須
クラウドに預けているからといって、企業の責任がなくなるわけではありません。適切なセキュリティ対策ができるクラウド環境を構築することが重要です。
マイナンバーの「特定個人情報」としての管理義務
マイナンバーを含む情報は、個人情報のなかでもとくに重要な「特定個人情報」に分類されます。そのため通常の個人情報保護法よりも厳しく管理しなければなりません。
企業の義務として、安全に取得・保管して利用したあと最終的に廃棄まで、ガイドラインに沿って行う必要があります。
- 利用・取得・提供
- 保管・廃棄
- 委託
- 安全管理措置
参考:『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』個人情報保護委員会
マイナンバー法の概要
マイナンバー法は、国民一人ひとりにマイナンバーと呼ばれる個人番号を割り当て、社会保障や税、災害対策で効率的な情報管理を行っていくことを目的としています。
マイナンバー法が施行される以前は、行政機関間で国民の氏名や住所などから個人情報を照合していたため、非効率な業務が数多くありました。マイナンバー制度によって、一元管理された情報をもとに各機関で処理できるようになったのです。
企業は社会保険や税の手続きで適切に扱うように義務づけられています。
クラウドで管理する場合の具体的な注意点
マイナンバーの管理は、外部の専門業者やクラウドベンダーに委託することが可能です。マイナンバー法によって認められています。
ただし、クラウドを利用する場合でも、委託元(企業側)の責任は免れません。自社内で管理する場合と同様に、利用者側が責任を持ってセキュリティ対策を徹底する必要があります。
最新の法改正情報を注視
近年では、マイナンバーが使用される行政事務が拡大され、健康保険証のほか運転免許証との一体化も開始されています。今後もマイナンバー法は特定個人情報を安全に取り扱うための役割を果たしていくため、法律や制度の改正に関する情報に注目していきましょう。
参照:『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』e-Gov法令検索
マイナンバー管理における必要な安全対策
マイナンバーは、厳重なセキュリティ対策のもとで正しく管理しなければなりません。クラウド上で管理する場合も、次のような基本的な安全対策を講じる必要があります。
- 基本方針の策定
- 取扱規程等の策定
- 組織的安全管理措置
- 人的安全管理措置
- 物理的安全管理措置
- 技術的安全管理措置
それぞれの安全対策について詳しく解説しましょう。
基本方針の策定
マイナンバーを含む特定個人情報を取り扱う事業者は、組織全体で適正な取り扱いができるように基本方針を策定する必要があります。
個人情報保護委員会が定めるガイドラインによると、基本方針に盛り込む内容として次の4つの事項が挙げられます。
- 事業者の名称
- 関係法令・ガイドラインなどの遵守
- 安全管理措置に関する事項
- 質問および苦情処理の窓口など
参照:『特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)』個人情報保護委員会
取扱規程等の策定
基本方針が定まったら、取扱規程を整備します。現行の法律を遵守し、個人情報が不正に流出するような被害から従業員を守るためにも、マイナンバーの具体的な取り扱い方法を定めなければなりません。
個人情報保護委員会が定めるガイドラインでは、以下の管理段階ごとに取扱方法や責任者・事務取扱担当者とその任務などを定める必要があるとされています。
- 取得
- 利用
- 保存
- 提供
- 削除・廃棄
参照:『特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)』個人情報保護委員会
組織的安全管理措置
組織的安全管理措置とは、組織がマイナンバーを取り扱うにあたって実施しなければならない体制整備のことです。具体的には、次のような対策が求められます。
- 組織体制の整備
- 取扱規程に基づく運用
- 取扱状況を確認できる環境の整備
- 情報漏えいのようなトラブルに対応する体制の整備
組織体制の整備や各種記録・点検を行う必要があります。
クラウドによるマイナンバー管理システムを利用すれば、組織的安全管理措置の一部に対応できるため、担当者の業務負担の軽減につながるでしょう。
人的安全管理措置
人的安全管理措置とは、マイナンバーが安全・適切に管理されるような人員体制を整えることです。具体的には次のような内容が定められています。
- 事務取扱担当者の監督
- 事務取扱担当者の教育
企業は、マイナンバーが適切に管理・運用されるよう、担当者を監督しなければなりません。たとえば、定期的にマイナンバーの管理体制を点検したり、他部署による監査を実施したりなどの対策が挙げられます。
また、マイナンバーを管理する担当者に対して定期的な研修や勉強会を実施し、適切な取り扱い方法を周知していくことも重要です。
物理的安全管理措置
物理的安全管理措置とは、マイナンバーを物理的に保管する際の管理体制を整備することです。担当者以外がマイナンバー情報を取り扱えないように、次のような対策を講じます。
- 管理区域の明確化
- 盗難や漏えいなどの防止
- 削除・廃棄方法の決定
具体的には、マイナンバーを管理するスペースの隔離と入退室を管理、盗難防止に対応したクラウドサービスの活用などの方法が挙げられます。
技術的安全管理措置
技術的安全管理措置とは、管理システム上でマイナンバーを保護する措置のことです。たとえば、次のような対策が挙げられます。
- アクセス制御
- アクセス者の識別と認証
- 外部からの不正アクセスの防止
マイナンバー情報を閲覧できる従業員をシステム上で限定したり、取り扱うデバイスを制限したりします。また、外部からの不正アクセスを防止するために、ウイルス対策ソフトのインストールも検討しましょう。
マイナンバーのクラウド管理に必要なセキュリティ機能
マイナンバーのクラウド管理では、適切なセキュリティ機能を導入することで、情報漏えいや不正アクセスのリスクを低減できます。
| 機能 | |
|---|---|
| ログ管理 | アクセス履歴を記録 |
| 暗号化 | データを保護(万が一の情報流出時にも内容を読み取れないようにする) |
| 権限設定 | アクセスを制限 |
| サイバー攻撃対策 | 標的型攻撃・ウイルス感染を防ぐ |
具体的にどのような機能なのか、以下で紹介します。
ログ管理
ログ管理によって、マイナンバーの取り扱い履歴を自動で記録し、誰が・いつ・どのデータを操作したかを確認できます。手間なく利用状況の把握が可能です。
不正アクセスやデータの改ざんを迅速に検知し、情報漏えいを防げます。正確な取り扱い履歴を記録することで、法令遵守も確保が可能です。
自社の運用に応じてアクセスログの保存期間が長いものを選びましょう。異常なアクセスを自動検知できる機能があるとより便利です。
暗号化
暗号化によるデータ変換技術で、万一マイナンバーが流出した場合も、情報を解読できないようにします。
ただし、暗号化されたマイナンバーも個人情報に当たるため、法令違反のリスクが完全に回避されるわけではありません。ほかのセキュリティ対策も併用する必要があります。
権限設定
権限設定は、マイナンバーの安全な管理において非常に重要です。ユーザーごとに適切な権限を設定することで、内部不正や情報漏えいのリスクを軽減できます。
運用では誰がどのデータにアクセスできるかを、段階ごとに細かく制御するのがポイントです。定期的にアクセス権限を見直し、不要な権限は削除しましょう。
サイバー攻撃対策
マイナンバーを管理するクラウド環境では、外部からの不正アクセスやウイルス感染を防ぐため、サイバー攻撃対策が必要となります。
標的型攻撃対策ツールの導入で外部からの攻撃を防御し、データを保護できます。定期的にシステムを更新し、最新のセキュリティパッチを適用すれば、脆弱性を減らせるので、攻撃に対する耐性を高められるでしょう。
マイナンバーのクラウド管理は委託になる? 本人の同意は必要?
マイナンバーのクラウド管理において、クラウド事業者の関与レベルによって「委託」に該当するかどうかが決まります。
委託に該当する場合、企業(事業者)には、クラウド事業者を適切に監督する義務が生じます。また、本人の同意が必要になるケースもあるため、慎重な対応が必要です。
クラウドベンダーがマイナンバーを扱う場合委託になる
クラウド事業者がマイナンバーを含むデータの保存・更新・バックアップ・削除を扱う場合、個人情報保護法上の「第三者提供」や「委託」に該当すると考えられます。
「第三者提供」や「委託」に該当するのであれば、本人の同意が必要です。
「委託」では委託元である事業者がクラウド事業者に対する監督責任を負わなければなりません。同時に安全に管理されているか、適切なセキュリティ対策が実施されているかを確認する必要があります。
委託でなくても事業者として管理が必要
クラウド事業者がマイナンバーを直接取り扱わない契約が締結され、適切なアクセス制御が実施されている場合には、委託には該当しません。
委託に該当しなくても、事業者(企業側)にはマイナンバーの管理責任があります。安全管理措置を適切に講じることが必要です。具体的には、自社でのデータバックアップやアクセス制御が挙げられます。
クラウドサービスを利用する際には、契約内容やセキュリティ対策を十分に確認し、適切な管理体制を整えましょう。
マイナンバー管理に適したクラウドサービスとは
マイナンバーを適切に管理するクラウドサービスを選ぶ際は、セキュリティ機能の充実度を確認することが重要です。
データの暗号化やアクセス制御、ログ管理、バックアップ機能などの基本的なセキュリティ対策が整っているかをチェックしましょう。ISOやISMAPといったセキュリティ認証の取得状況も判断材料となります。
マイナンバーを管理するクラウド選定時には、コストだけでなく運用フローに適しているか、社内システムとの連携が可能か、サポート体制が十分かといった点も考慮しましょう。導入前に試験運用を実施し、自社の業務に適しているかを確認することも大切です。
機能を備えたクラウドサービスを選ぶことで、マイナンバーの安全性を確保しつつ、管理負担を軽減できます。
→マイナンバー管理も効率化「One人事」サービス資料を無料ダウンロード

マイナンバーのクラウド管理サービスの選び方・比較ポイント
マイナンバーのクラウド管理サービスを選ぶ際には、複数の要素を考慮する必要があります。とくに、セキュリティ機能や外部連携、収集方法、価格、操作性などが重要です。比較ポイントを詳しく解説します。
マイナンバー管理のクラウドサービスを選ぶ際は、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。以下のポイントを基に、自社の業務に最適なサービスを選びましょう。
- 機能
- 外部連携
- 収集方法
- 帳票への出力方法
- 従業員規模
- 価格
- 操作性
- セキュリティレベル
マイナンバー管理システムの機能やメリットを知るには以下の記事もご確認ください。
単一機能タイプ・多機能タイプ
マイナンバー管理のクラウドサービスには、単一機能型と多機能型があります。
単一機能タイプは、マイナンバーの登録・管理に特化しており、労務管理システムと連携する必要があります。
多機能タイプは人事労務システムの一部としてマイナンバー管理機能を備えており、給与計算や労働時間の管理などと一体的に管理できます。業務効率が向上し、管理負担が軽減されます。
外部連携
すでに使用している業務システムと連携できることもサービス選定の重要なポイントです。連携が可能であれば、データの二重管理を避けられ、管理者の負担を減らせます。将来的なシステム拡張を視野に入れる場合は、複数の外部システムと連携できるかどうかも確認しておきましょう。
収集方法
従業員がマイナンバーを提出する方法も、クラウド型マイナンバー管理システムの使いやすさに直結します。スマートフォンで撮影して登録できるクラウドシステムを導入すれば、従業員の手間を削減できるだけでなく、管理者の負担も軽減できます。
また、遠隔地で勤務する従業員からも手軽に収集できると、紙ベースの管理と比較して業務の効率化につながります。
帳票への出力方法
マイナンバーを必要なフォーマットで出力できるかどうかを確認しましょう。
CSVファイルで出力できるシステムであれば、既存の給与システムや人事管理システムとの連携がスムーズです。カスタマイズ可能な出力形式の場合、企業ごとの業務フローに応じてデータを出力できます。
自動出力機能があれば、手作業によるミスの削減にもつながるでしょう。
従業員規模
小規模な企業であれば、初期費用が無料または低額で利用できるクラウド型マイナンバー管理システムが適しています。初期投資を抑えつつ、必要な機能の活用が可能です。
一方、大規模な企業では、管理すべき情報量が多くなるため、多機能型のクラウドサービスを選ぶとよいでしょう。カスタマイズが可能なプランが提供されていれば、企業のニーズに合わせた柔軟な運用が可能になります。
価格
クラウド型マイナンバー管理システムの価格は、初期費用と月額料金のバランスを考慮して選ぶ必要があります。初期費用がかからないサービスもありますが、月額料金が高くなるケースもあるため、長期的なコストを見据えて判断することが大切です。
また、利用者数に応じた価格設定や長期契約による割引があるかどうかも、コスト削減の観点から確認したいポイントです。追加機能による追加費用が発生しないかも事前に確認し、必要な機能とコストのバランスを見極めることが重要です。
コストバランスを試算するには以下の資料もぜひご活用ください。
操作性
従業員が自身でマイナンバーを登録する場合も、わかりやすい操作性が求められます。
直感的に操作できるマイナンバーシステムかどうかも、クラウドサービス選定の際に考慮したい要素です。シンプルでわかりやすいインターフェースであれば、管理者や従業員が迷わず業務を進められます。
操作が複雑なシステムでは、登録ミスや入力ミスが発生しやすくなるため、できるだけシンプルなものを選ぶとよいでしょう。
セキュリティレベル
ここまで紹介してきたように、マイナンバーを取り扱うクラウドサービスでは、セキュリティ対策の充実度が重要です。
データの暗号化やアクセス制御、ログ管理など基本的なものだけでなく、公的な認証基準を通過しているかも確認し、信頼性を確かめましょう。万が一を考慮して慎重に選定する必要があります。
企業の業務フローに適したクラウド型マイナンバー管理システムを選ぶことで、安全かつ効率的にマイナンバーを管理できます。
まとめ|マイナンバーはクラウドで安全に管理
マイナンバーのクラウド管理は、情報漏えいのリスクを最小限に抑えるだけでなく、業務効率の向上や安全管理の負担軽減にもつながります。本記事で紹介したように、適切なセキュリティ対策を備えたクラウド型システムを選べば、紙の管理よりも安全かつ効率的に運用できます。
また、人事労務システムとの連携により、マイナンバー管理を含む業務全般の効率化が可能です。導入にあたっては、セキュリティ機能は当然のこと、連携性や操作性、コストなどを総合的に比較し、自社に最適なシステムを選びましょう。
「どのクラウドシステムを選べばいいかわからない」という方は、本記事のポイントを参考に、自社に適したサービスを検討してみてください。
マイナンバー管理にも|One人事[労務]
One人事[労務]は、マイナンバー管理機能が備わった労務管理システムです。マイナンバーの取得、利用、廃棄を一括で管理し、情報漏えいや不正利用を防止します。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |