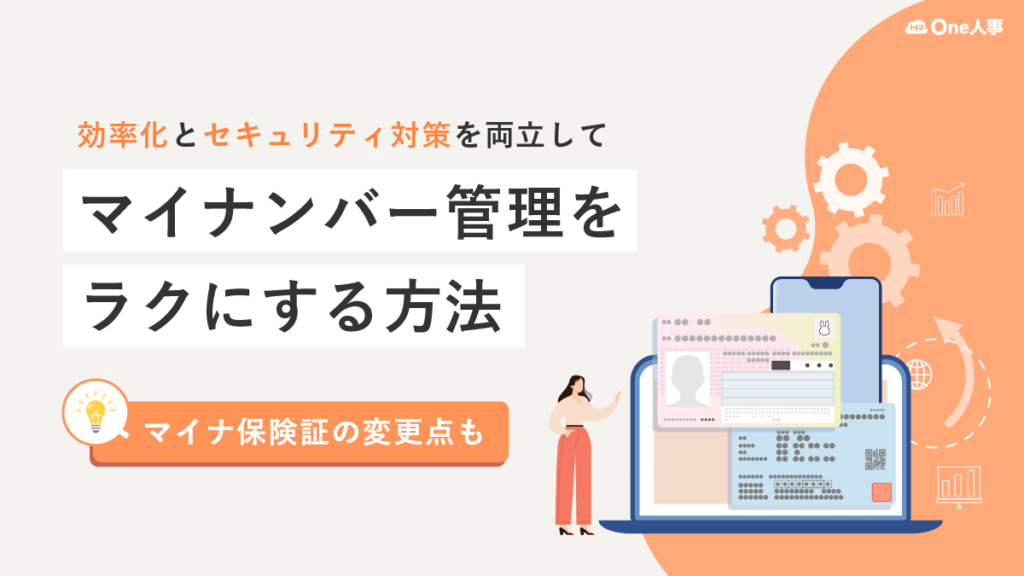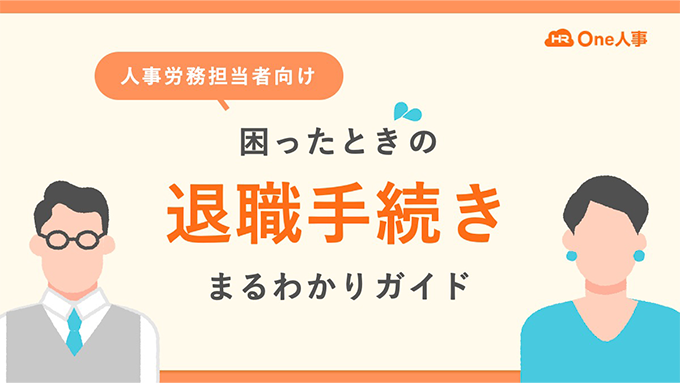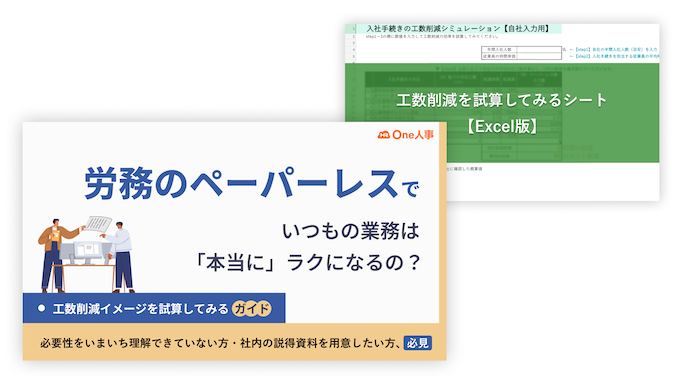退職者のマイナンバーの保管期間|効率的に削除・廃棄する方法についてもあわせて解説

会社で退職者がでた場合、税金関連や社会保険の脱退手続きなど多くの手続きが必要になります。
とくに退職者のマイナンバーが書かれている書類を廃棄する際は、保管期間のある書類もあるため扱い方には注意が必要です。書類をすぐに削除してしまわないよう、書類ごとの保管期間を把握しておきましょう。
本記事では、退職者のマイナンバーの保存期間や廃棄方法まであわせて解説します。
→マイナンバー管理にも|労務管理システム「One人事」資料をダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
マイナンバーを削除や廃棄する要件
マイナンバーが書かれた書類は、不要になった時点で削除・廃棄する必要があります。ただし書類によっては保存が必要なため、削除・廃棄する要件を確認しておきましょう。
- 不要になったら基本は廃棄する
- 法律で定められている保存期間を経過した
不要になったら基本は廃棄する
従業員が離職してマイナンバーが不要になったら、速やかに廃棄・削除することがマイナンバー法によって義務づけられています。
しかし、退職者についても税金や社会保険料などの事務処理が発生するケースも多く、従業員が退職してもすぐにマイナンバーを削除・廃棄する必要はありません。
マイナンバーは行政手続きのみ利用できるため、勤務先で事務処理をするためのマイナンバー収集や保管は認められています。ただし、事務処理が不要になれば、マイナンバーが書かれた書類やデータは速やかに廃棄・削除しましょう。
法律で定められている保存期間を経過した
所管法令で保存期間が定められていない書類やデータは、マイナンバー関連の事務を処理する必要がなくなった時点で廃棄・削除するのが基本です。
また、保存期間が定められている書類については、保存期間が経過したら廃棄・削除しなければなりません。
保存期間が定められている書類はのちほど詳しくご紹介しますが、参考までに一部ご紹介します。
| 保存期間が定められている書類 | 保存期間 |
|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 7年間 |
| 給与所得者の扶養控除等申告書 | 7年間 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 7年間 |
退職者のマイナンバー保管期間
退職者のマイナンバーが書かれた書類やデータの保管期間は、最長で従業員の退職後約7年です。人事労務関連書類は書類ごとに保存期間は異なりますが、控除等申告書などの保存期間が7年であることが理由です。
保存期間の起算日は、マイナンバーの記載された申告書などの提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日です。保管期間が過ぎたら、マイナンバーが記載されている書類やデータはすべて廃棄・削除しましょう。
ただし、書類のマイナンバー部分を切り取ったりマスキングしたりして番号を見えなくすれば、保存期間を過ぎても保存することは可能です。
マイナンバーを記載する主な書類の法定保存期間
マイナンバーが書かれた書類は、種類によって法定保存期間が異なります。それぞれの保存期間を正確に把握しておきましょう。
| 雇用保険関係書類 | 2年間 |
|---|---|
| 労災保険関係書類 | 保存義務なし |
| 社会保険関係書類 | 2年間 |
| 企業年金関係書類 | 保存義務なし(最長7年間) |
| 本人確認書類や扶養親族のマイナンバー | 保存義務なし |
雇用保険関係書類
マイナンバーが記載された雇用保険関係書類の保存期間は2年間です。
雇用保険の書類の控えは、完結の日から2年間(被保険者に関する書類は4年)保管しなければならないと、雇用保険法施行規則第143条に定められています。
しかし雇用保険関係書類の原本はハローワークで管理しているため、実は事業主がその控えを保管しておく必要はありません。ただし、保管をするのであれば保管方法に注意したうえで2年間保管しましょう。
労災保険関係書類
マイナンバーが記載された労災保険関係書類は、原則として事業主が保存する必要はありません。
労災保険関係書類のうち、障害補償給付支給請求書や遺族補償年金請求書などが、マイナンバーの記載が必要な書類です。これらの書類は原則として給付を受ける本人が提出するため、事業主は管理しないこととなっています。
本人の委託により、事業主や社会保険労務士が代理で書類の作成と提出をすることもありますが、そのような場合でも手続きが完了次第、マイナンバー情報は削除・廃棄しましょう。
社会保険関係書類
マイナンバーが記載された社会保険関係書類の保存期間は2年間です。
社会保険関係書類のマイナンバー情報の扱いは、雇用保険関係書類と同様に完結の提出から2年間保管することが定められています。
健康保険や厚生年金に関する書類も、原本は健康保険組合や日本年金機構で管理するため、事業主が控えを保管しておく必要はありません。
ただし、事業主の判断で控えを保存しておくことは可能です。この場合は健康保険法施行規則第34条や厚生年金保険法規則第28条において、それらに関する書類を完結の日から2年間保管することと定められています。
参考:『健康保険法施行規則』e-GOV法令検索
参考:『厚生年金保険法施行規則』e-GOV法令検索
企業年金関係書類
マイナンバーが記載された企業年金に関係する書類は、原則として事業主が保存する必要はありません。
マイナンバー情報が必要な企業年金に関係する書類とは、公的年金支払報告書や源泉徴収票などを指し、原則として控えを保管しておく必要はないとされています。
控えをとっておく場合は、税務における更正決定などの期間制限を考慮して、最長でも7年が限度とされています。ただし、最低保存期間ではなく最長の保存期間であることに注意しましょう。
本人確認書類や扶養親族のマイナンバー
本人確認書類や従業員が扶養している親族のマイナンバーについても確認しておきましょう。
本人確認のために、従業員のマイナンバーカードのコピーを提出してもらうことがあります。その場合は、コピーを保管することが認められていますが、法令によって保管が義務づけられているわけではありません。
また、保存期間についても定められていないため、不要なトラブルを避ける意味で、番号を確認したら速やかに廃棄することが推奨されています。
マイナンバーの削除や廃棄する方法
マイナンバーは重要な個人情報のため、復元されないよう完全に削除・廃棄できる方法で処理することが大切です。
- デジタルデータは復元できない状態にする
- 紙書類は焼却やシュレッダーで破棄する
- 専門業者に委託する
- ハードディスクを破壊する
- 保存が必要な紙書類にはマスキングする
デジタルデータは復元できない状態にする
マイナンバーをデジタルデータで保管していた場合は、復元できない状態にする必要があります。
デジタルデータが復元されると情報漏えいのリスクが高まるため、物理的な破壊方法や専用のソフトウェアを使用して確実にデータを廃棄することが重要です。
安全にデータ削除を行う方法として、データ処理の専門業者に依頼する方法もあります。
紙書類は焼却やシュレッダーで破棄する
マイナンバーを紙媒体で保存していた場合は、シュレッダーで粉砕したり焼却処理したりなど復元不可能な方法で破棄しましょう。
マイナンバー削除後は、削除した記録を残す作業も必要です。記録として残す内容は、書類名・部数・削除を担当した人・削除方法などを記載します。この際、記録用紙にマイナンバーを転記しないよう注意してください。
専門業者に委託する
マイナンバーの廃棄は専門業者に委託することも可能です。
ただし、書類の専門業者に廃棄の委託をする場合は、廃棄の証明書などの発行が必要になります。発行方法は業者によって異なり、紙もしくは電子発行のどちらかが一般的です。
証明書発行までにかかる時間は業者によって違うため、届くタイミングを事前に確認しておきましょう。
ハードディスクを破壊する
マイナンバーのデータを削除する場合は専用のソフトウェアを使用する、または物理的に破壊する方法が推奨されています。
しかし、物理的に破壊してしまうと買い直すコストがかかるため、データ削除専用のソフトウェアを使用するのがおすすめです。専用のソフトウェアを使用すれば、復元不可能な状態にしてデータを削除できます。
保存が必要な紙書類にはマスキングする
マイナンバーが書かれた紙書類が不要になった場合、破棄することが義務づけられています。
しかし、事務処理などで保存が必要な紙書類は、マイナンバーがわからないようにすれば、継続して保管することが可能です。たとえば、該当欄をマスキングをしたり、切り抜いたりする方法です。
書類に書かれたマイナンバーが見えないようにすることがポイントで、完全に番号が見えなくなるように加工しましょう。
効率的にマイナンバーを削除や廃棄する方法
効率的にマイナンバーを廃棄できる4つの方法をご紹介します。システムの導入や業務委託など、できることから検討してみてください。
- 廃棄しやすいシステムを導入する
- 年度別に保管する
- 必要のない書類にマイナンバーを記載しない
- 業務を委託する
廃棄しやすいシステムを導入する
マイナンバーを効率的に廃棄するには、専用システムの導入も一案です。
システムを選ぶ際は、マイナンバーを適切に廃棄できるかを考慮します。書類ごとに異なる法定保存期間の期限を管理する機能が備わったシステムなら、廃棄漏れのリスクを軽減できるかもしれません。
廃棄記録が残るシステムもあり、厳格で効率的な管理が実現しやすくなるでしょう。
年度別に保管する
マイナンバーを紙媒体で保管する場合は、年度ごとに分けておくと保管しやすくなります。
退職者のマイナンバーには廃棄期限が設けられているため、退職した年度ごとに書類をファイリングしておけば管理しやすくなるでしょう。
ただし、書類が分散してしまうと紛失や情報漏えいのリスクが高まるため、書類が混ざらないよう注意してください。
必要のない書類にマイナンバーを記載しない
記載する必要のない書類やデータベースに、削除したマイナンバーを書かないよう注意しましょう。
仮に「マイナンバー取扱記録簿」などにマイナンバーをメモ書きしただけでも、それ自体を適切な方法で廃棄しなければなりません。
マイナンバーを閲覧する際は原本やデータベースを用いて、データの出力を最低限にとどめることが効率化をはかるうえでも大切です。
業務を委託する
すべてのマイナンバー事務を外部に委託する方法も、効率的な業務にするには有効です。
自社でマイナンバーを扱うことがなくなり、マイナンバーの取得にはじまり管理や保管、廃棄まで一連の処理にかかる担当者の負担が軽減されるでしょう。
また、自社内の安全措置管理がマイナンバーに対応できる高度なレベルまで要求されなくなるため、委託先である外部業者を監督するだけで済むというメリットもあります。
ただし、業務を委託すると費用がかかるため、費用対効果を検証したうえで委託を検討しましょう。
マイナンバーを廃棄する際の注意点
マイナンバーの破棄するときは、自社と外部委託業者いずれの場合も、慎重に取り扱う必要があります。マイナンバーを廃棄する際の注意点を4点ご紹介します。
- マイナンバー情報が漏れないようにする
- 自社で廃棄した場合は記録に残す
- 外部委託する際は業務委託契約を締結する
- 外部委託先から廃棄証明書をもらう
マイナンバー情報が漏れないようにする
マイナンバーは重要な個人情報であるため、情報が漏れないように細心の注意を払って取り扱いましょう。現在はマイナンバーのみで行政手続きなどは行えないため、悪用されるなど被害を受ける可能性は低いと考えられます。
しかし、今後マイナンバーは健康保険証との一体化などできることの範囲が拡大するため、マイナンバーが漏えいしないよう十分注意しなければなりません。
自社で廃棄した場合は記録に残す
紙媒体で管理しているマイナンバーの廃棄は、廃棄したことがわかるように、書類名などを記録して残す必要があります。書式に決まりはなく、紙やエクセルなどに以下の事項を記録しておくとよいでしょう。
- 書類名
- 廃棄した年月日
- 廃棄した人の名前
- 廃棄方法 など
デジタルデータの場合は、システムなどを利用して削除した操作の記録が残るよう設定しましょう。
外部委託する際は業務委託契約を締結する
マイナンバーの廃棄を外部業者に委託する場合、業務委託契約書を結ばなければなりません。
委託した企業は外部委託先への監督責任が生じるため、契約書を通して、秘密保持に関する義務やマイナンバーの取り扱いについて取り決めましょう。
マイナンバーの廃棄を依頼する企業を選ぶ際は、どのような方法で廃棄しているか、安全管理措置を講じているかを企業の責任としてチェックする必要があります。
外部委託先から廃棄証明書をもらう
マイナンバー書類やデータの廃棄を外部委託した場合は、機密文書の廃棄業者が発行する廃棄証明書が必要です。発行方法は業者によって違い、紙または電子発行のどちらかになります。
また、廃棄証明書は5年または7年の保管が必要です。無くしたりほかの書類と混ざらないよう、ファイルに書類名を明記するなど保管方法に注意しましょう。
まとめ
従業員が退職してマイナンバーが不要になった場合、マイナンバー法に基づいて速やかに削除・廃棄することが義務づけられています。
しかし、マイナンバーが書かれた書類の中には事務手続きに使用するもの、所管法令で保管する必要がある書類もあるため、すぐに削除・廃棄する必要はありません。このような書類は事務手続きが不要になったタイミング、または保管期限が過ぎたら早めに削除・廃棄しましょう。
また、マイナンバーは重大な個人情報ですので、保管方法や廃棄方法に注意する必要があります。自社で保管・廃棄する場合は専用のシステムなどを活用して、確実に処理するようにしましょう。
マイナンバー管理のシステム導入には|One人事[労務]
One人事[労務]は、マイナンバー管理機能が備わった労務管理システムです。マイナンバーの取得、利用、廃棄を一括で管理し、情報漏洩や不正利用を防止します。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |