労災保険の手続きに必要な書類は? 誰が書く? 給付別提出先も紹介
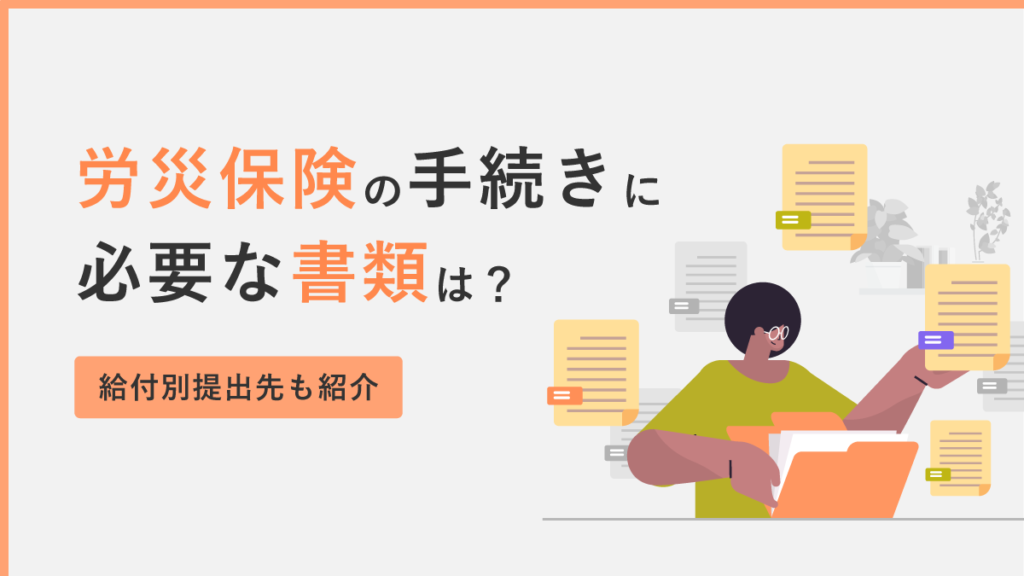
労災保険は労働災害に対する補償制度であり、業務中や通勤中のケガや病気に対してさまざまな給付金が用意されています。しかし、いざ労災手続きを進める際、「どの書類を準備すればいいのか」「提出先はどこなのか」と、具体的な手続き方法に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、労災保険の給付申請に必要な書類を紹介します。労災保険の加入手続きについても解説しているので、これから従業員を雇用する予定の企業もぜひ参考にしてください。
労災保険を含め、社会保険関係の手続きは順調にお済みですか。社会保険の提出書類や方法が整理できていない方は、以下の資料もぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
労災保険とは
労災保険とは、業務中や通勤中のできごとに起因するケガや病気を補償する公的制度です。病院での治療費の負担や、働けない間の経済的不安などをフォローし、労働災害にあった従業員を保護することを目的としています。
雇用形態にかかわらず、従業員を1人でも雇用している企業は労災保険に加入する義務があります。制度の性質上、労災保険料は企業の全額負担です。
労働保険と雇用保険、労災保険の関係性
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。つまり、労災保険は労働保険の一種といえます。
労災保険の目的が労働災害による傷病の補償なのに対し、雇用保険は失業中や休業中の労働者の生活や、再就職を支援することを目的としています。また、企業に対して雇用継続の支援も行っています。
労災保険は原則すべての従業員が対象である一方、雇用保険は以下の3条件を満たす人が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上(2028年10月以降は10時間以上)
- 雇用見込み期間が31日以上
- 学生ではない(定時制等除く)
参照:『雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要』厚生労働省
そのため、雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇用する場合は、労災保険と雇用保険の両方(=労働保険)に加入する必要があります。

労災保険の種類
労災保険の給付金には、次のようにさまざまな種類があります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 介護(補償)給付
- 二次健康診断等給付
手続きにあたって給付内容を確認していきましょう。
療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、業務中や通勤中のできごとに起因するケガや病気で療養する場合に、病院での治療費や入院費などが給付されるものです。
労働災害により治療を受ける場合、労災病院や労災保険指定医療機関を利用すれば、無償で治療を受けられます。申請手続きでは「様式第5号」という名の書類を使用します。
様式第5号の書き方などについて知るには以下の記事もご確認ください。
指定の病院以外を受診する場合は、「様式第5号」でなく「様式7号」の提出が必要です。指定機関の利用とは異なり、従業員が一度窓口で全額自己負担してから、後日かかった費用が給付されます。そのため忘れずに領収書を受け取らなければなりません。
休業(補償)給付
休業(補償)給付とは、労働災害による傷病の療養のため働くことができず、会社から給与が支給されない場合に給付されるものです。
給付基礎日額の60%に加えて、社会復帰促進等事業の特別支給金として、給付基礎日額の20%が給付されます。
給付基礎日額とは、労働災害が発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額を指します。
休業(補償)給付が受け取れるのは、休業4日目からです。
休業補償給付の申請手続きでは、「様式第8号」という名の書類を使用します。
休業補償についてより詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
傷病(補償)年金
傷病(補償)年金とは、労働災害によるケガや病気の療養を開始して1年6か月が経過しても治癒(症状固定)せず、「傷病等級」に当てはまる場合に支給される年金です。
支給額は傷病等級に応じて決定され、給付基礎日額の245〜313日分が給付されます。
障害(補償)給付
障害(補償)給付は、労働災害の傷病により障害が残った場合に給付されるものです。
障害等級が第1級~第7級の場合は障害(補償)等年金が、第8級~第14級の場合は障害(補償)等一時金が給付されます。
遺族(補償)給付
遺族(補償)給付とは、労働災害によって従業員が死亡した場合に、生計を一としていた特定の遺族に給付される年金です。従業員に該当する遺族がいない場合は、一定の範囲の遺族に対して一時金が給付されます。
葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)とは、労働災害により死亡した従業員の葬儀を行った人に対して給付されるものです。「31万5,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のうち、いずれか高い方が給付されます。
介護(補償)給付
介護(補償)給付とは、労働災害による障害で要介護となった場合に給付されるものです。
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、実際に介護を受けている場合に給付されます。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付とは、労働者が定期健康診断を受けた際に次のすべての要件を満たすと、自己負担なしで二次健康診断と特定保健指導を受けられるものです。
- 「腹囲またはBMI(肥満度)」「血圧」「血糖」「血中脂質」のすべての項目で異常が見られる
- 脳や心臓疾患の症状がない
- 労災保険の特別加入者ではない
脳や心臓疾患の状態を把握し、発症を予防することを目的としています。

労災保険の申請手続きに必要な書類
労災保険の各種給付を受けるためには、次のような書類を提出する必要があります。
- 各種給付請求書
- 治療費等の領収書
- 賃金台帳・出勤簿の写し
- 後遺障害診断書など
- 死亡診断書・戸籍謄本など
それぞれの書類について、以下で詳しく解説しましょう。
各種給付請求書
労災保険の手続きに必要な請求書は、給付の種類によって異なります。それぞれ決まった様式が用意されており、厚生労働省のホームページから該当するものを選んで使用します。
同じ様式番号でも、請求内容によって数種類のフォーマットが用意されているため、該当するものを間違えないようにしましょう。
参照:『主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)』厚生労働省
療養(補償)給付の請求書は、労災病院または労災保険指定医療機関を受診した場合と、それ以外の医療機関を受診した場合とで様式が異なるため注意が必要です。
また、療養(補償)給付は薬剤も対象となるため、薬の処方を受けた薬局の分も用意します。
治療費等の領収書
労災病院または労災保険指定医療機関以外を受診し、治療費等をあとから請求する場合には、費用の明細書と医療機関等の領収書が必要です。
賃金台帳・出勤簿の写し
休業(補償)給付の申請の際には、確認のため賃金台帳や出勤簿の写しを求められる場合があります。
後遺障害診断書など
労働災害による傷病でなんらかの後遺障害が残ってしまった場合は、医師による診断書が必要です。
死亡診断書・戸籍謄本など
障害(補償)年金差額一時金の支給申請を行う際は、死亡診断書や戸籍謄本または抄本を添付します。
障害(補償)年金差額一時金とは、従業員が障害(補償)年金を受給中に死亡したときに適用される制度です。
支給済みの障害(補償)年金と障害(補償)年金前払い一時金の合計額が、障害等級に応じた基準額に達していない場合、遺族に対して差額一時金が支給されます。
死亡診断書や戸籍謄本などは、遺族(補償)給付の申請時にも必要となります。

労災保険の申請書類を提出する流れ
職場の事故や災害により労災が発生してしまったら、一般的に以下の流れで手続きを進めます。
| 流れ | 詳細 | 人事労務担当者へのポイント |
|---|---|---|
| 1.労災事故の確認と報告 | 労災事故が発生したら、まず従業員から事故の内容を会社に報告 | 発生状況を確認するととmに、早期の受診を促す |
| 2.必要書類の準備と作成 | 各種給付請求書をダウンロードして記入 | 労働基準監督署や、厚生労働省のWebサイトからできる |
| 3.医療機関または事業主の証明を取得 | 療養補償は診療担当者、その他各請求書には事業主証明欄あり | 記入漏れがないかを確認する |
| 4.労働基準監督署へ提出 | 窓口持参、郵送、オンライン提出が可能 | 不備があればすぐに対応する |
| 5.給付の審査・決定 | 労働基準監督署長による調査 | 労働災害と認めれれた場合のみ給付が認められる |
手続きは原則として事故にあいケガや病気を負った本人が行い、本人の家族でも可能です。ケガや病気を負った従業員の負担を軽くするため、企業の人事労務担当者が代行しでも構わないでしょう。

労災保険申請書類の提出先
労災保険の申請書類は、給付の種類に応じて受診した医療機関(病院、薬局など)や所轄の労働基準監督署長に提出します。
給付の種類によって提出先が異なるため、整理しておきましょう。
| 給付の種類 | 提出先 | |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 労災病院または労災保険指定医療機関を受診した場合(様式第5号、様式第16号の3) | 受診した医療機関 |
| 医療機関を変更する場合、または複数の医療機関を受診する場合(様式第6号) | 新たに受診した医療機関 | |
| 労災病院または労災保険指定医療機関以外を受診した場合(様式第7号、様式第16号の5) | 所轄の労働基準監督署長 | |
| 休業(補償)給付(様式第8号、様式第16号の6) | ||
| 傷病(補償)給付(第16号の2) | ||
| 障害(補償)給付(様式第10号、様式第16号の7) | ||
| 遺族(補償)給付(様式第12号、様式第16号の8) | ||
| 葬祭料(葬祭給付)(第16号、第16号の10) | ||
| 介護(補償)給付(様式第16号の2の2) | ||
| 二次健康診断等給付(第16号10の2) | 二次健康診断等を受けた医療機関 | |
労災申請書類の提出期限
労災保険の各種給付には、それぞれ時効期限が設けられています。給付を受けるためには、時効を迎える前に申請書類を提出しなければなりません。
時効期限(提出期限)は、それぞれ以下のとおりです。
| 給付の種類 | 起算日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日ごとにその翌日 | 2年 |
| 休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとにその翌日 | 2年 |
| 傷病(補償)年金 | 監督署長の職権により支給決定されるため、請求手続きや時効はなし ※療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らない場合は、その後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」の提出が必要 | |
| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒(症状固定)した日の翌日 | 5年 |
| 遺族(補償)給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日 | 5年 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 被災労働者が亡くなった日の翌日 | 2年 |
| 介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の1日 | 2年 |
| 二次健康診断等給付 | 一次健康診断の受診日 | 3か月 |

労災保険の申請手続き書類の作成は会社が代行可能
労災保険の申請手続きに必要な書類は、原則として被災した労働者本人(またはその遺族)が作成して提出します。しかし、現実的には、労災事故後のケガや病気の治療中で本人が手続きに対応できない場合も少なくありません。
本人が何らかの事情で提出が難しい場合は会社が代行して申請手続きを進めることが可能です。
労災申請は必要書類が細かく分かれ、制度で手間がかかるため、多くの企業では労災手続きの代行が一般的に行われているようです。
労災保険の手続きに必要な書類は給付によって異なる
労災保険には「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」などさまざまな種類の給付があり、それぞれ必要書類が異なります。
なかには複数の様式が用意されているものもあり、受診した医療機関や労働災害の種類などに応じて、適切なものを選ぶことが大切です。
給付の種類によっては、請求書類だけでなく、診断書や領収書を求められることもあるでしょう。
労災保険の給付申請は、原則として従業員本人が行いますが、会社が代行することも可能です。従業員から労災申請を希望されたときに備えて、必要な書類や手続きを把握しておきましょう。
クラウド労務管理システムOne人事[労務]は、社会保険の申請手続きをオンラインで完結させる効率化ツールです。e-Gov電子申請にAPI連携し、窓口に出向かなくても、簡単に申請ができます。
2025年からは「労働者死傷病報告」など一部手続きの電子申請が義務化されました。社会保険申請のペーパーレス化が進んでいない企業は、検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]で実現できること・機能は、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが、課題の整理からお手伝いします。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします |
