2025年(令和7年)年末調整の変更点|税制改正による実務への影響を解説
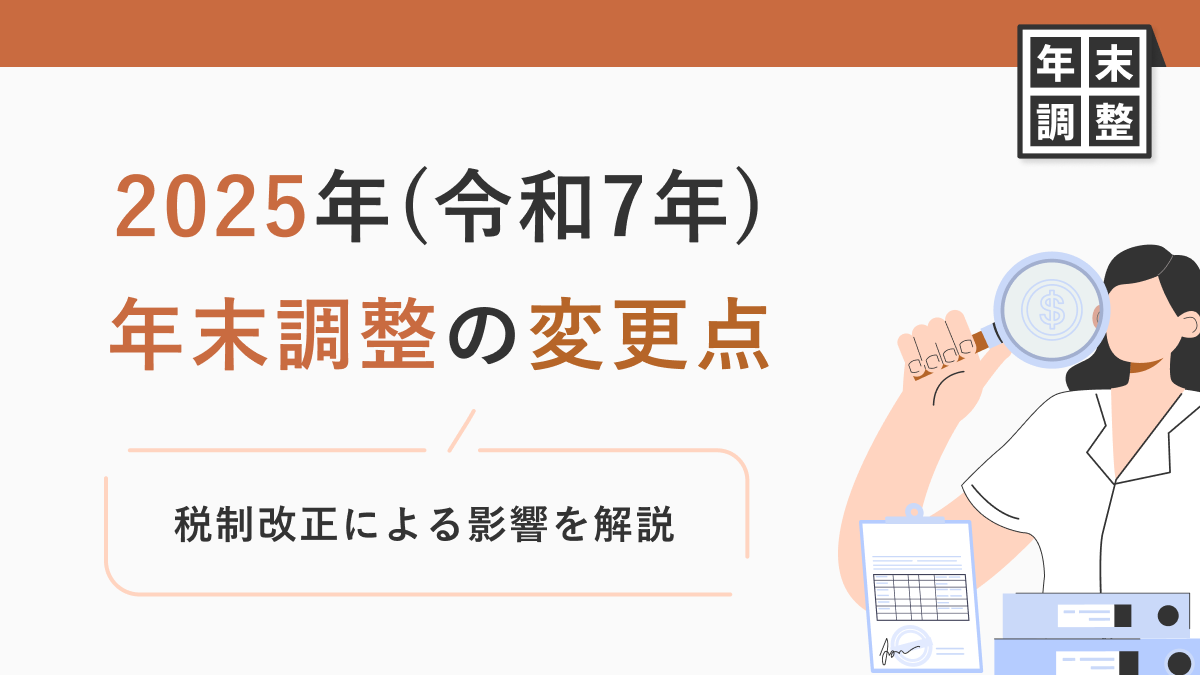
2025年(令和7年度)の年末調整では、物価上昇への対応や労働力不足解消を目的とした変更点があります。年末調整の実務にも影響があるため、企業の担当者は変更点の内容を正しく理解しなければなりません。
本記事では、2025年の年末調整における変更点や実務上の注意点、2026年の年末調整への影響も解説します。企業の担当者は、変更点に対する準備を整え、スムーズに取り組めるようにしましょう。

 目次[表示]
目次[表示]
2025年の年末調整における重要な変更点
2025年の年末調整における主な変更点は、以下のとおりです。
- 基礎控除の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族などの所得金額要件を引き上げ
- 住宅ローン控除の拡充措置継続
変更点のなかでも、年末調整を受ける本人の「基礎控除額」「給与所得控除額」の変更、「特定親族特別控除」の創設は、とくにおさえておきたいポイントです。
主な変更点の内容について解説します。
1.基礎控除の見直し
基礎控除の見直しでは、納税者の合計所得金額2,350万円以下の基礎控除額が10万円引き上げられます。本見直しは、昨今の物価上昇に考慮して、税負担などを軽減する目的があります。
見直し後の基礎控除額は、以下のとおりです。
| 合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 132万円以下(給与収入額200万3,999円以下) | 48万円 | 95万円(基礎控除58万円+特例37万円=95万円) |
| 132万円超336万円以下(給与収入額200万3,999円超475万1,999円以下) | 88万円(基礎控除58万円+特例30万円=88万円) | |
| 336万円超489万円以下(給与収入額475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円(基礎控除58万円+特例10万円=68万円) | |
| 489万円超655万円以下(給与収入額665万円5,556円超850万円以下) | 63万円(基礎控除58万円+特例5万円=63万円) | |
| 665万円超2,350万円以下(給与収入額850万円超2,545万円以下) | 58万円 |
出典:『令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)』国税庁
とくに注目したいのが、基礎控除の特例です。合計所得金額655万円以下の従業員は、変更後の基礎控除額58万円に加え、さらに上乗せして控除を受けられます。
上乗せされる金額は、合計所得金額に応じて5万から37万円です。
そのうち、合計所得金額132万円以下を恒久的措置、132万円超655万円以下は2年間の時限的措置とされています。
2025年の年末調整では、見直し後の基礎控除額を使って年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収した税額との差額を精算することになります。
担当者が注意したいのは、2025年の年末調整で変更後の金額を適用するだけでなく、2026年以降の源泉徴収税額表にも新しい基礎控除額を反映させる必要がある点です。変更にともない、正しく税額を計算できる体制を整えておきましょう。
2.給与所得控除の見直し
2025年の改正では、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へと引き上げられました。
対象となるのは 給与収入190万円以下の人 で、190万円を超える人は控除額に影響はありません。
給与所得控除の見直しにともない、控除計算に必要な計算表も改正されています。
2025年の年末調整では、改正後の控除額に基づいて所得税額を計算し、改正前に源泉徴収した税額との差額を精算する必要があります。
3.特定親族特別控除の創設
2025年の年末調整で新設された特定親族特別控除とは、生計を一にする特定の年代の親族(特定親族)がいる場合に適用される控除です。
特定親族1人ごとの合計所得金額に応じて、居住者の総所得金額等から3万円から63万円が控除されます。
特定親族1人あたりの合計所得金額における特定親族特別控除額は、以下のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額(居住者が控除される額) |
|---|---|
| 58万円超85万円以下(給与収入額123万円超150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超90万円以下(給与収入額150万円超155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超95万円以下(給与収入額155万円超160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入額160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入額165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入額170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入額175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入額180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入額185万円超188万円以下) | 3万円 |
出典:『令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)』国税庁
特定親族とは具体的に、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を指します。ただし、配偶者や青色申告事業専従者として給与を受け取っている人、白色事業専従者は対象外です。例として、里子を含む大学生年代の子どもなどが挙げられます。
つまり、被扶養者である特定親族の年収が103万円を超えても、扶養者は控除を受けられるようになりました。
たとえば、子どものアルバイト収入が増えたとしても、扶養者(年末調整の対象となる従業員)の控除額が増えるため、手取りが急に減ることはありません。
さらに、特定親族が「年収の壁」を気にして就業を調整する必要が薄れることで、労働力不足の解消も期待されています。
従業員が特定親族特別控除を受けるためには、申告が必要です。企業は従業員に向けて、特定親族特別控除について説明し、必要な申告書を提出してもらうよう案内しましょう。
4.扶養親族などの所得金額要件を引き上げ
基礎控除の見直しにともない、扶養控除などの対象となる扶養親族等の所得金額要件が10万円引き上げられます。
具体的な所得金額要件は、以下のとおりです。
| 対象者 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| ・扶養親族 ・同一生計配偶者 | 合計所得金額48万円以下(給与収入額103万円以下) | 合計所得金額58万円以下(給与収入額123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子ども | 総所得金額等の合計額48万円以下(給与収入額103万円以下) | 総所得金額等の合計額58万円以下(給与収入額123万円以下) |
| 配偶者特別控除対象の配偶者 | 合計所得金額48万円超133万円以下(給与収入額103 万円超 201 万 5,999 円以下) | 合計所得金額58万円超133万円以下(給与収入額123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 合計所得金額75万円以下(給与収入額130 万円以下) | 合計所得金額85万円以下(給与収入額150万円以下) |
参照:『令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)』国税庁
基礎控除の見直しにあわせ、家内労働者等の事業所得計算における必要経費の保障額も55万円から65万円へ引き上げられます。
2025年の年末調整では、扶養親族の所得要件引き上げにより、新たに扶養控除対象となる親族があらわれる可能性があります。
対象となる従業員には「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらえるよう、事前に確認・周知を徹底しましょう。
5.住宅ローン控除の拡充措置継続
住宅ローン控除については、2024年の拡充措置が継続されます。要点は以下の3つです。
- 借入限度額水準の上乗せ
- 床面積要件の緩和
- 既存住宅の子育て対応リフォームに関する特例措置
借入限度額水準の上乗せ
2024年から、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築住宅等に入居する際、借入限度額水準が引き上げられました。2025年も本内容の維持が決定しています。
対象の借入限度額水準は、以下のとおりです。
| 住宅種類 | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
対象となるのは、次のどちらかに該当する世帯です。
- 19歳以下の子どもを養育する世帯
- 夫婦どちらかが40歳未満の世帯
世帯が要件を満たすかどうかは、2025年12月31日時点の状況で判断されます。
床面積要件の緩和期限
2024年までの時限措置としていた床面積要件の緩和期限が延長されました。
本来、新築住宅の床面積要件は50㎡以上ですが、緩和措置として40㎡以上でも対象とされます。
ただし注意点として、「合計所得金額1,000万円以下」という所得要件を満たす必要があります。
子育て対応リフォームへの特例措置
子育て世帯や若者夫婦世帯が、既存住宅において子育てに対応するためのリフォームをした場合、費用を一部控除する特例措置も継続されます。
一般的な工事費用相当額の10%を、所得税から控除するという内容です。特例措置の延長期限は、2025年12月31日までです。
2025年の税制改正で注目される「103万円の壁」引き上げ
2025年の税制改正でとくに注目されているのは、「103万円の壁」が最大で「160万円の壁」にまで引き上げられる点です。
年収の壁引き上げにより、扶養内での就労を維持できる年収の範囲が広がることになります。
とくに、扶養内で働く子どもや配偶者がいる従業員にとっては、大きな影響があります。
103万円の壁とは
103万円の壁とは、所得税がかからない給与収入の基準を指します。アルバイトやパートを含めて企業で働く従業員は、給与所得から基礎控除額や給与所得控除額を差し引いた課税給与所得額によって、所得税が決まります。
改正前までは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合計した103万円が非課税ラインとされてきました。給与収入が103万円以下なら、課税所得は0円であるため、所得税もかかりません。
一方で、収入が103万円を1円でも超えると、超過金額は課税対象となり、所得税が発生します。
結果として、手取りが減少したり、親の扶養から外れたりするため、働く時間を調整する人が多くいたのです。
103万円の壁が引き上げられることによる変化
年収160万円(基礎控除以外の所得控除なし)を例として、パート従業員の課税所得がどう変わるのか以下で確認してみましょう。
【改正前】
| 160万円(年収)ー55万円(給与所得控除)ー48万円(基礎控除)=57万円(課税所得) |
57万円が課税対象となり、所得税がかかります。年収160万円すべてに課税されるわけではありませんが、手取りは減少します。
2025年の税制改正により、給与所得控除や基礎控除が拡充されるため、課税対象になる基準が引き上げられると、手取りはどのように変化するのでしょうか。
| 160万円(年収)ー65万円(給与所得控除)ー95万円(特例ありの基礎控除額)=0円(課税所得) |
控除額が収入を上回るため、課税所得は0円となり、所得税はかかりません。手取り収入や世帯収入が減少したり、学生が親の扶養から外れたりするリスクも避けられます。
ただし、基礎控除95万円はあくまでも、所得要件に応じた特例(時限措置)です。2025年以降の基礎控除額は原則58万円です。
103万円の壁が引き上げられる理由
103万円の壁が引き上げられる背景には、働き控えによる人手不足の解消と物価高にともなう生活コストへの配慮が挙げられます。それぞれの理由を詳しく解説します。
働き控えと人手不足の解消
扶養内で働く配偶者や子どもは、103万の壁を超えないよう就業時間を調整するのが一般的です。企業が賃上げをしても、労働者は収入を抑えるためにさらに勤務を減らし、人手不足が加速するという悪循環が生じていました。
103万円の壁は、扶養内で働く労働者にとっては「働きたくても働けない要因」、企業にとっては「人手不足を解消できない要因」となり、問題視されていたのです。
103万円の壁を引き上げれば、手取り額の減少リスクが抑えられ、働き控えによる人手不足の緩和が期待できます。
物価高にともなう生活コストへの考慮
昨今の物価高により、食品や日用品、ガソリンなどモノやサービスの値段が高くなっています。
103万の壁があると、扶養内で働く人は収入を増やせず、物価高に対応できないという矛盾が生じていました。
課題を解消するため、控除額の見直しによって、収入を増やしても扶養から外れにくい仕組みを整えることになったのです。
年収の壁の注意点
103万円の壁が引き上げられても、安心はできません。そのほかの年収の壁 にも注意する必要があります。
代表的なのが、106万円の壁や130万円の壁(社会保険上の壁) です。
社会保険上における被扶養者の年収が、社会保険上の壁を超えると、社会保険料の加入義務が発生します。
所得税だけを踏まえれば年収160万円を意識すればよいですが、社会保険の壁を超えると別の負担が発生するのです。
企業の担当者は、従業員に年末調整の変更点などを周知する際に、社会保険上の壁についてもあわせて説明しておくと親切でしょう。
2025年の年末調整における実務上の留意点
2025年の年末調整について、企業の担当者が注意したいポイントを解説します。
とくに留意したいのが、新たに扶養する家族がいる従業員や、税制改正が適用されるタイミングです。
担当者が誤った対応をしてしまうと、所得税の計算に誤りが生じ、従業員が正しい控除を受けられません。
扶養控除等(異動)申告書や特定親族特別控除申告書の確認
給与所得控除の見直しや特定親族特別控除の創設により、新たに扶養控除の適用を受ける従業員がいます。
該当者には「扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出してもらう必要があります。
年末調整の実務担当者は、申告遅れがないよう、早めの提出を呼びかけましょう。一般的な企業の提出期限は、例年11〜12月にかけてです。
また、2025年の改正で変更された控除額に関連して、記載内容に誤りや不備がないか必ず確認しましょう。
システム対応
給与計算システムや年末調整のソフトを使用している場合は、税制改正後の控除額が正しく更新・反映されているか確認が必要です。
法改正に自動対応するシステムでも、間違いなく適用されているかどうか確認しましょう。
公的年金における源泉徴収事務の対応
公的年金の源泉徴収事務にも留意しなければなりません。具体的な対応は以下のとおりです。
- 2025年12月の年金支払いでは、税制改正後の基礎控除額を用いて税額を計算する
- 税制改正前2025年11月までの源泉徴収税額との差額を精算する
公的年金等の受給者が還付金を受け取る場合は、公的年金等の支払者が還付金を支払います。
ただし、特定親族特別控除や新たに扶養控除等の適用を受ける従業員は、確定申告をしなければなりません。
企業の担当者は、該当する従業員がいるかどうかを確認し、適切に対応を伝えましょう。
参照:『令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(P.23)』国税庁
そのほか計算における留意点
年末調整では、給与所得から給与所得控除を反映させたうえで、基礎控除額や特定親族特別控除額を控除します。2025年の税制改正を踏まえた対応は、以下のとおりです。
| 時期 | 対応 |
| 2025年11月まで | 改正前の税制で対応 |
| 2025年12月以降 | 改正後の税制で対応 |
税制改正後の内容は、2025年12月1日に適用を開始します。
2025年11月までの源泉徴収事務などは変更ありませんが、2025年12月1日以降に行う年末調整では、税制改正後の内容を適用します。
つまり、年の途中で改正が行われるため、年末調整では改正前の源泉徴収との差額を精算しなければなりません。
計算ミスを防ぐため、社内で二重チェック体制を整えるといった対応をおすすめします。
2025年の年末調整における書き方のポイント
2025年の年末調整において、書き方を注意したい書類は以下の4種類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書(新規様式)
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
企業の担当者が書類の書き方を理解することで、あらかじめ従業員へ周知できるため、ミスや不備の防止につながります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において、書き方の変更点はありません。
しかし、新たに扶養対象となる親族がいる従業員は、変更内容を記載して提出してもらう必要があります。とくに以下の点に注意しましょう。
| 「異動月日及び事由」欄 | 新たに扶養対象となる親族がいる従業員は、年月日と理由を記載 |
| 「非居住者である親族」欄 | ・新たに扶養する親族が非居住者である場合は、「非居住者である特定親族」欄に「〇」を記入 |
| 「生計を一にする事実」欄 | ・1年間に送金等した金額を記入 |
「非居住者」とは、日本に住所を持たず1年以上日本に住んでいない者を指します。
給与所得者の特定親族特別控除申告書(新規様式)
特定親族特別控除の対象親族がいる従業員には、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出してもらいます。
特定親族特別控除申告書では、以下の点をポイントとして意識しましょう。
| 「非居住者である特定親族」欄 | ・特定親族が非居住者である場合は、「非居住者である特定親族」欄に「〇」を記入 ・「生計を一にする事実」の欄に、送金等した金額を記入 ・親族関係を証明する書類や送金したことのわかる書類の用意 |
| 「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」欄 | ・特定親族の合計所得金額の見積額を記入 |
| 「特定親族特別控除の額」欄 | ・見積額に基づいて「控除額の計算」表を活用し、控除額を記入 |
共働き夫婦の世帯など、ひとつの世帯で所得者が2人以上いる場合、控除を適用できるのはどちらか1人のみであることに注意が必要です。
共働きの従業員には、あらかじめ伝えておくとよいでしょう。
参照:『令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書』国税庁
給与所得者の基礎控除申告書
基礎控除額の見直しが行われたため、「基礎控除申告書」に改正後の基礎控除額が記載されているかどうかを確認します。
給与所得額が低いほど、基礎控除額は大きくなります。
企業の担当者は、従業員の給与所得額によって基礎控除額が異なる点に注意して計算しましょう。
給与所得者の配偶者控除等申告書
基礎控除や給与所得控除の見直しにともない、配偶者控除の控除額も変更されました。配偶者控除等申告書では、とくに以下の2点に注意します。
- 配偶者の合計所得金額が、改正後の給与所得控除額を反映した内容になっているか
- 改正後の給与控除額を反映した合計所得金額に対して、配偶者控除額は正しいか
基礎控除申告書と同様に、申告書の書き方に変更はありません。企業の担当者は、正しい金額が記載されているかどうかを確認しましょう。
2026年の年末調整における変更点
2025年の税制改正により、2026年の年末調整にも変更が生じます。主な変更点は、源泉徴収事務と子育て世帯に対する控除拡充です。
扶養控除等申告書に源泉控除対象親族を記載
2026年以降に支払う給与や賞与に対する所得税は、2025年の税制改正内容を反映した「令和8年分 源泉徴収税額表」を用いて計算します。
具体的な税額は、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された扶養親族等の人数で決まります。
特定親族特別控除が創設されたことによる扶養親族等の人数算定の変更は、以下のとおりです。
| 時期 | 扶養親族等の数を算定する基準 |
| 2025年分までの源泉徴収事務 | 源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の数 |
| 2026年分以降の源泉徴収事務 | 源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の数 |
2026年の年末調整における「扶養控除等申告書」には、「源泉控除対象親族」を記載することになります。
源泉控除対象親族の要件は以下の2点です。
- 控除対象扶養親族である
- 居住者と生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下である
特定親族特別控除の創設により、合計所得金額が100万円以下の特定親族も、源泉徴収税額を計算する際の控除対象として扱えるようになります。
2026年分の年末調整における実務では、源泉控除対象親族の記載について従業員への周知が必要です。担当者は、従業員から提出された申告書に源泉控除対象親族が正しく記載されているかどうかも確認しましょう。
子育て世帯等に対する控除の拡充や対応
2026年の年末調整では、子育て世帯等に向けた控除の拡充や対応も注目されています。
具体的には、生命保険料控除の拡充と住宅借入金控除の特別措置です。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
現行の生命保険料控除では、その年に支払った3種類の生命保険料に対して最大で各4万円(合計で最大12万円)の控除を受けられます。3種類の生命保険料は以下のとおりです。
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
2026年以降は、子育て世帯に対する一般生命保険料の拡充が予定されています。
具体的には、23歳未満の扶養親族がいる従業員に対して、一般生命保険料の控除額を4万円から6万円に引き上げる内容です。
生命保険料控除額が合計12万円までという点は変わりません。
子育て世帯や若者世帯に対する住宅借入金控除の特別措置
住宅ローン控除において、子育て世帯や若者世帯が2025年中に入居した場合は住宅借入金控除の特別措置が適用されます。
住宅借入金控除の適用について、初年度は従業員本人が確定申告をします。2年目以降は企業が年末調整で対応します。
2025年中に入居した際の住宅借入金控除が年末調整に影響するのは、2026年です。
なお、特別措置が2026年も継続されるかどうかは未定です。国土交通省の最新情報や2026年の税制改正内容を随時チェックするようにしましょう。

まとめ
2025年の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族の所得要件引き上げ、住宅ローン控除の拡充継続が盛り込まれています。
税制改正により、年収の壁や扶養控除の扱いにも影響が出るため、企業の担当者は正しく理解し、早めに準備を進めることが重要です。
また、今回は税制改正が年の途中から適用されるため、従業員からの質問や相談が例年より増えることが予想されます。
担当者は手続き対応だけでなく、問い合わせ窓口の体制も整えておくと安心です。

