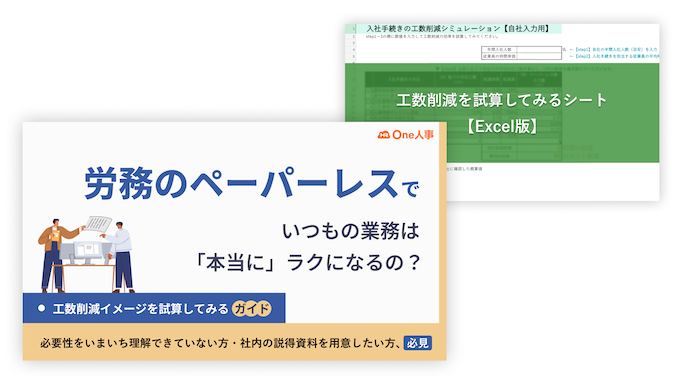年末調整で印鑑は不要? 訂正印の必要性や脱ハンコに向けた取り組みを解説

もともとは年末調整の書類の多くに押印が必要でしたが、2021年の税制改正によって押印が不要となりました。
本記事では、年末調整において押印が不要となった理由や訂正印の必要性についてわかりやすく解説します。年末調整の手続きで訂正が必要となるケースや、印鑑を廃止する具体的な取り組みなども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
→年末調整を効率化「One人事」の資料を無料ダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整では印鑑が不要に|脱ハンコで押印義務は廃止
2021年の税制改正によって、年末調整のの書類に印鑑を押す必要がなくなりました。
以前は、年末調整をはじめとする税務関係の書類には、法律で押印が求められていました。しかし、2021年4月1日から押印義務が見直され、一部の書類を除いて、ほとんどの書類で印鑑が不要となっています。
参照:『I 昨年と比べて変わった点』国税庁
参照:『税務署窓口における押印の取扱いについて』国税庁
▼年末調整以外の労務書類の押印については、次の記事でご確認ください。
印鑑・押印が不要となった4つの理由
近年「脱ハンコ」の動きが急速に加速しています。印鑑・押印が不要となった主な4つの理由を解説します。
- コンプライアンスの強化
- コスト削減や書類保管の負担軽減
- 生産性や業務効率の向上
- 環境にやさしい働き方と業務のデジタル化の推進
押印を廃止する流れには、業務改善や働き方改革につながる背景があります。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

コンプライアンスの強化
印鑑を押すには当然ながら紙の書類が必要です。しかし、紙の書類には紛失や改ざんのリスクがつきものです。書類を電子化することで、適切なセキュリティ対策が施されるため、コンプライアンスの強化につながります。
コスト削減や書類保管の負担軽減
印鑑による押印を廃止すれば、コスト削減や書類の保管にかかる負担を大幅に軽減できます。
ペーパーレス化により、紙代や印刷代だけでなく、捺印や製本、修正にかかる手間やコストを削減することが可能です。さらに、書類の保管や整理のための手間がかからなくなるため、業務効率化にもつながるでしょう。
生産性や業務効率の向上
押印を廃止することで、生産性や業務効率の大幅な向上が期待できます。
従来の印鑑・ハンコ文化には、「紙に押印しないと業務が進まない」「書類のやり取りに時間がかかる」といったデメリットがありました。押印の手間を省けば、より本質的な仕事やサービスの質向上に集中できるようになるでしょう。
▼実際のところペーパーレス化で、どれほど生産性が上がるのか、気になりませんか。年末調整を含め、ペーパーレス化による工数削減効果を試算するには、次の資料をぜひご活用ください。
環境にやさしい働き方と業務のデジタル化の推進
印鑑をなくし、ペーパーレス化を進めることで、紙の使用を減らし、環境負荷の軽減につながります。
また、押印のためだけに出社する必要もなくなり、時間や場所にしばられず柔軟に働けるようになります。コロナ禍で広まったテレワークやリモートワークといった多様な働き方の促進や、業務全体のデジタル化にも貢献するでしょう。
▼年末調整についてもペーパーレス化が進んでいます。具体的な方法を知るには、次の記事もご確認ください。
印鑑が不要になった年末調整の書類
年末調整で印鑑・押印が不要となった書類は、次のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書
年末調整は、従業員の所得税の過不足を精算するための手続きです。年末調整では、さまざまな書類を提出しなければなりません。
▼書類の保管期間を知るには、次の記事もご確認ください。
年末調整に訂正印は必要?不要?
年末調整で提出する書類に、訂正を示す印鑑は必要ありません。国税庁のホームページにも記載があるように、書き損じの箇所については二重線を引いて正しい内容に書き直すだけで、修正が完了します。
ただし、訂正印を押したからといって問題になるわけでもありません。
年末調整の誤りを正しく修正する方法
年末調整の書類の誤りを修正する方法として、修正液や修正テープの使用は認められていません。間違えてしまった場合は、二重線を引き、上の欄などの余白部分に正確な内容を記載します。
あまりにも訂正箇所が多い場合は、新しい書類を用意して従業員に書き直してもらうことも検討しましょう。源泉徴収票を発行する前であれば、申請書類の書き直しをしても問題はありません。

年末調整の提出期限
年末調整の提出期限は、毎年1月31日と定められています。期限を過ぎてしまうと修正対応ができなくなるため、注意しましょう。
企業は、従業員への確認や修正依頼が必要となることを想定したうえで、期限を厳守できるよう余裕を持って対応しなければなりません。
修正が間に合わないという理由で罰則されることはないものの、提出期限を過ぎてしまったら従業員本人による確定申告が必要です。万が一、確定申告をしないと、追徴課税の対象となるおそれがあります。
年末調整で訂正が必要となる3つのケース
「あとから扶養が変わった」「収入の見込みがずれていた」など、年末調整では提出後に訂正が必要になることもめずらしくありません。以下では、よくある3つのケースを紹介します。
- 記載内容に誤りがあった
- 扶養親族の人数に変更があった
- 従業員本人や配偶者の年収と見込み額に大きく差が生じた
記載内容に誤りがあった
年末調整の提出書類の記載内容に誤りがあった場合は、訂正が必要です。とくに、個人情報や金額など申請するうえで重要な情報に関する誤記載や未記入は、税務署からの指摘の対象となるため修正しなければなりません。
扶養親族の人数に変更があった
年末調整の申告をしてから、従業員もしくは配偶者の扶養親族の人数に変更が生じた場合も、訂正が必要です。結婚や離婚、死別などで扶養親族の人数が変わると、控除額も変わる可能性があるためです。
出産によって扶養親族が増えた場合も、夫婦それぞれの年収額に応じて所得金額調整控除の対象となり、訂正が必要になるケースがあります。
従業員本人や配偶者の年収と見込み額に大きく差が生じた
年末調整では、基本的に見込みの所得額をもとに手続きをするため、実際の所得と違いが生じる場合も少なくありません。
とくに、従業員本人や配偶者の所得によって控除額も変動するため、申告済みの金額と大きく異なる場合は訂正が必要です。
ただし翌年に給与改定があり、さかのぼって今年の分も支給される場合、増えた金額は翌年の所得として扱われるため、年末調整の訂正は不要です。
▼万一、間違いに気づかないとどうなるのでしょうか。詳しくは次の記事でご確認ください。
社内で印鑑・押印業務を廃止するには? 進め方
年末調整をはじめ脱ハンコの動きが進むなか、「自社ではどこから手をつければいいのか」と迷う担当者も多いのではないでしょうか。社内で印鑑を廃止するための3つのステップを紹介します。
- 押印の必要性を見直す
- 社内の書類フローから段階的に押印をなくす
- 電子契約サービスの導入を検討する
それぞれのステップについて、具体的に見ていきましょう。
1.企業内での書類で押印の必要性を話し合う
現状を把握するためにも、まずは社内で印鑑・押印の必要性について話し合う機会を設けましょう。
近年は、e-文書法や電子帳簿保存法の整備が進み、社内の書類だけでなく請求書や領収書なども押印を省略できるケースが増えています。自社の書類を棚卸ししたうえで、必要性を判断し、押印を廃止できる業務を集約しましょう。
具体的には、次のように書類を3つに分類すると、押印をやめられる業務がどこにあるのかが見えてきます。
- 押印が必要な書類
- 押印以外の処理で対応できる書類
- 押印が不要な書類
分類をもとに、押印が形式的になっている業務から優先的に見直すと、社内全体の理解が得られるでしょう。
2.社内において「脱ハンコ」に向けた取り組みを進める
脱ハンコの取り組みを推進するためには、印鑑を必要としていた企業体制を根本から変えていかなければなりません。
すべての書類をまとめて押印不要とするのではなく、まずは優先順位をつけることから始めましょう。申請書や稟議書のように、社内で完結する使いやすい書類から押印不要とするのがおすすめです。
脱ハンコに向けた取り組みと並行して、業務フローの見直しやインフラ整備も段階的に進めていきましょう。ワークフローシステムの導入もおすすめです。
3.電子契約サービスを導入する
社内における脱ハンコの動きが進んだら、社外との取引での押印廃止を推進するため、電子契約サービスの導入を検討しましょう。
電子契約サービスとは、取引に必要な契約を電子化するシステムのことです。活用により、電子文書の署名やタイムスタンプを付与でき、書類としての法的効力が発生します。
取引先が自社と異なるサービスを利用していても電子契約を締結できるサービスを選ぶと、印鑑廃止に向けてスムーズに手続きを進められるでしょう。
実績や希望のサービス、機能などを総合的に比較し、自社に最適なサービスを導入することをおすすめします。
▼各業務の電子化に向けた取り組みは、次の記事でご確認いただけます。
年末調整の間違いを防ぐ3つのコツ
提出ミスや記入漏れなど、年末調整の現場では毎年さまざまなトラブルが起こりがちです。
確認作業に追われる担当者の負担を減らすには、あらかじめおさえておきたい基本の対策があります。実務で役立つ3つのコツを紹介します。
1.従業員に早めに年末調整書類を手渡す
年末調整の手続きをする時期は、年末の業務が忙しくなるタイミングと重なります。担当者はもちろん、従業員たちに余裕を持って対応してもらうためにも、早めに書類を手渡すように心がけましょう。
保険会社から証明書が届き始める10月頃を目処に、年末調整の説明をしておくのがおすすめです。新入社員をはじめとした若手社員のなかには、年末調整の手続きを理解していない人もいます。メールや書面、ポスターなど、さまざまな手段を使って従業員たちに周知するとよいでしょう。
2.申告前のチェックを徹底する
年末調整におけるミスを回避するためには、申告前のチェック体制を強化する必要があります。
年末調整で提出すべき書類は多岐にわたります。また、年末調整の手続きは、たびたびルールが改正されている非常に煩雑な業務です。従業員の誤記載や未記入などの細かなミスを見落とさないために、複数人の担当者によるダブルチェックを徹底していきましょう。
▼回収書類のチェックに時間を取られていませんか。回収作業の手間を減らすなら年末調整の電子化がおすすめです。書類の一括チェック機能があるため、紙を目視で確認するよりもラクに確認を完了できます。
→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

3.従業員に事前確認を呼びかける
年末調整の間違いに気づかなかった場合や修正が間に合わない場合は、従業員自身で確定申告をする必要があります。確定申告をするとなると、従業員がやるタスクが増えてしまいます。
年末調整の担当者は、従業員に対して確定申告をするケースがある旨を伝えたうえで、提出書類や記入内容のミスが生じないように呼びかけることが重要です。
まとめ|年末調整の書類に印鑑を押す場所はない
年末調整において印鑑が不要な理由や、脱ハンコに向けた具体的な取り組みを詳しく解説しました。押印を不要とし、ペーパーレス化を進めることは、コスト削減はもちろん生産性や業務効率の向上に大きく貢献します。
企業内で脱ハンコをする書類の精査や電子契約サービス導入を検討し、社内のデジタル化を推進していきましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。回収書類は画面上で一覧表示され、申告内容も書類ごとに一括でチェックが可能。書類を一枚一枚目視で確認しなくても、対応漏れの防止に役立ちます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |