年末調整の提出はいつまで? 提出スケジュールや期限遅れの対応を解説
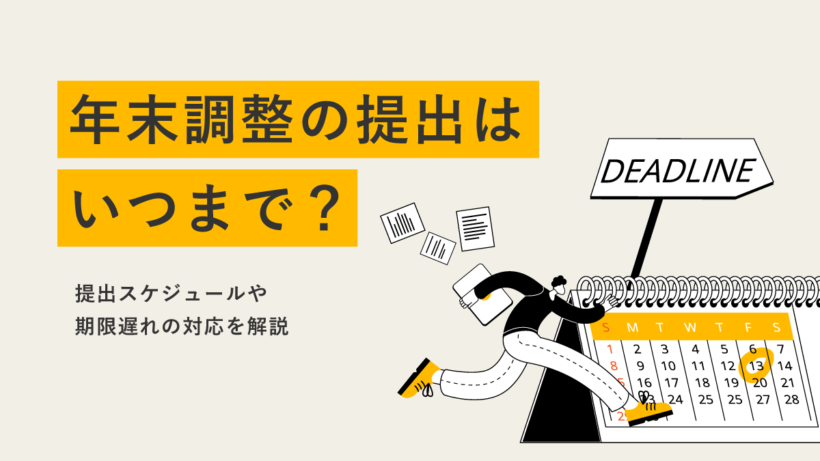
年末調整は、結局いつまでに何をすればよいのか整理できていますか。毎年担当しているものの、必ずバタバタしてしまうという担当者は少なくありません。しかも、提出が遅れた場合のリスクや対応まで考えると、不安になる方もいるでしょう。
年末調整は、従業員の所得税を精算するために企業に義務づけられた大切な手続きです。提出のタイミングや内容を間違えると、従業員に確定申告をしてもらう必要が出てきたり、企業としての信頼にかかわることもあります。
本記事では、年末調整の書類提出スケジュールや、提出が間に合わなかった場合の対処法をわかりやすく解説します。社内の案内文作成や説明にもぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
年末調整とは
年末調整とは、会社や雇用主が従業員の給与から源泉徴収した所得税・復興特別所得税を精算する手続きです。
企業が役員や従業員に給与を支払う際、所得税や復興特別所得税について源泉徴収を行うのが一般的です。源泉徴収とは、所得税や復興特別所得税を給与からあらかじめ差し引くことを指します。源泉徴収をされた役員や従業員には、確定申告をする必要がなくなるというメリットがあります。
しかし、源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額は、本来納めるべき税額と基本的に一致しません。そのまま放置してしまうと正しい納税ができないため、年末調整の手続きが必要なのです。多くの給与所得者は、年末調整の手続きによってその年の納税が完了します。
▼年末調整業務の進め方に不安がある方は、次の資料もぜひご活用ください。
年末調整の書類の提出期限はいつ?
| 提出元・提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 従業員から企業 | ・扶養控除等(異動)申告書 ・保険料控除申告書 ・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 11月上旬から12月上旬(※) |
| 企業から税務署 | ・支払調書・源泉徴収票・法定調書合計表 | 翌年1月31日 |
| 企業から市区町村 | ・給与支払報告書(総括表・個人別明細書) | 翌年1月31日 |
(※)一般的な企業の例です。
年末調整は、例外的な場合を除いて年末に行われます。社内の年末調整担当者が集めて処理した書類を、税務署や市区町村へ翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
企業は提出期限に向けて年末調整の準備を進めますが、手続きを完了させるためには従業員が提出する書類が必要です。
以下では、従業員側の書類の提出期限や、年末調整によって過払いが還付される時期を解説します。

従業員による申告書の提出期限
年末調整では、従業員から以下の書類を提出してもらう必要があります。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼配偶者控除等申告書兼特別親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書※
※特別親族特別控除は、令和7年の年末調整から適用されます。
年末調整で生命保険料や地震保険料などの控除を受ける場合には、保険料控除申告書と一緒に控除証明書の提出も必要です。
年末調整の書類の提出期限は翌年1月31日、源泉所得税の納付期限は翌年1月10日です。しかし、チェック作業のためにも、従業員には11月上旬から12月初旬を目処に提出してもらいましょう。
▼回収書類のチェックに時間を取られていませんか。回収作業の手間を減らすなら年末調整の電子化がおすすめです。書類の一括チェック機能があるため、紙を目視で確認するよりもラクに確認を完了できます。
→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

年末調整が還付されるタイミング
毎月給与から天引きされていた源泉徴収税額が本来支払うべき所得税額よりも多かった場合は、年末調整によって過払い分が還付されます。
所轄の税務署から還付金が支払われるタイミングは、12月から1月にかけてです。原則として、年末調整の手続きが完了した時期が早ければ、還付されるタイミングも早くなります。
従業員への還付は、年末調整後の最初の給与支給時(当年の12月)に、給与と一緒に行われるのが一般的です。ただし、企業によっては還付金を手渡したり、給与支給時とは異なるタイミングで振り込んだりする場合もあります。
年末調整で還付金が支払われる主なケースは、以下のとおりです。
- 生命保険や医療保険に加入している(生命保険料控除)
- 扶養家族が増えた(扶養控除)
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している(小規模企業共済等掛金控除)
- 住宅ローンを返済している(住宅借入金等特別控除)
支払った源泉徴収税額が本来払うべき所得税額を下回った場合は、年末調整後に支給される最初の給与から天引きされるのが一般的です。
年末調整の一般的なスケジュール
年末調整における大まかな流れは、次のとおりです。
| 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|
| STEP1.従業員による申告 | STEP2.年末調整の計算 | STEP3.法定調書の作成・提出 |
| ・年内に支払う給与の確定 ・申告書の配布/回収/チェック ・修正依頼などの個別対応 | ・年末調整の計算 ・所得税の過不足分の還付または追加徴収 | ・源泉所得税の納付 ・税務署への年末調整関係書類の作成/提出 ・自治体への住民税関係書類の作成/提出 ・年末調整関連書類の保存 |
それぞれのタイミングに、取りかかるべき業務内容を詳しく解説します。
11月に行う年末調整業務
11月に行う年末調整業務は、主に次のとおりです。
- 年内に支払う給与の確定
- 申告書の配布・回収・チェック
- 修正依頼などの個別対応
まずは、毎月の給与や賞与を含む年間給与を確定させる必要があります。たとえば、月末締め・翌月25日払いの企業の場合、11月末のタイミングで年内に支払う給与が確定しているはずです。確定した時点で、従業員に対して申告書や証明書を提出するように促しましょう。
従業員から回収した申告書や証明書の内容を確認し、誤りや不備があったら、当該従業員に修正や再提出を依頼するなどの対応が必要です。
12月に行う年末調整業務
12月に行う年末調整業務は、次のとおりです。
- 年末調整の計算
- 所得税の過不足分の還付または追加徴収
従業員が提出した申告書や証明書の内容から控除額を計算し、従業員の所得税を割り出しましょう。
給与から源泉徴収している所得税と、年間所得に応じて算出した正確な所得税の差額がないかを確認し、12月分の給与で過不足分を調整します。
1月に企業が行う年末調整業務
1月に行う年末調整業務は、次のとおりです。
- 源泉所得税の納付
- 税務署への年末調整関係書類の作成・提出
- 自治体への住民税関係書類の作成・提出
- 年末調整関連書類の保存
年末調整によって確定した所得税を、翌年1月10日までに所轄の税務署に納めます。
また、翌年1月31日までに、税務署や市区町村へ下記の書類を提出します。
| 税務署 | 市区町村 |
|---|---|
| ・支払調書 ・源泉徴収票 ・法定調書合計表 | ・給与支払報告書(総括表・個人別明細書) |
年末調整関連書類は、翌年1月10日の翌日より7年間保管しなければなりません。税務署長から提出を求められる場合もあるため、必要書類を適切に作成し、管理する必要があります。
年の途中で年末調整を行うケースとは?
基本的に年末調整は年末に処理しますが、退職や海外転勤によって、年の途中で対応が必要になるケースもあります。年末調整を年の途中で実施する「例外的なケース」について整理しておきましょう。
年末調整を退職時に行う
原則として、退職者の年末調整をする必要はありません。退職した従業員が再就職した場合は、転職先の企業で年末調整が実施されます。
ただし、次のような理由で再就職する見込みがないと判断できる場合は、従業員の退職時に年末調整の手続きをします。
- 従業員が亡くなった場合
- 著しく心身の不調をきたしたことを理由に退職する場合(退職後に他社に就職して給与の支払を受ける見込みがある人を除く)
- 12月に支給されるべき給与の支払いを受けたあとに退職する場合
- 本年中の給与総額が103万円以下のパートやアルバイトなどの従業員が退職する場合(退職後に他社に就職して給与の支払を受ける見込みがある人を除きます)
年末調整を出国時に行う
次の条件を満たす場合は、年の途中であったとしても、出国する日までに年末調整をする必要があります。
- 支払いが確定した年内の給与や賞与などの支給額が2,000万円以下である
- 海外支店へ転勤し、海外に住むことが決まっている
年の途中に出国するのではなく、年間を通して海外で勤務している場合は、従業員本人が確定申告の手続きをして、税務署に届け出ます。

年末調整の提出期限に間に合わない・提出が遅れた場合の対応
年末調整の提出書類が間に合わない、従業員からの提出が遅れているというときは、どう対応すればいいか不安になりますよね。実務の現場では、年末調整がスケジュールどおりに進まないこともあるでしょう。
年末調整の提出が遅れた場合の対処法を「従業員側」「企業側」、それぞれの視点で解説します。
従業員が提出期限に遅れた場合
社内で定めている提出期限に遅れたとしても、最終的に企業が税務署へ法定調書を提出する翌年の1月31日に間に合う場合、法律上は問題ありません。
ただし、企業の提出期限である1月31日を過ぎてしまうと、従業員自身で確定申告をする必要があります。確定申告の時期は、原則として毎年2月16日から3月15日です。
従業員が確定申告の手続きを怠ってしまうと、次のようなペナルティの対象となります。
- 無申告課税
- 延滞税
本来の納税額に加えて15〜20%の追加税を支払う「無申告課税」や、延滞した日数に応じた「延滞税」が発生するおそれがあります。
また、従業員の正確な年税額が確定しない限り、企業は差額分の還付ができないと理解しておきましょう。
企業が提出期限に遅れた場合
企業の提出が翌年の1月31日に間に合わなかったとしても、罰則を受けることはありません。数日程度の遅れであれば、事前に所轄の税務署に連絡しておけば待ってもらえるケースも多いため、一度相談してみるとよいでしょう。
提出が大幅に遅れてしまう場合は、従業員一人ひとりに確定申告をしてもらうことになります。
最悪の場合、脱税とみなされて「10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科されるおそれもあるため、提出期限は必ず守るように徹底しましょう。
提出期限後に年末調整の訂正・変更が必要なケースとは
年末調整の申告書を提出したあとで、内容を訂正したくなることも考えられるでしょう。
一般的に翌年1月31日までは、会社の担当部署を通じて、税務署が修正に応じてくれる可能性があります。
以下では、年末調整後に訂正や変更が必要になる代表的な2パターンと、対応方法を紹介します。
所得控除の変更が必要な場合
年末調整を提出したあとで、12月31日までに所得控除の内容に変更があると、申告内容の訂正と再計算が必要です。主に、以下のようなケースが挙げられます。
- 扶養人数の変更(結婚や出産、離婚などにより扶養家族に変更があった)
- 保険の加入(新たに保険に加入し、生命保険料や地震保険料を支払った)
いずれも、正しい控除額に基づいて還付額を再計算する必要があるため、早めの修正が重要です。また、申告書の記載に誤りがあり、本来よりも税額が少なく計算されていたなら、企業側で年末調整をやり直し、不足分の徴収・納付をしなければなりません。
給与や賞与を追加で支払わなければならない場合
年末調整を終えたあとに、12月31日までに給与や賞与の追加支給が発生するケースもあります。たとえば、未払いが発覚した場合や、支給タイミングがずれたことで年内分の所得として扱う必要が出てきた場合です。
この場合、追加分にかかる所得税をあらためて計算し、再度年末調整をやり直す必要があります。
企業側の都合による金額変更であるため、修正処理はすべて企業の責任で対応するのが原則です。
なお、1月1日以降に支払われたぶんは、翌年の年末調整に含まれるため、修正の必要はありません。
まとめ|年末調整の手続きは適切なタイミングで進めましょう
年末調整の手続きは、通常11月から翌年の1月頃にかけて行われます。従業員が勤務先に対して年末調整の申告書を提出するのは、当年の11月から12月上旬頃であるのが一般的です。
企業は、修正や訂正が必要となるケースを想定したうえで、余裕を持って必要書類の提出期限を設定しましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
