帳票とは? 意味や種類と管理保存方法、電子化のメリット・デメリットまで解説
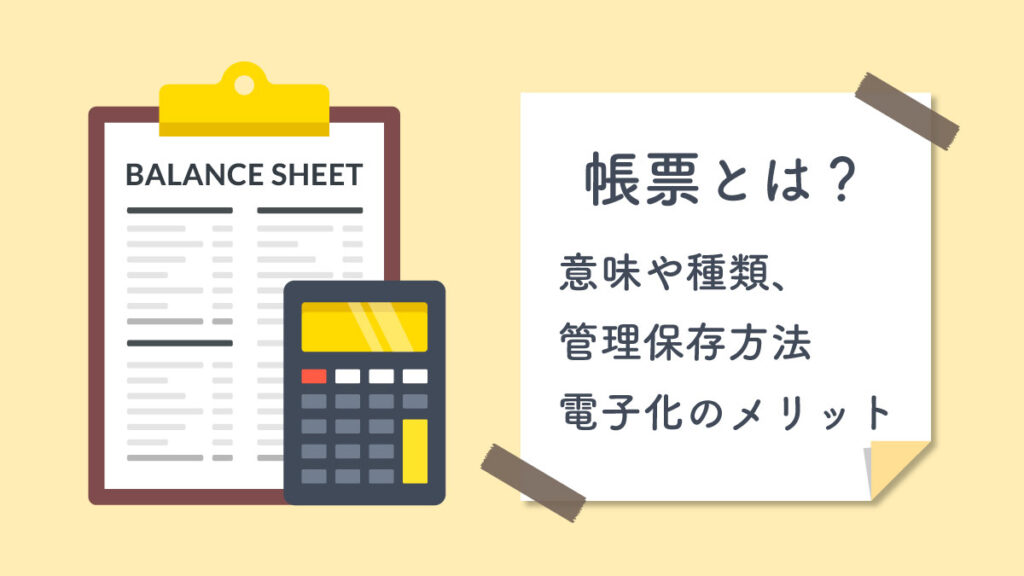
帳票管理は会社を経営するうえで欠かせない業務です。経営状況を客観的に把握できないと、会社の強みや課題がわからないままになってしまいます。
本記事では帳票を作成する目的や種類、具体例を紹介します。また、紙と電子で管理するメリット・デメリット、具体的な管理方法や関連する法律も解説します。人事担当者や経営者は参考にしてください。

 目次[表示]
目次[表示]
帳票とは|意味をわかりやすく
帳票とは、経営活動にかかわる書類のことです。取り引きや経理などのさまざまな書類を指し、経営状況が把握できるため必要不可欠です。
作成する目的・役割
帳票は経営状況を把握するために作成します。これまでどのような取り引きを行ってきたのか、支出はどのくらいなのかなどを可視化できれば経営の課題を洗い出せます。売掛帳や出納帳などさまざまな書類が対象です。
また、帳票は確定申告時に必要になるため、作成しておかなければなりません。書類に不備があると追徴課税の対象になる可能性があるため、日頃から適切に書類管理しておきましょう。
証憑(しょうひょう)書類との違い
証憑(しょうひょう)とは、取り引きの証拠になる書類です。証憑書類は以下のとおりです。
- 領収書
- レシート
- 契約書
- 納品書
- 見積書
- 履歴書
- 健康診断書
取り引きの過程を示す書類なので、経営状況をあらわす帳票とは役割が異なります。
帳票は2種類に大別できる
帳票は帳簿と伝票の2種類に分けられます。それぞれの目的について解説するので、ぜひ参考にしてください。
帳簿の例
帳簿とはお金の流れを記録する書類のことです。帳簿はさらに主要簿と補助簿に分かれます。違いは以下に記載しました。
| 帳簿 | 主要簿 | 総勘定元帳 | |
|---|---|---|---|
| 仕訳帳 | |||
| 補助簿 | 補助記入帳 | 現金出納帳 | |
| 預金出納帳 | |||
| 固定資産台帳 | |||
| 売掛帳 | |||
| 買掛帳 | |||
| 補助元帳 | 商品有高帳 | ||
| 仕入先元帳 | |||
| 得意先元帳 | |||
主要簿は日々の取り引きをすべて記録する書類のことです。補助簿は主要簿では把握しにくい、細かなお金の出入りを記録しています。
伝票の例
伝票とは、取り引き内容を記載した書類のことです。伝票をもとにして仕訳帳や会計簿帳が作成されています。
伝票は主に以下の5種類あります。
- 入金伝票
- 出金伝票
- 振替伝票
- 仕入伝票
- 売上伝票
それぞれの違いは以下の表にまとめました。
| 入金伝票 | 会社に入ってくる現金取り引きを記録する伝票 |
|---|---|
| 出金伝票 | 会社から出ていく現金取り引きを記録する伝票 |
| 仕入伝票 | 仕入れ取り引きを記録した伝票 |
| 売上伝票 | 売り上げがあった場合に記録する伝票 |
| 振替伝票 | 上記すべてに該当しない取り引きを記録する伝票 |
法律で定める帳票の保存期間
帳票は保存しなければならないと法律で義務付けられています。保存期間は法人税法で7年です。会社法では10年と定められています。
法人税法では原則7年
法人税法では帳票の保存期間が原則7年と決められています。期間は確定申告書類の提出期限の翌日から7年間。例外的に白色申告を行った年度で災害損失金額が生じた場合や、青色申告で提出して欠損金が発生したら10年間の保存が必要です。
会社法では10年
会社法では帳票関係の書類は10年間保存しなければならないと定められています。具体的には以下の帳票が対象です。
- 賃借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 会計帳簿
例外はなくすべての企業で行います。
帳票は紙での保存が原則
帳票は紙に出力した状態での保存が義務付けられます。しかし、電子帳簿保存法の要件を満たせば電子化して保存も可能です。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは帳簿や税金にかかわる書類の電子保存を認める法律のことです。従来は紙で保存しなければなりませんでした。
しかし、紙での保存だと場所を確保しなければならなかったり、コストがかかったりするなどの問題がありました。そこで、電子帳簿保存法が制定された結果、電子媒体での保存ができるようになっています。
帳票は電子・ペーパーレス管理が進められている
近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)が促進されており、人事や経理・営業などの部署でデジタル化が進んでいます。経理部門では、請求書の帳票発行業務などが対象です。従来は紙に印刷して郵送が一般的でした。印刷や封入のコストがかかり、時間を取られていました。
しかし、新型コロナウイルスの流行で、出社する機会が減り在宅でも帳票発行業務が行えるよう電子化での対応に変化しています。帳票を電子化できれば、いつでも手軽に閲覧できるためオフィスへの出社が不要。また、管理コストがかからずリスクや費用を抑えられるでしょう。
紙の帳票管理で発生する課題
紙の帳票管理で発生する課題は以下のとおりです。
- 作成に手間がかかる
- コストが高い
順番に解説します。
作成に手間がかかる
紙での帳票作成は手間がかかります。手書きで書類を作成すると時間がかかったり、字が汚くて文字が判別できなかったりする可能性があります。紙をファイルにまとめて保管する手間がかかるなど、さまざまな労力が必要になるでしょう。
コストが高い
紙で帳票管理を行うと管理コストがかかります。毎日かかる用紙代やスペースの確保による管理コストなど、さまざまな費用が発生します。
最大10年は保管しなくてはならないため、膨大な量の紙が必要です。電子化に移行することで、ペーパーレスにつながり管理コストも削減できるでしょう。
帳票を電子化するメリット・必要性
帳票を電子化するメリットは以下のとおりです。
- 帳票の作成時間が短くなる
- コストの削減
- セキュリティの強化
順番に解説します。
帳票の作成時間が短くなる
帳簿を電子化すれば手軽に作成可能です。最初に帳簿のフォーマットを作成しておけば、数字を入力するだけで帳票が完成します。住所や会社名など毎回同じ内容を記載する項目の入力の手間を減らして、効率的な帳票作成が行えるでしょう。
また、請求書をベースに納品書や見積書の作成も行えるため汎用性が高く、使いやすいことも特徴です。
コストの削減
電子化の導入で以下のコストが削減できます。
- 用紙代
- 印刷代
- 封筒代
- 郵送代
- 管理コスト
- 郵送作業にかかる人件費
電子化した帳簿はメールに添付して送信することが可能です。複数人に向けて同時に送信できるため業務効率も上がります。電子化により効率的な運営ができるため、大きなメリットが得られるでしょう。
セキュリティの強化
帳票の電子化はセキュリティ強化に繋がります。電子化を行えば、ファイルごとに閲覧制限をかけることやタイムスタンプの導入、電子署名で改ざんの防止が可能です。長期間の保存が必要な帳票にとってセキュリティは重要なため欠かせません。
帳票を電子化する方法
帳票を電子化する方法は以下のとおりです。
- エクセルで作成した帳票をPDFで出力する
- 帳票システムを導入する
順番に解説します。
エクセルで作成した帳票をPDFで出力する
エクセルで作成した帳票をPDFで保管する方法があります。PDFは汎用性が高いため、メールやクラウドサービスなどさまざまなツールを介して、他社に送付できます。
帳票システムを導入する
帳票システムの導入を検討しましょう。システムにもさまざまな種類があります。帳票の作成や送受信、管理など目的に応じた選択が可能です。
電子帳簿保存法に対応したシステムを導入するなら「JIIMA認証」を取得している製品を選択しましょう。JIIMA認証とは、市販のソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たした製品のことです。すべてのシステムが対応しているわけではないため、導入の際は認証の有無を確認するようにしましょう。
参照:『JIIMA認証制度』公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)
帳票を電子化するデメリット
帳票を電子化するデメリットは以下のとおりです。
- 費用が発生する
- 電子帳簿保存法に合わせた運用が必要
- 取引先にも帳票の電子化への理解が必要
順番に解説するので、ぜひ参考にしてください。
費用が発生する
帳簿の電子化に必要なソフトウェアやシステムの導入のために費用が発生します。システム導入にあわせてパソコンを購入した場合、さらに初期費用がかかります。
費用は、システムの機能が豊富になるほど増加しやすくなるでしょう。自社で必要な機能を確認し、必要な機能を揃えたシステムの導入が必要です。
電子帳簿保存法に合わせた運用が必要
帳票を電子化して保存するためには、電子帳簿保存法に沿った保管が必要です。そのため、保管方法やルールを把握する必要があります。適切に管理されていないと、追徴課税や青色申告の取り消しなどの罰則が科される可能性があります。
取引先にも帳票の電子化への理解が必要
ペーパーレス化が進むことで、取引先にも電子化での対応が求められます。自社だけでペーパーレス化を進めることは難しいため、取引先の協力が必要です。
しかし、取引先によっては導入を見合わせることもあるため、紙で帳票を作成しています。そのため、電子化を行う前に取引先へ意向を確認した方がよいでしょう。
帳票の電子化する際の注意点
帳票の電子化する際の注意点は以下のとおり。
- 電子帳簿保存法に対応しているシステムを選ぶ
- 自社の運用フローに即したシステムを選ぶ
- ツールが使いやすいかを考える
順番に解説します。
電子帳簿保存法に対応しているシステムを選ぶ
導入するシステムが電子帳簿法に対応しているか確認しましょう。せっかく導入しても、法律に適合していない場合、罰則を受ける可能性があります。「JIIMA認証」のあるシステムはすべて電子帳簿保存法に適合しているため、必ず認証を確認しましょう。
自社の運用フローに即したシステムを選ぶ
自社ですでに運用しているシステムと連携できるか確認します。たとえば、販売管理システムを導入している場合は、連携が可能かどうか、ファイル形式の規定はどうなのかを調べておきましょう。システムによっては連携できないこともあります。
ツールが使いやすいかを考える
従業員が使いやすいシステムを導入しましょう。業務が効率的に行えるシステムでも、現場で使いこなせなくては意味がありません。無料お試し期間を設けている企業もあるため、試験運用を行い自社に合っているシステムの導入をおすすめします。
帳票の電子化で業務効率化へ(まとめ)
帳票とは経営状況を把握するために欠かせない書類です。お金の流れを把握するための書類であり、法律に基づいて保存と管理を行いましょう。
紙での管理は作成に手間がかかったり、コストが高くなったりするデメリットが懸念されます。一方で電子化にすると、帳票の作成時間が短くなるだけでなく、コストの削減やセキュリティの強化などのメリットが得られます。
帳票の電子化システムを導入すれば業務が効率的になり、ほかの仕事に取り組めるでしょう。導入を検討している人はぜひ参考にしてください。
