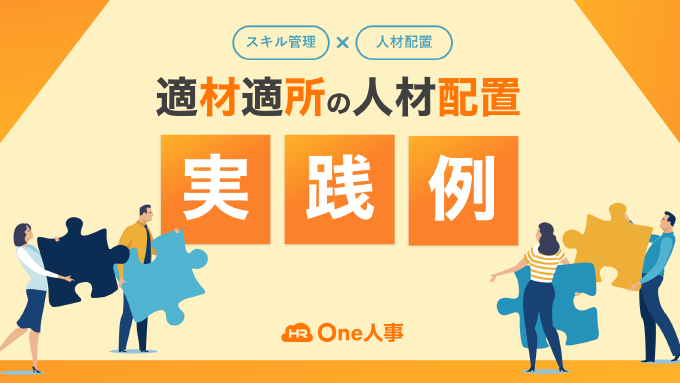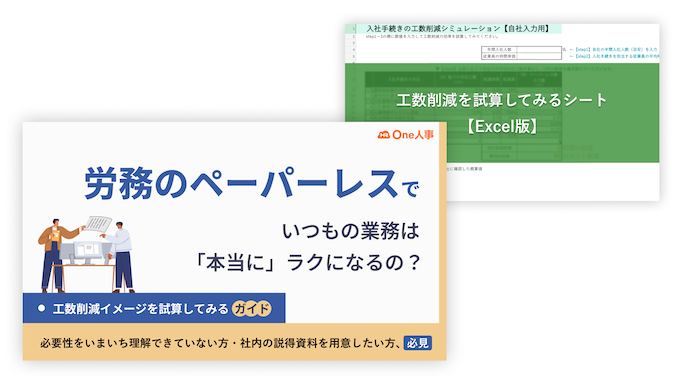平準化とは? 業務改善の進め方と実現ステップ、標準化との意味の違いも解説

平準化とは、業務負担や作業量の偏りをなくし、組織全体のパフォーマンスを安定させる大切な考え方です。忙しい時期や人手が限られた状況でも、一定の成果を出し続けるために欠かせません。
ただ、平準化の意味をわかっているつもりでも、いざ人に説明しようとすると迷ってしまうことはありませんか。
本記事では、平準化の意味を標準化との違いから整理しています。平準化による業務改善への具体策、実現に向けた進め方のステップも解説していていきます。明日から職場に取り入れるためのヒントとして参考にしてください。
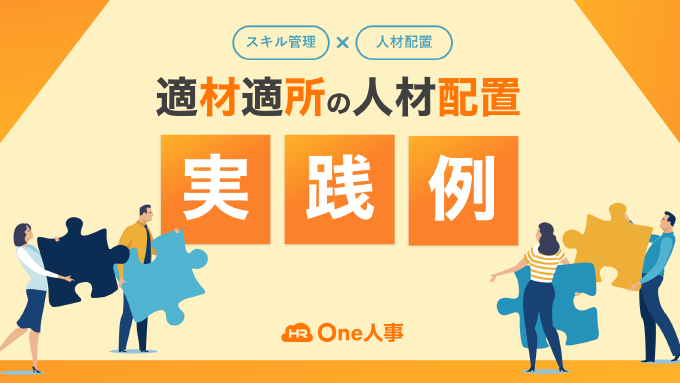
 目次[表示]
目次[表示]
平準化とは? 意味や使い方
平準化(へいじゅんか)の意味とは、バラついているものをできるだけ同じ状態にそろえ、均一にすることです。
たとえば、目の前に3つの箱があり、箱Aにはボールが2個、箱Bには3個、箱Cには7個入っているとします。
箱Aや箱Bと比べると、箱Cだけボールの数が多く、偏りがあります。そのため、一度すべてのボールを出して、3つの箱に4個ずつ分けると、ボールの数がそろいます。
| 平準化前のボールの数 | 平準化後のボールの数 | |
|---|---|---|
| 箱A | 2個 | 4個 |
| 箱B | 3個 | 4個 |
| 箱C | 7個 | 4個 |
「平準化」は、差をなくして均等にするという意味です。日常生活では以下のような使い方があります。
| 平準化の使い方(日常生活の例) |
|---|
| ・家の中の温度を平準化するために、扇風機を使って空気を循環させた ・負担を平準化するために、ごみ当番を交代制にした ・宿題の量を平準化するために日ごとに分けて計画を立てた |
ビジネスにおける業務平準化とは?
ビジネスにおける「平準化」とは、主に業務負担の調整を指す場合に使われる言葉です。
「業務平準化」という表現を耳にしたことはありませんか。業務平準化とは、特定の時期や人に偏りがちな業務量を、できるだけ均等に分け、偏りをなくすことです。とくに製造業と関連が深く、使われることが多くあります。
業務が偏ったまま放置されると、特定の従業員に過剰な負荷をかけてしまいます。身体的・精神的な負荷が続けば、疲労がたまり、やがて効率の低下やミスを招きかねません。
業務平準化の重要性
業務平準化に取り組むことは、特定の人に負担がかかるリスクを防ぎ、組織全体のパフォーマンスを守る大事な施策です。負荷の偏りをなくすことで、従業員のモチベーションを維持し、働きやすい職場環境を整備できます。
ただし業務平準化は、単に作業量を均一にしただけでは、達成されません。従業員一人ひとりのスキルや得意分野を考慮しながら、適切に配分することが重要です。
ビジネスシーンにおける例文
ビジネスシーンにおいて「平準化」という言葉を使った例文を紹介します。
| 平準化の使い方(ビジネスの例) |
|---|
| ・タスクの量を平準化するため、繁忙期に応援要員を配置した・シフト日数を平準化して、スタッフの負担を均等に分けた・生産工程を見直し、製品の生産量を平準化した |
業務負荷に応じて人員を配置するには、一人ひとりのスキルを把握しておくことで、最適化できます。スキルに応じた適材適所の人材配置を実現する方法を知るには以下の資料もご活用ください。
▼業務量に応じて適切に人を配置するには、日頃から各メンバーのスキルを把握しておくことが大切です。一人ひとりの得意分野を活かした最適な人材配置が実現するなら、以下の資料もぜひご活用ください。
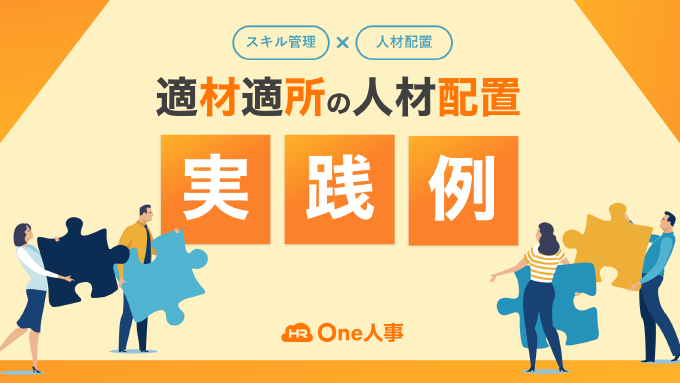
業務平準化と業務標準化との違い
業務平準化とよく似た言葉に、業務標準化があります。
業務「標準化」は、業務のやり方を統一して、全員が同じ手順で進められるようにすることです。効率化や品質向上が期待できます。
一方で、業務「平準化」は、特定の人に仕事が集中しないように、業務の量を均等に分けることを指しています。
どちらも業務改善のための取り組みですが、アプローチの仕方に違いがあり、目的も少し異なります。
まず業務標準化でやり方を統一し、業務平準化に取り組むとスムーズに進められると理解しましょう。
業務改善をはかるうえでは、組織の状況を見ながら、2つの取り組みを使い分けることが大切です。
平準化と均一化、平均化との違い
平準化は偏りをならして、全体の負担をバランスよく整えることを意味します。
一方、均一化は内容や手順を同じ状態にそろえることが目的です。平準化は柔軟な調整、均一化は一律化が重視される点が異なります。
また、平均化は大小や多少の差をなくし、全体を平均に近づける考え方です。
平準化は負荷の分散、平均化は数値的な不均衡の是正を重視しています。
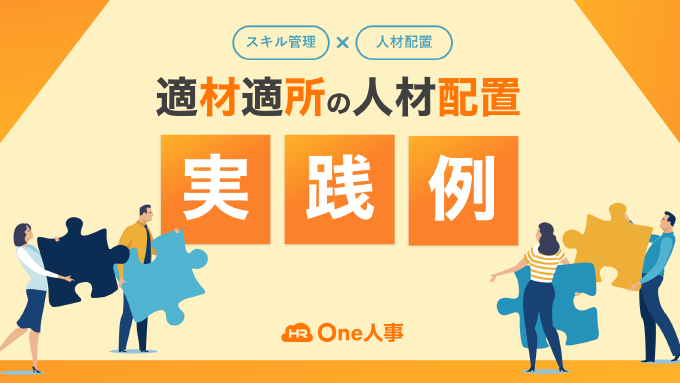
業務が平準化されていない状態
業務が平準化されていないと、特定の人に負担が偏り、チーム全体の働き方がアンバランスになってしまいます。心当たりがある方もいるかもしれません。
具体的には、主に次のようなケースがあてはまります。
- 人によって作業量が大きく異なる
- 季節や時期によって業務量に偏りがある
- 業務が属人化している
- 業務の定型化が進んでいない
平準化されていない状態を放置すると、いざというときに業務が回らなくなるおそれがあります。一つずつ確認していきましょう。
人によって作業量が大きく異なる
一部の従業員に仕事が集中している状況は、平準化できているとはいえません。
チームでタスクを分担しているつもりでも、気づけば優秀な人に仕事が集中していませんか。
業務量に偏りが生じる原因は、作業割り当ての仕組みが整備されていない、スキルの高い従業員にばかり仕事を振ってしまう、などが考えられます。どちらも職場ではよく目にする光景といえるないでしょう。
季節や時期によって業務量に偏りがある
業務平準化を考えるうえで、業種に応じた繁忙期と閑散期の差を考慮しなければなりません。
たとえば、観光業では連休や夏休みにお客さまが集中し、閑散期は一転して静かです。EC事業でも、送料無料キャンペーンやセールを行うたびに注文が増え、業務負荷が一気に跳ね上がります。
とはいえ、本当に問題なのは季節や時期によって「波があること」ではありません。 忙しさの波にあわせた人員や体制が用意されず、一時的に無理を強いられることです。
繁忙期が事前にわかっているなら、忙しい期間だけ外部に業務を委託するなど、負荷をならす対策を考えましょう。
業務が属人化している
業務平準化を妨げる大きな要因の1つが、属人化です。
属人化とは、業務のやり方や進捗状況が特定の人しか把握できておらず、会社がその人のスキルや経験に頼り切っている状態です。たとえば、担当者が休むと「何をどう進めればいいのかわからない」という状況に陥ります。
チームで分担しているつもりでも、実際には「できる人」と「できない人」が分かれているなら要注意です。
属人化が進むと、結果的に業務の平準化が進みません。
業務の定型化が進んでいない
業務平準化を実現するには、まず業務を定型化(標準化)しなければなりません。
作業の進め方が人それぞれだと、業務遂行にかかる時間や量、成果にばらつきが出るためです。
もちろん、すべての業務を定型化できるわけではありません。 一度きりのプロジェクトやお客さまごとに異なる対応が必要な業務は、定型化は難しいでしょう。
判断の目安は、作業をマニュアル化できるかどうかです。繰り返し発生するルーティン業務であれば、定型化しやすく業務の平準化にも向いています。
業務平準化に取り組むメリット
業務平準化を進めることで、どんな職場にメリットが期待できるのでしょうか。具体的なメリットは、次の4つです。
- 業務効率が高まる
- 属人化を解消して品質が安定する
- コストを削減できる
- 従業員のモチベーションを保てる
業務平準化の取り組みで、日々の仕事で感じる悩みや不安を一つずつ軽くしてくれます。
業務効率が高まる
業務平準化を進めると、業務効率を大きく向上させる効果が期待できます。
業務負担が一部の人に集中している職場では、疲労やストレスが積み重なり、集中力が低下しやすくなります。
結果として、ミスや遅延といったトラブルが増え、全体の生産性も下がってしまうことが少なくありません。
業務平準化によって作業量を均等に分担すると、特定の人への負荷が軽減され、心身ともに余裕を持って仕事に取り組めます。
リソースを配分することで、全体のスピードと正確さが上がり、業務品質の安定にもつながります。
属人化を解消して品質が安定する
業務平準化を進めると、属人化を防ぎながら、製品やサービスの品質を安定させられます。
属人化を放置すると、担当者が不在のときに業務が滞り、品質にばらつきが生じがちです。
平準化を意識して必要な知識や進め方をチームで共有し、誰でも同じ手順で作業できるようにすることが大切です。
平準化の仕組みが整うと、担当者が変わっても一定の水準でタスクを進められるため、顧客や取引先からの信頼を維持できるでしょう。
コストを削減できる
業務平準化はコスト削減にも影響があります。
特定の人に負荷が集中すると、残業や休日出勤が増えて割増賃金が発生し、結果的に人件費が膨らみがちです。
業務平準化を取り入れることで、作業量の分散が進み、時間外労働を最小限に抑えることが可能です。
疲労やストレスが原因の休職や離職も減らせるため、採用や教育にかかるコストの抑制効果も期待できるでしょう。企業全体の経営コストを見直すきっかけにもなります。
従業員のモチベーションを保てる
業務平準化を行うと、従業員のモチベーションを維持しやすくなります。
負担が大きい状態が続くと、「いつも自分ばかり大変だ」と不満が募り、やる気を失いやすいものです。
業務平準化を通じて一人ひとりの負担を均等に分けると、気持ちに余裕が生まれ、仕事に前向きに取り組む姿勢が生まれます。
職場に助け合う空気が広がるため、チームワークの向上にもつながるでしょう。
業務平準化の取り組みステップ・業務改善の進め方
業務平準化は、実際にどのような手順で進めればよいのでしょうか。ここからは、業務の偏りをなくし、働きやすい環境をつくるための具体的な手法を紹介します。一般的な進め方は以下のとおりです。
- 業務の流れや量について調査する
- 業務プロセスを見直す
- 業務の量や着手のタイミングを調整する
- マニュアル化を進める
- 役割分担を最適化する
- 業務フローを自動化する
1.業務の流れや量について調査する
業務平準化を進める最初の一歩は、業務の流れや量を調査することです。
どの作業がどのくらいの時間を要しているのか、どの工程で負担が集中しているのかを見つけましょう。フローチャートや手順書を作成すると、目に見える形で全体像が整理でき、課題が発見しやすくなります。
調査内容をもとに現場の従業員にヒアリングも実施します。
実際に業務に携わる人の声を集めることで、机上では分からない問題や、負担感の偏りを把握できます。
2.業務プロセスを見直す
業務平準化を実現するには、業務プロセスを見直します。今の進め方が本当に最適かどうかをあらためて考えましょう。
「ムリ・ムラ・ムダ」が潜んでいる場合は、思い切ってゼロから構築し直す覚悟も必要です。
思い切った改善は最初は抵抗があるかもしれませんが、あとから振り返ると「やってよかった」と感じるケースが多いものです。
3.業務の量や着手のタイミングを調整する
業務平準化を進める際は、業務量や作業を始めるタイミングを調整することも重要です。
繁忙期にあわせて人員を増やす、納期を分散させるなど、負担の集中を防ぐ工夫が求められます。調整によって、チーム全体の余裕を確保できます。
4.マニュアル化を進める
業務平準化を支えるために、定型化できる業務は積極的にマニュアル化しましょう。
非定型業務でも、考え方や手順を文章化するだけで属人化のリスクを減らせます。全員が同じ基準で作業できる環境を整える必要があります。
5.役割分担を最適化する
業務平準化の進め方では、適切な役割分担を行うことが重要です。業務の振り分けを担当するリーダーを立て、分担表を作成して、誰がどの作業を担当するのかを明確にしましょう。
業務効率化を妨げている要因を発見し、担当の偏りを減らすとともに、責任の所在もはっきりします。
6.業務フローを自動化する
業務平準化を進めるために、ITツールを活用して、業務フローを自動化するのもおすすめです。
たとえば、給与計算ソフトを活用すると、作業時間を大幅に短縮できます。ヒューマンエラーを減らせる点も大きなメリットです。
システムを新たに導入する場合は、一部の業務から試験的に進めると、現場への負担を最小限に抑えながら運用を定着させやすくなります。
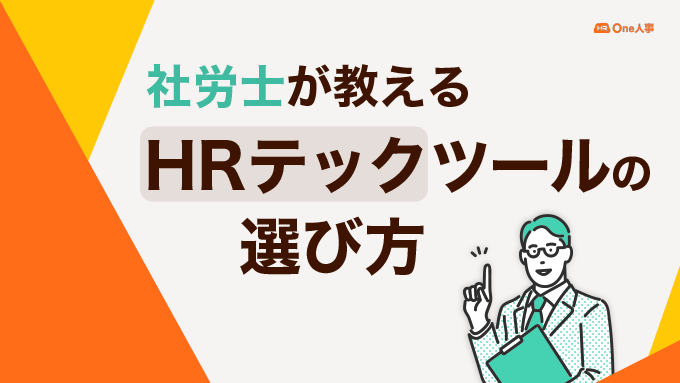
業務の平準化に取り組む際の注意点
業務平準化に取り組むときは、いくつか大切なポイントを意識して進めることが重要です。
次の注意点を押さえながら、無理なく取り組んでいきましょう。
まずは小さく始める
業務平準化に限らず、新しい取り組みは最初から大きく手を広げるより、小さく始めるほうが安心です。
とくに業務平準化は、チームの働き方や業務の進め方に大きな変化をもたらします。成功したときの効果も大きいですが、もし想定外の問題が起きた場合、影響も大きくなるものです。
まずは一部の業務や部署からスモールスタートで試してみると、現場に負担をかけずにノウハウを蓄積できます。
定期的に見直す
業務平準化を一度実現したとしても、維持するには定期的な見直しが必要です。変化に応じてバランスを調整し続けなければなりません。
業務の進行をこまめに管理し、業務量の偏りが出ていないか確認しましょう。小さなズレでも放置すると負担の偏りが広がるため、早めの対応が大切です。
定期的なチェックと改善を繰り返すことが、平準化のポイントです。
まとめ|作業量を可視化して業務平準化へ
ビジネスにおける業務平準化とは、業務負荷の偏りをなくし、働きやすい環境を整えることを意味します。
特定の従業員に業務が集中している状態は属人化を招きやすく、モチベーション低下や生産性の低下につながるおそれがあります。
業務の平準化に取り組めば、業務効率の向上や品質の安定、コスト削減など、さまざまなメリットが期待できるでしょう。
業務平準化を進めるには、まず負担の偏りがどこで起きているかを明確にすることが大切です。現場へのヒアリングを行い、現状を正しく把握したうえで、スモールスタートで取り組みましょう。
また、一人ひとりの業務量を把握するには、勤怠管理システムをはじめとするツールの活用もおすすめです。労働時間や残業時間を自動で集計し、部署やチームごとの偏りを可視化することで、改善策を考えやすくなります。

業務量の可視化に役立つ勤怠管理システム|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、業務量の可視化に役立つ勤怠管理システムです。One人事[タレントマネジメント]と連携することで、業務負荷に応じた配置の検討に役立ちます。
One人事[勤怠]やOne人事[タレントマネジメント]の初期費用や気になる操作性は、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務のお悩みに沿った資料を無料でダウンロードしていただけます。人事領域で業務改善に取り組む担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |