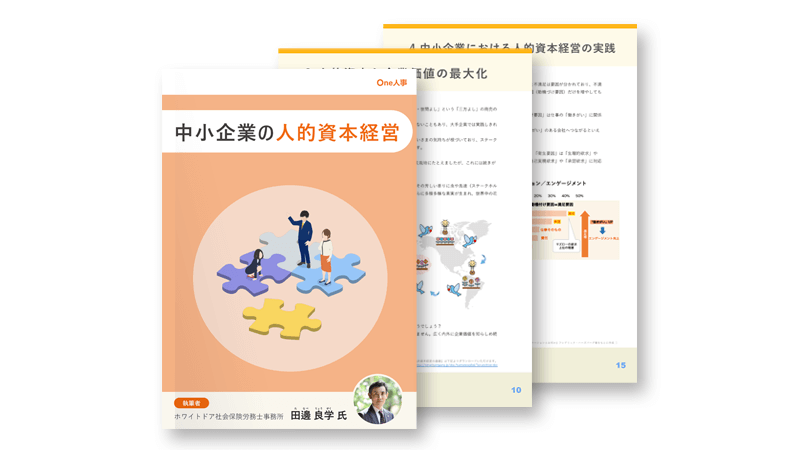経営戦略とは? 事業戦略との違いや種類、策定に使えるフレームワーク、事例を紹介

経営戦略は、企業が変化に翻弄(ほんろう)されず、経営目的を達成するための長期的な方針です。しかし「具体的に何をするものなのかわからない」「事業戦略と何が違うのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
本記事では事業戦略との違いや策定に使えるフレームワークなど、経営戦略の基礎を解説します。さらに、企業が実際にどのように戦略を適用しているかという事例も紹介するので、策定の参考にしてください。
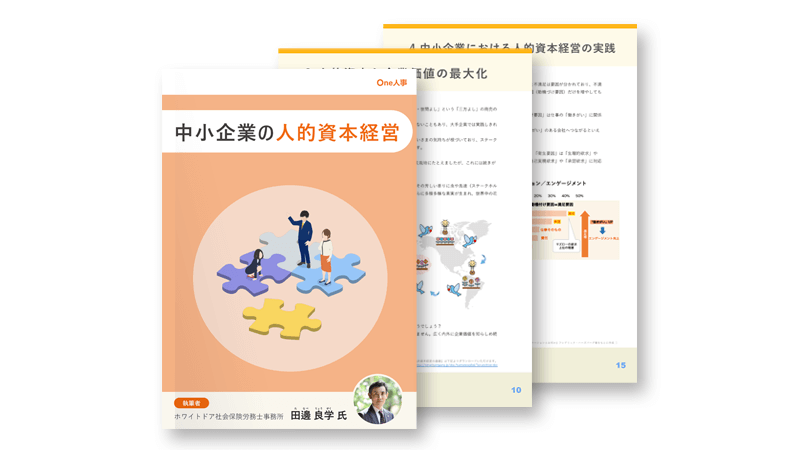
 目次
目次
経営戦略とは|簡単に解説
経営戦略とは、企業が社会や市場の変化に翻弄されず、経営目的や経営理念を達成するための長期的な方針や計画です。
企業全体の活動方針や組織体制づくり、財政面での指針など、4大経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をどのように分配するかを決定します。
策定する目的と必要性
経営戦略は、主に以下を目的として策定されます。
- 企業運営の行動指針とするため
- 具体的な行動指針を従業員に示すため
IT・AI技術の進歩や社会のグローバル化、労働環境の変化など、市場は目まぐるしく変動しています。経営戦略がないと、予想外の変化が起こったときに場当たり的な対応しかできず、自社にノウハウを蓄積するのは難しいでしょう。
企業が変動する社会の中で成長し続けるには、何を目指すべきかを見据えた行動指針が必要です。経営戦略はこの行動指針の役割を果たします。
また、経営陣が具体的な指針を従業員に示すことも、経営戦略の策定目的の一つです。経営戦略が漠然としていると、従業員は企業の目指す方向性を理解できず、経営が目的どおりに進められません。
経営戦略と似ている概念
経営戦略と似ている言葉には以下の5つが挙げられます。
- 経営戦術
- 経営計画
- 戦略経営
- 経営企画
- マーケティング戦略
それぞれの意味と経営戦略との違いを解説します。
経営戦術
経営戦術とは、経営戦略を達成するための具体的な施策です。企業によっては経営戦略と経営戦術を同義とすることもありますが、厳密には意味が異なります。
経営戦略は自社が目指すべき抽象的な目標を設定し、一方で経営戦術はその目標達成に向けた具体的な計画を必要とする点で異なります。
経営戦略をもとに経営戦術を計画し、実行すると考えるとわかりやすいでしょう。
経営計画
経営計画とは、経営全体の具体的な計画です。経営戦略を実現するための具体的な施策をどうするか取り決めています。単一事業の場合は事業計画と呼ばれています。
たとえば、経営戦略を「事業拡大のためにある分野で事業展開する」と決めた場合、経営計画は「事業展開をいつまでにどのように達成するか」を計画することです。
戦略経営
戦略経営とは、戦略的経営ともいわれ、あらかじめ決めた経営戦略をもとに「策定」「実行」「評価」のプロセスを繰り返し、戦略的に目標達成を目指す経営手法です。
フレームワークに沿って、多角的な視点から経営戦略を達成に導くのが、戦略経営といえるでしょう。
経営企画
経営企画とは経営戦略をもとにして、会社の持続的な成長のために、中長期的な計画の立案・実行をする業務です。自社の経営状態を把握して、ビジネスモデルの検討やコストの削減など、経営に関するさまざまな業務を行います。
経営企画は社内リソースを基準にした中長期計画、経営戦略は自社だけでなく社会全体の動きも考慮した長期計画と、どの視点で計画を立案したのかが異なります。
マーケティング戦略
マーケティング戦略とは、特定の商品やサービスをリリースする前に、いかにして市場に浸透させるかを考えることです。
企業全体の経営資源の配分を考える経営戦略と比べ、マーケティング戦略は、顧客ニーズに対象を絞って具体的な販売戦略を立てるのが特徴です。
経営戦略における3つの戦略レベル
経営戦略は以下の3つのレベルから構成されています。
- 全社戦略
- 事業戦略
- 機能戦略
各レベルについて解説します。
全社戦略
全社戦略とは、企業全体の方向性と範囲を定めるものです。
全社戦略は、自社がどの市場に参入するか、どのような事業ポートフォリオを持つかなど、企業全体に共通した中長期な目標や行動指針を決定します。
全社的な戦略であるため、責任は取締役や経営陣などの経営責任者が負います。
事業戦略
事業戦略とは全社戦略を実現させるため、事業ごとに行う経営戦略です。
多角的に事業を展開している場合、事業別に販売製品や従業員、資金をどのように分配するのか判断しなければなりません。事業を1つしか展開していない場合は、全社戦略が事業戦略になることもあります。
また、事業戦略の責任は、事業部長やエリア長などの事業統括責任者が負います。
経営戦略と事業戦略の違い
経営戦略は、企業全体の目標を達成するための方針で「全社戦略」「事業戦略」「機能戦略」の3つに分かれます。そのうち事業戦略は、事業ごとの目標を実現するために策定した方針を指します。
機能戦略
機能戦略とは、特定の部門や機能における戦略です。機能戦略は、具体的な活動を行うために、全社戦略と事業戦略よりさらに範囲を狭めた、部門ごとの活動方針をあらわします。たとえば、営業戦略やマーケティング戦略、財務戦略などが挙げられます。
機能戦略は、部門ごとに方針が異なりますが、どの部門であっても最終目標は全社戦略や事業戦略の実現にあることを忘れないようにしましょう。
機能戦略の責任者には、部門部長や現場リーダーなどが該当します。

経営戦略を構成する4つの要素
経営戦略は以下の4つの要素によって構成されます。
- 事業領域(ドメイン)
- 資源展開
- 競争優位性
- 相乗効果(シナジー)
それぞれの意味を解説します。
事業領域(ドメイン)
事業ドメインとは、展開する事業の分野や領域を示したものです。特定の製品やサービスをどのような顧客に提供するかを定義づけします。たとえば「40代男性に向けて、育毛剤を提供する」というように商品販売の大きな指針となります。
資源展開
資源展開とは、経営資源の獲得や配分のことです。企業は、4大資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をどのように使用して最大限の成果を上げられるのかを考えなければなりません。
「ヒト」の場合、いかに優秀な人材を採用で確保して、いかに教育して将来の経営候補に育てるのかを検討します。資源を適切に配分できると、効率的な経営につながります。
競争優位性
競争優位性とは、自社が競合他社より有利な状況にあることです。有利な状況をつくり出すだけではなく、他社が真似できない独自性も必要です。競争優位性が確立すれば、企業経営の安定につながるでしょう。
相乗効果(シナジー)
シナジーとは、ある要素がほかのものと組み合わさることにより、単体で得られる以上の成果を出すことです。相乗効果ともいいます。一方だけで利益が得られるような場合は、シナジー効果があったとはいえません。
既存の技術連携やノウハウ共有などによって、新しく何かを始めるよりも費用を抑えて、売り上げの増加が見込めるという特徴があります。
経営戦略の分類(方向性)
経営戦略を4つの分類ごとに解説します。それぞれの対極にある視点の違いを理解し、戦略策定の参考にしてみてください。
- 多角化/一極集中化
- 差別化/標準化
- 長期/短期
- グローバル/ローカル
多角化/一極集中化
多角化戦略とは、複数の異なる市場に進出して、リスクを分散させることです。「新規事業の展開」と言い換えられるでしょう。異なる市場からさらなる成長機会を探したり、事業の多様性を拡大したりして、1つの市場の変動に左右されないように自社の耐性を強化します。
対極にある一極集中化戦略は、特定の製品やサービス、市場にリソースを集中させる戦略です。特定分野での専門知識と効率性を高めて、市場浸透と競争優位を築くことを目的としています。
差別化/標準化
差別化戦略とは、製品やサービスに独自の特徴や付加価値を提供して、市場での地位を確立することです。ブランドの特異性を強調して、消費者の忠誠心と認知度の向上を目指します。
反対に標準化戦略は、製品やサービスを業界の標準に合わせて生産コストを削減し、より広い市場へのアピールを目指します。海外での製品展開では国際基準に達しているかを重視することや、自社の技術を標準としてリードし優位性をはかることなどが標準戦略を行う目的です。
標準化の例には、日本産業規格(JIS)によって定められた、乾電池の大きさや非常口のマーク、音楽CDなどがあります。
長期/短期
長期戦略とは、自社のビジョンと持続可能な成長に焦点を当てて、長期的な目標達成に向けた計画を立てることです。具体的には、継続的な研究開発やブランド価値の構築、長期的な顧客関係の育成などが挙げられます。
一方で短期戦略とは、早い成果を目指して、短期間での目標達成を目指すことです。1〜3年の範囲で考えるため、先が見えやすく、戦略を立てやすいのが特徴です。基本的に短期戦略は、あらかじめ立てた中期戦略を、さらに細分化したものです。
グローバル/ローカル
グローバル戦略とは、世界市場を視野に入れて、ブランドイメージと製品戦略を展開することです。国内だけにとどまらず、国境を越えた認知度の向上を目指し、さらなる利益の拡大を追求します。
反対にローカル戦略とは、特定地域のニーズに合わせて企業戦略を練ることです。地域の文化や居住者の好みを調査・分析し、地元市場での関係性構築と認知度向上を目指します。たとえば、地方に特化した飲食店の展開をイメージするとわかりやすいでしょう。
経営戦略を策定する基本のステップ
経営戦略を策定する流れは以下の6ステップです。
- 経営理念やビジョンの策定
- 外部環境の分析
- 内部環境の分析
- 競争優位や付加価値の検討
- 経営戦略の実行
- 経営戦略の評価・分析
始めに経営戦略の大元となる経営理念やビジョンを策定しましょう。経営理念は「経営者の信念や価値観」、ビジョンは「社会における存在意義やあるべき姿」をあらわします。
次に、社会や政治、競合他社など多様な視点で外部環境を分析します。その後、内部環境分析で社内資源を洗い出して、自社の強みと弱みを明確にしましょう。
外部分析と内部分析の結果から、競争優位性を確立できる付加価値を洗い出します。顧客がなぜ自社を選んでくれたのかを考えるとわかりやすいでしょう。現状だけでなく、将来的に提供できそうな付加価値なども考慮します。
経営戦略を実際に実行したら、一定期間が経過したあとに効果測定をして、自社に適している効果が得られたかを客観的に分析します。思いどおりにいかなかった場合は、分析結果をもとに修正し、「ステップ1」に戻り再検討したうえで、より自社に合った経営戦略を策定しましょう。
経営戦略の策定に使えるフレームワーク
経営戦略の策定に使えるフレームワークを3つ紹介します。自社で経営戦略を策定する際の参考にしてください。
- SWOT分析
- 5フォース分析
- 3C分析
やり方も簡単に解説するので、自社で経営戦略を策定する際の参考にしてください。
SWOT分析
SWOT分析とは、自社の外部環境と内部環境のプラス要因とマイナス要因をそれぞれ分析するフレームワークです。SWOT分析によって、事業の将来性やリスクを見つられるため、事業の戦略策定や意思決定に有効でしょう。
外部環境とは市場環境や競合他社、顧客ニーズの変化や動向を指し、内部環境と自社製品の価格や他社と比較した特徴、認知度などをあらわします。
SWOT分析は、自社の状況を客観的に捉えて分析できるメリットがある一方、結果が分析者の主観に偏りやすいデメリットがあります。そのため、SWOT分析は、複数人で実施して客観的に分析結果を捉えましょう。
| 内部環境 | Strength(強み) | Weakness(弱み) |
| 外部環境 | Opportunity(機会) | Threat(脅威) |
5フォース分析
5フォース分析とは、自社を取り巻く環境や脅威を以下の5つの要素から分析する手法です。
- 競合他社の脅威
- 代替品の脅威
- 新規参入者の脅威
- 買い手の交渉力
- 売り手の交渉力
近年類似サービスが多く流通していることから、競合他社との競争が激化しやすい傾向にあります。そのような状況で自社が生き残るためには、5フォース分析で自社の脅威を分析し、対策を練る必要があります。
| 分析要素 | 分析内容 | 具体例 |
| 競合他社の脅威 | 競合他社がどの程度自社の売り上げに影響を及ぼすか | ・競合他社の数 ・各社のシェア率や独自性、資金力、認知度 など |
| 代替品の脅威 | 既存商品がほかの商品でニーズを満たせてしまわないか | ・家庭用電話機ではなく携帯電話 ・紙の本ではなく電子書籍 など |
| 新規参入者の脅威 | 新規の競合他社が参入しやすい市場なのか | ・自社で培った技術の特許取得 ・異なる分野の企業との連携 など |
| 買い手の交渉力 | 類似製品が多く、顧客が購入価格を決定する立場にあるか | ・顧客ニーズやロイヤリティの調査 ・製品にかかるコストの見直し など |
| 売り手の交渉力 | 製品の供給元が少なく、仕入れ先が価格調整する立場にあるか | ・代替部品の有無の精査 ・自社での製造・開発 など |
3C分析
3C分析とは、以下3つの視点から経営戦略上の課題を見つける分析方法です。3Cとは「Customer(顧客)」「Competitor(競合他社)」「Company(自社)」の頭文字をあらわし、マーケティング視点から市場環境を分析します。
具体的な分析項目の例は、以下のとおりです。
| 分析対象 | 分析項目の例 |
| 顧客環境 | ・顧客のニーズ・購買に至るまでの行動・顧客になり得る人口 など |
| 競合環境 | ・市場シェア率・競合他社の特徴(強みや弱み)・競合他社の資金力や認知度 など |
| 自社環境 | ・市場シェアと推移・製品の特徴(強みや弱み)・自社の事業内容やビジョン |
3C分析だけでは各項目に偏りが生じやすいため「自社環境にはSWOT分析、競合環境には5フォース分析」のように、ほかのフレームワークと併用して、より具体的に調べる必要があります。
経営戦略の事例
経営戦略の成功事例を以下の企業別に紹介します。
- スターバックスコーヒージャパン株式会社
- ヤマハ株式会社
- 株式会社しまむら
スターバックスコーヒージャパン株式会社
スターバックスコーヒーは、「自分らしく過ごせる場所」として事業展開を行ったところ、多くのファンを獲得しました。
従来は、ビジネスパーソンをメインターゲットとしていましたが、高級感のある内装に変更したことで女性を中心とした顧客が増加しています。
参考:『高成長を維持し、 顧客体験の価値向上のための戦略的な取り組みを発表』スターバックスコーヒージャパン株式会社
セブン&アイ・ホールディングス株式会社
セブン&アイの事業内容は、コンビニエンスストアをはじめ、スーパーやプライベートブランドの展開など多岐にわたります。なかでもコンビニ事業については、国内で最多の店舗数を誇り、年々売り上げを増加させ、成果を出し続けています。
セブン&アイはセブン-イレブンの1号店を開店して以来、フランチャイズシステムによって店舗を拡大してきました。まずは「江東区から出るな」という経営方針のもと、セブン-イレブンやコンビニ自体の認知を徹底する、ドミナント戦略(高密度集中出店方式)を用いたのです。
また、高密度集中出店方式によって各地域に工場を持ち、時間帯ごとに新鮮な食品の販売やテスト販売の実施を実現しました。これらの戦略によって店舗展開を進めたことで、品質の高いサービス提供や地域の生活インフラの確立につながっています。
参考:『セブン&アイの挑戦』セブン&アイ・ホールディングス株式会社
株式会社しまむら
しまむらは、15,000世帯程度に1店舗を目安に、郊外中心に店舗を展開するドミナント戦略を採用していました。地域密集型にすることで広告を活用せずとも、認知や配送効率の向上に成果が出たようです。
さらに、店舗や建築基準を標準化することにより、各店舗を迅速に建設してできるだけ早い集客に努めるだけでなく、建築コストの削減にもつながりました。
また、郊外のためファミリー層が多く、20~50代の主婦層から指示を集めているのも特徴です。「そこまでお金はかけられないけど高品質なものがよい」というニーズに応えるため、徹底したコスト管理を行うことで品質を維持しています。
ほかにも、マタニティ専門店や若年層をターゲットにした専門店など、各年代に応じたブランドを展開することで、それぞれが補い合って集客力を高めています。
経営戦略の策定で考慮したい概念
経営戦略の策定をするにあたり、関連する用語を解説します。各用語の違いを理解し、自社で大切にしたい概念があれば、経営戦略に取り入れるとよいでしょう。
- 経営理念
- コアコンピタンス
- 企業遺伝子
- イノベーション
- インテグリティ
- サステナビリティ
- アントレプレナーシップ
経営理念
経営理念とは、企業運営を行ううえで大切にしたい、経営者の信念や価値観をあらわしたものです。主に経営の土台となる考え方を従業員に示すために策定されます。経営理念は、経営者の入れ替えによって変わる場合が多いのが特徴です。
コアコンピタンス
コアコンピタンスとは、他社に真似できない自社特有の能力です。コアは「中核」、コンピタンスは「能力」を意味します。
昨今、サービスの多様化による競争性の激化から、コアコンピタンスはとくに求められる傾向にあります。経営戦略を策定する際は、自社のコアコンピタンスが何かを念頭に置いて検討すると、スムーズに進められるでしょう。
企業遺伝子
企業遺伝子とは、企業や組織において長期的に伝わる価値観や行動規範などを、共有・継承していくことです。
近年使われることが多くなった言葉で、個人の性格と同じように企業にもさまざまな在り方が存在するという考えに基づいています。経営方針や社員教育などを通して、企業遺伝子を広く浸透させていくと自社の魅力が高まるかもしれません。
イノベーション
イノベーションとは、変革や革新を意味する言葉です。新たな技術や発想により、社会に大きな変化をもたらすことを指します。
イノベーションは技術革新のイメージが強いですが、ビジネスにおいては、既存のサービスや制度、ビジネスモデルに新しい価値を生み出す意味でも用いられます。
インテグリティ
インテグリティとは、誠実や真摯といった意味を持つ言葉です。欧米企業を中心に、経営方針や従業員が持つべき価値観を指す言葉として使われるようになりました。
インテグリティがある人とは、簡潔にまとめると正義感の強い人です。経営者であれば単に自社の利益を求めるだけでなく社会貢献ができるか、管理者であれば自分の評価だけでなく部下のために行動できるかなどが挙げられるでしょう。
組織のトップに立つリーダーやマネジメント層に重要な資質として、求められる傾向にあります。
サステナビリティ
サステナビリティ(持続可能性)とは、環境や社会に配慮した活動を行うことで社会全体を持続させていく考え方です。もともとは環境保護の分野で用いられましたが、現在では企業が果たすべき社会責任の一つとして重要視されています。
企業の取り組み事例としては、廃棄物の再利用による環境への負荷軽減やLGBTQ人材の活用による多様性の実現などがあります。
アントレプレナーシップ
アントレプレナーシップとは「起業家(企業家)精神」と訳され、新しい事業や高いリスクに挑戦する姿勢です。起業家だけではなく、会社員や学生など、課題への解決策を打ち出し、立ち向かう精神を持っている人が該当します。
先行きが不透明で変化の多いVUCAの時代の到来や、終身雇用制の崩壊により、企業は競争力の低下や人材の流動化など、不安定な状態にあるといえます。
アントレナーシップのある人材を雇用すると、リスクを恐れることなく積極的にビジネスに挑戦できる人材の活躍が期待できます。自社の競争力を高めるために、アントレナーシップは重要視されています。。
経営戦略と人事戦略の連動を(まとめ)
経営戦略とは、経営目的や経営理念を達成するための長期的な方針です。4大経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の分配方法を決定するものといえます。
経営戦略を策定する目的は、成長のために何を目指して進むべきかという全社的な行動指針を示すことです。
経営戦略を現場の従業員に落とし込むためには、細分化した部門ごとの戦略策定や、人事異動による人材の最適配置が必要になります。このように人材配置や人材育成によって組織の生産性を高める戦略は人事戦略と言います。
企業運営には経営資源の1つである「ヒト」、つまり従業員の働きが必要不可欠です近年は、経営戦略と人事戦略の連動が求められる傾向にあり、そのためにはタレントマネジメントシステムの活用がおすすめです。
タレントマネジメントシステムとは、従業員が持つ能力やスキルなどの人材情報を一元化し、客観的な人事評価や最適な人事配置・人材育成に役立つシステムです。
タレントマネジメントシステムの最終目標は、今いる限られた人材の能力を最大化して利益獲得につなげ、経営目標を達成することです。経営戦略をより効果的に実行するために、人事戦略にも注力したいと考える企業は、導入を検討してはいかがでしょうか。
タレントマネジメントを始めるには?
One人事[タレントマネジメント]は、従業員のスキルや適性データを一元管理し、人事戦略の推進を支援するサービスです。
組織にまつわる人の情報を見える化し、経営の意思決定支援にもお役立ていただけます。具体的な活用方法や初期費用、操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、自社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。入社から退社まで人の情報管理をシームレスに行いたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |