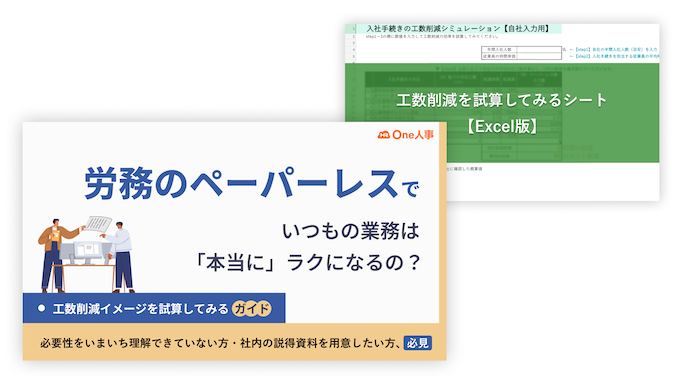RPAとは? 活用するメリットなどについてわかりやすく解説

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、ロボットを活用して人が行う定型業務を自動化する技術です。現在、多くの企業で導入が進み、働き方改革やDXの一環として注目されています。
本記事では、RPAの概要や導入によるメリットについて解説します。業務の自動化を検討している企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。
 目次[表示]
目次[表示]
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは
RPAは、従来、人がが対応していた作業を、ルールエンジン・AI・機械学習などの機能を備えたロボットが自動で代行・代替する技術です。
たとえば、データ入力やファイルの移動、システムへのログインなどの作業を自動化し、業務効率化とコスト削減を実現します。
また、人では対応できない高度な作業を担うケースもあります。
RPAの導入により、バックオフィス業務や顧客対応などのルーチンワークが効率化され、企業の生産性向上が可能です。
AIとの違い
RPAとAIの主な違いは、作業の自律性です。RPAはあらかじめ設定されたルールに基づいて作業を自動化するツールであり、基本的には人が決めた手順を忠実に実行します。
一方、AI(人工知能)は自律的に学習し、与えられた情報をもとに自分で判断します。
AIとRPAを組みあわせると、AIが情報を読み取り、RPAが自動で処理を進めることで、非定型業務も含む幅広い業務の自動化が可能です。RPAが「手や足」として実行を担い、AIが「脳」として判断を支えるとイメージするとよいでしょう。
マクロとの違い
RPAとマクロの違いは、自動化できる範囲です。マクロは、ExcelやGoogleスプレッドシートなど特定のアプリケーション内でのみ動作する自動化ツールです。VBAやGASといったプログラミング言語を用いて操作を記録し、繰り返し実行します。
一方、RPAは特定のアプリケーションに限定されず、複数の異なるソフトウェア間の操作の自動化が可能です。
RPAのクラス
RPAには3つのクラスがあり、以下の通り分類されます。
- クラス1:RPA(Robotic Process Automation )
- クラス2:EPA(Enhanced Process Automation)
- クラス3:CA(Cognitive Automation)
各クラスの特性や役割を明確にすれば、RPA技術の全体像や自社のニーズに最適なクラスを選択しやすくなるため、それぞれについて解説していきます。
RPA(Robotic Process Automation )
クラス1に該当するRPAは、定型業務を自動化します。具体的には、データ入力やメールの送信、ファイル整理といった繰り返し行う作業を自動化する技術です。
RPAは導入コストが低く、比較的簡単に運用できます。ただし、ルールに基づいた業務しか自動化できないため、複雑な判断をともなう作業には向いていません。
EPA(Enhanced Process Automation)
クラス2のEPAは、RPAにAI技術を組み合わせたもので、RPAよりも自動化が強化されています。定型業務に加えて、非定型業務や複雑なデータの処理も自動化が可能です。
たとえば、顧客からの問い合わせに対し、AIが自動で判断し、最適な回答を提供できます。また、業務の最適化や予測分析などにも有効です。
CA(Cognitive Automation)
クラス3のCAは、最も高度な自動化レベルを持ち、ディープラーニングや自然言語処理、データ分析、意思決定まで自動化できます。
複雑な問題の解決や業務改善を自動的に行い、将来的には意思決定もAIに任せることが可能です。
顧客サポートやセキュリティなど、さまざまな分野での活用が期待されています。
RPAが注目されている背景
なぜRPAが普及しているのでしょうか。注目されている4つの背景について解説します。
- 労働人口が減少している
- プログラミングの必要がない
- 費用対効果がわかりやすい
- 事例が増えつつある
労働人口が減少している
日本では少子高齢化にともない、生産年齢人口(15歳から64歳)が急速に減少しています。人口減少により、多くの企業において人手不足が問題となっているのです。
RPAを導入すれば、単純作業を自動化し、労働力をより重要な業務に集中させられます。人手が足りない部分をカバーするために有効といえるでしょう。
プログラミングの必要がない
RPAが注目されている理由の1つは、プログラミングの専門知識を必要としない点です。
従来の業務自動化は、IT部門や外部の専門業者に頼る必要がありました。
しかしRPAは、高度なプログラミングが不要であり、専門知識がなくても操作が可能です。
RPAにより、業務自動化に取り組みやすくなり、多くの企業が導入を進めているという背景があります。
費用対効果がわかりやすい
RPAは、導入後の費用対効果のよしあしを判断しやすい点が特徴です。
定型的な業務を自動化すれば、人件費の削減や作業時間の短縮が期待できます。
また、RPAは24時間365日稼働できるため、夜間の業務や大量のデータ処理にも対応が可能です。
RPAの常時稼働により社内リソースに余裕が生まれ、ほかの重要なコア業務に専念できるようになるでしょう。
事例が増えつつある
RPAの導入事例は年々増加しており、多くの成功例が報告されています。
導入時間が従来のシステム開発より短く、効果があらわれやすいため、成果を早い段階で確認でき、自社で導入を検討する際の説得材料や参考情報として活用できます。
まずは特定の部署でコストを抑えて短期間の導入を試み、結果をもとに全社展開へつなげるケースもあるようです。
RPAを活用するメリット
RPAを活用するメリットをもう少し具体的に見ていきましょう。主な3つのメリットを紹介します。
- 業務の効率化
- 人的ミスの防止
- コスト削減
業務の効率化
RPA導入のメリットは、単純作業を自動化することで業務効率を高められる点です。
手作業をロボットが瞬時に処理するため、従業員がコア業務に集中できる時間が増え、業務全体のスピードが上がります。
ロボットは休憩を必要とせず、常に一定の品質で作業を進められるため、業務プロセス全体を加速し、全体の生産性を大幅に高められるでしょう。
人的ミスの防止
手作業には、入力ミスや計算ミス、転記ミスなどヒューマンエラーのリスクがともないます。しかし、RPAは設定されたシナリオにしたがって正確に作業するため、ヒューマンエラーを防げる点がメリットです。
たとえば、経理部門でRPAを活用すれば、ミスのない請求処理や振り込み手続きが実現できます。
コスト削減
RPAを活用すれば、コスト削減が可能です。従業員が行っていた定型業務をロボットが代行するため、少ない人員で業務を回せるようになり、人件費を削減できます。
また、RPAの常時稼働で、人に支払う時間外手当や休日出勤手当などのコスト削減につながります。
RPAを適用しやすい業務・適用しにくい業務
RPAには多くのメリットがありますが、すべての業務に適しているわけではありません。
次に、RPAを適用しやすい業務と適用が難しい業務の特徴について解説します。
| 適用しやすい業務 | 適用しにくい業務 |
|---|---|
| ・パソコンだけで完結する定型業務 ・ルールが明確で手順が一定の作業 ・処理量が多く繰り返しが多い業務 | ・都度判断や意思決定が必要な業務 ・頻繁に手順が変わる業務 ・業務プロセスが複雑で例外処理が多い業務 |
| (例)データ収集・転記、大量メール送信 | (例)クレーム対応、特注品の対応、複数システムを横断する調整 |
適用しやすい業務
RPAを適用しやすい業務は、パソコンのみで完結する定型業務です。ルールが明確で、手順にしたがって繰り返し行う作業が多いため、高い効率で処理できます。
また、処理量が多い業務もRPAに適しています。たとえば、複数のシステムからデータを集めてエクセルに転記する作業や、大量のメール送信などの業務は、RPAの導入によって短時間での処理が可能です。
適用しにくい業務
RPAは設定されたルールにしたがって動作するため、都度判断を必要とする業務には向いていません。意思決定をともなう業務や頻繁に手順が変わる業務は、人の手で行うことが適しています。
また、業務プロセスが複雑な場合も、RPAを適用しにくいといえます。複数のシステムをまたぐ、例外処理が頻繁に発生する業務では、エラーが起こりやすく、効率化のメリットはあまり見込めません。
RPAの導入手順
実際に自社でRPAを導入する場合、どのように進めていけばよいのでしょうか。
ここからは、RPA導入を成功させるための具体的な手順について解説します。
導入目的を明確にするところから、適用業務の選定、目標設定まで、おさえたいポイントを順を追って確認していきましょう。
導入目的の整備
RPA導入時には、まず導入目的を明確にすることが重要です。目的が明確であれば、具体的な効果や目標が見えやすくなり、プロジェクト全体の方向性が定まります。
目的が不明確なままでは、RPAをどのような業務改善に役立てるかが曖昧(あいまい)になり、導入効果が薄れてしまうでしょう。
導入目的の例には、「働き方改革の推進」「人手不足の解消」「業務効率化」などが挙げられます。
適用業務の選定
導入目的を決めたら、実際に自動化する業務を選定します。現場の各部門で、どのような業務がRPAで自動化できるかを検討することが適切です。
自動化の効果が見込める業務を適切に選定すれば、より高い成果を得られます。
目標設定
最後に、導入目的に沿って、目標(KPI)を設定します。目標が明確であれば、達成に向けた効果の測定を行いやすく、導入後の改善もスムーズに進むでしょう。
たとえば、「年間◯時間の作業時間削減」や「ヒューマンエラーの◯%削減」など具体的なKPIを設定すれば、RPA導入の成功を定量的に評価できます。
RPAツールを選ぶ際のポイント
最後に、RPAツールを選ぶ際に必要な4つのポイントについて解説します。
- 専門知識を持っている人材がいるか
- どの程度の効果が見込めるか
- トライアルに対応しているか
- サポートが充実しているか
専門知識を持っている人材がいるか
RPAツールを選ぶ際は、エンジニアなど専門知識を持っている人材がいるかどうかが重要なポイントです。
RPAツールの導入では、運用やカスタマイズに一定の専門知識が求められます。とくに、複雑な業務の自動化やシナリオの作成には、プログラミングの知識やシステム構築のスキルが必要です。
ただし、専門知識がない担当者でも操作できるRPAツールが増えているため、必ずしも高度な知識は必要ありません。
どの程度の効果が見込めるか
RPAツールを選ぶ際には、どの業務を自動化すればどの程度の効果が見込めるかの事前検証が必要です。
期待される効果が把握できれば、導入後の効果測定がしやすく、費用対効果の検討にも役立ちます。
トライアルに対応しているか
RPAツールを導入する前に小規模のトライアルを実施し、操作性や実際の業務にどの程度効果を発揮するのかを確認します。
RPAツールを提供している業者によっては無料トライアルを提供しており、1週間や1か月など決められた期間内にテストができます。
ツールの機能や操作性などをチェックすれば、導入後のトラブルを未然に防げるでしょう。
サポートが充実しているか
RPAツールのスムーズな運用には、サポート体制が整っているかの確認が重要です。
とくに、トラブル発生時や設定調整時に適切なサポートが受けられるかどうかは、導入の成功に大きくかかわります。
RPAツールを提供している業者が継続的に質問に答え、理解を深めるための研修を設ければ、さらにツールを使いやすくなります。
まとめ|RPAを導入して業務効率化を実現
RPAは、業務効率化を実現するための重要な取り組みです。人の手をかけずに業務を迅速に処理できるため、社内の限られたリソースをより有効に活用できるようになります。
RPAの活用で、従業員は単純作業から解放され、本来注力すべき業務に時間とエネルギーを向けられるようになります。
企業の成長を促進し、競争力を高めるためにも、RPAの活用を積極的に検討してみましょう。