見える化・可視化の違いとは? 活用事例やメリット・デメリットを解説

「見える化と可視化の違いがよくわからない」
「自社で必要なのは見える化と可視化どちらか」
ビジネスシーンで使われる「見える化」「可視化」という言葉の意味を混同していませんか。実際には微妙な違いがあり、違いの理解が業務改善の成否を左右することもあります。
本記事では、「見える化」と「可視化」の意味や特徴を整理し、メリット・デメリットや具体的な事例まで解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
見える化とは
「見える化」の意味やどのような場面で使われるキーワードなのかについてご紹介します。
「見える化」の意味と使い方
「見える化」とは、本来目に見えない、見えづらい事柄を数値化や仕組みによって見える状態にして表面化させることを指します。ビジネスなどでは「業務内容や成果を見える化する」「社員の声を見える化する」といった使い方をします。
見える化の目的と重要性
ビジネスや社内における「見える化」の目的は、目には見えない事柄を数値やグラフなどの形にあらわして、課題解決のための詳細を理解することです。具体的には、各従業員の行動計画を示すアクションプランや表を利用した業務管理が例に挙げられます。
「見える化」は、業務内容の実態把握や改善作業にまで利用されることがあります。職場の課題を見つけやすくして、すぐに解決できる仕組みづくりや問題そのものが発生しにくい業務フロー改善に役立ちます。働きやすさの向上にも必要な取り組みといえるでしょう。
見える化の起源とは
見える化の起源は、1988年にトヨタ自動車株式会社所属の岡本渉氏が発表した論文、「生産保全活動の実態の見える化」だといわれています。
「見える化」の考えを製品化したものが、「あんどん方式」です。生産ラインに異常が生じたときに「あんどん」というランプが点灯する仕組みで、日本の「見える化」施策のパイオニアといえるでしょう。トラブルごとに点灯の色を変えることで、全従業員がトラブルの種類を迅速に把握できるよう工夫されています。

可視化とは
「見える化」と内容が混同されやすい「可視化」にはどのような意味があるのでしょうか。
可視化の目的と重要性
「可視化」とは、目には見えない内容を見える状態に整えておくこと、そして見たいときに見れる状態にしておくことを指します。
「見える化」と意味は近いですが、「可視化」の意義は「誰が見てもわかりやすい状況にしておくこと」です。具体的には、エンゲージメントサーベイやアンケート調査など、行動に起こさなければ見えてこない満足度や感想を表面化することが例に挙げられます。
「可視化」の目的は、見落としがちな事柄をわかりやすく表現し、「見える化」による課題解決へとつなげることです。施策の効果を得るためにも「可視化」を行う重要性は非常に高いでしょう。ちなみに「可視化」は、ビジネス以外にも研究や学習シーンでもよく使用されます。
「見える化」と「可視化」の違い
「見える化」と「可視化」は似た用語ですが、意味や目的は異なります。2つの用語について、より詳しく比較してみましょう。
「可視化」は「見える化」の一部
「可視化」は「見える化」の一部といえます。「見える化」の実現のために「可視化」が手段として用いられることが多いです。データや状況を可視化することで課題を見える化し、問題解決へつなげていくのです。可視化は見える化の手段ともいえるでしょう。可視化だけが目的になってしまうと、問題解決には結びつかないことがあるので注意が必要です。
改善行動を促すのが「見える化」
「可視化」は、目に見えないデータなどを見える状態にする手段のことです。これに対して「見える化」は、可視化されたデータを目にした人の行動を促す役割もあります。「可視化」は、見たい人がいつでもデータを見られるように実施します。一方「見える化」は、従業員の意思に関係なく、自然と目に入る状態に整え、課題解決を促すのです。
「見える化」は定性データの理解促進
「見える化」は、定性的なデータや状況を扱うときに使用されることが多いです。その一方で「可視化」は、定量的な事象をわかりやすく整理する際に使われるケースが多いようです。つまり、計測可能なデータを可視化したうえで、抽象的な情報を見える化していきます。たとえば「各従業員の勤務時間をグラフで可視化し、現在の業務効率化状況を見える化していく」という流れです。
見える化と可視化の違いは、明確な定義が決まっているわけではありませんが、おおまかにこのような使い分けをするといいでしょう。

「見える化」の事例
次に「見える化」のメリットとデメリットを事例を交えてご紹介します。
見える化のメリット
見える化の大きなメリットは、「仕事の全体像がつかめること」です。自分の担当する業務だけでなく、ほかの従業員が行う業務内容にも理解が深まったり、大きな視点で仕事が進められるようになります。何かわからないことがあったときも、相手の担当業務にあった的確な質問ができるでしょう。
具体的な事例としては、「タスク管理表の作成」が挙げられます。各従業員が抱えるタスクを表でまとめ、いつでも見える場所に提示(オンラインも可)しておくと、課題解決がスムーズに行えます。相手の進捗状況を把握できるため、業務の依頼などを適切なタイミングで実施できるでしょう。
そのほか、見える化のメリットは以下のとおりです。
- ケアレスミスを回避できること
- 透明性のある人事評価が行えること
- 業務量のコントロールができること
- 残業時間を削減できること
職場全体の働きやすさを向上し得るので、取り組む価値はあるでしょう。
見える化のデメリット
見える化のデメリットは、「本来の目的を見失ってしまうこと」かもしれません。見える化が業務のなかに自然と溶け込むと、生産性は向上するでしょう。しかし「見える化を進めること」が目的になってしまうと、余計な業務が増えるだけです。「全体を見ながら、効率よく仕事を進めなければならない」という思いだけが先走ってしまい、結果に結びつかないことがあります。
そのほか、見える化のデメリットは、以下のとおりです。
- 型にはまった業務しか行えなくなること
- 従業員の自由度が下がること
- プライバシーが守られないこと
社員のなかには、自分の業務内容を必要以上に開示することにストレスを感じる方もいるかもしれません。必要に応じて配慮と調整を行いましょう。

「可視化」の事例
次に、可視化のメリットとデメリットについて事例を交えながらご紹介します。
可視化のメリット
可視化のメリットは、「新しい内容を分析できること」です。目には見えない定量データなどを可視化すると、今まで利用していなかった分析方法が浮かぶかもしれません。それによって新たな仮説の構築につながり、業績を上げるきっかけになることもあります。
具体的な事例としては「プロセスマップの作成」があります。各従業員の業務内容をフローチャート化して図やテキストにまとめ、それぞれの担当者の名前も記しておきます。組織体系や自分自身の業務の模範図がわかるため、トラブルが起こった際も冷静に対処できるはずです。可視化されたデータがあれば、業務のあり方の再分析もできるでしょう。
そのほか、可視化のメリットは以下のとおりです。
- 課題点の迅速な把握が可能になること
- 従業員全員が同じビジョンを持てること
- 各業務分担への振り分けがスムーズに行えること」
「見える化」と似てい概念ではあるので、メリットは共通する部分もあります。
可視化のデメリット
可視化のデメリットは、時間がかかることでしょう。とくに、業務の進め方を個人の裁量に任せてきた企業だと、考え方を一から見直さないといけないかもしれません。多くのメリットを得るためには、まず可視化を当たり前のものにする改革が必要でしょう。
可視化から見える化につなぎ、結果を出すまでにもさらに手間と時間がかかります。十分な準備をして、社員の負担にならないよう余裕を持って取り組むようにしましょう。
そのほか、可視化のデメリットは以下のとおりです。
- 反対する従業員と話し合う手間がかかること
- 今まで浸透してきたシステムや文化を変える負担の大きさ
- 一時的に業務量が増えること」
可視化には、一定以上の時間や手間がかかります。しかし、可視化の仕組みを一度整えれば、メリットを得られるでしょう。全社的に施策として取り組むといいかもしれません。
見える化・可視化を経営への効果
「見える化」と「可視化」は、企業経営にどう関わってくるのでしょうか。実践的な側面で解説します。
見える化・可視化は無駄を省く
見える化と可視化を有効に活用すると、経営にもによい影響をもたらします。無駄を省き、短い時間内で成果をあげられる可能性が高まるからです。今まで明確にされてこなかった社内状況を可視化し、業務の進捗や企業のあり方を見える化することで、的確に現状を把握できるようになるでしょう。
見える化・可視化の注意点
実際に見える化と可視化に着手する際、すべてのデータを可視化する必要はありません。業務に関するデータや事象をすべて可視化して見える化につなげてしまうと、担当従業員の業務量が膨大になってしまう恐れもあります。また、業務のすべてを監視されているような気分になるため、従業員も窮屈さを感じるかもしれません。職場で優先的に着手すべき課題を精査し、それらを改善できる可能性のあるデータをまずは可視化するといいでしょう。
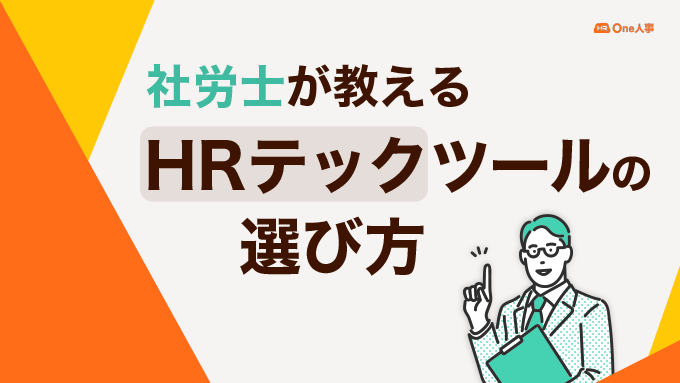
まとめ|社内の「見える化」「可視化」を促進するには?
「見える化」「可視化」は似ているようで役割が異なります。可視化はデータや情報を整理する手段、見える化はそれを行動や改善につなげる仕組みまでを指します。
大切なのは、「可視化」から「見える化」へどうつながるかの設計です。可視化からの見える化が成功すれば、業務の属人化を防ぎ、現場の判断スピードを上げ、経営判断にも役立つでしょう。
しかし、「どのデータを可視化すればいいのか」「どうやって見える化につなげるのか」と悩む担当者も少なくありません。
とくに社内の人材情報は、タレントマネジメントシステムの活用がおすすめです。
人材情報を可視化・見える化へ|One人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、従業員一人ひとりのスキルや経歴情報を可視化し、人事評価や人材配置を見える化できます。不透明になりがちな人事評価基準も、目標管理を見える化することで、納得感のある評価に結びつけられるでしょう。
柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトではサービス紹介資料のほか、人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。人事労務をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
