給与明細の重要な項目「住民税」について基本事項や注意点を解説
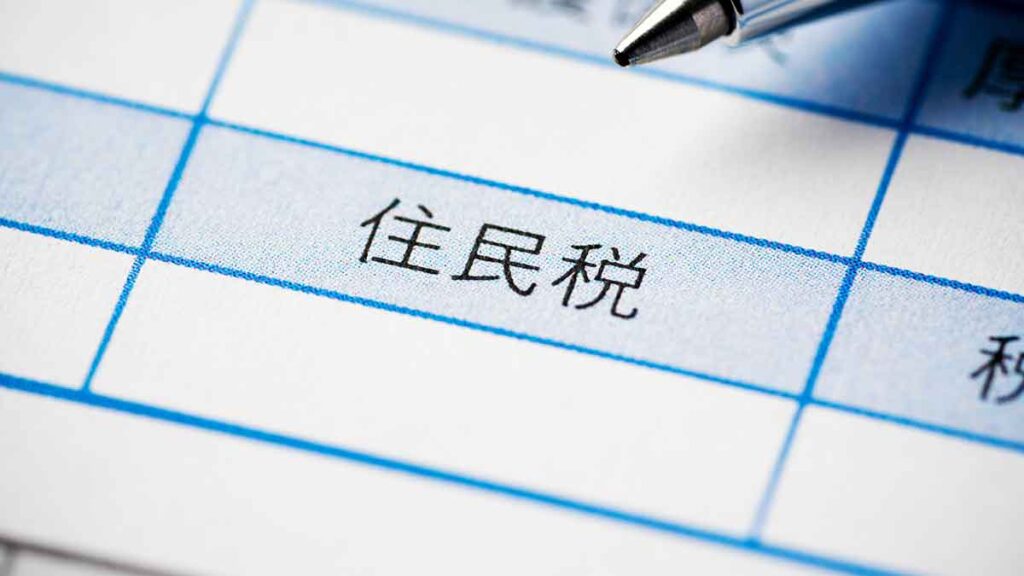
従業員に給与を支給する際、企業は給与明細を作成・交付しなければなりません。給与明細にはさまざまな項目が記載されていますが、そのなかの一つに住民税があります。従業員の住民税は企業が計算する必要があるため、基本を理解しておきましょう。
本記事では、給与計算の担当者に向けて、給与明細の記載項目や住民税の計算方法、注意点などを解説します。給与計算業務を効率化するヒントも紹介するので、ぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
給与明細とは
給与明細とは、給与の支給額や給与計算の根拠となる情報が記載された書類です。一般的には、給与を支給する前のタイミングで、企業から従業員に対して交付されます。
給与明細は電子データとして交付することも可能ですが、従業員が紙の明細書の発行を希望する場合は、これに応じなければなりません。
給与明細の発行は義務
給与明細について所得税法第231条により、「給与を支払う者は、給与を受け取る者に対して支払明細書を交付しなければならない」と定められています。
給与明細の交付は法的な義務であり、企業は従業員に給与を支払う際、速やかに給与明細を提供しなければなりません。また、正規雇用やパート・アルバイト、契約社員などの雇用形態にかかわらず、すべての従業員に給与明細を交付する必要があります。
なお、派遣スタッフの給与支給については派遣元に責任があり、給与明細も派遣元から交付されます。
給与明細の主な項目
給与明細の記載項目は、大きく分けると以下の3種類です。
- 勤怠情報
- 支給額
- 控除額
勤務情報
給与明細には、労働日数や労働時間、残業時間などの勤怠情報が記載されます。給与は労働の対価として支払われるものなので、勤怠情報は給与計算における根拠として使用されます。
記載内容は企業ごと、従業員の勤務形態ごとに異なりますが、欠勤日数や有給休暇の取得日数が記載されるケースも多いでしょう。
支給額
従業員に支給される賃金総額と、基本給・各種手当などの内訳を記載します。
残業手当や休日出勤手当、深夜手当などは法律で定められていますが、そのほかの多くの手当は会社の裁量に任せられています。たとえば、以下のような手当を支給する場合が多いでしょう。
- 通勤手当
- 出張手当
- 住宅関連手当 など
控除額
給与から控除(天引き)されるものを記載します。基本的に、給与から控除されるものは社会保険料と税金の2種類です。
社会保険料には、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料が該当します。従業員が40歳以上の場合は、介護保険料も必要です。一方、税金は所得税・住民税の2種類が天引きされます。
なお、社会保険料のうち労災保険料を除く保険料は企業と従業員がそれぞれ一定割合を負担して納付します。給与から天引きされる保険料は従業員負担分のみなので、計算の際は注意しましょう。
給与明細に記載される「住民税」とは
住民税とは、その地域に住む人々で、地域社会や生活の維持・発展にかかる費用を負担し合うことを目的とした税金です。納付された住民税は、教育・福祉・消防救急・環境保全など、自治体におけるさまざまな行政サービスに活用されます。
また、住民税は、個人の所得に対して課税される税金の一つです。給与所得から各種所得控除(社会保険料控除や配偶者控除など)を差し引き、残りの金額に税率をかけて計算します。
住民税には、都道府県民税と市区町村民税の2種類があります。つまり、従業員から徴収した住民税は、従業員が暮らす都道府県と市区町村、それぞれに分けて納付されるのです。
なお、住民税は、その年の1月1日に従業員の住民票があった自治体に納付します。税額の算出に用いる所得額は、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入が対象です。
住民税には「均等割」と「所得割」がある
住民税は、均等割と所得割に分けられます。
均等割とは、住民税のうち、地域の住民が均等に負担する部分です。市区町村民税は年額3,500円、都道府県民税は年額1,500円と、個人の所得に関係なく一定額を負担します。
2023年度までは復興特別税として、都道府県民税と市区町村民税に、それぞれ500円が上乗せされていました。そして2024年度からは、森林環境税として計1,000円が徴収されます。金額は変わりませんが、徴収される項目は変更されるので覚えておくとよいでしょう。
一方、所得割とは住民税のうち、個人の所得に応じて負担する金額が異なる部分です。税率は基本的に一律10%で、所得が大きくなるほど税額がアップします。
なお、通常は都道府県民税4%+市区町村民税6%の割合ですが、指定都市に居住している場合は道府県民税2%+市区町村民税8%の割合で徴収されます。
参考:『住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか?』財務省
住民税の納付方法
住民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
- 特別徴収
- 普通徴収
それぞれの納付方法について、以下で詳しく解説します。
特別徴収
特別徴収とは、企業が従業員の住民税を計算し、給与からの天引きで徴収し、各自治体へ納付する方法です。前年度の所得から住民税を計算し、年額を12回(12か月)に分けて毎月の給与から天引きします。
つまり、給与明細に記載されている住民税は、この特別徴収の仕組みを利用したものです。
普通徴収
普通徴収とは、個人が住民税を自分で納付する方法です。主に個人事業主やフリーランスなどの自営業者が利用する方法で、自治体から個人宛に納税通知書が交付されます。
普通徴収や特別徴収に関するルールは「地方税法」によって定められており、原則として企業に属する従業員は普通徴収を利用できません。ただし一定の例外もあり、「給与支払いが不定期」「給与支払い者が2名以下」などの場合は、普通徴収に切り替えられます。
特別徴収する住民税の注意点
特別徴収によって住民税を給与から天引きする際は、以下の2点に注意しましょう。
- 入社と同時に天引きされるとは限らない
- 給与明細に記載されるが源泉徴収には記載されない
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
入社と同時に天引きされるとは限らない
住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の収入をもとに計算され、翌年の6月から翌々年の5月まで納付するものです。
新卒入社をはじめ、収入のない期間が長かったケースなど、前年の所得がない従業員の住民税は計算しません。新入社員の場合は、入社した年の所得をもとに住民税を計算し、入社翌年の6月から天引きを開始します。
前年の所得があるか否かは個別の事情により異なるため、従業員それぞれの状況を見て判断しましょう。
給与明細に記載されるが源泉徴収票には記載されない
給与明細と同じく、源泉徴収票には給与から天引きされた税金に関する情報が記載されています。ただし、源泉徴収票に記載されるのは、所得税に関する情報のみです。従業員の1年間の収入と納付した所得税が記載されており、通常は年末調整のあとに発行します。
従業員それぞれの状況に合わせて対処することが大切です。
| 発行のタイミング | 記載されている情報 | |
|---|---|---|
| 給与明細 | 月1回(給与支払いがあったとき) | 勤怠情報や支給額、社会保険料や所得税・住民税などの控除額 |
| 源泉徴収票 | 年1回(年末調整のあと) | 1年間の収入、所得税額 |
住民税を計算する3ステップ
従業員の給与から天引きする住民税は、おおむね以下の手順で計算します。
- 「課税標準額」を計算する
- 「所得割」を計算する
- 住民税を計算する
1.「課税標準額」を計算する
課税標準額とは、課税の対象となる金額です。住民税を計算する際は、所得金額をそのまま用いるのではなく、さまざまな控除を適用してから税率を乗じます。
具体的には、給与所得から給与所得控除・所得控除を差し引いた金額を課税標準額として扱います。
給与所得控除とは、給与所得者が納める税金を計算する際、収入に応じて差し引ける金額のことです。2020年以降の給与所得控除は、以下のように定められています。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
収入から給与所得控除を差し引いた金額を、「給与所得」と呼びます。
一方で所得控除とは、給与所得からさらに差し引ける控除です。すべての人が対象となる「基礎控除」のほかに、従業員の家族構成や保険の加入状況などに応じてさまざまな金額が控除されます。
| 所得控除の例 |
|---|
| 社会保険料控除 生命保険料控除 配偶者控除 扶養控除 ひとり親控除 |
2.「所得割」を計算する
ここまでの内容をもとに課税標準額を算出し、住民税の所得割を計算します。住民税の税率は、基本的に一律10%です。そこからさらに税額控除額を引くと、所得割の金額を算出できます。
税額控除には配当控除や外国税額控除などいくつかの種類がありますが、ふるさと納税をはじめとする、寄付金を支払うと利用できる寄附金税額控除が有名です。
3.住民税を計算する
上記で算出した所得割に、均等割を一律5,000円(市区町村民税3,500円+都道府県民税1,500円)加算します。復興特別税や森林環境税など、その時点で適用される金額を上乗せし、最終的な計算結果を住民税として徴収しましょう。
給与明細の発行を効率化する方法
給与明細を作成するためには、給与支給額や勤怠情報、税金や社会保険料の控除額など、さまざまな情報を把握する必要があります。担当者に負担がかかってしまうケースも多いでしょう。
給与明細に関する業務の効率化を目指すなら、以下の方法がおすすめです。
テンプレートを活用する
テンプレートを活用すれば、書類作成の手間を軽減できます。無料でダウンロードできるテンプレートも多くあるので、積極的に活用しましょう。
また、一般的なテンプレートでは対応しづらい場合、Excelなどで自社に合わせたテンプレートを作成するという方法もあります。
Web給与明細システムを導入する
Web給与明細システムを導入すれば、作業を大幅に効率化することが可能です。
給与明細の発行業務を効率化するだけでなく、システムのアップデートによって税制・法律の改正にも自動的に対応できます。給与明細を電子データとして発行できるため、企業のペーパーレス化にも一役買ってくれるでしょう。
住民税の基本をおさえて、給与明細に正しく記載しましょう
住民税は、地域の住民同士がお金を出し合い、地域社会の維持・発展を支えるためのものです。従業員の住民税は企業が計算・徴収し、各自治体に納める必要があります。給与明細にも天引きした住民税額を記載しなければならないので、正しい計算方法や金額を把握しておきましょう。
給与明細業務の負担増にお困りなら、Web明細システムの導入もおすすめです。
給与計算をより速く正確に|One人事[給与]
One人事[給与]は、ミスができない給与計算をWeb上で完結させるクラウドサービスです。
- 【給与計算】毎月ミスがないか不安
- 【給与明細】紙の発行が面倒
- 【勤怠との照合】勤怠データと一括管理したい
という悩みの解決を支援し、担当者の負担を軽減します。さらに勤怠管理システムOne人事[勤怠]と連携すると、勤怠データの取り込みがスムーズになり集計が自動化できます。
One人事[給与]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、年末調整の電子手続きをはじめ労務管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

