出退勤管理の方法とは? システムやエクセルの活用と見直しのポイントを解説
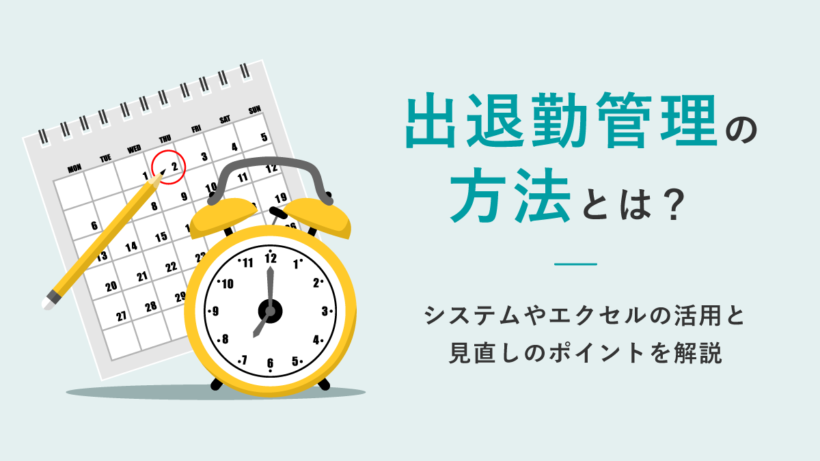
出退勤管理において「エクセル作業が限界」「打刻ミスの修正に時間がかかる」という悩みの声は少なくありません。
本記事では、出退勤管理の基本と重要性、主要な管理手法の特徴、システムの比較ポイントまでをわかりやすく解説します。もっとラクに・正確に、出退勤を管理するためにお役立てください。
→出退勤を管理できるシステムOne人事[勤怠]の資料をダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
出退勤管理の重要性
出退勤管理は、従業員の始業時刻と終業時刻を記録する業務であり、勤怠管理のもっとも基本にあたります。
勤怠管理には、残業や休暇、有給取得日数の管理など幅広い内容が含まれますが、正確な出退勤の記録がなければ、ほかの勤怠項目の管理も成り立ちません。
出退勤管理の3つの目的
出退勤管理には主に次の3つの目的があります。
- 労働時間の正確な把握
- 給与計算の根拠となる記録の確保
- 労働基準法など法令の遵守
なかでも労働時間の把握は、労働基準法第32条で「1日8時間・週40時間」という法定労働時間の上限を守るために企業に義務づけられています。
また、2019年の労働安全衛生法改正により、企業には客観的な方法で従業員の労働時間を把握し、記録・保存することが求められています。
もし出勤・退勤の記録が不十分で、残業代の未払いが発生した場合、意図的でなくても法令違反とされて罰則を受けて、社会的信用を失う可能性も否定できません。
労働時間の記録はそのまま給与計算や社会保険・税額の根拠にもなるため、ミスがあれば連鎖的に多くのトラブルが発生します。

出退勤管理の意味合いは立場で異なる
出退勤管理の意味合いは、立場によって異なります。
- 従業員にとっての出退勤管理=安心の根拠
- 企業にとっての出退勤管理=リスク対策
従業員にとっては、働いたぶんの給与が正確に支払われるという安心の根拠になるでしょう。 一方で企業にとっては、コンプライアンスを守り、未然に労務トラブルを防ぐためのリスク対策という側面が強くなります。
働き方の多様化にともない、出退勤管理のあり方も変わってきました。正社員、パートタイマー、フレックス勤務、テレワーク、直行直帰など、雇用形態や勤務形態に応じた柔軟な管理手法を検討しなければなりません。
出退勤管理を適切に行うことは、勤怠管理全体の精度を高め、企業として社会的責任を果たす役割があります。
出退勤管理の対象
出退勤管理は企業規模や業種を問わず、すべての事業所で必要な業務です。とくに労働基準法では、従業員を1人でも雇用している事業所に対して、労働時間の記録と保存が義務づけられています。
出退勤管理の対象を、企業と従業員に分けて確認していきましょう。
企業・事業所
出退勤管理は、業種や規模を問わず、原則すべての企業・事業所に求められる義務です。
労働基準法第4章が適用されるすべての事業場に対して、労働時間の把握と記録が義務づけられているためです。たとえ従業員が1人しかいない小規模事業所でも、出退勤を含む勤怠管理は必須です。
ただし、例外として、農業や水産業など自然条件に左右される一部の業種は、労働時間規制が適用除外とされています。
また、実務上は中規模・大規模の企業ほど、複数の勤務形態や就業パターンが混在しやすく、管理が煩雑になります。
たとえば小売業やサービス業ではシフト制、製造業では変形労働時間制、IT業界や事務職ではテレワークやフレックスタイム制が広く導入されており、多様な働き方に対応した出退勤管理の整備が重要です。
参照:『第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇』e-GOV法令検索
従業員
出退勤管理の対象となるのは、雇用形態にかかわらず、ほぼすべての従業員です。正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員まで、就業しているすべての労働者が対象です。
もともと、労働基準法第41条では「管理監督者」「裁量労働制の対象者」などが労働時間規定の適用除外とされていましたが、2019年の労働安全衛生法改正により、健康管理の観点から労働時間の把握が義務化されています。
つまり、管理職であっても「勤怠管理は不要」とはいえなくなりました。
また「みなし労働時間制」が適用される働き方においても、企業は所定の労働時間や年間休日の取得状況などを適切に管理・把握する必要があります。
勤務形態や就業形態が多様化する今、企業には「どの従業員に、どの方法で出退勤管理を行うべきか」を明確にし、対応できる柔軟な管理体制を構築することが求められています。
参照:『労働基準法第41条』e-GOV法令検索
参照:『労働安全衛生法』e-GOV法令検索
出退勤管理でよくある課題・トラブル
出退勤管理においては、多くの企業がさまざまな課題やトラブルに直面しています。とくに中小企業では、紙やエクセルといったアナログな手法で管理しているケースが多く、非効率な運用や法令対応の難しさに悩まされることが少なくありません。
よくある出退勤の課題は以下のとおりです。
| よくある課題 | 例 |
|---|---|
| 出退勤の記録ミスや漏れが多い | 手書きやエクセル入力では、打刻忘れ・記入漏れ・修正忘れなどのミスが起きやすい。 |
| 集計作業に時間がかかる | 複数の勤務形態を手作業で集計するため、月末や締め日に業務が集中し、担当者の負担が大きくなる。 |
| アナログ管理が非効率である | 紙やエクセルでは転記や確認作業が多く、ミスの温床に。リアルタイムな申請・承認や自動処理ができない。 |
| テレワーク・フレックス制に対応しにくい | 出社前提の打刻機では、在宅勤務や柔軟な勤務時間に対応できず、実態とのズレが生じやすい。 |
出退勤管理の課題は、単なる業務効率の低下にとどまりません。給与計算ミスや未払い残業、労務コンプライアンス違反といった重大なリスクにもつながるため、見直しが必要でしょう。
出退勤管理の4つの方法とメリット・デメリット
企業の出退勤管理には、主に以下の4つの方法があります。
- 出勤簿
- エクセル
- タイムカード
- 出退勤管理システム(アプリ)
従業員の働き方や企業の運用体制によって、最適な管理方法は異なります。それぞれの特徴を理解し、自社の規模や業態にあった方法を選ぶことが大切です。
出勤簿による出退勤申告
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 導入コストが低い | 記入ミスや改ざんのリスクが高い |
| 運用方法が簡単 | テレワーク時の管理が困難 |
| カスタマイズが容易 | 保管スペースが必要 |
紙の出勤簿は、小規模な事業所を中心に今も利用されている出退勤管理の方法です。手書きや押印で記録できるため運用はシンプルですが、一方で客観性や正確性に欠けるという課題があります。
とくに、自己申告による不正やサービス残業が見過ごされやすく、労働時間の実態把握が難しくなりがちです。また、出勤簿は労働基準法により5年間の保存義務(当面3年)があり、物理的な保管場所の確保も必要になります。
エクセルでの出退勤管理
| メリット | デメリット |
|---|---|
| データの集計が容易 | 入力ミスのリスクがある |
| 保存が電子的に可能 | リアルタイム性に欠ける |
| カスタマイズが自由 | データのバックアップが必要 |
エクセルを使った出退勤管理は、中小企業を中心に広く利用されています。関数を使えば、自動的に労働時間を計算できるため、紙よりは管理の手間が軽減されるでしょう。
ただし、出退勤時刻の入力は従業員本人が行うため、エクセルでも入力ミスや不正申告のリスクが残ります。
また、リアルタイムでの把握が難しく、給与計算までに数日間の集計作業が発生するケースもあります。
タイムカードによる出退勤記録
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 操作が簡単 | 打刻漏れのリスクがある |
| 導入コストが低い | テレワーク対応が困難 |
| 客観的な記録が可能 | 集計作業に時間がかかる |
タイムカードは、打刻によって出退勤時間を客観的に記録できる方法です。導入コストも比較的抑えられ、操作もシンプルなので今も一定の企業で導入されています。
一方で、直行直帰やテレワークには対応できず、勤務形態が多様な職場では不便に感じることも少なくありません。また、打刻ミスや修正対応、集計作業の負担が発生しやすい点にも注意が必要です。
出退勤管理システム(アプリ)による出退勤記録
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 正確な労働時間の記録 | 導入コストがかかる |
| 自動集計による効率化 | システムトラブルの可能性 |
| テレワーク対応が可能 | 従業員教育が必要 |
出退勤を管理できるシステムやアプリは、スマートフォンやパソコンを使ってリアルタイムで打刻・集計ができる方法です。
位置情報の取得や生体認証など、不正防止機能も充実しており、テレワークや外勤にも対応が可能です。
ただし、導入にはコストがかかり、従業員に新しい操作を覚えてもらう必要があります。
また、スマートフォンの位置情報の取得に抵抗感を持つ従業員もいるため、社内での運用ルールを明確にしておくことが大切です。

出退勤管理システム導入・比較時の注意点
最後に出退勤管理システム導入時の比較ポイントを紹介します。とくに注意したい点は以下のとおりです。
- 現場の運用フローに合ったシステムを選ぶ
- 労働基準法を満たせるかを確認する
- コストとサポート体制を各社比較する
現場の運用フローに合ったシステムを選ぶ
出退勤管理システムは現場の働き方や運用フローに自然に組み込めるかが重要です。
たとえば、外回りの多い営業職や直行直帰の勤務がある場合は、スマートフォンでの打刻機能が欠かせません。
固定端末での打刻しかできないシステムでは、むしろ出退勤管理が煩雑化してしまうこともあります。
また、以下のような勤務形態に対応しているかも確認しましょう。
- シフト制、フレックスタイム制、裁量労働制など複雑な働き方
- 正社員・パート・派遣など雇用形態の多様性
- 部署・職種ごとの運用ルールの違い
労働基準法を満たせるかを確認する
出退勤管理システムが最新の法令に対応しやすいかを必ず確認しましょう。
とくに以下のような機能は必要です。
- 時間外労働の上限管理・アラート通知
- 有給休暇の自動付与と取得状況の記録
- 客観的な労働時間の記録(ICカード・GPS・生体認証など)
働き方改革により、従業員の健康管理やワークライフバランスを意識した出退勤管理が求められるため、以下のような機能もあると安心です。
- 残業時間の可視化とレポート出力
- 過重労働者へのアラート
- 労務担当者が一目で把握できるダッシュボード
労働時間を正しく把握し、法令に準拠した運用を行うために複数社で比較しましょう。
コストとサポート体制を各社比較する
出退勤管理システムを選定する際は、初期費用・月額費用・機能追加にかかるコストをトータルで比較検討する必要があります。
一見安価に見えても、必要な機能がすべて有料オプションであれば、結果的に割高になることもあるためです。
また、以下のようにサポート体制が充実していると安心です。
- 導入支援や操作説明をしてくれる担当者の有無
- トラブル時の問い合わせ対応の迅速さと柔軟さ
- 初期設定やカスタマイズ対応の範囲
出退勤データには従業員の氏名・勤務時間・給与にかかわる個人情報が含まれます。そのため、次のようなセキュリティ対策が万全かどうかも確認しましょう。
- 通信の暗号化、データのバックアップ体制
- ログイン制御や権限設定
- システム障害時の復旧体制
情報漏えいやデータ紛失は企業の信頼性に影響します。安心・安全な出退勤管理を継続できるかも選定の大事なポイントです。

まとめ|出退勤管理を見直すならシステム活用の検討を
出退勤管理は、従業員の労働時間を正確に把握し、企業が法令を遵守するうえで欠かせない業務です。しかし、アナログな方法では記録ミスや集計負担が発生しやすく、業務効率や労務リスクの観点からも限界があります。
とくに近年は、テレワークやシフト制など多様な働き方への対応が求められ、従来の出退勤管理方法では実態に合わないケースも増えています。
出退勤管理の課題を解消するには、システムの導入・見直しがおすすめです。リアルタイムでの記録・集計・アラート機能・法令対応など、システムならではのメリットを活かすことで、正確性・効率性・安全性を兼ね備えた体制を構築できます。
自社の働き方や運用体制に合った出退勤管理のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。
出退勤管理のミスを減らすOne人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な管理をクラウド上でシンプルにする勤怠管理システムです。出退勤の打刻だけでなく、以下のような勤怠管理全体の課題解決を支援しております。
- 出退勤の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題の整理からご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
