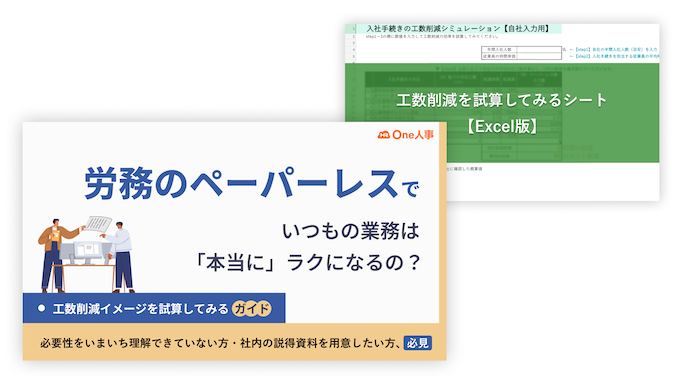勤怠管理システムの乗り換えで外せない比較ポイント|見直しのタイミングやよくある失敗例も紹介
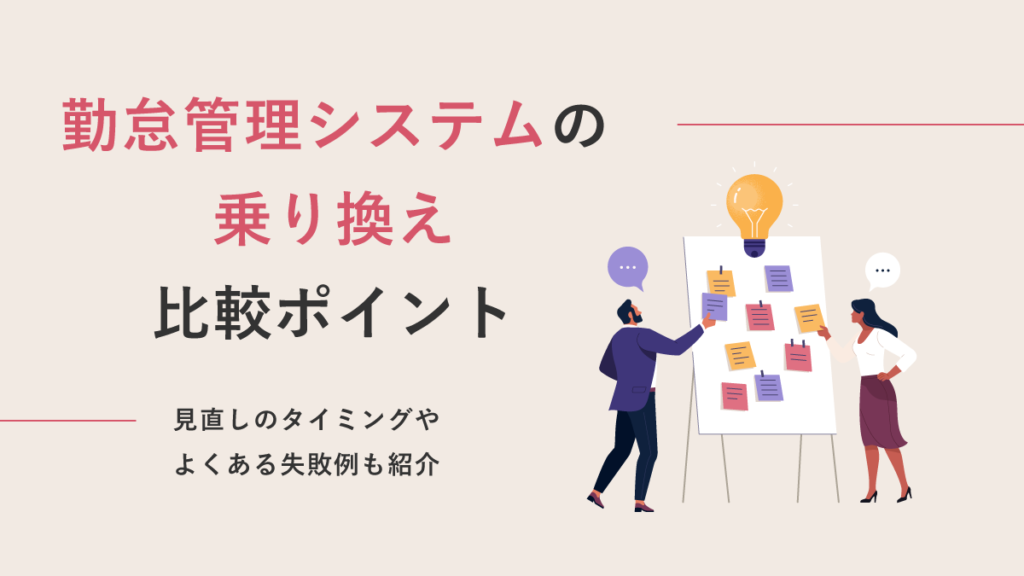
現在ご利用中の勤怠管理システムは、本当に使いやすいといえますか。
毎月の勤怠データの集計に時間がかかり、ミスでやり直しが発生する、従業員から不満が出ている──。課題を抱えながらも「今のままで何とかやれているから……」 とあと回しにしている企業も少なくありません。しかし、従業員数の増加や雇用形態の変化、法改正の影響など、自社の成長フェーズに合わせて最適な勤怠管理の方法が変化するのは当然です。効率化のはずが逆に手間が増えているなら、それは「切り替えのタイミング」といえるでしょう。
本記事では、勤怠管理システムの乗り換えに役立つ比較ポイントや見直しの進め方を解説しています。「もう後悔したくない」とお考えの人事労務担当者は、ぜひ最後までお読みください。
→勤怠管理にもう手間をかけない|「One人事」の資料を無料でダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
勤怠管理システムの導入後に気づくよくある失敗例
業務の効率化やミス削減を目的に、勤怠管理システムを導入している企業は少なくありません。しかし、導入後に「失敗した」、段々と「合わなくなってきた」という声もよく聞かれます。そこでまずは、勤怠管理システムの導入後に気づく、よくある失敗例を紹介します。
| 失敗例 | 結果 | 対策(事前の確認事項) |
|---|---|---|
| 法改正への対応に追加費用がかかった | アップデートが有料で予算を超えた | ・法改正の対応が標準機能か・更新費用の発生 |
| 会社独自の就業ルールを設定できない仕様だった | フレックスに未対応 休暇の申請は紙のまま運用することになった | ・独自の勤怠ルールを事前に整理→対応可否・柔軟な設定変更 |
| サポート範囲に初期設定が含まれていなかった | 希望する運用開始時期に間に合わなかった | ・サポート範囲 ・導入スケジュール ・設定から定着まで伴走してくれるか |
| 現場の従業員が使いこなせなかった | 説明や問い合わせ対応で、結果的に担当者の仕事が増えた | ・ UI/UXの使いやすさ・使う従業員が直感的に操作できるか |
| 給与計算システムとの連携がスムーズにいかない | 情報の二重登録、転記ミスの修正で余計に時間をとられた | ・連携方法(API/CSV/ワンデータベース) ・給与の管理業務とどのように連携していくか |
なお、現在タイムカードや紙、エクセルで勤怠管理をしている企業の方で、初めてのシステム導入をお考えなら、以下の記事もご確認ください。
勤怠管理システムが合わないと感じる理由
せっかく苦労して導入した勤怠管理システムに不満を持ち、「失敗した」と感じてしまうのはなぜなのでしょうか。今の勤怠管理システムが合わないと感じる理由には、いくつかの特徴があります。もし1つでも当てはまるなら、勤怠管理システムを見直す時期にきているのかもしれません。
使いづらい・処理が遅い
「シンプルで誰でも使える」勤怠管理システムだと思っていたのに、実際には設定や操作が複雑で、現場が混乱してしまったというケースです。
| 「合わない」「使いにくい」と感じる場面の例 |
|---|
| ・勤怠の修正手続きが複雑で、従業員が毎回人事に問い合わせる ・画面の読み込みが遅く、毎日の打刻や申請がストレスになる ・操作マニュアルがわかりにくく、新人が習得するのに時間がかかる |
勤怠の予実管理ができない
勤怠実績と予実管理が煩雑だと、法令順守のチェックやシフト計画がスムーズに進まない原因にもなります。
| 「合わない」「使いにくい」と感じる場面の例 |
|---|
| ・シフト予定と実際の勤務時間がずれていても、自動でアラートが出せない ・勤務時間の乖離がわかりにくい ・過重労働リスクが見えにくい |
設定サポートが不十分と感じる
勤怠システムは、導入時の設定が複雑になりがちですが、サポート範囲が不十分な場合、本稼働までに時間がかかってしまいます。
| 「合わない」「使いにくい」と感じる場面の例 |
|---|
| ・メールサポートしかなく、急ぎで対応できない ・細かいルールの反映がうまくいかない ・社内で何度も試す羽目になる |
多様な働き方に対応しきれない
近年、多くの企業がリモートワークやフレックスタイム、副業など多様な働き方が推進されています。しかし、勤怠管理システムに柔軟性がなく、多様な打刻方法に対応していないと、運用負担が増大してしまいます。
| 「合わない」「使いにくい」と感じる場面の例 |
|---|
| ・在宅勤務・出社を自動で識別できない ・位置情報が取得できない ・フレックスタイム制に対応できない |
給与計算と連携できず手作業が発生している
勤労怠管理システムの大きな役割の一つは、給与計算に必要な実労働時間のデータを正確に集計することです。しかし、給与計算システムとの連携がスムーズにできなければ、アナログ作業が増えてしまいます。
| 「合わない」「使いにくい」と感じる場面の例 |
|---|
| ・データ形式が合わず、毎月手作業でフォーマット変換をする必要がある・API連携がないため、手動でCSVファイルをアップロードしている ・二重登録の際にミスが発生し、計算が合わない |
勤怠管理の方法やルールは組織によってさまざまです。自社の就業ルールに対して、システムの機能が不十分であったり、単純に「使いづらい」と感じていたりすると、不満がたまるのも無理はないでしょう。

勤怠管理システムを乗り換えを検討したいタイミング
勤怠管理にさまざまな課題を抱えている企業は少なくありませんが、具体的に乗り越えに最適なタイミングはあるのでしょうか。移行は、システムが「使いにくい」「合わない」と感じたタイミングはもちろん、企業の成長や環境の変化も考慮することも大切です。
- 現場から「使い短い」という声が上がるようになってきた
- なぜか手作業が増えてきた
- 別のシステムを入れたことで連携工数が発生するようになった
- 従業員数が増え、組織の成長にシステムが追いつかない
- コストが増し、運用負担が大きくなっている
- 製品を提供するベンダーのサポートが手薄になっている
- 契約更新のタイミング
以上のような状況が発生した場合は、システムの乗り換えを本格的に検討してみてもよいでしょう。

勤怠管理システムの乗り換えはどれほど面倒?
今のシステムに不満を持っていても、労力や手間を考えて移行に踏み出せない担当者もいるでしょう。しかし、勤怠管理システムの乗り換えはポイントさえおさえれば、導入にかかる面倒を最小限に抑えられるはずです。
やみくもに有名な大手サービスを選んだり、とりあえず一括で資料を請求したり、あるいはタイムカードに戻る前に、まずは要件を整理しませんか。ポイントは「社内整理」と「実態把握」です。
→勤怠課題の整理からお手伝い|「One人事」サービス資料を無料でダウンロード
勤怠管理システムをスムーズに乗り換えるには?|事前に社内で確認しておきたい5つのこと
勤怠管理システムを切り替える前に、「とりあえず良さそうなシステムを選ぶ」のではなく、社内の課題や要件を明確にすることが重要です。
システムの導入後に「思ったように使えなかった」「結局手間が増えた」と後悔しないために、事前に社内で確認しておくべき5つのポイントをおさえてから踏み切りましょう。
非効率な業務を洗い出す
まずは現状の勤怠管理システムの運用で、どの業務が負担になっているのかを洗い出しましょう。
- 毎月の勤怠集中やデータ処理に時間がかかっている
- 申請・承認フローが煩雑で、管理者の負担が大きい
- 手作業での修正が多く、ミスが発生しやすい
非効率な業務がどこにあるのかを理解し、「新しいシステムで何をを実現したいのか」を明確にすることで、勤怠管理システムを見るポイントがより具体的になります。
現場の要望をヒアリングする
新しい勤怠管理システムを導入しても、現場の従業員が使いこなせなければ意味がありません。
- 現場の従業員が最新システムを使いこなせていない理由を確認する
- 「どんな機能があれば使いやすくなるか?」をヒアリングする
- 人事担当者だけでなく、実際に打刻・申請を行う従業員メンバーの意見を反映する
現場のニーズを無視してシステムを決めると、「導入したのに誰も使いこなせない」「結局手作業が増えた」という失敗につながりやすいため、事前のヒアリングは欠かせません。
自社の勤怠管理の特性を把握する
部署や職種、雇用形態によって、勤怠管理のルールや必要な機能は異なります。正社員とシフト制のアルバイトスタッフでは、重視したいポイントが異なるため、どのような機能が必要か把握しておくことが重要です。
- 配置ごとに異なる勤怠管理ルール(夜勤・フレックスなど)を整理する
- 直行直帰・出張・リモートワークの管理方法を明確にする
職種ごとの勤労怠管理の特性を洗い出すことで、「従業員にとって適したシステムか?」に注目して判断しやすくなります。
→勤怠課題の整理からお手伝い|「One人事」サービス資料を無料でダウンロード
優先順位を決める
勤怠管理のルールはとくに、会社によって個性があるので、システムに合わせてルールを見直すほうが、実現イメージに近い場合があります。
そのため勤怠管理システムを切り替える際は、「一度にすべての要望を満たすシステム」は存在しないことを前提に、優先順位を決める必要があるかもしれません。
- 「最優先で解決すべき課題は何か?」を明確にする
- 独自のルールが複雑すぎる場合は、運用の見直しも検討する
- システムに合わせてルールを最適化すると、よりシンプルな運用が可能になることも
自社の勤怠ルールが「本当に必要か?」を見直すことが、効率化につながるケースもあります。
導入スケジュールを立てる
勤怠管理システムの移行は、スムーズな移行ができるかどうかが重要です。
- 現行システムの契約期間や更新タイミングを確認する
- 移行にかかる期間を試算する
- 複数のシステムを比較検討するための十分な時間を確保する
企業の業務スケジュールと照らし合わせ、余裕をもって勤怠管理システムの移行を計画できると、現場の負担も抑えられます。

勤怠管理システムの乗り換えで外せない8つの比較ポイント・注意点
勤怠管理システムの乗り換え検討では、長期的に活用できるかを見極めるかどうかが重要です。以下の8つの比較ポイントをおさえて、後悔のないシステム比較を進めましょう。
自社に必要な機能に過不足はないか
勤怠管理システムの乗り換えでは、比較前に整理した「現状の課題」「実現したいこと」を踏まえて、自社の課題解決につながる機能がそろっているかを確認することが重要です。
- 業務負担を軽くする?(勤怠集計の自動化、打刻ミスの軽減など)
- 従業員が使いやすい?(申請の自動化、モバイル対応など)
- 管理者の業務効率が向上するか?(レポート機能、アラート通知など)
ただし、「必要な機能があるか」だけでなく、その機能が本当に「業務改善に貢献するのか」という検討も必要です。
候補に上がっている勤怠管理システムの標準機能に対して不足がある場合、運用を見直したり優先順位を入れ替えたりする方が、結果的に効率化が進む場合もあります。
クラウド型か、オンプレミス型か
勤怠管理システムには、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。
それぞれの特徴を踏まえて、自社の運用体制に適した提供形態を選びましょう。
| クラウド型 | オンプレミス型 | |
|---|---|---|
| 導入コスト | ○(初期費用を抑えられる) | ×(サーバー購入費用など) |
| 導入スピード | ○(比較的速い) | ×(構築期間が必要) |
| カスタマイズ性・自由度 | △(制限あり) | ◎(自由度が高い) |
| システム間の連携 | ◎(API、ワンデータベースなど連携しやすくなっている) | △(カスタマイズ次第) |
| セキュリティ | ○(ベンダーの対策による) | ◎(自社で管理) |
| 保守管理の手間・法改正への対応 | ◎(ベンダーが対応) | ×(自社で対応するか、アップデートを依頼するか) |
スピーディーな導入で、比較的低コストを重視するならクラウド型、高度なセキュリティ対策や独自のカスタマイズが必要ならオンプレミス型が適しているでしょう。
→クラウド型勤怠管理システム|One人事[勤怠]の特長を見てみる
導入・維持コストは予算に収まるか
勤怠管理システムの乗り換えにかかる費用は、大きく分けて「初期導入費用」「維持費用(ランニングコスト)」「オプション料金」の3つがあります。
導入費用だけでなく、維持にかかる費用や追加も事前に確認し、数年単位でコストを試算するのがポイントです。
| 主な費用 | 備考 |
|---|---|
| 初期導入費用 | クラウド型は無料が多いが、設定代行やレクチャー費用が発生する場合も |
| 維持費用(ランニングコスト) | 一般的に従業員1名あたりの従量課金制 |
| オプション料金 | 基本機能以外の追加費用 ICレコーダーなどの打刻ツールの追加費用 |
乗り換えでもIT導入補助金を利用できる場合があるため、申請対象を確認しましょう。
従業員数の増加や利用する機能の拡張を見越し、総合的に費用対効果を見極める必要があります。
システムの費用対効果を見積もるには、以下の資料もご活用ください。入社手続きと年末調整の工数削減例を紹介していますが、勤怠管理の対応工数に置き換えることで、導入効果の試算にお役立ていただけます。
使いやすいか、わかりやすいか
ITやシステムと聞くと、なかには耳が痛くなる人もいます。操作に不慣れな従業員の目線に立ち、誰でも簡単に操作できるかどうかは、乗り換えでも重要なポイントです。
- 勤怠の打刻や申請が直感的に操作できるか
- 画面デザインが見やすく、視認性が高いか
- スマホやタブレットでの利用が可能か
勤怠の打刻や申請は、一人ひとりの日々の業務にかかわるものです。誰にとっても画面が見やすく、迷うことなく使えるかを確認しましょう。
無料トライアルの機会を利用して、使い倒すことをおすすめします。
→30日間使い倒すOne人事[勤怠]の無料トライアルお申し込みは【こちら】
設定に手間がかからないか
勤怠管理システムを導入してから、運用開始までの間で、担当者の目線で設定にどれほどの手間がかかるのかを慎重に検討します。
とくにルールが複雑な企業では、システムの初期設定に時間がかかる場合があります。初期設定をサービス提供者に任せることも視野に入れましょう。
サポート体制は十分か
操作性に関する質問はもちろん、導入前の設定代行や導入後の伴走支援があるか否かを確認します。
勤怠管理システム乗り換え後のサポートが充実しているかどうかも、検討時の重要なポイントです。操作性に関する質問はもちろん、導入前の設定代行や導入後の伴走支援があるか否かを確認します。
| サポート範囲の例 |
|---|
| ・担当者の有無 ・問い合わせ方法 ・初期設定代行 ・導入後の活用・定着支援 |
サポートの充実度を事前に確認し、いざというときに備えましょう。
→運用開始率100%【挫折させない導入サポート】「One人事」サービス資料
給与計算ほか、ほかの業務と連携できるか
勤怠管理は、給与計算などその他の業務領域と密接にかかわるため、スムーズに連携できるかを確認しましょう。
- 今使っている給与計算システムとデータ連携できるか
- API連携やCSVによるデータの出力・インポートが可能か
- システム間のデータ移行に時間がかかるか
| 連携方法の例 |
|---|
| ・API(OSに接続して異なるソフト間でデータ共有を可能にする仕組み・CSVファイルの出力・アップロード※1つのデータベース(マスタ)で管理しているなら連携作業が発生しない |
連携がスムーズであったり、1つのデータベースで管理できたりすると、人事全体の業務効率化につながります。勤怠管理の枠にとどまらず、広い視点での活用を考えることが重要です。
中長期的に活用イメージを描けるか
勤怠管理システムは、「導入して終わり」ではなく、定着させ、長期的に活用できるかが重要です。
導入に失敗したり定着しなかったりするのは、導入前後の活用を中長期的にイメージできていないことが原因の一つかもしれません。
比較の過程で見失いそうになったら、自社が「やりたいこと」に立ち返りましょう。そのうえで「5年後、10年後も使えるシステムか」という視点がポイントです。
定着するための体制構築や、データを活用する仕組みづくりも忘れてはなりません。
勤怠管理システムOne人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をシンプルにする勤怠管理システムです。
- 業務負担が減らない
- 自社のルールに対応できず、例外処理が増えている
- 給与計算や労務管理との連携が不完全で、手作業が発生する
今の勤怠管理に課題がある企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
労働時間の集計ミスによる給与の未払いや労務コンプライアンス違反といったトラブルを避けるためにも、One人事[勤怠]をぜひご検討ください。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |