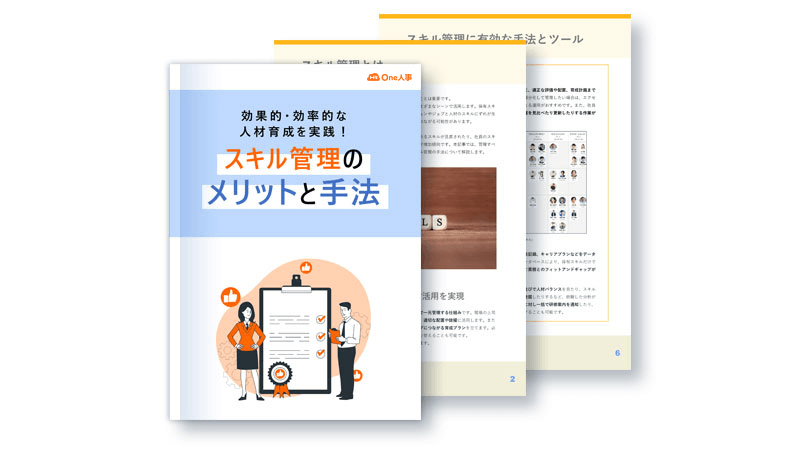協調性とは【意味をわかりやすく】 ある・ない人の特徴や高めるマネジメントを解説

協調性とは、個々人がチームや組織全体の利益のために協力し合う能力を指します。
ビジネスでは、1つの事業やプロジェクトに対し、配属先のメンバーと役割を分担し、利益を出さねばなりません。
人事評価の基準に「協調性」の項目を取り入れている企業もいるでしょう。マネジメントにおいては、メンバーの協調性を引き出すことも課題の一つとなります。
本記事では、協調性の定義やビジネスシーンにおける重要性、協調性が高い人の特徴(行動特性)などを解説します。
→メンバーの協調性の高い・低いを可視化「One人事」の資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
協調性の意味をわかりやすく解説
協調性とは、自分の意見や考えと異なる視点を持つ人々とも、共通の目標や課題に対して効果的に連携し、協力して取り組むことができる能力や態度を指すものです。
相手の意見を尊重し、異なる視点を受け入れる柔軟性や、共同での問題解決のためのコミュニケーションスキルも含まれます。
協調性の起源
協調性の起源については、人類の進化、社会的な背景、心理学、そして生物学的な側面から多角的に考察されています。
| 進化的背景 | 食料確保・敵からの防御・繁殖など生存に不可欠。狩猟採集社会では大きな獲物の捕獲や食料共有という強調により生存と繁栄を維持してきた。 |
| 社会的背景 | 人間社会は役割分担と協力を前提に成り立つ。協調性は重要な社会的価値として育まれてきた |
| 心理学的側面 | 協調性は人間関係構築の基本。共感・理解・コミュニケーション能力などと深くかかわる。 |
| 生物学的側面 | 一部の研究が脳やホルモンとの関連を示唆。オキシトシンは信頼や愛情など協調を促す感情に影響する。 |
参考:『協調性とその起源― Agreeableness と Cooperativeness の概念を用いた検討』J-STAGE
協調性の意味への誤解
協調性というと、「周りに合わせる力」や「空気を読む能力」といった意味合いで捉えがちです。
確かに、集団のなかで調和を保つためには、ときに周囲の意見や感情を尊重し、自分の意見を控えることも必要です。しかし、それだけが協調性のすべてではありません。
本来の協調性とは、自分と異なった意見を持つ人とも、目標達成に向けてともに助けあえる能力です。異なる視点を受け入れて尊重する柔軟性に加え、自分の考えを適切に伝え、他者と円滑なコミュニケーションをはかる力も求められます。
協調性が高い人は、単に周りに合わせるだけでなく、メンバー間の橋渡し役として調和を保ちながら業務を推進します。場合によってはリーダーシップを発揮し、全体を導かなければなりません。
つまり協調性とは、単なる多様な意見や価値観を受け入れ、それを活かしてチーム全体を前進させる力です。協調性の本質的な意味を理解し、日々のビジネスや人間関係に活かすことが重要です。
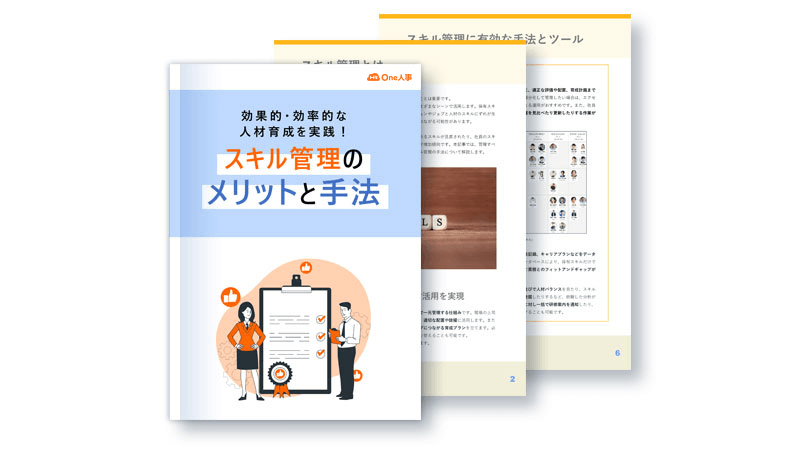
協調性はなぜ大事? ビジネスにおける重要性
ビジネスの現場では、多様なバックグラウンドや専門知識を持つ人々が共同で作業を進めなければなりません。職場では、協調性は極めて重要な役割を果たします。
たとえば協調性を発揮できると、ビジネスの現場では、以下のようなメリットが得られます。
| メリット | 例(具体的なシーン) | |
| 情報の共有と知識の統合 | 異分野の知識を組みあわせ、総合的な解決策や新しいアイデアを創出できる | マーケティングと開発部署が連携し、市場ニーズに適した製品を開発 |
| リスクの低減 | 多様な視点で判断ミスや見落としを防ぐ | 異なる部門の意見を取り入れ計画を修正 |
| 効率的な業務遂行 | 役割分担と情報共有がスムーズに行われ、業務効率が高まる | タスク重複を避けリソースを最適活用 |
プロジェクトを成功させるには、多様な意見やスキルを持つメンバーが協力して業務に取り組み、より質の高い成果を生み出す必要があります。協調性は、ビジネスの成果を上げるうえで欠かせない要素なのです。
協調性がある人の行動特徴
ここまで協調性の定義や、ビジネスシーンで求められる協調性について、イメージを持っていただけたかと思います。
では、協調性の高い人はグループのなかでどのような立ち振る舞いをする人が多いのでしょうか。
以下では、とくに多く見受けられる特徴を紹介します。
- 人の意見を否定しない
- 主体的に動く
- 優先順位のつけ方が上手である
- 報連相を欠かさない
人の意見を否定しない
協調性が発揮される場面でもっとも多く見られるのが、メンバー同士で意見の食い違いがあったときの対応です。
自分なりに考えた意見や施策を考えてきたのですから、「今日のミーティングではそれを通したい」「自身が主導したい」といった思いは、少なからず誰しもあるでしょう。
とはいえ、施策に対する考え方は十人十色です。必然的に意見の食い違いが発生します。
協調性が高い人は、自分の意見を一方的に主張するのではなく、「Aさんの意見は私を含め、ほのメンバーにはない着眼点ですね」「AさんとCさんの意見をあわせて、〇〇したら業務効率が上がると思う」といったように、他者の意見を否定せず、話し合いを前に進める傾向あります。
主体的に動く
協調性が高い人は、他者との調和を保ちつつ、自分の役割を理解し、主体的に行動します。単に自分のタスクを遂行するだけでなく、チームや組織全体の目的や方向性を踏まえた動きができることを意味します。その過程では、自分の意見を適切に伝え、円滑なコミュニケーションを取る力も欠かせません。
一見すると協調性と主体性は相反するように思えるかもしれませんが、実際には密接に関連しています。
真の協調性を持つ人は、他者と協力しながらもみずからの役割を最大限に発揮できるのです。担当業務を進めながら、事業やプロジェクト全体の円滑化を意識して行動する人が多く、「洞察力がある」も同時に持ちあわせている人が多いでしょう。
優先順位のつけ方が上手である
協調性は他者との関係を円滑に進める力ですが、そのなかには「優先順位のつけ方がうまい」という特徴があります。
協調性が高い人は、多様な意見や要求を尊重しつつ整理し、全体の目的やゴールに沿ってもっとも重要な課題から着手できるのです。
たとえば、プロジェクトで複数の提案が出た場合、協調性のある人はそれらを取りまとめ、成功に直結する行動を優先します。こうした判断はチームの効率や生産性を高め、信頼関係も深めるでしょう。
「優先順位のつけ方」とは、単なるタスクの順番決めにとどまらず、複雑な状況での意思決定やコミュニケーションの質を引き上げる力でもあります。
真の協調性を持つ人は、この力を活かし最適な行動を選択できるのです。
報連相を欠かさない
報連相を欠かさないという行動は、ビジネスの現場で極めて重要です。自分の業務内容や進捗、完了見込みを定期的に共有することで、チーム全体の業務がスムーズに進み、予期せぬ問題にも迅速に対応できます。
判断に迷ったとき、協調性の高い人は自己判断で進めず、上長やメンバーに相談します。多角的な意見を取り入れ、より適切な判断をしています。
相談を通じてミスのリスクを減らし、チームの知識や経験を最大限に活用しているのです。こうした姿勢は「協調性の高い人は仕事ができる」と評価される理由の一つです。
情報共有や相談を通じてコミュニケーションを活性化し、生産性や効率を高める協調性は、ビジネスの成功に欠かせない能力です。
協調性がない人の行動特徴
協調性が高いと認識される特徴とは反対に、「協調性が低い」と誤解されてしまう振る舞いもあります。
- 意見の食い違いを受け入れない
- 発言しない
- 1人で悩む
- 報連相をしない
自社のメンバーに該当する人がいないか考えながら、確認していきましょう。
意見の食い違いを受け入れない
ミーティングで意見が対立した際、「自分が絶対に正しい」と主張し続ける行動は、自信のあらわれである一方、協調性を欠く印象を与えてしまいます。強い主張には深い専門知識や経験が根拠となる場合も多く、価値がある意見であることも少なくありません。
しかし、チームで成果を出すには、異なる意見や視点を持つメンバーとの協力が不可欠です。自分の考えを伝える際は、相手の立場を尊重し、双方の意見を融合させる姿勢が求められます。
意見の食い違いは、新たな視点やアイデアを取り入れる絶好の機会でもあります。多様な背景や経験を持つメンバーの発想は、自分一人では生まれない革新的なアイデアを生むでしょう。
発言しない
意見が求められる場面で沈黙すると、業務への関心が低い、または自分の考えに自信がないと受け取られ、強調性を欠く行為です。
ミーティングやディスカッションは、意見を共有して方向性を決める重要な場です。発言しないと、関与したくないと誤解されてしまうでしょう。
発言は情報伝達だけでなく、メンバーとの信頼関係を築く手段でもあるため、沈黙によって関係構築の機会を逃してしまうおそれもあります。
意見がすでに出ていたり、タイミングを逃したりしている場合でも、短く簡潔に自分の立場を示すことが大切です。たとえば「賛成です」「私も同じ考えです」と、伝えると周囲への協調的な姿勢を示せるでしょう。
1人で悩む
業務を進めるなかで、予算の使い方など自分だけでは判断しきれない場面は少なくありません。こうした状況で1人で抱え込むと、業務が停滞して進行が遅れ、協調性を欠いてしまいます。
たとえば、予算を独断で決定した結果、あとになって不適切と判明し、プロジェクト全体の遅延やコスト増加を招くこともあります。
本来、複雑な判断が必要な場面では、多角的な視点や経験を持つ他のメンバーや上長の意見を取り入れることが不可欠です。
判断に迷ったときは、1人で悩まず協力を求める姿勢が求められます。社内への相談を怠ると、協調性が低いと判断されてしまうでしょう。
報連相をしない
報連相を怠ると、チームから協調性がないと評価される大きな要因となります。
業務内容や進捗状況を共有しなければ、周囲が正しい情報を得られず、作業の重複や情報の行き違いが発生します。結果として、プロジェクトの効率が落ち、メンバー間の信頼関係も損なわれるでしょう。
たとえば、上長から特定のタスクを任されても、ほかのメンバーに伝えていなければ、別のメンバーが同じ作業を進めてしまうことがあります。さらに、進捗を共有しなければ、周囲に「何をしているのかわからない」と感じられ、チーム全体に不安や不信感が広がるおそれもあります。
報連相は単なる業務報告ではなく、チームの一体感と信頼を保つための基礎的なコミュニケーション手段です。怠れば、仕事の成果にも人間関係にも悪影響があります。
協調性がない人を放置するリスク
協調性が低いメンバーを放置すると、チームの健全な機能や組織の持続的な成長の阻害要因です。早期の対応やサポートが求められます。
協調性が低いメンバーを放置すると、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
あるチームに、協調性の低いメンバーが1人いると仮定しましょう。そのメンバーは、情報共有や意見交換が苦手で、コミュニケーション不足に陥りがちです。放置すると、まず本人がストレスを感じやすくなります。自分の考えが伝わらないことから孤立感が強まり、業務への意欲も低下します。
影響は個人の問題だけにとどまりません。情報の行き違いや作業の遅れ、ミスが増え、チームの雰囲気や一体感が損なわれます。信頼関係がくずれることで、協力体制も弱まってしまいます。
さらに長期化すると、メンバー全体のモチベーションや生産性が下がってしまうでしょう。協調性の欠如は、組織全体の健全な運営や成長を阻害するため、早めのサポートが大切です。
協調性を高める育て方
チームの成果や雰囲気は、メンバー同士の協調性によって大きく左右されます。いくら能力の高い人材が集まっていても、連携が取れなければ情報共有は滞り、業務の重複やミスが増え、成果が見込めません。
事態を未然に防ぐためには、上長が日常的に「協調性を引き出す工夫」を意識的に行うことが重要です。メンバーの強みを活かし、互いに助け合える環境を整えることで、チームの信頼関係と一体感は自然と高まるでしょう。
優秀な人材の離職や事業の停滞を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを引き上げるために有効なポイントは、以下の3点です。
- 業務課題に対し、当事者意識を持たせる
- ミーティングにおける心理的安全性を確保する
- 雑談の時間を設ける
業務課題に対し、当事者意識を持たせる
協調性を高めるためには、従業員一人ひとりが自分の業務の意味や役割を理解し、当事者意識を持つことが欠かせません。しかし、会議やミーティングで発言しない背景には、自分の業務が全体のビジョンや目標にどのようにかかわっているのかを理解できていないことがあります。業務目的の不明瞭さを解消するには、日報や定期的な1on1ミーティングが有効です。
日報では、日々の業務で直面している課題や進捗、不安や疑問を可視化できます。1on1面談では、日報の情報をもとに上長がフィードバックを行い、業務の方向性や重要性を直接伝えることが可能です。
定期的なコミュニケーションを継続することで、従業員は自分の業務が会社全体の成果に与える影響を理解できるようになるでしょう。結果として、仕事への興味ややりがいが高まり、主体的な行動やミーティングでの積極的な発言につながります。
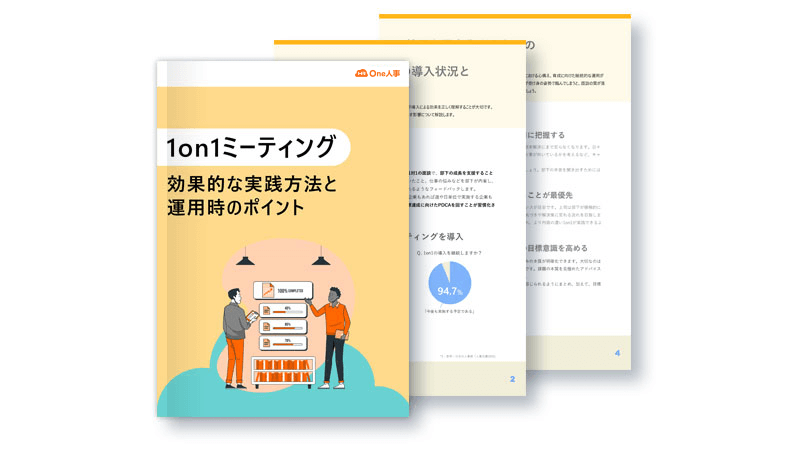
ミーティングにおける心理的安全性を確保する
チームの協調性を高めるには、メンバーが安心して意見を言える環境づくりも大切です。その土台となるのが「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、自分の意見や考えを自由に表現しても、否定や罰を受けることなく受け入れられる環境を指します。Googleの研究でも、生産性や創造性を高める鍵として注目されており、心理的安全性の高いチームでは、過ちの共有や質問、新しいアイデアの提案も安心して行えます。
ミーティングで心理的安全性を高めるには、上長が「ここでの発言は評価の対象にはしない」と明確に伝えることが効果的です。一言が安心感を生み、従業員は異なる意見や斬新な提案をおそれずに発言できるようになります。
心理的安全性が確保された場では、意見の尊重や協力的な議論が自然に生まれます。結果として、協調性が高まり、意思決定の質やイノベーションの創出にもつながります。上長の一言や態度が、健全で生産的なコミュニケーションの土台をつくるのです。
参考:『「効果的なチームとは何か」を知る』Google re:Work
雑談の時間を設ける
雑談の時間は、従業員同士の協調性を高める有効な方法の一つです。業務の枠を離れてリラックスした会話をすることで、メンバー同士が人間的な一面や趣味、価値観を知るきっかけになります。相互理解は、日常業務でのやり取りを円滑にし、信頼関係を築く土台となるでしょう。
たとえば「2週間に一度、30分間」といった形式で定期的に雑談の時間を設けると、コミュニケーションの壁が低くなり、意見交換がオープンになります。また、派閥や孤立を防ぐ効果もあり、チーム全体の雰囲気を健全に保てます。
雑談の時間は単なる休憩ではなく、結束力を強化し、日常業務にも前向きな影響を与える戦略的なアプローチです。
協調性がある・ないを判断する評価面談での質問
評価面談の場で「どのような質問をすれば、従業員の協調性を見極められるのか」と悩むケースは少なくありません。
そこで協調性の有無を確認する質問例を5つの観点から紹介します。面談項目の参考にぜひお役立てください。
チームワークに関する質問
従業員がチーム内での協力や協調性をどのように実践しているかを確認する質問です。
- 最近のプロジェクトやタスクで、チームメンバーとの協力がとくに必要だった瞬間はありましたか?
- チーム内で意見の対立が起きたとき、あなたはどのように対応しましたか?
コミュニケーション能力に関する質問
従業員が他者とのコミュニケーションを円滑に行っているか、または困難をどのように乗り越えているかを確認する質問です。
- ほかのメンバーとのコミュニケーションで困難を感じた経験はありますか?その際、どのように解決しましたか?
- ほかのメンバーからフィードバックや意見を受け取った際、どのように受け止めましたか?
問題解決能力に関する質問
従業員がチーム内の問題や課題に対してどのように取り組んでいるかを確認する質問です。
- チーム内での課題や問題を解決する際、あなたの役割は何でしたか?
- チームとしての目標達成のために、みずから率先して行動した経験はありますか?
柔軟性に関する質問
従業員が新しいアイデアや異なる意見に、どれだけ柔軟に対応しているかを確認する質問です。
- ほかのメンバーの意見や提案に柔軟に対応することができましたか?
- 新しいアイデアや方法を受け入れる際、どのようなアプローチを取りましたか?
リーダーシップに関する質問
従業員がチームをリードする場面での行動や、ほかのメンバーからどうのように信頼を得ているかを確認する質問です。
- チームのなかでリーダーシップを取ることがあった場合、どのようなスタイルでリードしますか?
- チームメンバーからの信頼を得るためにどのような取り組みをしていますか?
自己認識に関する質問
従業員自身がみずからの協調性についてどのように認識しているか、または自己改善のための取り組みがあるかを確認する質問です。
- あなた自身の協調性の強みと改善点は何だと感じますか?
- 最近、自分の協調性を高めるために学んだことや取り組んだことはありますか?
まとめ|従業員の協調性を可視化するには?
協調性は、チームワークや成果に直結する重要な要素です。協調性を正確に評価・育成するには、感覚的な判断ではなく、明確な指標と仕組みが必要です。
タレントマネジメントシステムを活用すれば、協調性を含む人材の能力データを集約して可視化し、、組織全体の傾向や推移を分析しやすくなります。これにより、プロジェクトへの適切な人材配置や、協調性が高いメンバーをアサインするといった判断が可能です。
また、協調性が不足している従業員に対しては、研修やOJTなどの育成計画を立てやすくなります。データ活用によって、組織全体の協調性向上と人材活用の最適化が実現できるでしょう。
従業員の能力を可視化するタレントマネジメントシステム
従業員の協調性レベルを見える化し、人材配置や育成に活かしていきたいなら、タレントマネジメントシステムのOne人事[タレントマネジメント]がおすすめです。
One人事[タレントマネジメント]は、人材データを一元管理して可視化することで、適材適所の配置や成長支援が直感的に行える設計となっています。現場責任者や経営層の立場に応じた機能も充実し、配置の判断や育成計画、評価の公平性確保にも活用が可能です。
自社の人事労務課題に応じて、必要な機能だけを選んでスモールスタートできますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトではサービス紹介資料はもちろん、人材管理に関するお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。また、無料トライアルもできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |