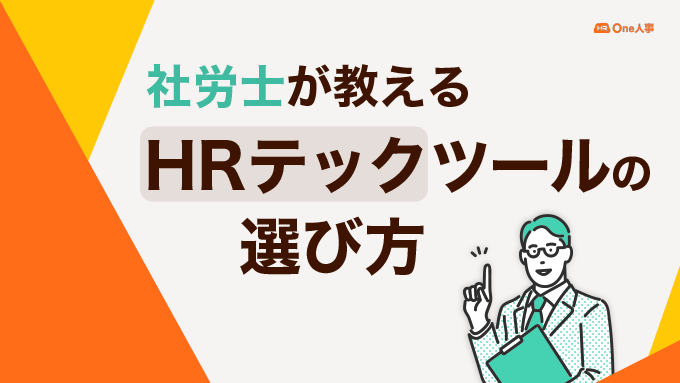人事はAI活用でどう変わる? 活用事例やメリット・デメリットと注意点も紹介
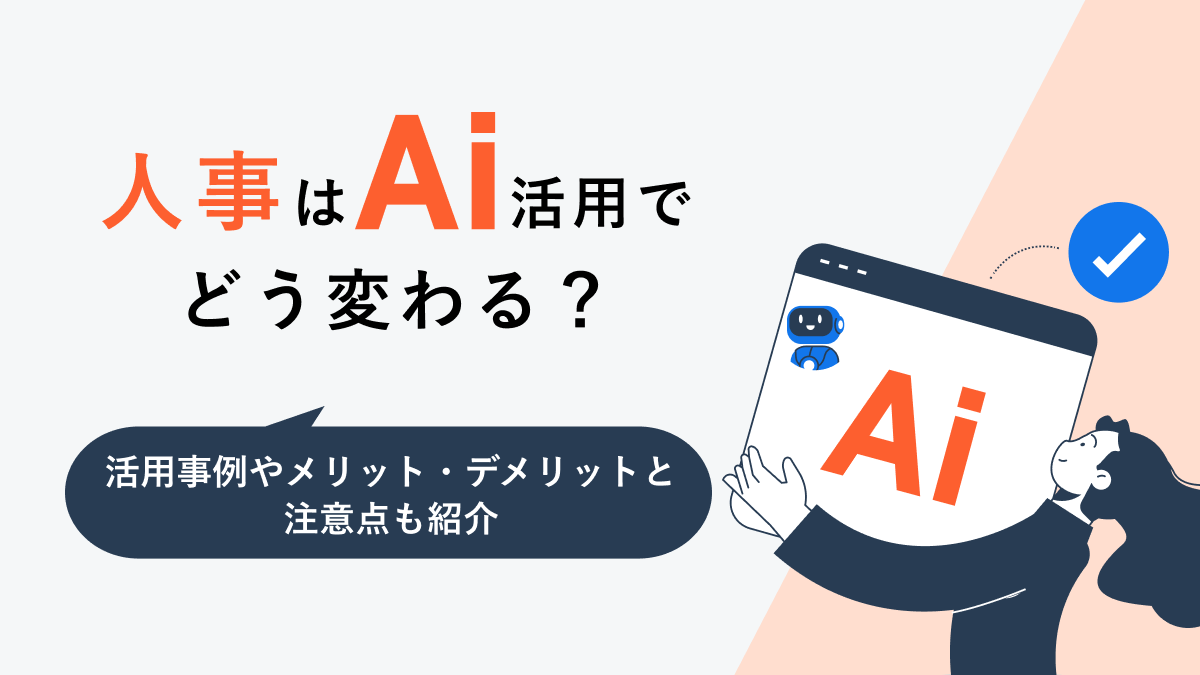
人事のAI活用は、評価の属人化を防ぎ、業務の負担を軽減する手段として注目されています。
人事担当者がAIを活用することで、人事評価のあり方を根本から変革すると期待されていますが、導入は慎重に検討しなければなりません。
本記事では、人事評価にAIを活用するメリットやリスク、先進企業の事例についてわかりやすく解説します。
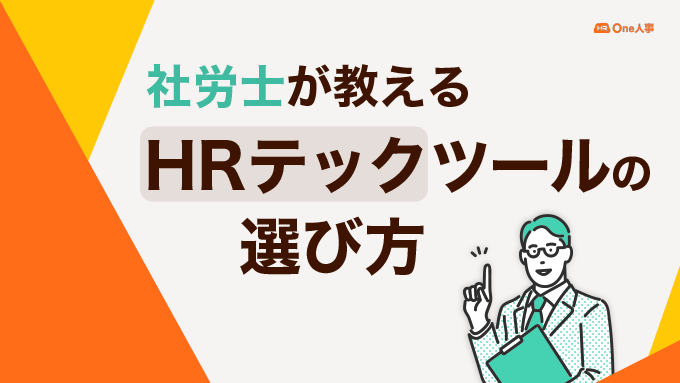
 目次[表示]
目次[表示]
人事はAI活用でどう変わる?
人事のAI活用は、業務のあり方を大きく変えつつあります。近年、防衛省が人事評価にAIを導入したことが注目され、国内でもAI活用が一気に広がりました。
AIは、繰り返し行う定型業務を自動化し、勤怠管理や書類作成、データ入力などの負担を軽減します。結果として、人事担当者は空いた時間を創造的な仕事や問題解決にあてられるようになりました。
さらに、AIは人材育成のパーソナライズにも力を発揮します。従業員一人ひとりの能力や志向に応じた学習コンテンツの提案や、個別の成長支援が可能になりつつあります。
人事のAI活用による変化は、戦略的思考やデータ分析力といった新たなスキルが求められるきっかけにもなるでしょう。
すでに日本企業でも、採用選考の効率化や離職リスクの予測、適材適所の人材配置などでAI活用が進み、成果を上げる事例が増えています。
人事にAIを取り入れることで、人事部門は「管理の役割」から「組織を支える戦略的パートナー」へと進化しつつあります。
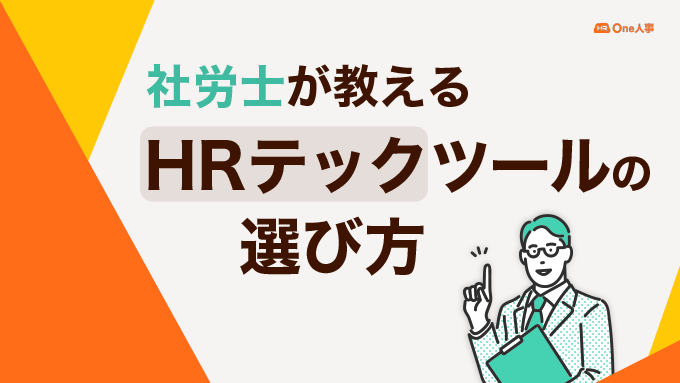
AIを活用できる人事業務
人事の現場では、採用候補者の選考や育成計画の立案など、人による多くの作業や判断が必要とされてきました。
今ではAIの進化によって、業務の一部を自動化・効率化できるようになっています。
ここからは、人事業務の各領域でAIがどのように活用されているのか、具体例を紹介します。
人事評価での活用例
人事AIの活用は、人事評価の透明性と公平性を高める手段として注目されています。評価業務は属人化しやすく、従業員の不満や疑念を招きやすい領域です。AIは過去のデータを学習し、客観的な基準で評価を支援します。
たとえば、評価シートの集計や分析を短時間で行い、部門ごとの評価傾向や、優秀な社員に共通する行動特性を明らかにします。また、評価基準が明確になることで、社員も納得しやすくなります。
AIが人事評価バイアスを検出し補正する機能もあり、公平性を支えるでしょう。評価の質を高めたい方にとって、人事におけるAIの導入は一つの選択肢といえます。
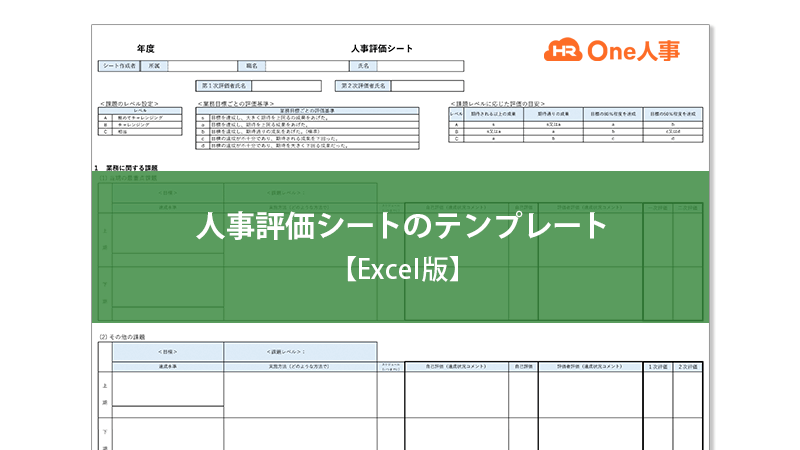
採用での活用例
人事AIの活用は、採用活動の質とスピードを同時に高めています。
たとえば、過去の採用データをAIが分析し、魅力的な求人内容を自動で作成することが可能です。
また、動画面接評価をAIに任せることで、選考にかかる時間を約70%削減した企業もあります。
履歴書の読み取りや面接日程の調整といった作業も自動化できるため、担当者は応募者との対話に専念できます。
「応募者対応に追われて戦略に手が回らない」と感じる方にとって、AIは人事採用の可能性を広げるでしょう。
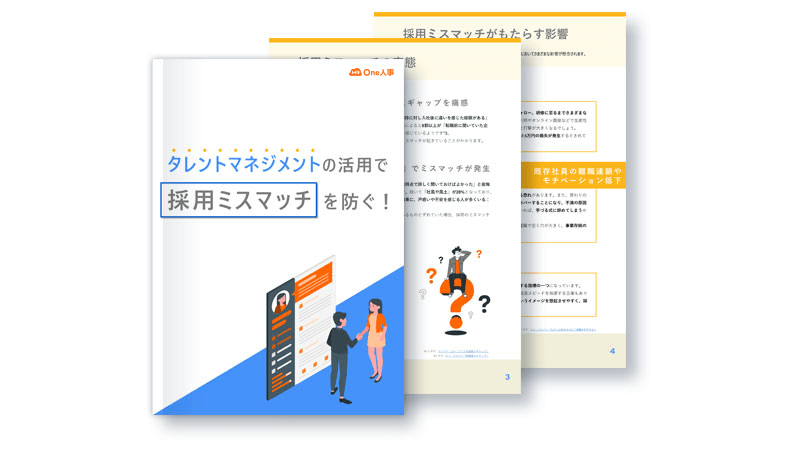
人材育成での活用例
人事AIは、従業員一人ひとりの特性にあわせた育成プランを提案できます。
従業員のスキルや実績を総合的に分析し、最適な研修や学習内容を自動で用意する仕組みです。
キャリアパスの設計も、AIが必要な情報を整理し提案を支援します。過去の業績データをもとに、将来のキャリアパスを提示し、必要なスキルや目標を明確にします。
本人が「何を伸ばせばいいのかわからない」という不安を和らげ、企業として計画的なスキルアップを後押しできるでしょう。
人事部門が個人の成長に伴走するうえで、AIは有用な支援ツールとなります。
社内問い合わせ対応での活用例
人事AIは、社内問い合わせの対応にも活用が進んでいます。
勤怠や給与、福利厚生など、繰り返し寄せられる質問に、AIチャットボットが24時間対応が可能です。
FAQの自動生成やデータベース化もAIが活用できる場合があります。
社内問い合わせ対応へのAI活用により、対応の標準化と効率化が進み、戦略的な業務に集中できるようになります。
「ほかの仕事が進まない」という悩みを持つ人事担当者には、AI導入が大きな助けになるはずです。
タレントマネジメントでの活用例
AIはタレントマネジメントへの活用も広がっています。
従業員のスキルや特性を分析し、評価や適材適所の配置を支援するのが主なAIの活用例です。
さらに、エンゲージメントの状態や退職リスクを可視化することで、個別フォローや職場の改善につなげることが可能です。
人材をどう活かすかに悩む人事担当者にとって、AIは人材管理において、データドリブンな判断を後押しするツールといえるでしょう。

人事分野でのAI活用事例
人事業務へのAI導入は、採用や評価の質を高めたり、従業員エンゲージメントを強化したりと、組織にさまざまな価値をもたらしています。
しかし「本当に成果が出るのだろうか」「自社でも活用できるのだろうか」と感じる方もいるかもしれません。
先進的な企業がどのように人事領域でAIを取り入れ、どんな変化を実現しているのかは気になるところです。
ここからは、人事AIを活用して具体的な成果を上げている企業の事例を紹介します。
取り組みの背景や工夫のポイントを知ることで、導入を検討する際のヒントにしてください。
【ソフトバンク株式会社】新卒採用選考での動画面接の評価を簡略化
人事AIの活用は、採用選考の公平性や効率を高めています。
ソフトバンクは新卒採用に動画面接評価を導入し、AIシステムを活用しました。
過去の動画データとベテラン担当者の評価を学習したAIが、応募者の特性を客観的に分析します。
結果として、選考時間を短縮しつつ、企業の求める人物像にあう候補を的確に抽出できるようになりました。
移動や調整の負担も軽減し、学生・企業双方にメリットが生まれています。
評価の質を保ちながら効率化を進めたい人事担当者にとって、参考になる事例です。
参考:『新卒採用選考における動画面接の評価にAIシステムを導入』ソフトバンク株式会社
【NECソリューションイノベータ】AIによる人事管理データの分析を実現
人事AIの活用事例として、NECソリューションイノベータの取り組みも注目されています。
同社は人事管理データをAIで分析し、業務適性やスキルの傾向を数値化しました。
モデル社員のデータを学習させることで、後任候補の適性や配置を客観的に判断するクラウドを提供しています。
また、研修効果の統計分析や離職リスクの予測にも活用し、人的資源の最適化を推進。
膨大なデータを活かし、判断の精度を高めたい企業には有効なアプローチといえるでしょう。
参考:『NECソリューションイノベータ、「NEC HR Tech クラウド」の最新版を提供開始』NECソリューションイノベータ株式会社
【サイバーエージェント】新卒配属の配属先をマッチングシステムで最適化
人事AIは新卒社員の配属にも影響を与えています。サイバーエージェントは、独自のマッチングシステム「miCAel(ミカエル)」を導入し、適性や希望をもとに配属先を提案しています。
この仕組みはAIに全面的に意思決定を任せるのではなく、人事担当者と面談を重ねながら最終決定するのが特徴です。
データを活用しつつ、人の視点を大切にする運用が社員の納得感を高めています。AIと人の判断を組み合わせることで、配属の精度を上げたい場合に参考になるでしょう。
参考:『サイバー、新卒配属にAI活用 170人×100部署マッチング』日本経済新聞
【IBM】AIアシスタントを活用して採用枠を約3割削減に成功
人事AIの活用を先進的に進めるIBMでは、社内デジタルアシスタントを開発し、人事業務の自動化を推進しています。
約100の業務プロセスをAIで効率化し、非顧客対応部門の業務負担を大幅に削減しました。将来的に約3割をAIに置き換えると発表しています。
一方で、従業員の評価や組織開発といった分野は、引き続き人間が担う方針を採用しています。
AIが強みを発揮する領域と、人の判断が必要な領域を分ける取り組みは、導入を検討する企業にとってヒントとなるでしょう。
参考:『IBMはAIが可能な職種の採用を一時停止するとCEOのアルヴィンド・クリシュナ氏が発表』Bloomberg
参考:『役割の再編 | IBM、AI導入で人事業務の94%を自動化』HR Grapevine
【セプテーニ】新卒採用でAIチャットボットやVRアプリを導入
人事AIの活用は、採用活動の体験価値を高める取り組みにも広がっています。
インターネット広告やメディアコンテンツを手掛けるセプテーニ・ホールディングスは、新卒採用でAIチャットボットやVRアプリを導入しました。
とくに2019年度には、内々定者向けに自宅で1日就業体験ができる『VR Internship』を提供。
業務内容や働く環境をリアルに知る機会をつくりました。
同社は『人的資産研究所』を設置し、インターン経験が入社後の活躍に影響することをデータで確認しています。
こうした仕組みは、応募者に安心感を届けるとともに、企業理解を深める手助けになります。
「採用で会社の魅力をうまく伝えられない」と感じる人事担当者にとって、参考にしたい活用例です。
参考:『プレスリリース(2018.05.09)』株式会社セプテーニ・ホールディングス
【株式会社松屋フーズホールディングス】AIの面接サービスを導入
人事AIの活用は、昇格試験にも広がっています。
松屋フーズでは、AI面接サービス『SHaiN』を導入し、店長昇格試験をオンライン化しました。
AIが約300とおりの質問を選び、対話を通じて評価を行います。
面接会場やスケジュール調整の負担をなくし、公平で一貫した評価基準を実現。
候補者の移動時間やコストも削減され、受検者の負担も軽減しています。
人事評価の精度と効率を同時に高めたい企業にとって、参考にできる活用例です。
参考:『採用活動だけではない。昇格試験の課題も解決したSHaiNの価値』SHaiN
人事にAIを導入する5つのメリット
人事にAIを取り入れることで、現場はどう変わるのでしょうか。
「人がやるべきこととAIに任せること、線引きはどこにあるのか」「導入した企業は実際に何を得ているのか」と考える方もいるはずです。
ここからは、人事AIの活用がもたらす具体的な5つのメリットを紹介します。
- 業務負担が軽減される
- 評価の公平性が高まる
- コスト削減につながる
- データを活用して意思決定の精度を高められる
- 従業員のパフォーマンス向上につながる
どのメリットも、人事部門の可能性を広げるヒントになるでしょう。
業務負担が軽減される
人事AIの導入は、人事評価にかかる業務負担を大幅に軽減します。従来は評価シートの配付や集計、確認に多くの時間が必要でした。とくに評価シートの作成と回収は、担当者の負担が大きい作業です。
AIはタスクを自動化し、迅速かつ正確に処理できます。
たとえば、評価データをまとめて分析し、複数の職種にあわせて評価内容を一元管理することが可能です。
人事担当者は手間のかかる定型業務から解放され、戦略的な仕事や従業員とのコミュニケーションに集中しやすくなります。
評価の公平性が高まる
人事業務にAIを活用すると、評価の公平性を高める効果が期待できます。従来の方法では人の主観やバイアスが評価に影響するのは避けられない課題でした。
AIは設定した評価基準に基づき、一貫した判断を行います。
たとえば、社員の業績やスキルデータを客観的に評価し、評価者ごとのばらつきを補正します。
データによる客観的な評価が取り入れられると、従業員が「自分の努力が正しく評価されている」という納得感が生まれやすくなります。
結果的に従業員からの信頼感やモチベーションが高まり、組織全体の健全な成長にもつながるでしょう。
コスト削減につながる
人事AIの導入は、コスト面でも多くのメリットが考えられます。
人事評価にかかわる人件費や紙の印刷コストが減るだけでなく、作業時間の短縮も大きな効果です。
とくに大企業では、評価シートやデータ処理の自動化による削減効果が明らかです。
さらに、適正な評価が社員の定着率を高め、採用コストを抑える好循環も生まれるでしょう。
AIが過去の人事採用データを分析し、コスト削減のヒントを提示することも可能です。
人とAIの知見を組みあわせて、長期的に無駄を減らせるはずです。
データを活用して意思決定の精度を高められる
AIは、大量の人事データを統計的に分析するのが得意です。過去の業績や評価を整理し、将来の意思決定に役立つヒントを見つけ出せます。
たとえば、高い成果を出す社員に共通するスキルや行動を明らかにし、採用や育成の基準づくりに活かすことが可能です。
また、退職リスクの高い従業員やリーダー候補を見つけるのも、AIなら短時間で対応できます。
勘や経験に頼っていた人事の判断も、データに基づいた客観的なものに変わっていくでしょう。
従業員のパフォーマンス向上につながる
人事でAIを活用すると、従業員一人ひとりのパフォーマンスを高められます。
AIは膨大な評価データをもとに、それぞれの強みや課題を可視化するため、どの方向にスキルを伸ばせば成果につながるかがはっきりします。
たとえば、成果を上げている人の行動パターンや成功事例を全社員に共有することが可能です。
データは人事施策の判断材料となり、適材適所の人材配置や個別の教育プログラムの設計にも役立ちます。
また、明確なデータに基づく異動や育成は、結果として組織全体の学びが加速し、パフォーマンスの底上げが期待できるでしょう。生産性の向上にもつながります。
人事にAIを導入する3つのデメリット
人事業務にAIを導入することで多くのメリットが得られる一方で、無視できない課題やデメリットもあります。
ここでは、人事業務にAIを導入する際に注意したい3つのデメリットを解説します。
- 業務がブラックボックス化する
- 従業員から反発されるおそれがある
- 新たな導入コストと運用負担が発生する
導入を進める前に、リスクを整理し、適切な対策を考えるヒントにしてください。
業務がブラックボックス化する
AIによる人事評価の課題の一つが、評価プロセスのブラックボックス化です。
AIは膨大なデータをもとに評価結果を導きますが、判断の根拠を説明しきれないケースも少なくありません。
そのため、従業員が評価結果に疑問を持ったとき、十分な根拠を示せず、納得を得にくい場合があります。
さらに、AIは過去の評価データを学習して判断するため、学習データに偏りがあると評価結果も偏ってしまうでしょう。
AIの課題を防ぐには、できるだけ説明可能なAIを選び、最終判断を人が確認するといった対策が重要です。
従業員から反発されるおそれがある
AIを活用した人事は、従業員に心理的な抵抗感を与えることがあります。
昇進や昇給など、個人のキャリアに影響する決定にAIがかかわると、不信感や不安を抱く従業員は少なくありません。
実際に、評価の理由を質問しても十分に説明できない場合、納得感を損ねるおそれがあります。
反発を抑えるためには、AIは補助的な役割であり、最終判断は人が行うことを明確に伝え、導入前から社員との対話を重ねることが大切です。
新たな導入コストと運用負担が発生する
AIを人事評価に導入すると、新たなコストや運用負担が発生します。
初期費用としてソフトウェアのライセンス料や開発コストが発生し、クラウド型サービスでも利用人数に応じた月額料金や設定費が必要です。
運用後も、データの更新やモデルの再学習、精度維持のためのメンテナンスが欠かせません。
評価の正確性はデータの質に左右されるため、常に最新情報を管理する必要があります。
また、評価者や従業員への使い方の教育やルール整備も重要です。
負担を抑えるには、小規模な試験導入から始め、費用対効果を慎重に検討することが現実的な進め方でしょう。
人事にAIツールを導入する際の注意点
人事業務にAIを導入することで、業務効率は上がる一方で、「本当に運用できるだろうか」「従業員の反発を抑えられるだろうか」と不安を感じる方もいるはずです。
ここからは、人事にAIツールを導入する際におさえておきたい3つの注意点を解説します。
- AIによる明確な評価基準を従業員に周知する
- 最終的な判断はAIではなく人間が行う
- 自社の環境に適したAIツールを選定する
導入に失敗しないために参考にしてください。
AIによる明確な評価基準を従業員に周知する
AIを活用した人事評価を成功させるには、評価基準を従業員にわかりやすく伝えることがポイントです。
評価の仕組みが不透明だと「自分は正しく評価されているのか」と不安を感じ、モチベーションが下がる原因になります。
そのため、AIがどのデータをもとに評価を算出しているのか、どのような基準でスコアを決定しているのかできるだけ開示しましょう。
業績の達成度やプロジェクトへの貢献度、スキルの習得状況など、評価に使う主な指標を共有することが大切です。
事前に評価プロセスを説明し、導入後も基準を定期的に見直して周知することで、納得感と信頼を維持できます。
最終的な判断はAIではなく人間が行う
AIを人事評価に取り入れる際の大前提は、AIはあくまでも支援ツールという認識を持つことです。
AIが示す結果は「忖度」もなければ「倫理観」もなく、確率に基づくものです。必ずしも全て正しいとは限りません。だからこそ最終判断は人間が行う必要があります。
たとえば、育児や介護など個人的な事情、数字にあらわれにくいチームへの貢献などはAIだけでは評価しきれません。
評価結果をそのまま採用せず、バイアスや不正確さがないか人がレビューすることが重要です。納得感を得るためにも、AIと人の適切な役割分担を明確にしましょう。
自社の環境に適したAIツールを選定する
AIを活用した人事システムには多くの種類があり、自社の制度や運用にあったものを選ぶことがポイントです。
必要な機能や精度、過去の実績を事前に把握しましょう。
たとえば、評価コメントの分析や異動の提案など、活用シーンにあった機能が搭載されているかを見極めます。
操作性や使いやすさも重要で、導入前にトライアルを行うと安心です。
比較検討を重ね、自社の規模や業種に最適なツールを選びましょう。
AI活用で人事はなくなるのか?
AIの急速な進化によって、人事業務の多くが自動化される可能性が高まっています。ルーティンワークや大量のデータ処理などは、すでにAIで効率化が進んでいます。
このままでは、「人事部門そのものが将来なくなるのでは」と心配されている方もいるかもしれません。
たしかにAIは人事を大きく変えています。採用プロセスの効率化、データ分析による高度な意思決定、従業員一人ひとりに合わせた学習機会の提供など、活用の幅は広がりました。
ただし、AIがすべての人事業務を代替できるわけではありません。
対話や感情の理解、倫理的な判断といった、人間にしかできない大事な人事領域も残っています。社内コミュニケーションを円滑にするには、人事担当者の役割が欠かせません。
人事業務の未来は「AIとの共存」にあります。AIには定型業務やデータ分析を任せ、人間は創造的で戦略的な判断に集中する役割分担が広がっていくでしょう。
大切なのは、AIを上手に活用しながら、人にしか生み出せない価値を発揮することです。
まとめ|人事のAI活用で業務最適化
人事業務へのAI導入は、定型業務の効率化にとどまらず、採用や評価、育成など人材マネジメントの質を大きく高める力を持っています。AIがデータに基づく公平な評価や離職リスクの予測を支える一方で、最終的な意思決定や人間らしい配慮は人事担当者の役割です。
今後の人事には、テクノロジーを理解し活用する力と、戦略的な視点が求められます。AIと人間が互いの強みを補完し合いながら、組織と従業員の成長を後押しする「人事の進化」が始まっています。