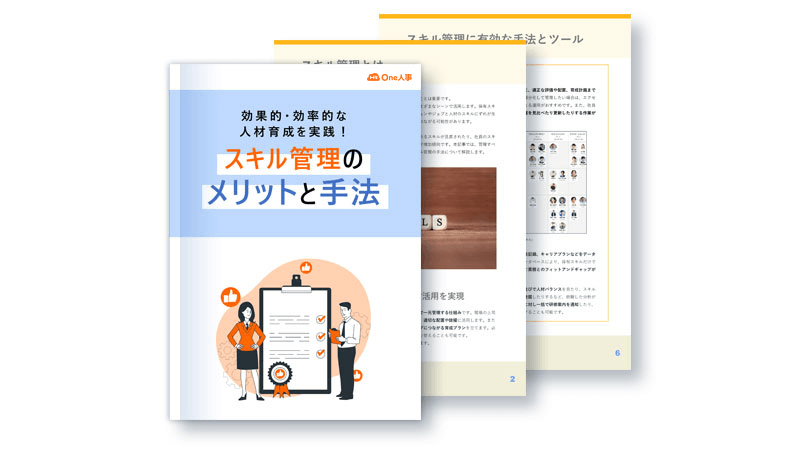自己肯定感が低い原因 【今から始められる】高める方法や低い人の特徴も解説

自己肯定感とは本来の自分を受け入れている感覚です。自己肯定感が低い状態では、周囲が過剰に気になったり、自分に否定的になったりして、人間関係の面でデメリットが生じがちです。
そこで本記事では、自己肯定感が低い人の特徴や原因、自己肯定感の低さが招く影響を解説し、高めるための効果的な方法やメリットについてもご紹介します。自己肯定感の低さが気になる人は、ぜひお役立てください。
 目次[表示]
目次[表示]
そもそも自己肯定感とは?
自己肯定感とは、他人と比べず、ありのままの自分を肯定して認めることです。たとえば「〇〇ができるから、自分には価値がある」といった根拠がなくても、自分に存在価値があることを感じられている状態です。
自己肯定感が高いと、周囲を気にせず主体的な行動ができたり、無条件に自信を持てたりします。一方、自己肯定感が低いと、自分を認められない、他人と比較して自分はダメだと落ち込みやすいなど、生きづらさを感じやすいでしょう。
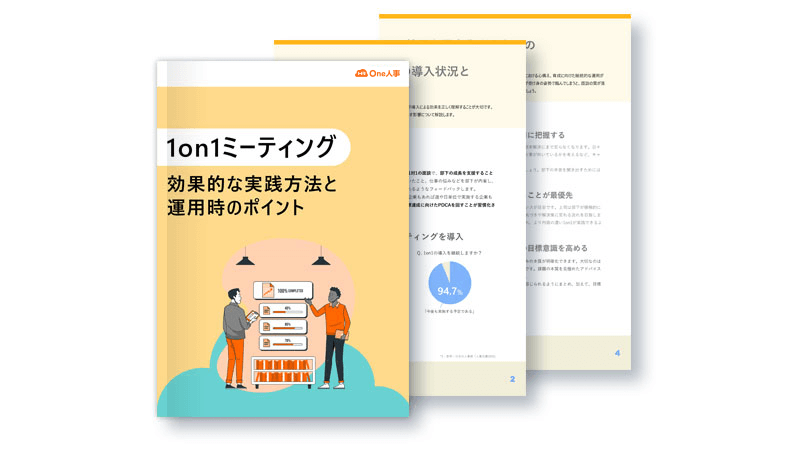
自己肯定感が低い人の特徴4つ
自己肯定感が低い人に見られる4つの特徴を紹介します。
他人と比較してしまう
他人と自分を比べることは、ときにはいい影響を与えます。たとえば「あの人みたいになりたい」と思うことが原動力につながったり、人の失敗から反面教師としたりすることもできるでしょう。他人を観察し、行動や成果について考えることは、自分の成長に役立つでしょう。
しかし、自己肯定感が低い人は「この人は幸せそうなのに自分は幸せではない」「この人は容姿や能力が優れているのに自分は劣っている」というように、他人と比較して自分を卑下してしまうケースがあります。
とくに、他人の成功や華やかな側面だけに焦点を当て、自分の欠点や失敗ばかりに目を向けると、自己肯定感が著しく低下します。このような比較は、みずからの能力を正しく評価することを妨げ、成長や幸福感に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
完璧主義で失敗を恐れる
完璧主義で失敗を恐れるのも、自己肯定感が低い人によく見られる特徴の一つです。これは、自分の弱みを受け入れられないという心理状態から生じます。
完璧主義者は、ものごとがうまくいかないときやミスをしたとき、自分が傷つかないように自己防衛してしまいます。その結果、挑戦すること自体を恐れてしまい、やる前にあきらめるケースが増えるでしょう。
また、これらの繰り返しによって、自分に対する信頼と自尊心の喪失を招き、さらに自己肯定感を低下させる負の連鎖を生み出します。
自分でものごとを決められない
自己肯定感が低い人は、自分の選択に自信を持てず、ものごとを決められない傾向があります。何かを決めるという行為は、決断に対する自信と、それにともなう責任を受け入れる覚悟が必要です。自己肯定感が低い人には、このような自信や覚悟が欠けているため、自分で決断しにくいのです。
そのため、普段からも家族や友人など周囲の人の意見を優先することが多いでしょう。
何をしてもダメだと感じる
「何をしてもダメだ」と感じるのも、自己肯定感が低い人に見られる一般的な特徴です。
このような感覚は、過去のうまくいかなかった記憶が強かったり否定された経験が多かったりする人に顕著にあらわれます。ネガティブな記憶が心に強く残り「自分にはよいところがない」「何をやってもうまくいかない」といった思い込みにつながります。
また、新しいことに挑戦して失敗したときは「やはりダメだったか」という安心感に似た落胆の感情をおぼえ「挑戦しなければよかった」と後悔してしまうのです。
自己肯定感が低くなる原因7つ
自己肯定感が低くなるのには原因があります。主な7つの原因を取り上げて解説します。
親が過保護だった
親の過保護は、自己肯定感が低くなる原因の一つです。子どもに対してよかれと思って親が何でもやりすぎると、子どもは自分で決める機会を失ってしまいます。
たとえば、親が「あなたは私がいないと何もできない」「私の言ったことをやっていればいい」などと言うことで、子どもは自分で決められなくなり、自分の意思決定に自信が持てなくなります。
子どもの自己肯定感を高めるためには、親が子どもの考えや意見をできるだけ尊重し、適切な場面で子ども自身に意思決定をさせることが重要です。
過去にいじめなどのトラウマがある
いじめのようなトラウマは、自己肯定感を低下させる重要な原因の一つです。兄弟や友達と比べられて否定されたり、学校で仲間外れにされたりした経験は、自己肯定感に深刻な影響をおよぼします。
これらの経験は、自分には価値がないからこのような扱いを受けたという思考に陥る原因となり、その結果、自分自身を否定的に見る傾向を強めてしまいます。
また、自己肯定感の低下だけでなく、自己信頼の喪失にもつながり、将来的にさまざまな心理的な問題を引き起こす原因にもなりかねません。
褒められる機会が少なかった
子ども時代に両親や周りの大人から褒められていたかどうかは、自己肯定感の形成に大きな影響を与えるとされています。褒められる機会が少ないと、子どもは「自分には価値がない」と感じることが多くなります。
とくに、褒められるのに何か意味が必要だったり、無関心な態度を取られ続けたりされると「自分には価値がない」「〇〇ができないと自分には存在価値がない」という思い込みに陥りやすくなるでしょう。
コンプレックスを抱えている
コンプレックスを抱えていることも、自己肯定感が低くなる原因です。コンプレックスには、次のようなものがあります。
- 容姿
- 年収
- 学歴
- 家庭環境
幼少期に大人に甘えられなかった
自己肯定感は、幼少期に大人に甘えられなかったことで低くなるケースもあります。家庭環境において親が多忙であったり、下の兄弟にばかり手をかけていたりする場合、子どもは満足に愛情を受けられないでしょう。
このような状況は、長男や長女に多く見られ「役に立たなければ自分に存在価値はない」と考えてしまい、自分に対して否定的です。
両親の仲がよくなかった
両親の仲がよくないなど、家族間でのコミュニケーション不足や愛情が受けられないことが原因になる場合も多いでしょう。
子どもは、両親のけんかを目の当たりにすると、不仲が自分のせいだと考えるようです。その状態が長く続くほど自分を責めてしまい、自己嫌悪や自信のなさにつながるでしょう。
自分を謙遜しすぎる
日本人の国民性として、謙虚さや謙遜をよいこととする慣わしがあります。そのため、本来はよいことでも、自信満々な行動や言動をよくないと捉えがちです。相手が不快に思わないよう、自分を謙遜しすぎてしまい、それが自己肯定感の低さの原因につながっています。
自己肯定感の低さが招く影響
自己肯定感の低さが招く影響を5つ取り上げて、それぞれ解説します。
自分の好きなように生きられない
自己肯定感は、自分の望む人生を送るために重要な要素です。自己肯定感が低いと、何かに依存したり、他人の評価にとらわれたりすることが多くなります。自分の意思で自由に行動しづらくなり、好きなように生きられないといった影響が出てしまいます。
チャレンジできない
自己肯定感が低いと、ネガティブな考えや失敗を恐れる気持ちに支配されて、挑戦的な決断をためらうようになります。また、チャレンジして失敗した場合、それを受け入れることができず、新しい世界に飛び込むのをやめてしまうケースも多いでしょう。
人間関係を上手に築けない
自己肯定感が低い人は自分の考えに自信を持てず、意見を述べにくいでしょう。また、後輩やほかの人へのアドバイスや指示を出すことが苦手です。
さらに、周りの人の目を過度に気にしてしまい、自分から人とコミュニケーションを取ったり、積極的に関係を深めたりすることが難しい傾向にあります。そのため、人間関係を上手に築けず、孤立を感じやすくなる可能性があります。
周囲の評価が得られにくい
自己肯定感が低い人は、自主的な行動やアイデアの提示について苦手意識があり、指示されたことしか行わない傾向が見られます。
また、積極的に行動しないことで思うような成果が得られず「自分は何をしてもうまくいかない」というネガティブな思考に陥りがちです。このような消極的な態度や思考によって、周囲の評価が得られにくくなります。
精神的に悪影響をおよぼす
自己肯定感が低いと、ストレスや自己嫌悪感など精神的に悪影響をおよぼす可能性があり、精神疾患につながるリスクが高まります。たとえば、パニック障害やうつ病、不安障害などが発症しやすいため、注意が必要です。
自己肯定感を高めるのに効果的な方法
自己肯定感を高める、効果的な方法を9つご紹介します。
自分自身を見つめ直す
自分は自己肯定感が低いことを理解し、認めるとよいでしょう。そのためには、自分のよいところも悪いところもひとまず受け入れ、紙に書くなど言語化することが有用です。自分を変えるには、自己理解から始めてみることをおすすめします。
自己肯定感が低くなった原因を把握する
過去のトラウマやコンプレックス、傷ついた経験などは、誰でも思い出したくないものです。しかしこれらについて振り返り、自分と向き合うことが大切です。思い出すことによって、自分が苦手なものごとを整理できるようになるでしょう。
自分の長所や成功体験を振り返る
自分の長所や成功体験を振り返ると、自己肯定感が上がります。「大したことない」などと人と比べがちですが、小さなことでも何でもよいので思い出してみるとよいでしょう。今までふたをしていただけで、自分にも長所があることに気づけるはずです。
小さな成功体験を積み重ねる
自己肯定感が高い人が、特別大きなことを成し遂げてきたわけではありません。小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感が高まります。
日常的にしていることでも構わないので、まずは目標を決めましょう。成功体験をメモに残すなど、自分の成果が積み重なっていることを意識することがポイントです。
他人に「してもらったこと」を重視する
他人が自分に対して「してくれなかったこと」を考えるのではなく「してくれたこと」に着目してみるのもおすすめの方法です。
自己肯定感が低い人は悪い方向に考えがちですが「してもらった」ことを意識すると、自分が他人に支えられ、認められていると感じやすくなります。
自分を応援してくれる人のそばにいる
自分を否定したり傷つけたりする人の近くにいると、どんどん自己嫌悪に陥るものです。そのため、自分を認めてくれる、応援してくれる人のそばにいるとよいでしょう。応援してくれる人がいない場合は、自分によい影響を与えてくれる人の近くにいるのがおすすめです。
感情を発散させる
ネガティブな感情は悪いものと認識されがちですが、誰しも抱くものです。大切なのは、このような感情を自分の中にため込まず、吐き出せているかという点です。信頼できる人やカウンセラーなどに話し、ときには感情を発散させる必要があります。
発想の転換をしてみる
自己肯定感を高める方法として、発想の転換をしてみることもおすすめです。たとえば「どうせ自分にはできない」から「どうすればできるようになるか」に、「将来への不安感に駆られる」を「今から備えられる、早く気づいてよかった」に変えてみましょう。
「〜しなければ」や「〜するべきだ」と考えると、目標を達成できなかったときに「失敗してしまった」と思いやすいです。「〜した方がいい」「〜してみよう」という考え方にシフトするとよいでしょう。すぐに考え方の転換はできませんが、気づいたときに意識して習慣化してみることが大切です。
自分を認めて信頼する
自分を認めて信頼しましょう。このとき、よい部分だけでなく、よくない部分も受け入れることがポイントです。
自己肯定感を高めるメリット4つ
自己肯定感を高めることで得られるメリットを4つ取り上げて解説します。
人に優しくなれる
自己肯定感が高まると自分の心に余裕を持てるため、人に気配りできるようです。幸せそうな人を、自分とは別のこととして捉えられると、その様子を微笑ましく思えるでしょう。困っている人を助けようと思う気持ちも生まれやすくなります。
嫌なことがあっても気分を切り替えられる
誰しもミスをすると落ち込むものです。しかし、自己肯定感が高いと、失敗しても次に活かそうと考え、ほかのことをして気を紛らわし、深く考えすぎずにすむでしょう。
他人に振り回されない
自分の意思に基づいて意思決定をできるようになるのも、自己肯定感を高めるメリットの一つです。周りの意見と違っても、自分の意見を尊重して「私はこう思うんだけど」と率直に意見を主張できます。
人間関係を築きやすくなる
自己肯定感が高いと自分に自信が持てるので、人間関係を築きやすくなります。積極的に人に声をかけたり、気楽にコミュニケーションを取れたりするでしょう。
自己肯定感の低さを克服するには自分を認めることから
自己肯定感とはありのままの自分を肯定し認めることで、日本では低い人が多いとされています。自己肯定感が低い原因は多岐にわたり、生育環境や幼少期の経験が影響していると考えられています。
自己肯定感が低いと、自分の好きなように生きられない、チャレンジできないなどデメリットが多く指摘されています。自己肯定感を高めるには自分を認めてあげることが大切です。
自分自身を見つめ直したり、自己肯定感が低くなった原因を把握したりするなどの方法で高めていくとよいでしょう。