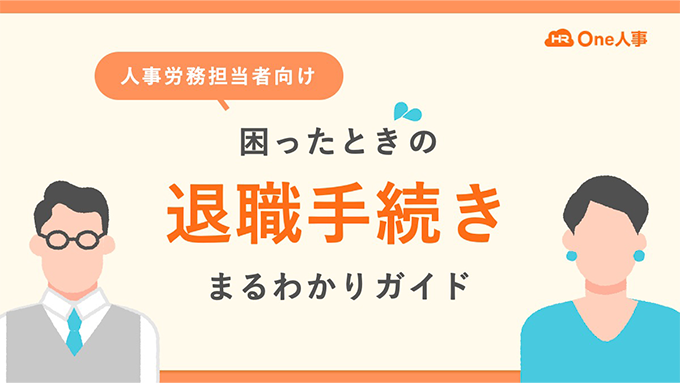退職証明書の書き方|項目と必要なケースも解説
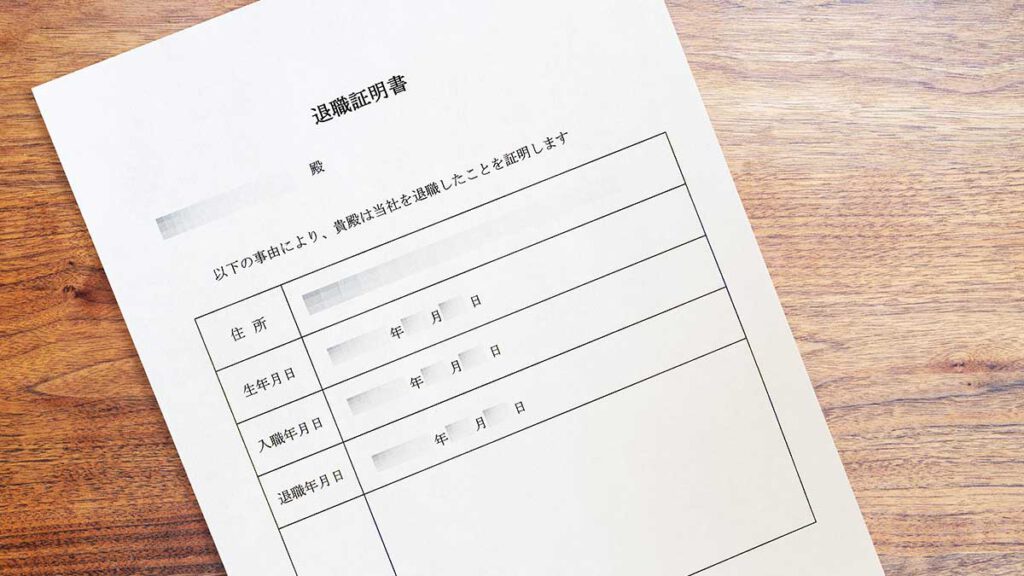
退職証明書は、文字のとおり「退職したこと」を証明する書類です。「退職証明書の書き方がわからない」「記載すべき項目が知りたい」と悩んでいる企業の人事労務担当者もいるのではないでしょうか。本記事では、退職証明書の書き方について具体例を交えながら解説します。発行が必要なケースや類似書類との違いなども紹介するので、ぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
退職証明書とは
退職証明書は、「証明書の発行を希望する人が、間違いなく会社を退職したこと」を証明する書類です。企業には、退職者からの希望に応じて退職証明書を発行する義務があります。退職証明書は以下の内容を証明できます。
- 複数の企業に属していないこと
- 前職の実務経験
- 前職の賃金
- 前職の役職
退職証明書は前職での経験や待遇を証明する書類です。そのため、多くは「転職活動で必要」という理由から発行を求められます。
退職証明書に書くべき事項
退職証明書に記載した方がよい内容は、主に以下の5種類です。
- 業務の種類
- 使用期間
- 賃金
- 退職理由
- その事業における地位
それぞれの項目について、詳しく解説します。
業務の種類
退職証明書に書くべき項目として、「業務の種類」が挙げられます。営業職や技術職など退職者が、会社で担当していた仕事内容を記載しましょう。経理と総務を兼務していた場合など業務内容が複数ある場合は、すべて記載します。
書き方は「わかりやすく」が基本ではあるものの、あまりに簡潔すぎると第三者に伝わりにくくなってしまいます。実務経験の証明として使用する可能性も考えて、できる限り詳細に書くのがおすすめです。なお、記載ルールを設けている企業もありますので事前に確認しておきましょう。
使用期間
退職証明書には、「使用期間」を記載しましょう。使用期間とは、従業員が会社に在籍していた期間です。書き方の決まりはありませんが、西暦または和暦で統一し、日付まで詳細に書くのがおすすめです。
| 書き方の例 | ||
|---|---|---|
| 入社年月日 | 2011年4月1日 | |
| 退職年月日 | 2022年3月1日 | |
| 使用期間 | 2011年4月1日~2022年3月1日 | |
賃金
在籍中の賃金も、退職証明書の代表的な項目です。一般的には、直近の月給や年収を記載します。会社によっては、「半年分の収入を記載する」などのルールを設けているところもあるでしょう。なお、金額は手取り額ではなく、社会保険料や税金が控除される前の金額を記載するのが一般的です。
退職理由
退職理由も、退職証明書の主な項目です。以下の中から該当する理由を選択します。
- 自己都合による退職
- 契約期間満了による退職
- 定年による退職
- 当社勧奨による退職
- ◯◯による解雇
- その他(上記に該当しない場合)
なお、退職者本人が希望しない場合は、退職証明書に退職理由を記載してはなりません。退職理由は転職活動にも大きな影響を及ぼすため、退職者に確認を取りましょう。とくに、退職理由が「解雇」の場合は注意が必要です。原則的には「◯◯による解雇」と理由を添えることになっていますが、退職者が拒否した場合は「解雇」とだけ記載します。
その事業における地位
業務の種類とともに、役職を記載する場合もあります。「営業部部長」「◯◯プロジェクトのリーダー」というように、最終的な役職を記載しましょう。なお、役職がない場合は、「一般職」と記載することで問題ありません。
退職証明書の役割
退職証明書は企業が自主的に発行すべき書類ではなく、公的書類でもありません。ただし、使用シーンは限られているものの、以下の重要な役割があります。
- 正式に退職したことを証明する失業保険の申請に使う
- 各種保険の重複加入を防ぐ
- 国民健康保険や国民年金の加入に必要
正式に退職したことを証明する
退職証明書の主な役割は、「正式に会社を退職したこと」の証明です。企業が「当該者が確かに退職したこと」を証明することで、従業員の二重在籍を防げるでしょう。退職したことの証明は、一定期間勤務していたことの証明でもあります。転職先に退職証明書を提出することで、「企業名」や「業務の種類」からこれまでの実績を裏づけることが可能です。
失業保険の申請に使う
通常、失業保険の申請には、離職票を用いるのが一般的です。「離職票を紛失してしまった」「発行が遅れている」などの理由がある場合は、退職証明書を代替書類として使用できる可能性があります。ただし、最終的な申請には離職票が必要です。あくまで「離職票が手もとにないが、できるだけ手続きを進めておきたい」という場合に活用できます。退職者から相談を受けた場合は、仮受付までしかできないことを伝えてあげると親切です。
各種保険の重複加入を防ぐ
退職証明書には、各種保険の重複加入を防ぐ役割もあります。「退職したこと=各種保険の資格を喪失したこと」を証明し、雇用保険や厚生年金保険、健康保険などの重複加入を防ぐことができるでしょう。
国民健康保険や国民年金の加入に必要
本来、国民健康保険や国民年金の加入手続きには離職票が必要です。しかし、なんらかの理由から離職票が手もとにない場合は、代わりに退職証明書を使うことが認められています。
退職証明書を発行する際の注意点
公的な書類ではないものの、退職証明書の発行は法的な決まりごとが設けられています。悪質な場合は罰則が科せられることもあるため、事前に把握しておきましょう。
発行は原則拒否できない
退職証明書の発行は、労働基準法に定められた企業の義務です。原則的に、企業は退職証明書の発行を拒否できません。正当な理由なく手続きを遅らせたり、発行を拒否したりした場合は、労働基準法第22条の違反となり、同法第120条1項により30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
申請期限は2年
退職証明書の発行義務は、退職から2年間と定められています。退職から2年を過ぎていれば、企業は退職証明書の発行を拒否できます。あくまで「拒否できる」だけのため、もちろん2年を超過したあとも発行は可能です。
希望する内容のみを記載する
労働基準法第22条3項には、以下の内容が明記されています。
| 退職時等の証明 |
|---|
| ③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 |
上記のとおり、退職者が希望しない項目は、退職証明書に記載しないでください。退職者が転職先に退職理由を知られたくないと申し出た場合、退職証明書には退職理由を記載しないで作成します。事前に退職者と認識をあわせておくと、書類作成をスムーズに進められるでしょう。
しかし、退職者は、一般的にどのような項目を記載するのか理解していない可能性もあります。そのため、ある程度のテンプレートを用意しておき、そこから記載したい項目を選んでもらう形式にするのがおすすめです。
具体的な理由を記載する
退職理由は、第三者が見てもわかりやすいように記入しましょう。とくに「会社都合」と記載する場合は、なるべく具体的な理由を記載するのがおすすめです。
| 「会社都合」と記載する場合の例 |
|---|
| 早期退職人員整理事業縮小 など |
なお、記載項目は退職者の意思が優先されます。「具体的な理由は書かないでほしい」と言われた場合は、企業は退職者の要望に応じなければなりません。
離職票と被る部分は統一する
退職証明書と離職票には、いくつか同じ項目があります。たとえば「退職理由」や「賃金」などは、離職票にも記載するのが一般的です。離職票と矛盾がないよう、退職証明書も内容をあわせておきましょう。
とくに、退職理由は失業保険の受給期間を左右する重要な項目です。離職票に「事業主からの働きかけによるもの」と記載されているにもかかわらず、退職証明書には「自己都合による退職」と記載されていると、退職理由に矛盾が生じていることになります。
2つの書類に矛盾がある場合、失業保険の受給申請ができません。転職先から不審に思われてしまうと、不利益を被る恐れがあります。
予備を保管しておく
退職証明書を発行する際は、コピーを保管しておきましょう。退職から2年間は、退職者から発行や再発行を求められる可能性があります。コピーを保管しておくと記載内容をすぐに確認でき、書類作成がよりスムーズに進むメリットがあります。
類似した書類との相違点
退職証明書と類似する書類として、『離職票』や『在籍証明書』、『解雇理由証明書』などが挙げられます。名称や記載項目が似ていて混同されがちですが、それぞれ異なる役割があるため注意が必要です。
離職票との違い
離職票は、主に失業保険を受給するために提出する書類です。退職証明書は企業が発行し、離職票は公共職業安定所長によって発行されます。退職証明書の書式は企業ごとに異なりますが、離職票には規定のフォーマットがあります。
在籍証明書との違い
在籍証明書は、その名のとおり在籍していることを証明する書類です。在籍証明書には、主に以下の項目を記載します。
- 入社年月日
- 雇用形態
- 勤務地
- 勤務日数・時間
- 業務内容
- 役職
- 賃金 など
記載項目は非常に似通っていますが、退職証明書と在籍証明書では発行するタイミングが異なります。
| 発行するタイミング | |
|---|---|
| 退職証明書 | 在籍証明書 |
| 退職後 | 在籍中 |
退職証明書が退職後に発行する書類であるのに対し、在籍証明書は在籍中に発行するものです。退職証明書には発行義務がありますが、在籍証明書の発行はあくまで任意です。退職者から求められても、応じる義務はありません。しかし、以下の理由から従業員が在籍証明書を必要としている可能性があるため、とくに問題がない限りは発行しましょう。
- 認可保育園や認定こども園への入園・更新
- 住宅ローンの審査
- 転職先への提出
- 在留資格の更新(外国人労働者の場合)
解雇理由証明書との違い
解雇理由証明書は、従業員が「自分が解雇された正確な理由」を知るための書類です。企業は、解雇予告された従業員から解雇理由について請求を受けた場合、遅滞なく証明書を発行する義務があります。
| (退職時等の証明)第二十二条 |
|---|
| ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 |
解雇理由証明書は退職理由が「解雇」の場合にのみ発行されるのに対し、退職証明書はそのほかの理由でも発行されます。退職証明書にはさまざまな項目がある点も大きな違いです。
退職証明書の書き方のポイントを押さえましょう
退職証明書の書式に明確な規定はありません。一般的には「業務の種類」「使用期間」「賃金」「退職理由」「その事業における地位」などの項目を記載します。記載する項目は退職者に決定権があるため、どの項目を記載するのか事前に確認しておくとスムーズです。退職者から請求された場合は遅滞なく発行する必要があるため、あらかじめテンプレートを用意するなどして準備を進めておきましょう。退職関連の手続きをはじめとした人事労務の負担を軽減するなら、「One人事」がおすすめです。
「One人事」は人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。電子申請や年末調整、マイナンバー管理など幅広い業務の効率化を助け、担当者の手間を軽減。費用や気になる使い心地について、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。