育児休業給付金の条件|もらえない人は? 2人目以降の注意点や延長・転職の場合も解説
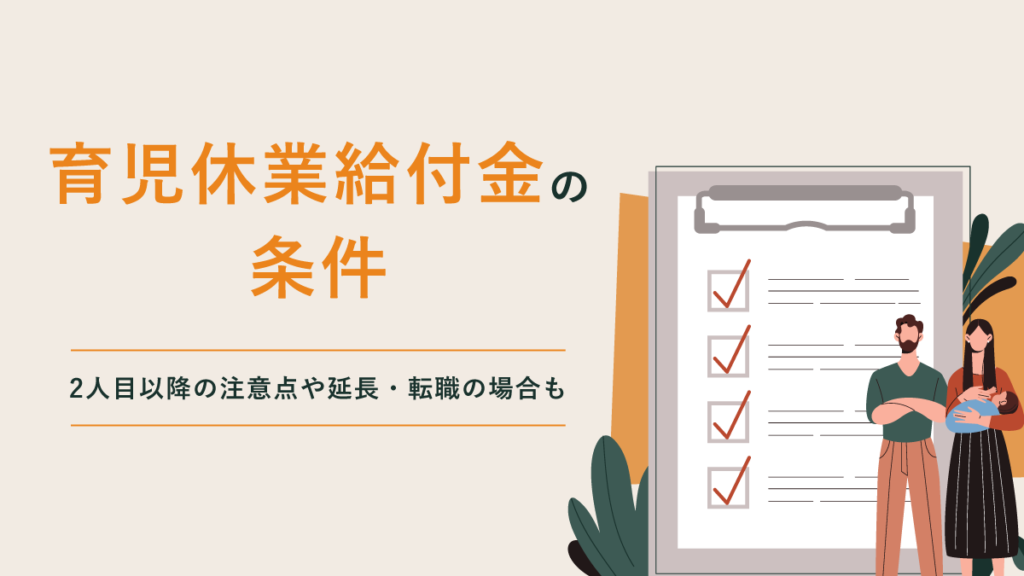
育児休業給付金は、条件を満たさなければ支給されません。育児休業を取得する従業員はもちろん、企業の担当者も育児休業給付金の条件を正しく理解する必要があります。
本記事では、育児休業給付金の条件をわかりやすく解説します。育児休業給付金をもらえないケースや第2子以降の条件についても紹介しますので、「自分は受給できるのか」と不安を感じている方や、人事労務担当者として適切な対応を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
▼育児休業給付金について一からおさらいするには以下の記事もご確認ください。
→育児休業手当(育児休業給付金)とは? いくらもらえる? 期間や計算方法と申請手続きを人事向けに解説
 目次[表示]
目次[表示]
育児休業給付金の条件
育児休業給付金とは、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者が受給できる給付金のことです。
育児休業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。全員共通の基本条件は以下の4つです。
【基本条件(全員共通)】
- 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(11日以上ない場合は就業した時間が80時間以上の)月が12か月以上ある
- 育児休業中に、会社から「休業前の8割以上の賃金」が支払われていない
- 育児休業中の就業日数が、1か月に10日以下(1か月に10日を超える場合は80時間以下)
- 原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者
賃金の8割以上が支払われていたり、育休中に働きすぎたりすると育児休業給付金の条件から外れます。
さらに有期雇用契約に限っては、追加で2つの条件があります。
【有期雇用のみ適用される条件】
- 同じ会社で1年以上継続して勤務
- 育休終了時(子どもが1歳6か月になる時点)まで契約更新見込み
| 雇用形態 | 必要な条件 |
|---|---|
| 主に正社員(無期雇用) | 基本条件の4つを満たすこと |
| 契約社員・パート・派遣社員(有期雇用) | 基本条件+1年以上の勤務継続+契約更新見込み |

育児休業給付金をもらえないケース
育児休業給付金は、育休を取得したすべての人が受け取れるわけではありません。以下のいずれかに当てはまる場合、支給対象外となります。
- 雇用保険に未加入
- 育休開始前の雇用保険加入期間が12か月未満
- 育児休業中に一定以上働いた
- 3回以上に分けて育児休業を取得した
- 産後パパ育休で28日間を超過した
もらえない理由とともに解説していきます。
雇用保険への未加入
育児休業給付金は、雇用保険の給付として雇用保険料を財源として支給されるため、雇用保険に未加入の場合は支給されません。
育児休業はパートやアルバイトでも取得できる制度ですが、雇用保険の加入条件が週の所定労働時間が20時間以上のため、そもそも雇用保険に加入していなければ対象外です。
育休開始前の雇用保険の加入期間が12か月未満
育児休業給付金は、育児休業を開始した日以前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または賃金支払基礎日数が11日以上ない場合は就業した時間数が80時間以上ある雇用保険の加入月が12か月以上ある場合に支給されます。
育児休業を開始した日以前の2年間で、雇用保険の加入期間が12か月に満たない場合は育児休業給付金は対象外です。
育児休業中における一定以上の就労
育児休業給付金は「子どもを養育するために休業している」ことが前提の制度です。対象者に対して労働を提供する義務をなくす目的があります。
そのため育休中に一定以上の就労をすると支給対象外です。しかし一部の例外も設けられています。
育休中に働いても受給できる条件
育児休業中に就労しながら育児休業給付金を受け取る条件は、以下のとおりです。
- 就業日数が1か月に10日以下(1か月に10日を超える場合は80時間以下)
- 恒常的や・定期的な就労ではない(例:月曜日は必ず働くなどルールがある)
- 育児休業中の賃金が賃金月額の80%未満
日数や頻度、賃金額によって育児休業給付金支給の対象外となります。仮に「就業日数が9日」だったとしても、賃金が育休前の80%以上になると給付金は支給されません。
育児休業中の就労は、企業側と従業員の合意によって認められます。企業の一方的な指示によって、育児休業中の従業員を就労させることはできませんので注意しましょう。
参照:『育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について』厚生労働省
参照:『育児休業中の就労について』厚生労働省
育児休業の分割取得が3回以上
育児休業は原則として2回までに分けて取得できます。3回目の育休を取得した場合、3回目の育児休業給付金は支給されません。
ただし、子どもの病気など特別な事情により、3回目の休業取得が認められると、給付金も支給対象となります。
産後パパ育休の支給期間を超過
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、主に男性を想定した制度で子が生まれて8週間以内に、最大で4週間(28日)の育児休業を最大2回に分けて取得できる制度です。
産後パパ育休(出生時育児休業)は最大28日間までが給付対象です。29日目以降は育児休業給付金の対象外になるため、注意しましょう。

育児休業給付金の条件|2人目以降の注意点
育児休業給付金を受給するには、育児休業開始日前2年間に「11日以上就業した月」が12か月以上あることが条件の1つです。
ただし、第1子の育児休業中に第2子を妊娠・出産した場合、「2年間に12か月以上の就業」が満たせないケースがあります。
そこで設けられている救済措置が、通称「4年遡りルール」と呼ばれる制度です。
4年遡りルールとは、育休開始日以前の2年間にケガや病気や出産など、やむを得ない事情の休業があった場合は、休業開始前最長で4年間を適用対象とするルールです。
育児休業開始前の2年間で30日以上給与を受け取れなかった期間がある人は、最大4年前まで遡って計算できます。
第3子以降の給付金はどうなる?
第1子、第2子に連続して、第3子以降も育児休業を取得しようとすると、4年遡りルールを適用しても、育児休業給付金の条件が満たせなくなります。
従業員が第3子以降の育児休業給付金を受けるためには、第1子または第2子の育児休業終了後に職場復帰し、1年以上就労する必要があるのです。
1年以上働けば、第3子の育児休業においても、育児休業給付金を受給できます。
参照:『令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します~育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です~』厚生労働省
育児休業給付金の条件|転職後でももらえる?
育児休業給付金は、原則として「育休開始前2年間に雇用保険の加入期間が12か月以上あること」が条件です。では、転職した場合はどうなるのでしょうか。
条件にあるように、転職前後で「雇用保険の被保険者期間」が途切れていなければ受給の対象です。転職前に1年以上のブランクがある場合は対象外となるため注意しましょう。
また、前職のさらに空白があり、前職で6か月しか働いていない場合は、転職後に6か月以上働く必要があります。
念のため、会社の就業規則を確認しておくと安心です。
育児休業給付金の条件|延長できるケース
育児休業給付金は、育児休業と紐づいているため、子どもが1歳になるまでの支給を原則としています。
しかし、育休期間は特定の条件を満たせば1歳6か月まで延長が可能で、1歳6か月時点で状況が変わっていなければ最大2歳まで延長が可能です。同時に育児休業給付金の受給期間も延長できます。
延長できるケースの代表例は以下のとおりです。
- 保育園に入れない場合
- 配偶者の死亡や病気など、育児が困難な特別な事情がある場合
2025年4月からは、延長理由の基準が厳格化されました。具体的には、延長申請時の書類が追加されています。
「入所保留通知」に加えて「保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」も提出しなければなりません。
2025年4月以降に育児休業延長を行う人は、厚生労働省や市区町村などの公的情報を確認しておきましょう。
企業側も、育児休業給付金制度にかかわる重要な内容として、正しく理解しておく必要があります。
そもそも育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、育児休業を取得した雇用保険の被保険者が受け取れる給付金です。
また育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために仕事を休む制度です。法律で決められた制度であるため、企業は従業員の申し出を拒否できません。
育児休業中は給与の支払いは不要です。給与支給の有無は企業が判断しますが、一般的に、就労していない従業員に対して給与を支給する企業は多くありません。
働く人が安心して育児に専念できるように、国が給付金制度制度を設けています。
育児休業給付金の内容
育児休業給付金の内容について、一覧表で紹介します。
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 原則として子どもが1歳に達する日の前日(1歳の誕生日の前々日)まで |
| 対象 | 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者 |
| 条件 | 1.育休開始前2年間に「11日以上就業した月(11日以上就業していない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月)」が12か月以上 2.育休中の給与が、休業前の給与の8割未満である 3.育休中の就業が月10日以下(10日を超える場合は80時間以下) 4.【有期雇用】 1年以上継続勤務+子が1歳6か月になるまで雇用継続の見込みがある |
| 申請方法 | 企業がハローワークに申請する |
| 延長 | 保育園に入れないなどの条件を満たせば、最大2歳まで延長可能 |
申請手続きは、原則として企業が行います。遅延すると、従業員が育児休業給付金を受給できる時期も遅れてしまうため注意しましょう。
育児休業給付金の計算
育児休業給付金は、育児休業開始前に支給された給与を基準として計算します。具体的な計算式は、以下のとおりです。
| 育児休業給付金額=休業開始時賃金日額×支給日数×給付率 |
給付率は、育児休業開始から経過した日数によって変動する点に注意が必要です。育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%で計算します。
休業開始時賃金日額には、上限額と下限額が設定され、それぞれの金額は以下のとおりです。
| ※2025年7月31日まで | 休業開始時賃金日額 |
|---|---|
| 上限額 | 15,690円 |
| 下限額 | 2,869円 |
育児休業給付金の上限額と下限額は、毎年8月1日に見直されています。育児休業給付金を受ける人や、企業の担当者は、最新の上限額を確認しましょう。
育児休業給付金に関連した制度
育児休業給付金には、育児休業以外にも関連する制度があります。具体的にどのような制度が活用できるのか、確認してみましょう。
| 産後パパ育休(出生時育児休業) |
|---|
| ・主に男性が最大4週間(28日間)の育児休業を取得できる制度 ・子どもの出生日から8週間以内に最大28日間 ・出生時育児休業給付金の支給あり ・育児休業給付金と同様の計算式で給付率67% |
| パパ・ママ育休プラス |
|---|
| ・育児休業を1歳2か月まで延長できる制度 ・両親が育児休業を取得することで適用 ・実際に育児休業を取得できる期間は1年間 ・育児休業を延長する制度、育児休業給付金の受給期間も延長 |
| 出生後育児休業給付金 |
|---|
| ・2025年新設・両親ともに子の出生直後の一定期間に14日以上の育児休業を取得することで適用 ・育児休業の取得率向上を目的・受給期間は出生後28日間 ・支給額は「休業開始前賃金×日数×13%」 ・育児休業給付金と組み合わせ、休業開始前賃金の約10割に近づく |
仕事を休むと収入がなくなる(減る)と考えがちですが、実は複数の制度を活用することで、休業前の賃金に近い水準を維持できる場合があります。
仕事を休むと収入がなくなる(減る)と考えがちですが、複数の制度を活用すると、休業前の賃金に近い水準を維持できる場合があります。
通常の育児休業給付金と、出生後育児休業給付金を組み合わせると、産後直後の一定期間は手取りが大きく減ることを防げるのです。また「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば、夫婦で育児休業を取得しつつ、給付金の受給期間の延長が可能です。
企業側は従業員が安心して出産や育児を迎えられるよう、育児休業や育児休業給付金について正しく案内しましょう。
参照:『育児休業給付の内容と支給申請手続』厚生労働省
参照:『令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について』厚生労働省
まとめ
育児休業給付金を受給するためには、基本的な4つの条件を満たすことが必要です。有期雇用契約の場合は、さらに条件が加わります。また、連続して2人目を出産する場合などは、特別条件が適用されます。
育児休業を取得する従業員は、自分が受給対象であるかをチェックし、必要な手続きを把握したうえで準備を進めましょう。一方、企業の人事労務担当者は、育児休業給付金の仕組みを正しく理解し、従業員からの問い合わせに対応できるようにしておくことが大切です。
本記事で紹介した内容を参考にしつつ、最新の情報については厚生労働省の公式ページを確認することをおすすめします。育児休業給付金を正しく活用し、育児と仕事を両立しやすい環境を整えましょう。
育児休業における労務管理も効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、企業における人事労務業務を効率化できるクラウドシステムです。育児休業に関する各種手続きや管理業務の効率化にお役立ていただけます。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
