育児休業制度とは【育児休暇との違い】期間や給与の扱いと手続きを人事担当者向けに解説
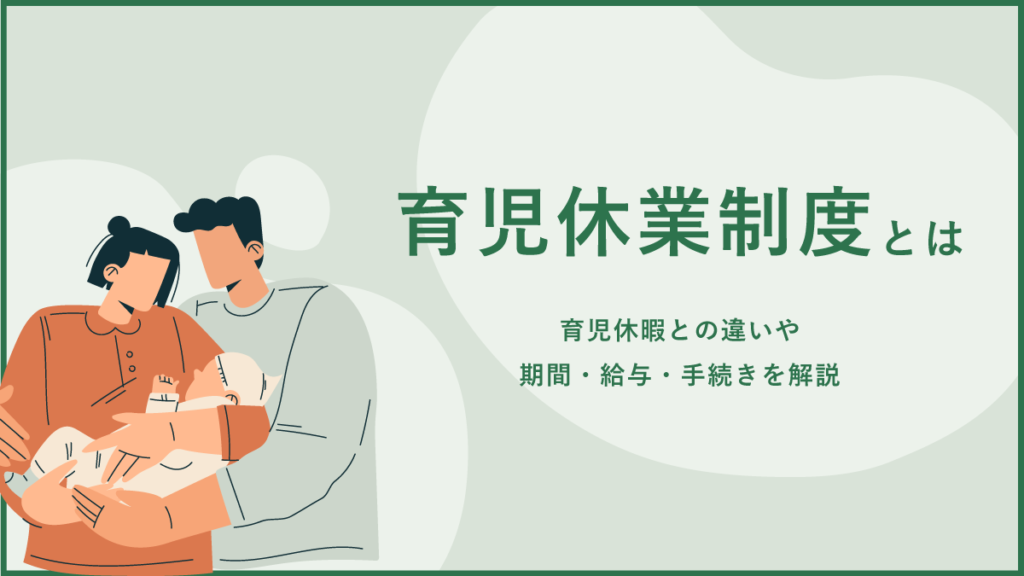
育児休業制度は、1歳未満の子どもを養育する従業員が取得できる休業制度です。法律で定められており、一定の条件を満たせば企業の規模や業種にかかわらず取得できます。
人事担当者としては、育児休業制度の基本を理解しておくとともに、取得希望者への適切な対応や、社内の育休取得率向上に向けた施策の検討も求められるでしょう。
本記事では、育児休業の制度の基本から「育児休暇との違い」「育休中の給与の扱い」「申請・手続き」など、人事担当者が押さえておきたいポイントを解説します。
→従業員の育児休業にともなう労務管理も効率化「One人事」資料をダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
育児休業とは? わかりやすく解説
育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために仕事を休業する制度です。『育児・介護休業法』に基づく法定制度であり、一定の条件を満たせば、最長2歳まで延長も可能です。
企業は、従業員から育児休業の申し出があった場合、「繁忙期だから」「人材不足だから」といった理由で拒否することはできません。
もし正当な理由なく断ると、各都道府県労働局による調査が行われ、厳しい行政指導が入る可能性もあります。
申し出を受けたら、まず「育児休業申出書」を受理し、就業規則や労使協定に基づいて適切な対応が必要です。
参照:『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律 第6条』e-Gov法令検索

育児休業と混同されやすい関連制度
育児休業には、「育児休暇」や「産前産後休暇」、「子の看護休暇」など、混同しやすい制度があります。それぞれの制度の目的や適用範囲にどのような違いがあるのか、育児休業と対比させながら解説します。
| 制度 | 制度主体 | 対象 | 目的 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 育児休業 | 国 | 1歳未満の子を養育する両親 | 育児 | 原則1歳(最長2歳) |
| 育児休暇 | 企業 | 企業が定めた対象者 | 育児支援 | 企業による |
| 産前産後休業 | 国 | 出産する女性 | 母体保護 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間 |
| 子の看護等休暇制度 | 国 | 小学校3年生修了までの子を持つ親 | 看護 | 年5日(2人以上は年10日) |
育児休業と育児休暇との違い
育児休業と育児休暇の大きな違いは、制度を定めている主体にあります。
育児休業は、育児・介護休業法に基づく法定制度であり、企業は従業員の申し出を拒否できません。
一方、育児休暇は、企業が独自に定める福利厚生制度であり、各社で内容が異なります。たとえば、育児休暇を「子どもが3歳になるまでの特別休暇」としている企業もあれば、「運動会や授業参観などの学校行事のための休暇」としている企業もあります。対象者や取得条件に法的な決まりはありません。就業規則にルールを記載しておく必要があります。
また、育児休業は給付金制度があり、就労に対する給与は無給が基本ですが、育児休暇は企業ごとに「有給」とするか「無給」とするか設定が可能です。
育児休業と産前産後休業との違い
育児休業と産前産後休業は、取得する目的と対象者が異なります。
育児休業は、1歳未満の子どもを養育するための休業であり、1歳未満の子どもを育てる人であれば、男女ともに両親が取得可能です。
一方、産前産後休業は、出産前後の母体保護のための休業であり、出産前後の女性のみを対象とします。
対象が異なるため、当然ながら取得時期も異なります。育児休業は最長2歳まで延長可能ですが、産前産後休業は産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の取得です。
「育児・介護休業法」に基づく育児休業に対し、産前産後休業は「労働基準法」によって定められている点にも大きな違いがあります。
子の看護等休暇制度とは
育児休業と子の看護等休暇の違いは、目的や取得日数です。
育児休業は、1歳未満の子どもを育てるための長期休業であるのに対し、子の看護等休暇は、子どもの病気・ケガの看護や入学式等を参加を目的とした短期の休暇です。
小学校3年生修了前の子ども1人につき、年5日まで取得できます(2人以上なら年10日)。また、時間単位で取得できるため、従業員にとって、子どもの急な体調不良でも柔軟に休めるのが特徴です。
育児休業の取得条件
育児休業を取得するためにはどのような条件を満たさなければならないのでしょうか。具体的な条件を紹介します。
| 条件 | |
|---|---|
| 無期雇用 | 1歳未満の子ども(実子または養子)を養育している |
| 有期雇用 | ・子どもが1歳6か月に達する日(誕生日の前日)まで雇用契約がある ・契約満了が明らかでない |
2022年以前は「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件もありましたが、法改正を機に撤廃されています。入社1年未満の従業員でも育児休業を取得できるようになりました。
育児休業の対象外となる人
以下に該当する人は、育児休業制度の対象外です。
- 日雇い
- 労使協定で規定された一定の労働者
労使協定で規定された一定の労働者とは、雇用期間が1年未満の人や、育児休業に合理的な理由がない人を指します。
合理的に認められない理由の例は以下のとおりです。
- 育児休業申出の日から1年以内に雇用契約終了が決まっている
(※育児休業を1歳6か月または2歳まで延長する場合は、6か月以内)
- 週の所定労働日数が2日以下
企業によってルールは異なる可能性があるため、気になる方は自社の就業規則や労使協定を確認しましょう。
参照:『そのときのために、知っておこう。育児休業制度』厚生労働省
参照:『育児・介護休業法のあらまし』厚生労働省都道県労働局雇用環境・均等部(室)
育児休業の期間
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できます。 ただし、一定の条件を満たせば、1歳6か月または2歳まで延長が可能です。詳しい背景や注意点、延長に必要な対応について解説していきます。
原則は1歳になるまで
育児休業の期間は、最大で子どもの出生日(または養子縁組成立日)から、1歳の誕生日の前日までです。この期間内であれば、従業員は自由に日程を指定できます。
女性の場合は、産後に「産前産後休業」を取得するため、産後休業の期間終了後から、育児休業の扱いになります。
一方男性は、子どもの出生日から育児休業の取得が可能です。
延長する場合
育児休業は、一定の条件を満たす場合に「1歳6か月まで」または「2歳まで」延長できます。
| 育児休業を1歳6か月まで延長できる条件 |
|---|
| (子どもが1歳になった時点で判断) ・労働者本人または配偶者が引き続き育児休業を取得している ・育児休業の継続が必要な場合 |
| 育児休業を2歳まで延長できる条件 |
|---|
| (子どもが1歳6か月になった時点で判断) ・労働者本人または配偶者が引き続き育児休業を取得している場合 ・育児休業の継続が必要な場合 |
いずれも保育園に入所できないなどの事情が該当します。
注意したいのは、育児休業の延長を希望する場合、従業員は「都度申し出る」必要があります。 1歳到達前に1歳6か月までの延長を申請し、さらに1歳6か月到達前に2歳までの延長を申請してもらいましょう。
延長時の手続き
保育所に入所できないことを証明するためには、自治体が発行する「保育所入所保留通知」などが必要です。
また、保育所に内定したにもかかわらず、自己都合で辞退した場合、延長は認められません。たとえば、第一次申し込み時に内定したあと、正当な理由なく辞退し、第二次申し込みで落選した場合、育児休業の延長は不可となります。
人事担当者は、育児休業の延長申請があった際に、「保育所入所保留通知」の提出を求めるなど、必要書類を適切に確認することが重要です。
育児休業に関連する新制度と企業の義務
近年、父親である男性の育児休業取得を促進するための新たな制度が創設され、企業の義務も拡大しています。
具体的には、以下の2つのポイントが重要です。
- 「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設
- 男性従業員に関する育児休業の取得状況の公表義務化
それぞれの制度の内容と企業の対応について解説します。
産後パパ育休(出生時育児休業)制度とは
産後パパ育休とは、子どもの出生日から8週間以内に、最大4週間の育児休業を取得できる制度です。まぎらわしいですが、通常の育児休業とは異なります。
- 通常の育児休業とは別に取得できる(通常の育児休業と併用可能)
- 2回に分けて取得することが可能
- 休業期間中の就業が可能(通常の育児休業は原則不可)
産後パパ育休と通常の育児休業を合わせて利用することで、男性が育児休業をより柔軟に取得できるようになりました。
参照:『令和3(2021)年法改正のポイント|育児休業特設サイト』厚生労働省
男性従業員に関する育児休業の取得状況を公表義務化
2025年4月の『育児・介護休業法』改正により、従業員300人を超える企業には、男性の育児休業取得状況の公表が義務づけられました。2025年3月以前は、従業員1,000人を超える企業にのみ義務づけられていたものが拡大されました。
| 対象企業 | 従業員300人以上の企業(今後、中小企業にも拡大の可能性あり) |
|---|---|
| 公表内容 | 男性従業員の育児休業取得率 |
| 公表方法 | 企業のホームページなど |
企業は育児休業の取得状況を可視化し、男女ともに育休を取得しやすい職場環境を整えることが求められています。
育休取得率が高い企業は、「子育てに理解のある企業」として好印象を与えるため、人材採用において優位に働きます。今いる従業員のエンゲージメント向上にもつながるでしょう。
企業の人事担当者は、育児休業取得率の計測・報告を適切に行い、社内制度を整備することが重要です。
参照:『令和5年(2023年)4月1日施行の内容』厚生労働省
参照:『男性の育児休業取得率等の公表について』厚生労働省

育児休業中の給与補償| 給付金と社会保険料免除の仕組み
育児休業制度を利用している従業員は、原則として企業から給与は支払われません。 育児休業は「就労を前提としない制度」であるためです。
しかし、国は育児休業中の給与を補うために、給付金の支給や社会保険料免除の制度を整備しています。
企業の人事担当者は、制度を正しく理解し、従業員へ適切に説明する必要があります。
ここでは育児休業中に受け取れる「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」と、「社会保険料免除の仕組み」について詳しく解説します。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対して支給される給付金です。受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
| 育児休業給付金の対象者と条件 |
|---|
| 育児休業開始日前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある |
| 職場復帰を前提としている |
| 休業開始前1か月の賃金の8割以上が支払われていない |
| 育休中の就業日数が、1か月あたり10日以下(または80時間以下) |
有期雇用労働者は上記の条件に、同一企業で1年以上継続勤務していること、かつ子どもが1歳6か月になるまで雇用契約を継続することが追加されます。

給付額の計算方法
育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で算出します。時期により割合が異なるため注意しましょう。
| 育児休業180日目まで | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
|---|---|
| 育児休業181日目以降 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
たとえば、育児休業前の賃金が月20万円だった場合、以下のように支給されます。
| 時期 | 受給額例 |
|---|---|
| 育児休業180日目まで | 13万4,000円 |
| 育児休業181日目以降 | 10万円 |
出生時育児休業給付金とは
出生時育児休業給付金は、「産後パパ育休(出生児育児休業)」の取得に際して、申請により受けられるお金です。金額は通常の月額賃金の約7割程度です。
| 給付額の計算方法 |
|---|
| 出生時育児休業開始時賃金日額×出生時育児休業をした日数(上限28日)×67% |
ただし上限額が日額「15,690円」(令和6年8月1日~令和7年7月31日)と決められています。ひと月に換算すると最大「294,344円」となります。
支給期間は産後パパ育休の期間と同じ、最大4週間です。
育休中の社会保険料の免除
育児休業中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。
| 免除の対象となる保険料 |
|---|
| 労働者の社会保険料(健康保険・厚生年金)企業側の社会保険料(事業主負担分) |
本来、従業員の社会保険料は、従業員本人と企業側の双方で負担しなければなりません。しかし、企業が年金事務所や健康保険組合に申請することで、双方の社会保険料を免除できます。
免除期間は、育児休業の開始月から、終了日の翌日が含まれる月の前月までです。4月1日から9月30日まで育児休業を取得した場合、4月~9月分の社会保険料が免除されます。
| 例 | |
|---|---|
| 育休開始 | 2025年4月1日 |
| 育休終了 | 2025年9月30日 |
| 免除対象の保険料 | 2025年4月から2025年9月分 |
開始月と終了日の翌日が含まれる月が同じでも、開始月に14日以上の育児休業を取得した場合は、例外的に免除の対象です。
支給日の月末時点で育児休業を取得している従業員への賞与についても、保険料が免除されます。ただし、賞与を支払った月の月末を含み、連続して1か月を超える育児休業を取得していることが条件です。

育児休業の手続きの流れ|申請手続きと期限を解説
育児休業を取得するためには、企業と従業員の双方が適切な手続きを行うことが必要です。
申請期限や必要書類の提出に漏れがあると、育児休業給付金の支給が遅れたり、社会保険料の免除が適用されない可能性もあります。
育児休業に関する申請手続きの流れと、それぞれの申請期限について詳しく解説します。
手続きの流れ
育児休業の申請は、企業と従業員の双方が対応する手続きがあります。
【企業が行う手続き】
- 従業員からの報告
- 個別に制度の周知・意向確認
- 育児休業申出書を受け取り、通知書の交付
- 社会保険料免除の申請(年金事務所・健康保険組合へ提出)
- 育児休業給付金の申請(ハローワークへ提出)
男性従業員が産後パパ育休取得を取得する場合は、出生時育児休業給付金の申請も対応する必要があります。
【従業員が行う手続き】
- 会社への報告
- 育児休業の申出書を企業に提出
- 育児休業給付金を受けるための書類準備
育児休業を延長する場合は、保育所入所保留通知の取得と提出も必要です。
必要書類の準備
育児休業制度に関する手続きは、原則として企業が公的機関に必要書類を提出して進めます。
とくに社会保険料免除や育児休業給付金の申請は、従業員の生活にも密接にかかわるため、遅れないように注意しましょう。
育児休業の取得・給付金・社会保険料免除に関する必要書類は以下のとおりです。
| 制度 | 必要書類 | 目的 |
|---|---|---|
| 育児休業 | ・育児休業申出書 | 従業員が企業に育児休業取得を申し出るための書類 |
| 育児休業 | ・健康保険 ・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 | 育児休業中の社会保険料免除を受けるための書類 |
| 育児休業給付金 | ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ・支給期間の賃金を証明できる賃金台帳や出勤簿など ・母子手帳のコピーなど、育児の事実を確認できる書類 ・育児休業申出書(男性の場合、または、女性で育児休業開始日と法定日が異なる場合) | 育児休業給付金を受給するために必要な書類 |
従業員から報告を受けた時点で、制度の内容や用意してもらう書類の説明をしておくと、後の対応がスムーズになります。
必要書類の提出先
育児休業の給付金申請では、企業が管轄のハローワークへ必要書類を提出します。書類の提出は、電子申請も可能です。
社会保険料免除の手続きは、年金機構の事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)、健康保険組合に加入している場合は健康保険組合にも申請します。
申請期限
育児休業の申請期限は、制度ごとに以下のように定められています。
| 申請内容 | 期限 |
|---|---|
| 育児休業の申請 | 休業開始予定日の1か月前まで |
| 育児休業の延長申請 | 休業開始予定日の2週間前まで |
| 育児休業給付金(初回) | 休業開始から4か月を経過する日が属する月末まで |
| 育児休業給付金(2回目以降) | ハローワークが指定する期限まで(対象期間の初日から4か月を経過する日が属する月末まで) |
| 社会保険料免除 | 育児休業を取得するたび(育児休業などの期間中または育児休業等が終了したのち、終了日から起算して1か月以内の期間中) |
育児休業給付金は、原則として2か月ごとに申請が必要な点に注意が必要です。育児休業給付金の支給単位期間は1か月であり、2支給単位ごとに企業が申請します。また、初回は、育児休業が開始したあとすぐに申請をするわけではありません。
参照:『育児休業給付の内容と支給申請手続』厚生労働省
参照:『育児休業中の保険料免除について』厚生労働省
まとめ
育児休業制度は、1歳未満の子どもを養育する母親と父親が仕事を休業できる制度です。
育児休業中は、企業からの給与支給は原則ありませんが、国の制度により「育児休業給付金の支給」や「社会保険料の免除」を受けられます。
育児休業の取得や給付金の受給など、各種申請手続きは企業側が主体となって進める必要があります。
企業の担当者は、申請方法や必要書類、期限を正しく理解し、従業員がスムーズに手続きを進められるよう支援しなければなりません。
申請漏れや遅延が発生しないよう、早めに準備し、適切にサポートしましょう。
育児休業における労務管理も効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、企業における人事労務業務を効率化できるクラウドシステムです。育児休業に関する各種手続きや管理業務の効率化にお役立ていただけます。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

