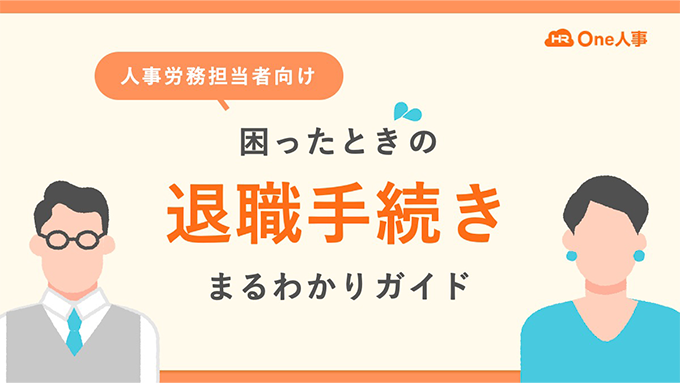雇用契約解除とは?実施方法や正当な理由、注意点を解説

雇用契約の解除は、労働法で厳しい条件が設けられ、「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上の相当」と認められる場合に限られます。
- 問題のある従業員を法的に問題なく雇用契約解除できるのか
- 経営が厳しく人員整理が必要。どのような雇用契約解除の手続きが必要か
人事担当者や経営者は、以上のような悩みを抱えたことがあるかもしれません。
本記事では、雇用契約解除の基本的な考え方から実施手順、正当な理由、注意点までをわかりやすく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
雇用契約解除とは? 基礎知識と法的定義
雇用契約解除とは、企業(使用者)または従業員(労働者)の意思表示で、雇用契約を終了させることです。
基本的には、企業側の意思による終了を「解雇」、従業員の意思による終了を「退職」と呼びます。
| 解雇 | 企業側からの申し出 | 普通解雇 |
| 整理解雇 | ||
| 懲戒解雇 | ||
| 諭旨解雇 | ||
| 退職 | 従業員側の申し出 | 会社都合退職 |
| 自己都合退職 |
※整理解雇は雇用保険上、「会社都合退職」となる
解雇には、業績の悪化などを理由とする「整理解雇」や、重大な規律違反を理由とする「懲戒解雇」など、いくつかの種類があります。
また、諭旨解雇とは、懲戒解雇相当の事由がある場合に会社が従業員に退職届の提出を勧告し、一定期間内に出せば懲戒解雇とせず、出さなければ懲戒解雇とする懲戒処分です。
一方で退職は、会社側の事情によって離職する「会社都合退職」と、本人の意思による「自己都合退職」に分けられます。
雇用契約解除に関する法的根拠
雇用契約解除について法的根拠となるのは、主に以下の規定です。
| 労働契約法第16条 | 合理性・相当性を欠く解雇は権利濫用として無効 |
| 民法第627条 | 期間の定めのない雇用契約は、各当事者がいつでも解約の申入れができる |
| 労働基準法第20条 | 解雇は原則30日前に予告が必要。予告しない場合は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の必要 |
| 労働組合法第7条 | 労働組合への加入・活動を理由とする解雇を禁止。不当労働行為として無効 |
| 男女雇用機会均等法第6条・第9条 | 性別、婚姻、妊娠、出産、産前産後休業・育児休業を理由とする解雇を禁止。とくに妊娠中・出産後1年以内の解雇は原則無効 |
| 育児・介護休業法第10条 | 育児休業や介護休業を申請・取得したことを理由とする解雇・不利益取扱いを禁止 |
参照:『労働契約法第16条・17条』e-Gov法令検索
参照:『民法第627条・第628条』e-Gov法令検索
参照:『労働基準法第20条』e-Gov法令検索
参照:『労働組合法第7条』e-Gov法令検索
参照:『男女雇用機会均等法第6条・第9条』e-Gov法令検索
参照:『育児・介護休業法第10条』e-Gov法令検索
参照:『労働契約の終了に関するルール』厚生労働省
法律により、企業側からの解雇は、いつでも自由にできるものではありません。合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く一方的な雇用契約の解除は無効です。「誰が見ても納得できる理由」が必要なのです。
雇用契約解除と雇止めの違い
「雇用契約の解除」と「雇止め」は似ているように感じられるかもしれませんが、性質は異なります。
- 雇用契約の解除:雇用契約期間中に契約を終了すること
- 雇止め:有期契約の満了で更新しないこと
| 雇用契約の解除(解雇) | 雇止め | |
|---|---|---|
| 契約形態 | 無期契約でも発生 | 有期契約の満了時 |
| 法的な根拠 | 労働契約法16条・17条 | 労働契約法19条 |
雇用契約解除のうち解雇は、契約期間中に使用者が一方的に契約を打ち切る行為です。労働契約法第16条・第17条に基づいて有効性が判断されます。
一方で雇止めは有期労働契約が満了した際に、更新されず、そのまま契約が終了することを指します。解雇は使用者の意思に基づく法律行為による終了、雇止めは期間満了という事実による終了という違いです。
有期雇用契約における契約解除
有期雇用契約の期間中に解除する場合は、労働契約法第17条・民法第628条に基づき「やむを得ない事由」が必要です。
| 労働契約法第19条 | 合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない雇止めは無効 |
| 労働契約法第17条 | 有期雇用契約は「やむを得ない事由」がなければ、雇用契約の満了まで解雇はできない |
| 民法第628条 | 有期雇用契約は「やむを得ない事由」があれば、すぐに解除が可能 |
参照:『労働契約法第17条・19条』e-Gov法令検索
参照:『民法第628条』e-Gov法令検索
また、労働契約法第19条では、有期雇用契約における、いわゆる雇止めの法理が規定されています。繰り返し更新してきた契約で、更新が当然と期待できる事情がある場合は、解雇と同様に制限を受けます。
企業が雇止めをする際は、方針を早めに決定し、労働者に対して合理的に説明しなければなりません。
雇用契約解除(解雇・退職)の種類と理由
では企業が雇用契約解除を検討する際、「誰が見ても納得できる」合理的な理由とはどのようなものを指すのでしょうか。法律で認められている解雇の種類と、それぞれの判断基準について解説します。
企業による普通解雇
普通解雇とは、労働者が雇用契約の内容にしたがって労務を提供できない場合に行われる解雇です。
たとえば、能力不足や勤務態度の著しい勤怠不良、心身の疾患によって業務の遂行に支障が出ているケースなどが該当します。
ただし、「労務の提供が不十分」と判断するには、使用者の主観ではなく、社会通念に照らして妥当と認められる必要があります。
企業側も、いきなり解雇するのではなく、配置転換や教育指導、業務内容の見直しなど、改善に向けた措置を講じなければなりません。努力を経てもなお業務に支障がある場合に、普通解雇が最終的に検討されます。
企業による懲戒解雇
懲戒解雇は、企業秩序を著しく乱す重大な違反行為に対して行われる、もっとも重い処分です。懲戒解雇が有効となるためには、就業規則に懲戒解雇の事由が明確に定められており、あらかじめ規定された行為が該当していることが前提です。
主な懲戒解雇事由としては、次のようなケースが挙げられます。
- 重要な経歴を詐称して雇用された
- 正当な理由なく無断欠勤が長期におよび、出勤の督促にも応じない
- 会社の機密情報を漏えいした
- 会社の信用や名誉を著しく損なう行為をした
一度の遅刻や軽微な規律違反などは、社会通念上、懲戒解雇ほど重い処分は認められないでしょう。企業は処分の重さが妥当かどうか、慎重に検討する必要があります。
企業による整理解雇
整理解雇とは、経営上の必要性に基づき行われる人員削減を目的とした解雇です。いわゆる「リストラ」に該当します。ただし、経営悪化を理由にした解雇は、安易に認められるものではありません。次の4要件をすべて満たす必要があります。
- 人員削減の必要性(経営上の危機が現実的である)
- 解雇回避努力義務の履行(配置転換・新規採用の抑制・役員報酬の削減などの努力をしたか)
- 被解雇者選定の合理性(選定基準が客観的・公正であるか)
- 労働者・労働組合との協議(説明や相談の機会を設けたか)
配慮を欠いた整理解雇は、たとえ経営が苦しい状況でも「不当解雇」と判断されるため注意しましょう。整理解雇はあくまで最終手段であり、企業は誠実な手続きを尽くさなければなりません。
企業による諭旨解雇
諭旨解雇とは、本来であれば解雇に相当する行為があった場合に、従業員に退職届の提出を勧告して一定期間に出せば懲戒解雇としない懲戒処分です。
懲戒解雇のように一方的な処分ではなく、従業員に働きかけて退職届を提出してもらうことで懲戒解雇としない措置のことです。企業としては、従業員の今後を考慮した、いわば温情的な対応です。
ただし、あくまで本人の同意が前提であり、退職届の提出を強制することはできません。従業員が応じない場合は、懲戒解雇など別の手続きを検討する必要があります。
会社都合による従業員の退職
会社都合退職とは雇用保険上の区分で、会社の事情によって従業員が退職せざるを得なくなるケースを指します。
たとえば、会社の倒産や業績不振によるリストラ(整理解雇)、有期契約社員や派遣社員の一定の条件の契約終了(雇止め)、または一定の条件の早期退職制度への応募などです。
会社都合で退職した場合、失業給付を受け取る際に、7日間の待機期間で受給がスタートします。給付を受けられる期間も長く、最大330日まで支給されることがあるのが特徴です。
自己都合による従業員の退職
自己都合退職とは、働く人自身の理由で会社を辞めることをいいます。雇用保険上の区分で、転職や独立、家族の介護、引っ越しなど、理由はさまざまです。
原則として、退職は労働者の自由です。そのため「一身上の都合により」と申し出れば雇用契約は解除できますが、有期契約途中の退職に、病気や介護などやむを得ない事情が必要になります。
失業給付では、会社都合退職に比べて条件が不利です。給付が始まるまで7日間の待機期間と離職日により1か月または2か月の給付制限期間があり、受給できる期間も最長150日ほどです。また、会社によっては退職金が減る場合もあります。
雇用契約解除の手続き(企業側)
企業が従業員との雇用契約を解除する際は、法律に基づいた適正な手続きを踏むことが求められます。法的要件を満たしていないと「不当解雇」と判断されるおそれがあるため、企業側は慎重な対応が必要です。
ここでは、企業が雇用契約を解除する際の手続きの流れと注意点を中心に解説します。
手続きの流れ
雇用契約解除の手続きは、解除の種類(解雇・雇止めなど)によって多少異なりますが、基本的な流れは共通しています。以下の手順に沿って進め、トラブルのリスクを最小限に抑えましょう。
1. 現在の雇用状態と契約内容の確認
契約解除を決定する前に、まずは現在の雇用状況や契約内容(更新回数・契約期間・更新条項など)を確認します。
有期契約の場合は、労働契約法第17条に基づき「やむを得ない事由」がなければ契約途中での解除はできません。
通知は書面で行うのが基本です。 書面には以下の項目を明記しましょう。
- 契約終了日と発効日
- 理由(雇止め・解雇の別)
- 最終勤務日までのスケジュール
- 退職金や未払い給与の支払い方法
- 貸与物の返却手続き
- 問い合わせ先
退職日までに引き継ぎや社会保険の手続きを済ませ、必要に応じて雇止め理由証明書を発行します。
2. 解除理由の妥当性と証拠の確認
能力不足や勤務態度の勤怠不良、経営悪化など、解除の理由が「客観的に合理的」かどうかを判断します。不当な雇用契約解除とみなされないよう、勤務記録や指導履歴など、客観的な証拠を整理しておきましょう。改善の機会を与えた過程を裏づける記録を残すことも大切です。
雇用契約解除に関する説明は、必ず書面または記録に残します。一方的な判断や感情的な対応は避け、法的要件に基づいた手続きを徹底しなければなりません。
3. 通知・予告の実施
雇用契約の解除を決定したら、従業員へ契約終了の通知を行います。
解雇を行う場合は、労働基準法第20条により「30日前の予告」または「30日分以上の平均賃金の支払い」が必要です。
ただし、以下の条件にあてはまる場合は、事前に所轄の労働基準監督署長から「解雇予告除外認定」を受けることで手当の支払いは免除されます。
- やむを得ない事由による経営破綻等を理由とする解雇
- 懲戒処分を理由とする解雇
- 日雇いの労働者(1か月を超えて引き続き雇用される場合は対象)
- 2か月以内の有期契約労働者(所定の期間を超えて引き続き雇用される場合は対象)
- 試用期間である労働者(14日を超えて引き続き雇用される場合は対象)
有期労働契約の場合は、3回以上更新または通算1年以上の勤務がある従業員に対して、30日前の雇止め予告が求められます。予告を怠ると、解雇無効や損害賠償請求につながるおそれがあるため、基本に忠実に対応しましょう。
4. 必要書類の準備と退職手続き
雇用契約解除に関する通知書や、社会保険・雇用保険関連の届け出書類を準備します。退職日までに貸与物の返却、業務の引継ぎ、最終給与の支払い、有給休暇の消化を完了させましょう。
雇用契約解除通知書の作成方法
雇用契約を解除する際は、契約解除通知書を交付することをおすすめします。文書として残すことで、契約解除の事実と理由を明示し、労働者に正式に通知することが可能です。万一、のちに労務トラブルに発展した場合も、正当性を示す証拠資料として重要な役割を果たします。
通知書に記載する項目
契約解除通知書に決まった様式はありませんが、契約解除に関する内容は網羅しておく必要があります。以下の事項は必ず明記しましょう。
- 解除する契約名
- 解除の理由
- 解除する日付(解除するまでの猶予期間)
- 解除に関する法的根拠
- 退職手続きに関する事項
雇用契約解除の理由については、客観的に合理的な理由であることを明確に示すことが重要です。勤務態度に問題があるからといって、使用者の主観に基づいて安易に労働者を解雇すると、訴訟に発展するおそれがあるため注意しましょう。
通知書の作成・交付のポイント
雇用契約解除通知書を交付する際のポイントは、以下のとおりです。
- 書面交付を原則とし、口頭のみの通知は避ける
- 労働者に内容を説明し、確認の署名をもらう
- 主観的な表現やあいまいな理由は書かない
- 客観的事実に基づいて記載する
- 通知書は企業側で控えを保管し、発行日・交付日を明確に残す
書面では感情的な表現を避け、事実と法的根拠に基づいた冷静な記述を心がけましょう。
労働者との信頼関係を維持しつつ、法的リスクを最小限に抑えることが重要です。
雇用契約解除を従業員から申し出られた場合
従業員から雇用契約解除の申し出があった場合は、意思を尊重して対応します。ただし、有期契約の場合は、介護や病気など「やむを得ない事由」がなければ、契約途中での解除は認められません。
退職の意思表示は口頭でも有効ですが、日程や理由を明確にするために退職届を提出してもらうのが望ましいでしょう。
期間の定めがない契約では、申し出から2週間後に退職が成立します(民法627条)。就業規則に「1か月前までに申し出ること」と定めていたとしても、法律では2週間前の申し出で足りるため、会社が2週間より前の申し出を強制できません。
退職日が決まったら、会社は貸与物や健康保険証の返却、最終給与の処理などを進めます。
離職票の区分(自己都合・会社都合)を誤らないように案内することも大切です。
雇用契約解除時に注意したいポイントとトラブル防止策
雇用契約を解除するときは、法的な要件を満たすだけでなく、トラブルを未然に防ぐための配慮も欠かせません。雇用契約解除の際に、おさえておきたいポイントを解説します。
契約解除理由を明確にする
雇用契約解除には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの条件が必要です。理由があいまいだったり、経営者の主観に偏っていたりすると、不当解雇と判断されるおそれがあります。
就業規則に解雇事由が定められているか、またその内容が合理的かを確認しましょう。たとえば「勤務態度不良」を理由にする場合は、いつ・どのような行動があったのかを記録しておくことが大切です。
また、解雇理由証明書を交付する際は、就業規則の該当条文と具体的な事実を明記します。一度発行すると、理由の追加や変更は原則できません。誤りのないよう慎重に作成しましょう。
契約解除は書面で通知する
解雇の通知は口頭でも可能ですが、将来のトラブル防止のためには書面で通知するのが基本です。書面を交付するときは、受け取りを証明できるようサインや日付も書いてもらいましょう。もし受領を拒否される可能性がある場合は、内容証明郵便で送付するなどの対策をします。
解雇は最終手段とする
いきなり雇用契約解除に踏み切る前に、まずは退職勧奨を検討します。本人と面談し、会社としての考えや理由を伝えたうえで、退職届の提出を促す方法です。本人の同意を得られれば、不当解雇のリスクを減らせます。
また、経営上の理由による整理解雇を行う場合は、次の4要件を満たす必要があります。
- 人員削減の必要性がある
- 解雇を避ける努力をしている(経費削減・配置転換・希望退職の募集など)
- 解雇対象者の選定が合理的である
- 労使間で誠実な協議を行っている
専門家にも相談する
解雇や契約解除は、判断を誤ると大きな法的リスクがあるため、次のような場合は、弁護士など専門家への相談をおすすめします。
- 解雇理由の正当性に不安がある
- 従業員との交渉が難航している
- 紛争に発展しそうなケース
日本の法律では、解雇の有効・無効を明確に線引きする基準がなく、過去の判例をもとに判断されます。そのため、事前に専門家へ相談し、リスクを把握したうえで対応を決めることが重要です。
また、解雇の正当性を裏づける証拠は、解雇前に確保しておく必要があります。解雇後に集めようとしても困難な場合が多いため、早い段階から弁護士の助言を受け、記録の残し方を整えておくと安心です。
雇用契約を解除するときの企業側の義務
雇用契約を解除する際、企業側には法律で定められた義務があります。重要なのが「解雇予告」と「解雇予告手当」の支払いです。
解雇予告
企業が従業員を解雇する場合、30日前までに予告するか、もしくは30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)必要があります(労働基準法第20条)。
通知は口頭でも有効ですが、書面による「解雇予告通知書」**を交付するのが安全です。
通知書には以下の内容を明記します。
- 従業員の氏名
- 解雇日
- 解雇理由
- 就業規則の該当条項
交付時は、本人の署名をもらうか、受け取りを拒否された場合は内容証明郵便で送るなど、確実に記録を残しましょう。
解雇予告手当の計算方法
解雇予告をしない、または30日未満しか期間がない場合は、不足日数分の手当を支払います。計算式は次のとおりです。
| 解雇予告手当 = 不足日数 × 平均賃金 |
平均賃金は、直近3か月の賃金総額 ÷ 総日数で算出します。即時解雇なら解雇と同時に、予告と併用する場合は解雇日までに支払わなければなりません。
なお、勤続3か月未満の従業員や試用期間中は、計算から除外できるケースもあります。給与記録を確認し、正確に処理しましょう。
雇用契約解除に関するよくある質問
最後に、雇用契約解除に関して、よく寄せられる質問について回答を解説します。
契約解除通知書は必ず必要ですか?
法的には必須ではありませんが、書面で残すことをおすすめします。口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、 契約終了の意思を明確に記録しておくことが大切です。
なお、双方が合意のうえで契約を解除する場合は、書面がなくても無効にはなりませんが、
万が一の争いに備えて、合意内容を簡単な書面やメールで残しておくと安心です。
自己都合退職と会社都合解除の違いは?
退職の原因がどちらの意思によるものかで区別されます。
- 自己都合退職:転職・家庭の事情・健康上の理由など、本人の意思による退職
- 会社都合退職:経営悪化・リストラ・倒産など、会社側の事情による退職
懲戒解雇は「解雇」ではありますが、雇用保険上は自己都合扱いとなるケースもあります。
一方、会社都合退職は失業給付の待機期間が短く、給付日数も長くなる点が特徴です。
30日未満の予告期間の場合、罰則はありますか?
労働基準法第20条では、30日前の予告または30日分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いを義務づけています。いずれも行わずに解雇すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、解雇予告手当は遅くとも解雇日までに支払わなければなりません。遅延した場合は損害金が発生することもあるため、支払期日には注意しましょう。
有期契約でも途中解除できますか?
原則として、有期契約の途中解除はできません。「やむを得ない事由」がある場合に限り、例外的に認められます。
たとえば、会社側では経営危機や事業縮小など、労働者側では健康悪化や家庭の重大な事情などが該当します。
「やむを得ない事由」は、正社員の解雇よりも厳しく判断されます。「少し働きぶりが悪い」などの理由では認められず、契約を続けることが事実上困難なほどの事情が必要です。
労働者側も同様で、自己都合での途中退職は原則できません。ただし、契約期間が1年を超える場合は、開始から1年経過後であれば、理由を問わず退職が可能です。
まとめ
雇用契約の解除は、企業にとって慎重な判断が求められる手続きです。
労働契約法や労働基準法などに基づき、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ無効とされる可能性があります。
また、解雇を行う際には、事前の予告や説明、書面による通知といった手続きを正しく踏むことが不可欠です。
不当解雇と判断されれば、企業の信用や法的責任に大きな影響を与えます。労務トラブルを防ぐためには、指導・改善の記録を残し、誠実な説明と手続きで対応することが重要です。
雇用契約書の作成・管理を一元管理できると、法令遵守と業務効率化を両立できるでしょう。