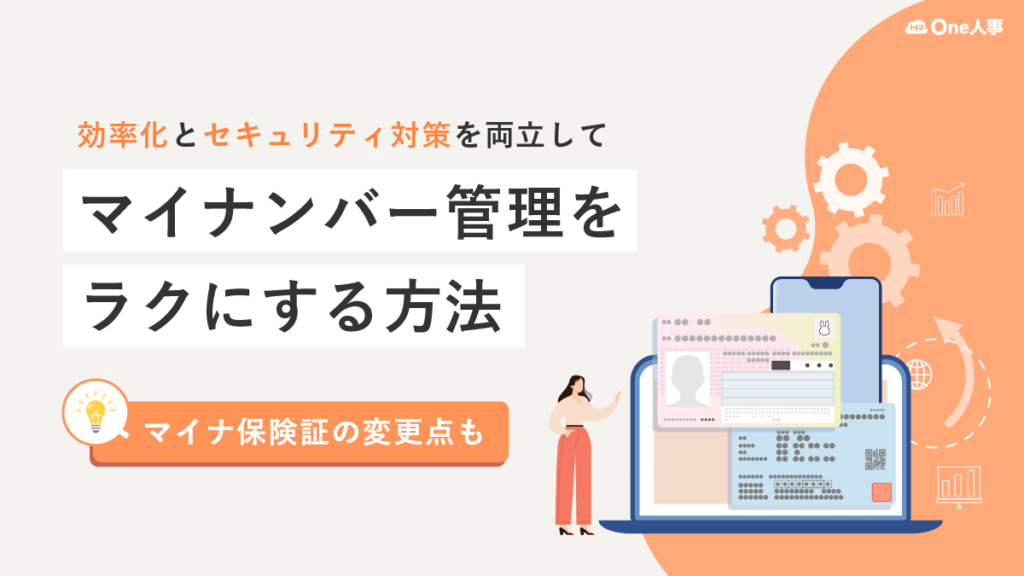雇用保険の住所変更は必要? 各種保険や税などの変更手続きについても解説
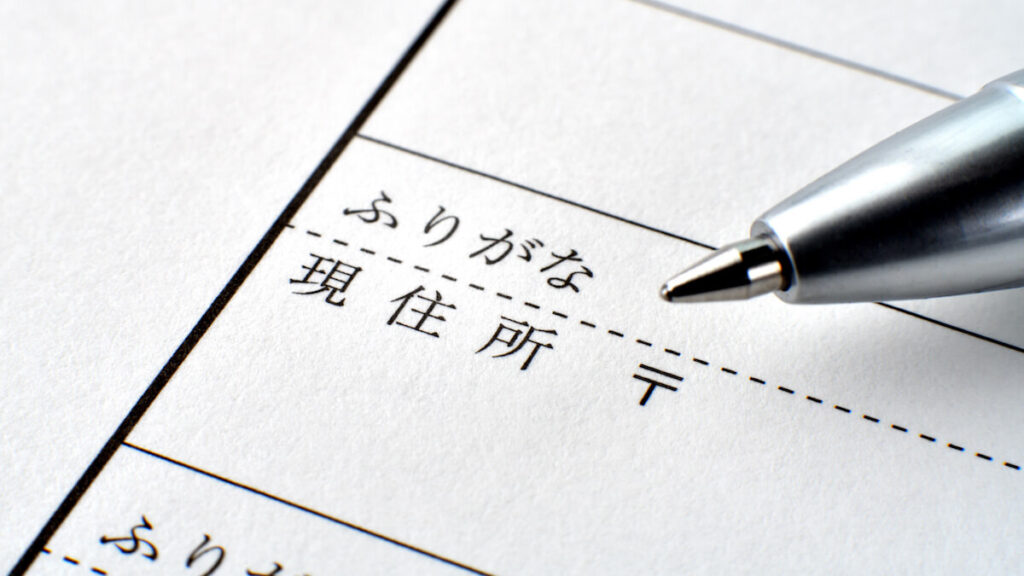
従業員を1人でも雇用している企業は、原則的に雇用保険への加入義務があります。
各種保険においては加入後にもさまざまな手続きを行いますが、従業員が引っ越した場合、住所変更の届出は必要なのでしょうか。雇用保険を含む各種保険は制度によってルールが異なるため、住所変更が必要なのか不明なケースも多いでしょう。
本記事では、雇用保険の基本的な仕組みから企業が行うべき手続き、住所変更の必要性まで網羅的に解説します。企業で各種保険の手続きを担当している方は、ぜひ参考にしてください。

 目次
目次
雇用保険の概要についておさらい
雇用保険の住所変更を解説する前に、まずは雇用保険制度についておさらいしましょう。また、企業と従業員における雇用保険の加入条件をそれぞれ解説します。
雇用保険とは
雇用保険とは、雇用にまつわる多種多様な支援を提供する公的保険制度です。広義では社会保険の一つとして数えられますが、狭義の社会保険には含まれません。労災保険とあわせて「労働保険」として区別されます。
雇用保険に加入している場合には、就労や雇用継続に関するさまざまな給付を受けられます。たとえば、失業中の求職者に支給される「基本手当」が雇用保険における給付の代表例です。
失業や休業など、雇用にまつわるリスクを軽減できる雇用保険は、企業と従業員それぞれにとって重要な保険です。
雇用保険の対象となる企業
雇用保険は、国が実施する強制保険制度の一種です。
従業員を1人でも雇用する企業は、原則的に雇用保険への加入が義務付けられています。従業員を雇い入れた場合は、企業の責任において速やかに手続きを行いましょう。
なお、例外として、常時雇用している従業員が5人未満である個人経営の農林水産業は、暫定任意適用事業として任意加入が認められています。

雇用保険の対象となる従業員
以下の条件を満たす従業員は、雇用保険の加入対象です。
- 31日以上雇用される見込みがあること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと(例外あり)
基本的に学生は雇用保険の被保険者とはなりません。しかし、定時制高校や大学の夜間学部に通う学生、休学中の学生などは、学生であっても雇用保険の被保険者です。
被保険者についてはほかにもさまざまなルールがあるため、詳しくは厚生労働省が公表している資料をご確認ください。

企業が従業員の現住所の把握が必要な場合
企業が従業員を雇用するにあたって、現住所の把握が必要な場合を解説します。
- 総務部門の業務
- 通勤手当の支給
- 従業員の安否確認
総務部門の業務
企業の総務部門は、社会保険や雇用保険などの各種手続きを担当しています。手続きには従業員の住所を記入しなければならない場面も多く、現住所を正確に把握することが必要です。
通勤手当の支給
多くの企業は、従業員の通勤にかかる費用を補助するため「通勤手当」を支給しています。通勤手当の金額を正確に計算するためには、従業員の現住所の情報が必要不可欠です。万が一、住所の情報が誤っていたら、支給額に過不足が生じるおそれがあります。
従業員の安否確認
企業は、災害時に従業員の安否確認を行います。休日でオフィスにいない従業員に連絡がつかない場合、自宅を訪問することもあります。そのようなとき、現住所の情報が誤っていたら、企業に課せられた安全配慮義務を果たせなくなってしまいます。
雇用保険に関する企業の手続きや書類
雇用保険に関する手続きは、事業主の責任において行う義務があります。従業員の入退社時や雇用形態の変更時に必要な手続きを紹介します。
入社時に必要な手続き・書類
雇用保険の加入手続きは「従業員を雇用した日」または「雇用保険の加入要件を満たした日」が属する月の翌月10日までに行うよう定められています。つまり、従業員の入社時の手続きは、入社日から起算して翌月10日までに実施します。
その際、必要となるのが「雇用保険被保険者資格取得届」です。従業員の氏名や個人番号(マイナンバー)、資格取得年月日などの必要事項を記入し、管轄のハローワークへ提出しましょう。
届出が受理されると以下2点の書類が交付されるため、従業員へ直接渡します。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険資格取得等確認通知書
退職時に必要な手続き・書類
従業員が退職する際は、以下2点の書類を管轄のハローワークへ提出します。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
上記の提出期限は、被保険者資格を喪失した日の翌日から10日以内です。被保険者資格は退職日の翌日に失われるため「従業員が退職した日の翌々日から10日以内」と覚えておきましょう。
なお、雇用保険被保険者離職証明書(以下、離職証明書)は、基本的には失業給付の受給申請に用いられます。退職者の転職先が決まっている場合は失業給付の手続きを必要としないため、離職証明書の提出も不要です。(一部例外を除く)
雇用形態の変更に必要な手続き・書類
雇用保険の加入条件には「週の所定労働時間」が含まれます。
労働時間の変動によって、新たに雇用保険の適用条件を満たすケースもあれば、逆に適用範囲から外れるケースもあるでしょう。従業員の雇用形態が変わることで労働時間が増減した場合は、雇用保険の加入条件を満たしているかどうか、あらためて確認することが大切です。
雇用形態の変更によって雇用保険が適用される場合は、すみやかに加入手続きを行いましょう。
また、反対に雇用保険の適用外となる場合は、所定労働時間が週20時間未満となった前日に離職したとみなして手続きを行います。退職や役員への昇格時と同様に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークへ提出しましょう。
なお、育児や介護などで労働時間の変更が臨時的・一時的(おおむね6か月以内)に変更となる場合、資格喪失手続きは不要です。
参照:『事業主が行う雇用保険の事務手続に係る取扱いの変更について』東京労働局
企業が必要な手続きを怠ると、雇用保険法第83条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、場合によっては、雇用保険料の追徴金や延滞金の納付が求められることもあるでしょう。

最新の雇用保険の保険料率
保険料率とは、社会保険の計算に用いられる基礎数値です。雇用保険の保険料率は定期的に見直しが行われており、上がるときもあれば、下がるときもあります。
企業で雇用保険料の計算を担当している方は、常に最新の保険料率を把握することが大切です。以下の表では、2025年度(2025年4月1日から2026年3月31日)までの雇用保険料率を整理しています。
| (1)労働者負担 | (2)事業主負担 | (1)+(2)雇用保険料率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (2)事業主負担の合計 | 失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | |||
| 一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 5.5/1,000 | 3.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業※ | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 6.5/1,000 | 3.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 6.5/1,000 | 4.5/1,000 | 17.5/1,000 |
出典:『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』厚生労働省
雇用保険料率は事業内容によっても異なるため注意しましょう。
雇用保険を含む住所変更が必要なものと不要なもの
従業員の引っ越しにともなう住所変更の必要性は、制度によって異なります。従業員から住所変更の報告を受けた際に的確な対応をとれるよう「住所変更が必要なもの」「住所変更が不要なもの」を把握しておきましょう。
雇用保険の住所変更手続きについて
雇用保険の場合、従業員の住所が変更になっても特別な手続きは必要ありません。
なお、失業給付は「居住地の管轄のハローワーク」でしか受給申請ができないため、以下の条件を満たす場合は住所変更が必要です。
- 離職後の引っ越しが決定している
- 退職者本人が希望している
退職者に離職票を発行する際は、引っ越し予定の有無について事前に確認をとりましょう。
社会保険の住所変更の手続きについて
健康保険や厚生年金保険などの社会保険関連の場合、従業員の住所変更があった際には迅速な手続きが求められます。
なお、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている従業員は、住民票を移すと社会保険の登録情報も自動で更新されるため、企業側の手続きは不要です。
ただし、以下のような理由から、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられていない可能性も考えられます。
- 前住所から住民票を移動させていない
- 海外赴任などによりマイナンバーが付与されていない
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない従業員は「マイナンバー未収録者一覧」として企業に共有されるため、該当者に関する手続きには十分注意しましょう。
労災保険の住所変更手続きについて
労災保険は「国と企業」の間で保険関係が成立しており、保険料の全額を企業が負担します。そのため、基本的には従業員の住所変更は不要です。
ただし、企業で加入している損害保険や傷害保険などでは住所変更が必要な場合もあるため、別途保険会社に確認しましょう。
住民税と所得税の住所変更手続きについて
従業員に課せられる住民税は、まず毎月の給与から天引きするかたちで徴収されます。そして毎年1月1日に、居住していた自治体に対して1年分を全額納付する仕組みです。
所得税については、年の途中で住所が変わった場合、企業が「給与支払報告書」を1月1日時点で居住していた自治体に提出します。
年末調整を行う際は、給与所得者の「扶養控除等申告書」に新住所を確実に記載しましょう。税務の手続きにおいては、納税先と居住地を合致させることが重要です。
住所変更が必要なケースを把握し、迅速に対応しましょう
雇用保険においては、従業員の住所変更手続きは原則不要です。
ただし、離職票を発行する場合など、例外的に住所変更が必要になるケースもあります。そのほか、住所変更の必要性は制度によって異なるため、手続きが必要なケースを的確に把握しておきましょう。
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。従業員の入退社手続きや年末調整の効率化を実現し、担当者の負担を軽減することで、人材活用の基盤をつくります。気になる費用や操作性は、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。