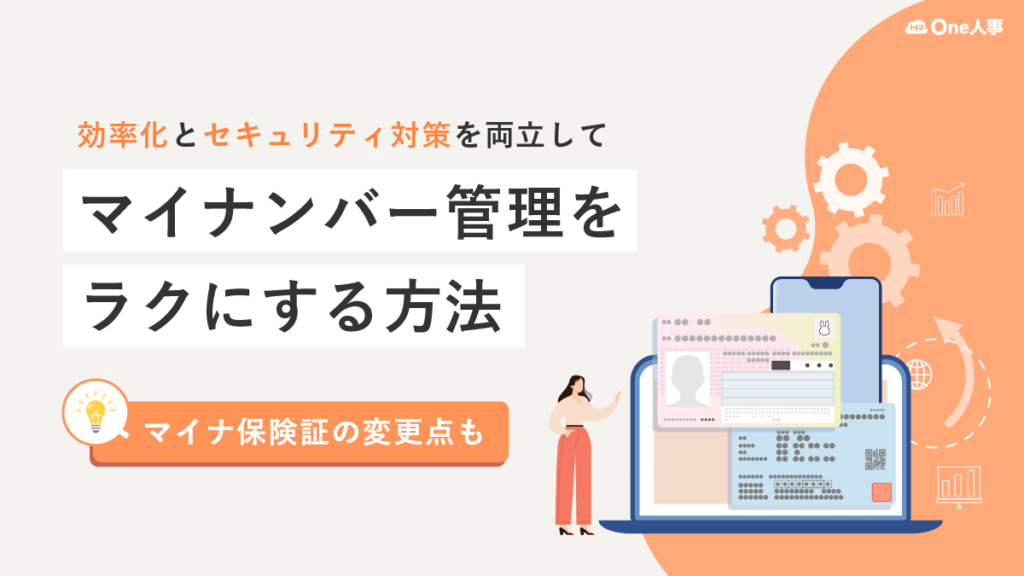雇用保険手続きにマイナンバーは必須? 拒否・ない場合の対応と被保険者番号の確認方法も解説
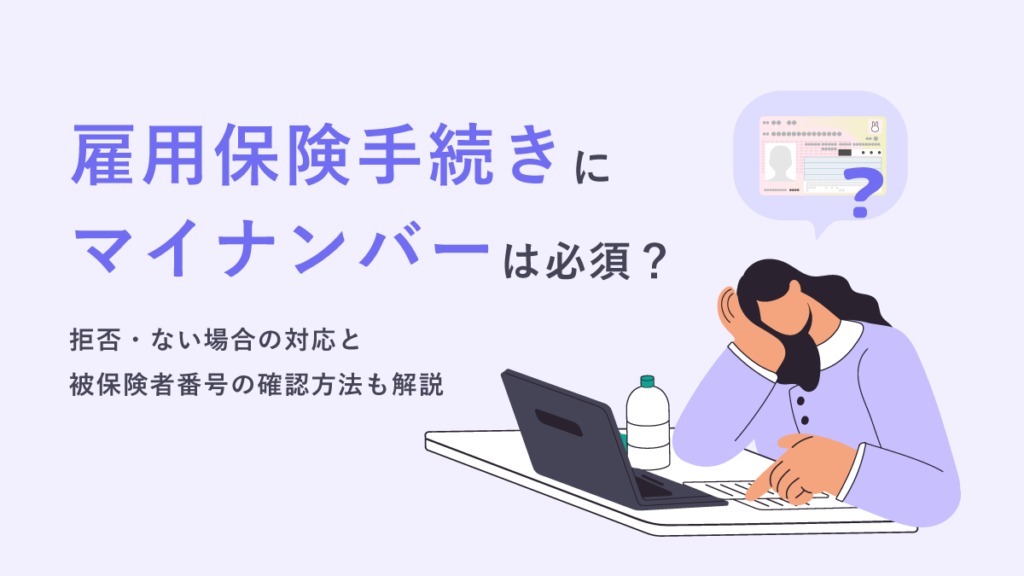
従業員に雇用保険のマイナンバー提出を求めたら、「拒否された」という場面ではどのように対応すればいいのでしょうか。
2022年1月から雇用保険の手続きにマイナンバーの記載が義務化され、企業の人事労務担当者も対応が求められています。しかし、従業員から「提出したくない」「マイナンバーを会社に渡すのは不安」といった声が上がることもあります。
では、会社へマイナンバーの提出は本当に必須なのでしょうか。 また、提出を拒否された場合、会社はどのように対応すればいいのでしょうか。
本記事では、人事労務担当者が知っておきたい「マイナンバーの提出義務の有無」「必要な理由」「未提出時の対応策」「代替手段」について解説します。記事を読めば、マイナンバーの取り扱いに関する疑問が解消され、スムーズに雇用保険の手続きを進めることができるようになります。
▼雇用保険手続き全般に不安がある方は以下の資料もぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
雇用保険手続きにマイナンバーは必要?
従業員の雇用保険の加入手続きでは、それぞれのマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての人に割り当てられた、個人を特定する12桁の番号です。
たとえば、『雇用保険被保険者資格取得届』や『雇用保険被保険者資格喪失届』などには、マイナンバーの記載欄が設けられています。また、『雇用継続交流採用終了届』や『雇用保険被保険者転勤届』のようにマイナンバーの記載欄がない書類でも、別途『個人番号登録・変更届』の添付が必要になることもあります。
マイナンバーの記載がない場合は、不備があるとして再申請を求められる可能性もあるため、担当者は十分に注意が必要です。
雇用保険の加入手続きをおさらいするには以下の記事をご確認ください。
マイナンバーを記載しなければならない雇用保険手続き
申請書類に記載欄がある場合は、手続きのたびにマイナンバーを記載しなければならないと思われるうかもしれません。
しかし、雇用保険資格取得届を除き、届け出の対象となる従業員が別の届け出の際に、すでにマイナンバーを提出していれば、記載を省略できます。
マイナンバーの記載を省略する場合は、各種届出書の欄外などに「マイナンバー届出済」と記載します。電子申請の場合は欄外がないため、備考欄に記載しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届には備考欄がないので、社会保険労務士欄の直下のスペースに記載します。
個人番号登録・変更届の添付が必要な書類については、すでにマイナンバーを届け出ている場合は記載を省略できます。その場合、「マイナンバー届出済」の記載も不要です。
マイナンバーを記載しなくてもよい雇用保険手続き
雇用保険の対象となる従業員を初めて雇用する際の『雇用保険被保険者資格取得届』については、マイナンバーの記載を省略できません。
また、ハローワーク側でマイナンバーがすでに届け出られていることを確認できなかった場合は、再申請を求められます。マイナンバーを届け出のうえ、再度申請書を提出しましょう。
参照:『雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
参照:『雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
参照:『雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A』厚生労働省
参照『平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
雇用保険とマイナンバーが紐づけされる理由
マイナンバーは、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)』により、利用範囲が厳しく制限されています。
雇用保険については、番号法第9条と別表第1において、雇用保険の資格取得や確認、給付手続きでマイナンバーを使うことが定められています。
つまり法律によって、雇用保険の手続きでマイナンバーを利用することが明確に決められているのです。
また、雇用保険法第7条・第82条をもとに定められた『雇用保険法施行規則』により、各種手続きに使う書類の様式が決められています。そのため、マイナンバーの記載欄がある書類については、様式に沿ってマイナンバーを記載しなければなりません。
雇用保険番号とマイナンバーを紐づけると行政手続きが簡素化できる
マイナンバー制度は個人番号を目印として情報を連携することで、社会保障や税金に関する手続きを簡単にすることを目的としています。
雇用保険の手続きでも、雇用保険被保険者番号とマイナンバーを結びつけ、行政事務を効率化し、手続き対応の負担軽減が可能です。
具体的には、国民健康保険料(税)の減免手続きや介護休業給付の申請では、添付書類を省略できるといったメリットがあります。
雇用保険情報とマイナンバーは、年金情報のように自動で紐づけられないため、こうしたメリットを受けるためには、別途手続きが必要なのです。
参照:『雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A』厚生労働省
雇用保険手続きでマイナンバーの記載が必要な場面
マイナンバーの記載欄があり、手続きの都度、マイナンバーの記載が必要なのは以下の書類です。
| 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号) | 雇用保険の被保険者資格を持つ従業員を雇用したときに提出する書類 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号) | 退職や役員への昇格などにより、従業員が被保険者ではなくなったときに提出する書類 |
| 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3) | 雇用保険の被保険者が60歳に達し、高年齢雇用継続給付を申請する際に提出する書類 |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5) | 雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、育児休業給付を申請する際に提出する書類 |
| 介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6) | 雇用保険の被保険者が介護休業給付を申請する際に提出する書類 |
雇用保険資格取得届を除いて、対象となる従業員が届け出の際に、すでにマイナンバーを提出していれば、「マイナンバー届出済」と記載することで記載を省略できます。
参照:『事業主の皆様へ 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします』厚生労働省
参照:『雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
別途『個人番号登録・変更届』の添付が必要な場面
マイナンバーの記載欄はないものの、別途『個人番号登録・変更届』の添付が必要なのは以下の書類です。
| 雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2) | 被保険者が、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員ではなくなったときに提出する書類 |
| 雇用保険被保険者転勤届(様式第10号) | 被保険者が同一事業主の別の事業所に転勤したときに提出する書類 |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2) | 高年齢雇用継続給付を2回目以降に申請する際の書類 |
| 育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2) | 育児休業給付を2回目以降に申請する際の書類 |
対象となる従業員が届け出の際に、すでにマイナンバーを提出していれば、マイナンバーの記載を省略でき、「マイナンバー届出済」という記載も不要です。
参照:『被保険者についての諸手続き』厚生労働省福島労働局
参照:『雇用継続交流採用終了届』厚生労働省
参照:『高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
マイナンバーを記載した雇用保険手続きの提出方法
雇用保険手続きでマイナンバーの記載が必要な場合、個人情報の漏えいを防ぐため、電子申請が推奨されています。
事情があってどうしても郵送したい場合は、普通郵便ではなく、厳重に取り扱われる「書留郵便」を利用するのが原則です。
電子申請をする際は、行政手続きのオンライン申請サービス『e-Gov』 を利用します。e-Govで電子申請を行うには、以下のいずれかが必要です。
- 『Gビズ』のID 1つのIDで複数の行政サービスを利用できる認証システム)
- 電子証明書(オンライン上での押印やサインの代わりとなるもの)
電子証明書は、紙の書類でいう「印鑑証明」のような役割を持ち、オンライン申請の際に本人確認を行うために使われます。
雇用保険関係手続きの電子申請の詳しいやり方については、以下の関連記事をご確認ください。
雇用保険手続きでマイナンバーがない場合・提出を拒否された場合
雇用保険の手続きでは、マイナンバーの提出が法律で義務づけられています。従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合は、「法律で定められた手続きであること」を説明し、理解を求める必要があります。
しかし、かたくなに従業員が提出を拒否する場合は、「提出を拒否された」旨を申し出れば、マイナンバーが未記入・空欄でも手続きは受理されます。企業にはマイナンバーの届出義務がありますが、従業員には提供を強制できないためです。
マイナンバーを提出できない場合の処理方法
電子申請をする場合は、備考欄に「本人の事情によりマイナンバー届出不可」と入力して提出します。「雇用保険被保険者資格喪失届」には備考欄がないため、社会保険労務士欄の下のスペースに記載します。
ただし、マイナンバーの届出は原則として必要であり、事業主の義務でもあるため、できるだけ従業員に納得してもらえるようていねいに説明しましょう。
参照:『雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
参照:『雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
参照:『雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A』厚生労働省
雇用保険手続きにともなうマイナンバー回収・管理方法
マイナンバーは重大な個人情報のため、徹底した管理が必要です。
回収時の注意点
従業員からマイナンバーを提出してもらうには、「何のために使うのか」を明示したうえで回収することが大切です。たとえば、雇用保険の手続きに使用するのであれば、目的を従業員に周知してから提出を依頼しましょう。
また、マイナンバーを受け取る際は、なりすましを防ぐための身元確認が義務づけられています。
【マイナンバーカードあり・なしによる身元確認の方法】
- あり→マイナンバーカードの提示で確認
- なし→個人番号通知書+本人確認書類(運転免許証など)のセットで確認
▼マイナンバーの回収・管理方法に不安がある場合は以下の記事もご活用ください。
保管の注意点
提出されたマイナンバーは、盗難や漏えいが起こらないように施錠管理が厳重な場所で、管理する必要があります。また、必要なときにすぐ確認できる方法で保管しなければなりません。
主な管理方法として、以下の2つがあります。
- 書類やメールで提出→紙で管理・保管
- 労務管理システムで登録→システムで管理・保管
しかし、紙はかさばるので保管場所の確保に困る可能性があり、必要な情報を探すのにも時間がかかります。
一方、労務管理システムなら保管のためのスペースは必要なく、すぐさま情報を探し出せます。
セキュリティ対策が充実したシステムを利用すれば、盗難や漏えいのリスクを抑えられるため、安全な管理方法としておすすめです。
One人事[労務]は、マイナンバー管理にもお役立ていただける労務管理システムです。マイナンバーの取得、利用、廃棄を一括管理し、情報漏えいや不正利用の防止にお役立ていただけます。詳しい機能はサービス紹介資料をご確認ください。
▼万一、漏えいしたらどうなる?と思ったら以下の記事でご確認いただけます。
マイナンバーを通して雇用保険番号はわかるのか? 確認方法
すでに雇用保険とマイナンバーの紐づけが完了している場合、従業員は『マイナポータル』から雇用保険被保険者番号や手続き履歴を確認できます。
【確認方法】
- マイナポータルにログイン
- 「あなたの情報」をクリック
- 分野で「社会保障(雇用・労働)」を選択
- 分野詳細で「雇用」を選択
雇用保険に関するさまざまな情報の閲覧が可能です。ただし、マイナポータルにログインするためには、マイナンバーカードを発行している必要があります。
参照:『マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!』厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
マイナンバーと雇用保険番号が紐づけされている場合、「マイナポータル」から雇用保険被保険者番号や手続き履歴を確認できます。
マイナンバーの回収・管理、雇用保険の申請を効率化するには?
雇用保険関係の手続きでは、多くの書類にマイナンバーの記載欄が設けられています。
被保険者のマイナンバー届け出は、法律に定められた企業の義務です。一部、記載を省略できる届け出もありますが、その場合でも「マイナンバー届出済」と記載するといった注意点があります。
また、従業員から提出を拒否された場合でも、法律で定められた規則であることを十分に説明し、理解を求めることが大切です。
マイナンバーの回収・管理や雇用保険手続きを効率化するなら、労務管理システムの導入がおすすめです。紙での管理に比べて保管スペースの確保が必要なく、情報の検索性や機密性も向上します。専用システムなら従業員の大切な情報を安全に効率的に管理できるでしょう。
労務管理の効率化に|One人事[労務]
One人事[労務]は、入退社にともなう従業員情報の回収・管理や行政手続きを支援する労務管理システムです。安全なマイナンバーの回収・管理にもお役立ていただけます。
また『e-Gov』との連携により、各種雇用保険事務のペーパーレス化を実現し、手続きの効率化を実現できます。
「One人事」で実現できることや活用方法は、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。貴社の課題にあわせて、部分的な導入もご相談が可能です。
当サイトではサービス紹介資料のほか、人事労務のノウハウに関するお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。人事労務管理に課題がある企業はお気軽にお申し込みください。