雇用保険と社会保険の4つの違い【比較表】目的や加入条件から解説|パートは片方加入でもOK?
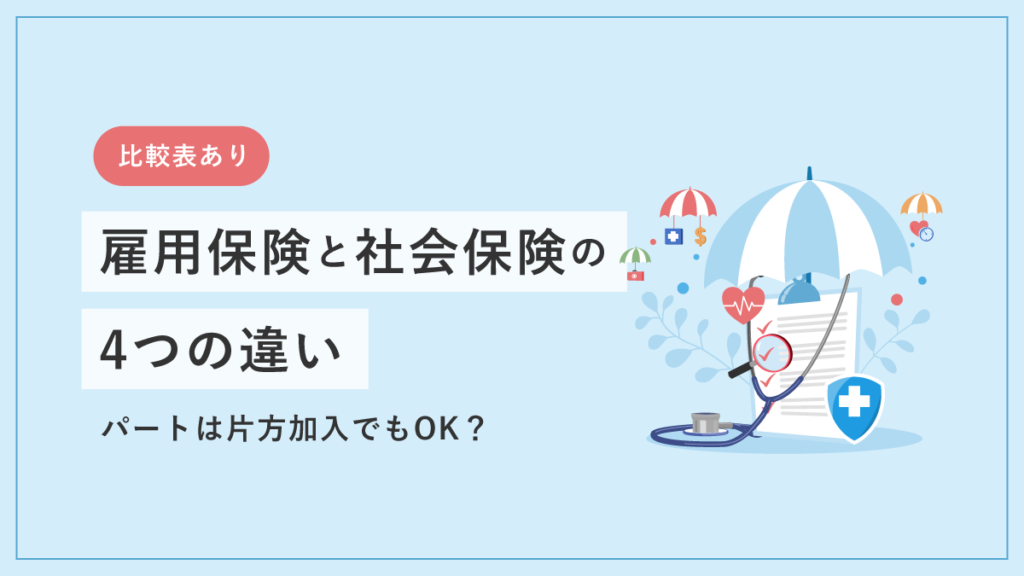
雇用保険や社会保険は、どちらも私たちの生活を支える公的保障制度です。企業は一定条件を満たす従業員を雇用保険や社会保険に加入させる義務がありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
本記事では、雇用保険と社会保険の違いを4つのポイントで解説します。加入が必要な条件も詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
 目次[表示]
目次[表示]
雇用保険は主に失業・休業リスクに対して生活を保障する
雇用保険とは、失業者の生活の保障や、雇用安定をはかるための公的保険制度です。失業または休業中の労働者に対し、給付金やハローワークでの就職支援などを通じて再就職をサポートします。
たとえば、労働者の状況に応じて次のような給付金が支給されます。
| 基本手当 | 失業中の生活が保障される |
|---|---|
| 技能習得手当 | 公共職業訓練を受けるときに支給される |
| 育児休業給付 | 子どもが生まれて育児休業を取得すると受け取れる |
| 介護休業給付 | 家族の介護のために休業を取得すると受け取れる |
また、従業員の雇用継続が困難な企業や労働者のキャリアアップを支援することも雇用保険の目的の一つです。雇用保険は、業務中のケガや病気などを保障する労災保険と合わせて「労働保険」と呼ばれることもあります。
企業は、雇用保険の加入条件を満たす従業員を1人でも雇用していると、管轄のハローワークに「雇用保険事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
保険料は企業と従業員の双方が負担し、それぞれの保険料率に応じた金額を支払います。

社会保険は主に健康・高齢リスクに対して生活を保障する
社会保険とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つの保険制度の総称です。
| 健康保険 | 病気やけがで病院を受診する際、自己負担額を1~3割に抑えられる制度 |
|---|---|
| 介護保険 | 40歳以上の従業員が対象。将来介護が必要になったときに、さまざまな介護支援にかかる自己負担額を抑えられる制度 |
| 厚生年金保険 | 会社勤めの人を対象とした公的年金制度。全国民が加入する国民年金に上乗せで納付し、老後に年金を受け取れる 病気やケガで障害を負ったときの「障害年金」や、加入者の死亡時に遺された家族に支給される「遺族年金」も含まれる |
狭義の社会保険は健康保険・介護保険・厚生年金保険を指す言葉ですが、広義では労働保険も社会保険に含まれます。(※本記事では、断りがない限り、狭義の社会保険と労働保険を区別して解説します。)
社会保険は、病気や加齢にともなう身体の衰え、収入減などに備えるための制度です。
日本では国民皆保険・国民皆年金を採用しているため、すべての国民に加入が義務づけられています。会社勤めの人は健康保険や厚生年金保険、自営業者や個人事業主などは国民健康保険や国民年金に加入するのが一般的です。
また、すべての法人は社会保険の強制適用事業所であり、雇用する従業員がいなくとも社会保険に加入する義務があります。3つの社会保険の保険料は、企業と従業員が半分ずつ負担する仕組みです。

雇用保険は広義の社会保険に含まれる
広義では労働保険も社会保険に含まれるため、労働保険である雇用保険も社会保険の一つと考えられます。
| 広義の社会保険 | 狭義の社会保険 | ・健康保険 ・介護保険 ・厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 労働保険 | ・雇用保険 ・労災保険 |
労務担当者は業務で社会保険を扱うことが多いため、それが広義と狭義のどちらを指すのか、都度整理する必要があるでしょう。
雇用保険と狭義の社会保険の4つの違い【比較表】
雇用保険と社会保険は、どちらも私たちの生活を支援する制度です。各種保険制度の加入者となれば、病気やケガ、身体の衰え、失業など、人生におけるさまざまなリスクに備えられます。
ただし、雇用保険と社会保険は制度としての根本的な目的や保障内容が異なり、対象者や加入条件にも違いがあります。
雇用保険と社会保険の違いは、主に以下の4つです。
| 雇用保険 | 狭義の社会保険 | |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の生活維持や再就職支援 | 病気やケガなどのリスクに備え、生活の安定をはかる |
| 保障内容 | 失業・休業中の生活支援 | 医療費や介護費の支援、年金支給 |
| 保険対象者 | 労働者に対する保障という性格が強い | すべての国民に対する保障という性格が強い |
| 加入条件 | 厳しい | 比較的易しい |
目的の違い
雇用保険の目的は、失業中の求職者や、育児・介護などで休業中の人の生活を支援することです。また、雇用の安定化をはかり、失業者に対しては再就職に向けたサポートを行います。
一方、社会保険は病気やケガ、老齢などのあらゆるリスクに備え、誰もが健康的で安定した生活を送れるよう支援することを目的としています。
保障内容の違い
雇用保険の保障内容は、失業中や休業中の人への給付金が中心です。それぞれの状況に合わせて申請できる多様な給付金が用意されています。
一方、社会保険は医療費や介護費の負担軽減、老齢にともなう収入減に備えるための年金支給などが主な保障内容です。
保険対象者の違い
雇用保険は、企業に使用される労働者のうち一定条件を満たす人を対象としています。
一方、社会保険は雇用の有無にかかわらず、全国民に対する保障という性格が強いです。省庁が統合される前は、厚生省が管轄していたことも影響しているでしょう。
日本では国民皆保険・国民皆年金が採用されているため、すべての人に対していずれかの形式で加入が義務づけられています。
加入条件の違い
雇用保険はすべての労働者を対象とするわけではなく、加入するためには一定の条件を満たす必要があります。
なお、狭義の社会保険にも加入条件が設けられており、健康保険や厚生年金保険に加入するためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。しかし、それらの条件を満たさない人も、国民健康保険や国民年金には加入できます。
社会保険は基本的にすべての人が加入しますが、雇用保険は人により加入しない場合があると覚えておきましょう。
雇用保険と狭義の社会保険の加入条件
雇用保険と社会保険には、一定の加入条件が設けられています。加入条件は事業所・労働者それぞれに設定されているため、企業は自社と雇用する従業員が条件を満たしているか把握し、適切に手続きを行わなければなりません。
- 雇用保険に加入すべき事業所
- 雇用保険に加入すべき労働者
- 狭義の社会保険に加入すべき事業所
- 狭義の社会保険に加入すべき労働者
雇用保険に加入すべき事業所
個人経営の農林水産業などの一部例外を除いて、労働者を1人でも雇用している事業所は、規模や業種にかかわらず雇用保険に加入する義務があります。
参照:『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』厚生労働省
雇用保険に加入すべき労働者
労働者が以下の条件に当てはまる場合、企業は該当する従業員を雇用保険に加入させなければなりません。
- 31日以上継続して雇用されることが見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
参照:『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』厚生労働省
狭義の社会保険に加入すべき事業所
社会保険の加入条件を満たす事業所を適用事業所といい、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類に分けられます。
強制適用事業所とは、社会保険の加入が義務づけられている事業所のことです。一方、任意適用事業所とは、社会保険に任意で加入できる事業所を指します。
強制適用事業所として認められるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる事業所です。
- 常時5人以上の従業員を使用する事業所(農林漁業やサービス業などを除く)
- 常時、従業員を使用する国や地方公共団体、法人の事業所
株式会社や合同会社などの法人は、強制適用事業所に該当するため、多くの企業には社会保険の加入義務があるといえます。
一方、強制適用事業所の条件を満たさなくても、働く人の半数以上が希望するのであれば任意適用事業所として認められます。
任意適用事業所とは、強制適用事業所に該当せず、厚生労働大臣の認可により社会保険の適用を受けた事業所です。任意適用事業所の申請をするためには、従業員の過半数の同意が必要です。その後、認可を受けることで従業員は社会保険に加入します。
任意適用事業所の場合は、健康保険か厚生年金保険のどちらか一方のみに加入することも可能です。
狭義の社会保険に加入すべき労働者
社会保険の適用事業所で常用的に使用される労働者については、企業が社会保険に加入させる義務があります。そのため、基本的に正社員は社会保険の加入条件を満たすと考えてよいでしょう。(厚生年金保険は労働者が70歳に達するまで)
パートやアルバイトでも、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上ある人は社会保険の加入対象です。
また、特定適用事業所であれば、基準に満たない場合でも、以下の条件を満たせば社会保険に加入させる必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 給与が月88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
雇用保険と狭義の社会保険の違いを区別するためのQ&A
最後に、雇用保険と社会保険の加入に関するよくある質問に回答します。
- 雇用保険と社会保険はパートや扶養内でも対象ですか?
- 雇用保険と社会保険の加入はセットですか?
- 雇用保険のみ加入して社会保険に入らないことはできますか?
- 雇用保険と社会保険に入らないとどうなる?
雇用保険と社会保険はパートや扶養内でも対象ですか?
パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、所定の要件を満たす従業員は雇用保険と社会保険の加入対象です。
また、扶養の範囲内で働いている従業員も、加入条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。ただし、扶養には「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」の2種類があり、社会保険上の扶養の方が上限年収が高く設定されています。
| 年収の壁 | |
|---|---|
| 税制上の扶養 | 103万円 |
| 社会保険上の扶養 | 106万円:企業の規模により扶養から外れる 130万円:扶養の上限ライン |
税制上の扶養範囲を超えていても、社会保険上の扶養範囲内に収まっていれば、社会保険への加入は必要ありません。
一方、社会保険上の扶養の上限ラインを超えて働く従業員は、社会保険に加入させる必要があります。
雇用保険と社会保険の加入はセットですか?
従業員の働き方によっても異なりますが、同時に加入することは可能です。
雇用保険のみ加入して社会保険に入らないことはできますか?
事業所または従業員が社会保険の適用条件を満たしていない場合は、雇用保険にのみ加入するケースもあるでしょう。
たとえば、パートやアルバイトで週の所定労働時間が20時間以上あっても、月給が88,000円を超えないのであれば、雇用保険にのみ加入する可能性があります。
雇用保険と社会保険に入らないとどうなる?
社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、手続きを怠ると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。
一方、雇用保険の手続きを怠ると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、未加入だった期間の保険料を最大2年までさかのぼって支払うことになり、延滞金を科せられる場合もあるでしょう。
未加入が発覚したら、それぞれの専門機関にすみやかに相談することが大切です。
雇用保険と社会保険の違い理解して適切に手続きを
雇用保険と狭義の社会保険は、制度の目的や保障内容、加入条件などが異なります。従業員の働き方によっては、雇用保険と社会保険に同時加入、または雇用保険にのみ加入するケースもあるでしょう。
雇用保険や社会保険は加入義務のある強制保険であるため、条件を満たす事業者と労働者については加入手続きが必須です。それぞれの制度の概要や加入条件への理解を深め、必要な手続きを正しく進めましょう。
労務管理をペーパーレスに|One人事[労務]
One人事[労務]は、煩雑な労務管理をクラウド上で完結させる労務管理システムです。
- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い
- 【年末調整】記入漏れ・修正対応に追われている
- 【退職手続き】離職証明書の作成が面倒
という悩みがある担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
