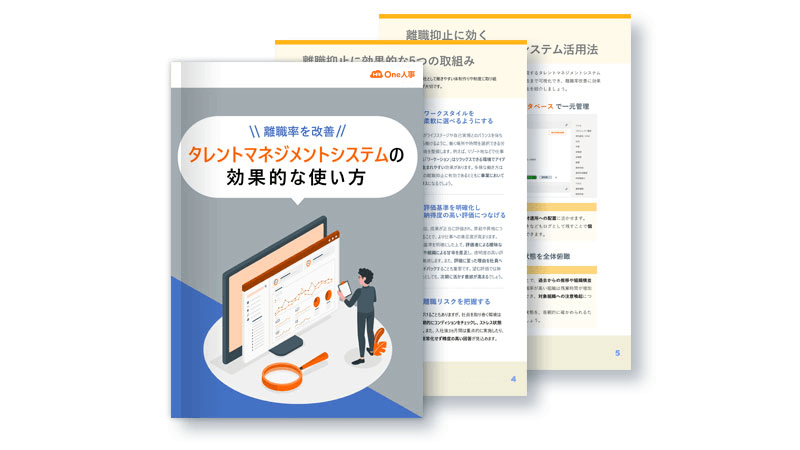なんでもかんでも「ハラスメント」にされる|対処法と管理職を萎縮させないコツ
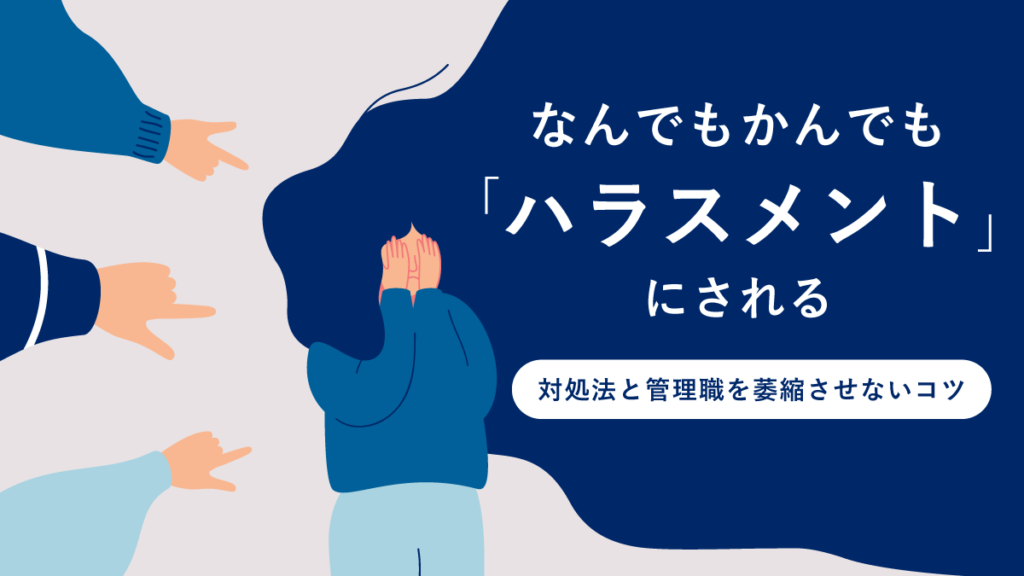
2020年6月に『改正労働施策総合推進法』(以下、パワハラ防止法)が施行され、中小企業も2022年4月より対象となりました。パワハラ防止が義務化されて以降、企業はパワハラ問題に積極的な対応をとるようになった一方で、新たな課題や問題も発生しています。
最近では、どのような行為に対しても、すぐ「ハラスメント」と主張する従業員がいて困っているという企業も少なくありません。企業として、どのように対応すべきか悩んでいる人事担当者も多いでしょう。
本記事では、なんでもかんでもハラスメントとされてしまう原因を詳しく解説します。すぐにハラスメントとする風潮によって生じるリスクや具体的な対処法も紹介するため、企業の人事担当者はぜひ参考にしてください。
 目次[表示]
目次[表示]
なんでもかんでも「ハラスメント」になる時代
ハラスメントという概念が浸透してきた昨今では、上司や同僚の言動に対して不快感を覚えた従業員が、過剰に反応して「ハラスメント行為だ」と主張するケースが増えてきました。
なんでもかんでもハラスメントと認定する行為は「ハラスメント・ハラスメント」といい、通称「ハラ・ハラ」とも呼ばれています。
本記事では、なんでもかんでもハラスメントとする行為を便宜上「ハラスメント・ハラスメント」と定義し、解説していきます。
▼多すぎるハラスメントの種類を確認したい方は以下の記事もご確認ください。
なんでもかんでもハラスメントが発生する5つの原因
なんでもかんでもハラスメントと主張する行為が発生する主な原因は、次の5つが考えられます。
- ハラスメントに対する意識の高まり
- 上司と部下のスキル・経験の逆転
- 上司のマネジメント力不足
- 職場のコミュニケーション不足
- ストレスを感じやすい職場・労働環境
ハラスメントに対する意識の高まり
2020年にパワハラ防止法が施行されてから4年以上の月日が経過し、ハラスメントに対する意識が高まったことが、なんでもかんでもハラスメントとされやすくなっている理由の一つです。
これまでは「パワハラ」や「セクハラ」などが代表的なハラスメント行為として知られてきましたが、近年ではさまざまな種類のハラスメント行為が定義されるようになりました。
道徳や倫理に反した言動で嫌がらせをする「モラハラ(モラルハラスメント)」や、妊娠・出産を理由に嫌がらせや不当な扱いをする「マタハラ(マタニティハラスメント)」などが挙げられます。
ハラスメント行為を許さない風潮が強まり、過剰に反応しすぎた結果として、ハラスメント・ハラスメントが生まれたといわれています。
ただし、相手の行為を不快に感じるか否かには個人差があり、判断は難しいといえるでしょう。
参照:『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律』e-Gov法令検索
上司と部下が持つスキル・経験の逆転
若手の管理職に経験豊富な部下がついた場合のように、上司と部下の持つスキルや経験値が逆転するケースでも、ハラスメントが起こりやすいと考えられています。
経験や知識不足の上司に対して部下が不信感を持つと、上司への指摘や批判が強くなってしまう場合があります。
たとえ部下であっても、上司を無視したり、指示にしたがわなかったりすると「逆パワハラ」とみなされるケースもあると覚えておきましょう。
上司のマネジメント力不足
上司のマネジメント力不足があると、なんでもかんでもハラスメントとされやすくなります。
指示がわかりにくかったり、現場の意見に耳を傾けてもらえなかったりすると、上司に対する不信感は増すばかりでしょう。
その結果、部下の不満が爆発し、上司に対してストレスをぶつけたり、嫌がらせをしたりなどの行為に発展してしまうケースもあります。
職場のコミュニケーション不足
職場におけるコミュニケーション不足は、業務効率の低下だけでなく、言われのないハラスメント認定を発生させる要因の一つです。
コミュニケーション不足によって誤解や不満が生じやすくなり、従業員は上司や同僚の考え方や価値観を理解しづらくなります。
その結果、自分の偏見や考えを強く押しつけるようになってしまうおそれがあるため、注意が必要です。
普段から互いに意見を言い合ったり、相談したりできるような風通しのよい環境を整備することで、ハラスメント行為を抑制できるでしょう。
▼ハラスメントに気を遣いながら1on1を実施するのは大変と感じていませんか。1on1ミーティングのコツをまとめた以下の資料も参考にしてみてください。
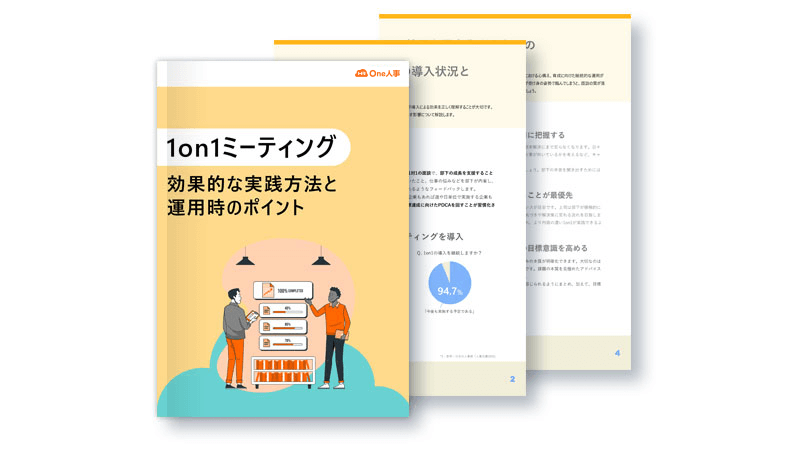
ストレスを感じやすい職場・労働環境
ハラスメント行為が起こる理由の一つに、日常的にストレスを感じやすい労働環境があります。
厚生労働省の調査によると、長時間労働や慢性的な人手不足など、ストレス要因が職場に存在すると従業員の心身の健康に悪影響をおよぼすと報告されています。
ストレスの多い職場環境下では、上司や部下、同僚などが互いを尊重する気持ちの余裕がなくなってしまうでしょう。
その結果、コミュニケーションの質が低下し、ハラスメント行為が横行するおそれがあります。
組織に対して不満を持つ従業員が多いと、なんでもかんでもハラスメントとされる傾向が強まるのです。
参考:『労働の場におけるストレス及びその健康影響に関する研究報告書』厚生労働省
なんでもかんでもハラスメントに関連する法律
ハラスメント行為は今や大きな社会問題となっており、さまざまな法律によって防止措置を講じるように定められています。
しかし、ハラスメント・ハラスメントについて定義する法律は、2024年10月時点では存在しません。
そのため、ハラスメント行為に関連する法律をよく把握したうえで、なんでもかんでもハラスメントと主張されてしまわないような環境の整備を進める必要があります。
ハラスメント行為に関連する代表的な法律は、以下のとおりです。
- セクハラ:男女雇用機会均等法第11条
- パワハラ:労働施策総合推進法第30条の2
- マタハラ:育児・介護休業法第25条
2024年11月1日に施行されたフリーランス保護法では、フリーランスに対するハラスメント防止のためにも義務づけられました。
今後、過剰なラスメントについても、企業に対する措置義務が定義される可能性もあります。企業として、最新の法改正の情報を確認・把握しておくようにしましょう。
参照:『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』e-Gov法令検索
参照:『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律』e-Gov法令検索
参照:『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』e-Gov法令検索
▼2025年の人事労務にかかわる法改正と、その対応については以下の資料をご活用ください。

なんでもかんでもハラスメントの具体例
過剰なハラスメント認定・ハラスメント警戒行為とみなされる例を4つ紹介します。
- 特定の従業員のプライバシーを侵害するほど監視する
- ハラスメント行為を受けたと嘘の発言をする
- 何度名前を呼んでも反応がないため肩をたたいただけで、セクハラだと主張する
- 間違った言葉遣いを指摘したことに反撃をする
以上のようにはさまざまなタイプが存在します。
該当するか判断できない場合には、上司や人事部などに相談するよう従業員に周知しましょう。
▼以下の記事ではクラッシャー上司と呼ばれる人の特徴をチェックリストで紹介しています。
なんでもかんでもハラスメントによって生じる4つのリスク
職場に過剰なハラスメント意識が生じることで起こり得るリスクには以下4つが挙げられます。
- 正しい指摘や注意をしづらくなる
- 生産性が低下する
- 離職者増加によって人員不足に陥る
- 従業員のモチベーションが下がってしまう
正しい指摘や注意をしづらくなる
なんでもかんでもハラスメントとみなす行為が横行する職場では、部下が上司をおどすケースも少なくありません。
上司はハラスメントへの指摘をおそれるあまり、部下に対して正しい指摘や注意をしにくくなります。
その結果、部下が適切な教育を受けられず、成長が止まってしまうのが大きなデメリットといえるでしょう。
生産性が低下する
過剰なハラスメント意識が横行する職場では、生産性の低下を招くリスクが高まります。
ハラスメント行為があると従業員がストレスを感じやすく、モチベーションが著しく低下したり、精神的に病んだりするおそれもあります。
また、部下に依頼したい仕事があっても「なんでもかんでもハラスメントにされかねないから頼みにくい」と感じ、仕事を抱え込んでしまう上司も少なくありません。
その結果、時間外労働が増え、業務効率や生産性の低下につながります。
離職者増加によって人員不足に陥る
過剰なハラスメント認定となる職場では、誰もがストレスを感じやすいため、離職者も増えがちです。
離職者が出ると、現場に残された従業員は退職者の分の業務を一時的に請け負うこととなり、身体的にも精神的にも大きな負担がかかるでしょう。
その結果、さらなる離職者が生まれ、慢性的な人員不足の状況に陥ってしまうリスクがあります。
従業員のモチベーションが下がってしまう
ハラスメントに対して過敏な職場では、雰囲気が悪くなり、従業員のモチベーションも低下しがちです。
ハラスメント行為を受けることを怖がり、従業員同士の交流を避けるようになるでしょう。
普段から十分なコミュニケーションがとれていないと、企業に対する帰属意識も薄れがちです。
その結果、仕事に対する意欲やパフォーマンス性も低下してしまい、最悪の結果として企業の業績悪化を招きかねません。
以上のように、なんでもかんでもハラスメントとみなす行為は、企業にとって大きなダメージとなるのです。
なんでもかんでもハラスメントに対する5つの対策法
なんでもかんでもハラスメントにしてしまう行為への対処法は以下の5つが挙げられます。
- ハラスメントの判断基準を明確にする
- ハラスメントに関連する研修会や勉強会を実施する
- 従業員のメンタルヘルスケアに力を入れる。
- 気軽に相談できる窓口を設置する
- なんでもかんでもハラスメントをする従業員への対応策を検討する
ハラスメントの判断基準を明確にする
企業として、各種ハラスメントについての判断基準や定義、方針を明確に示しましょう。判断基準が不明瞭だと「不快に感じたこと=ハラスメント行為」とされてしまいます。
どのような行為がハラスメントに該当するのか、明文化することが重要です。
具体的な判断基準については、厚生労働省が公表しているハラスメントの定義を参考にするとよいでしょう。
参照:『職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)』厚生労働省
ハラスメントに関連する研修会や勉強会を実施する
過剰なハラスメント認定防止のために、全従業員を対象とした研修会や勉強会を定期的に実施することが望ましいといえます。
とくに、管理者向けにはハラスメントに関連する研修会や勉強会を実施しましょう。
研修会や勉強会は、それぞれの従業員の立場に合った内容で実施しなければなりません。管理職のマネジメント不足が顕著な場合は、マネジメント研修の実施を検討します。
直属の上司のリーダーシップに任せすぎてしまうと、ハラスメント行為が発生するリスクが高まります。
マネジメント研修に、部下への接し方や業務の進め方などを盛り込むと、管理職を萎縮させない職場環境の整備にもつながるでしょう。
従業員のメンタルヘルスケアに力を入れる
たとえ指摘した内容が正しかったとしても、指摘された従業員が精神的に不安定な状態だと「ハラスメント行為を受けた」と感じてしまいます。
休職・離職対策のためにも、日頃から従業員のメンタルヘルスのケアに力を入れていきましょう。
メンタルヘルスケアのために企業ができることとして、次のような施策が挙げられます。
- 産業医との定期的な面談
- 従業員に対するアンケート調査
- ストレスチェックの実施
- 職場環境や業務量の見直し
詳しい取り組み方については以下の記事もぜひご覧ください。
従業員たちに心身ともに健康な状態で働いてもらうためにも、働きやすい職場や良好な人間関係を構築していきましょう。
気軽に相談できる窓口を設置する
行き過ぎたハラスメント認定による被害にあった従業員のためにも、相談窓口を設置します。
パワハラやセクハラだけでなく、なんでもかんでもハラスメントも含めて総合的に相談を受ける窓口であれば、相談の敷居が低くなり、より多くの人が声を上げやすくなるはずです。
社内窓口のほか、外部の相談機関に委託することも可能です。社外に相談窓口を設置する場合は、人事部と連携しながら適切に対応できる体制をつくりましょう。
なんでもかんでもハラスメントをする従業員への対応策を検討する
社内で過剰なハラスメント認定が横行しているようであれば、企業としてハラスメントに特化した対応体制の整備をおすすめします。
具体的には、次のような対応策を検討するとよいでしょう。
- 事実関係を確認する担当者や手続き方法を明確にする
- 被害者のケアに向けた仕組みをつくる
- 加害者に対する改善指導に向けた仕組みをつくる
ハラスメントが発生したら都度、事実確認をして、再発防止に向けた対策を講じ、防止体制を強化していきましょう。
まとめ|すべての従業員に対してハラスメント教育を
なんでもかんでもハラスメントにしてしまう行為は、ハラスメントの判断基準を明確に定義して周知したり、従業員同士のコミュニケーションを活性化させたりすることで減らせます。
すべての従業員に対するハラスメント教育を徹底し、誰もが安心して働きやすい環境を整備していきましょう。