従業員の入社手続きにともなう雇用保険・社会保険・税関連の届け出|必要書類や期限
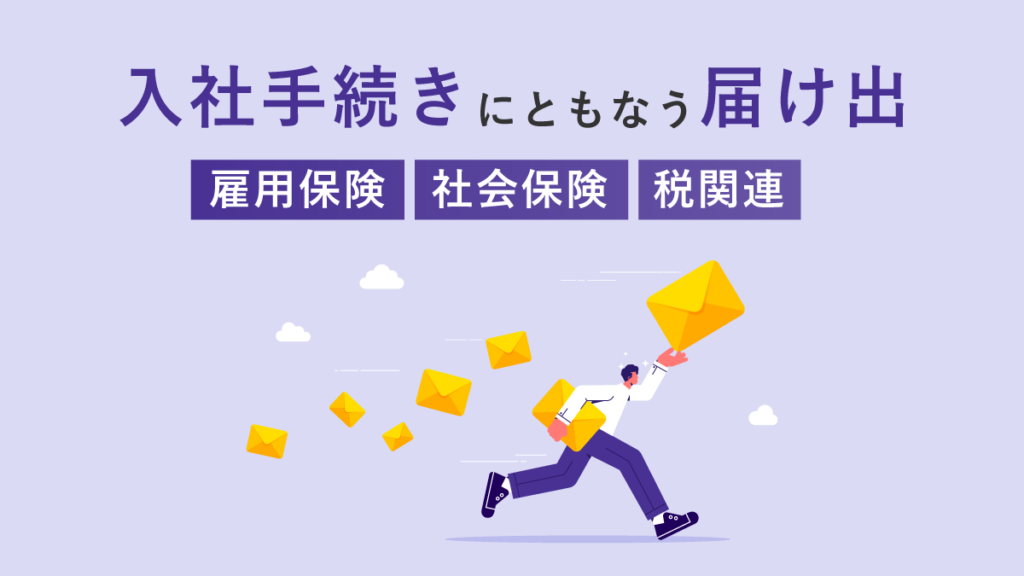
新入社員の入社手続きで、社会保険や雇用保険の手続きに不安を感じていませんか。とくに近年は紙の書類だけでなく 電子申請も進んでおり、対応方法につまずく人もいるかもしれません。
本記事では入社時の公的手続きについて
- いつまでに
- 何を
- どこへ提出するのか
「社会保険」「雇用保険」「税関連」ごとに整理しています。手続きを効率的に進めるためにご活用ください。入社手続きの不安は、これ1冊|完全ガイドは以下より無料ダウンロードできます。

 目次[表示]
目次[表示]
入社手続きで必要な雇用保険・社会保険の届け出(一覧)
| 保険 | 書類 | 期限 | 提出先 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 | 雇用日から5日以内 | 年金事務所・事務センター | 窓口/ 郵送/電子申請 |
| 雇用保険 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 入社月の翌月10日まで | ハローワーク | 窓口/ 郵送/電子申請 |
雇用保険被保険者資格取得届は、一部の法人で電子申請が義務化されています。詳しくは厚生労働省のリーフレットでご確認いただけます。
参照:『2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。』厚生労働省
入社手続きのタイミングだけでなく、途中で加入条件を満たすようになった場合も、加入手続きが必要であることも覚えておきましょう。具体的には、パートタイム労働者が正社員に転換するケースが考えられます。
入社手続きにともなう社会保険の届け出
新入社員の入社手続きでは、まず社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得を進める必要があります。期限は雇用日から5日以内です。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を準備し、基礎年金番号またはマイナンバーを記載したうえで、年金事務所または事務センターに提出しましょう。
電子申請の場合は「e-Gov」または「e-Gov」と連携したシステムを利用します。
申請が受理されると、マイナ保険証で、新入社員が保障を受けられるようになります。マイナ保険証が利用できない場合には、資格確認書が発行されます。
以下で社会保険の適用条件を確認し、手続きをスムーズに進められるようにしておきましょう。
社会保険の適用事業所(手続きが必要な事業所)
適用事業所とは健康保険や厚生年金保険の加入が義務づけられている事業所のことです。社会保険が適用される事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」があります。常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所です。法人の場合は従業員が1人以上いれば、強制適用事業所とみなされます。
社会保険の加入対象者(手続きが必要な従業員)
正社員であれば、原則として社会保険に加入します。また、パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入します。
条件を満たさない場合でも、従業員数51人以上の企業であれば、2か月以上の雇用見込みがあって週20時間以上働き、月額8.8万円以上の賃金を得ている人は対象となります。ただし、定時制などを除く昼間学生は対象外です。
なお、条件を満たしていても70歳以上は、厚生年金保険に加入できません。
参照:『就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き』日本年金機構

入社手続きにともなう雇用保険の届け出
新入社員の入社手続きでは、雇用保険も資格取得申請が必要です。
従業員を雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
電子申請の場合は「e-Gov」または「e-Gov」と連携したシステムを利用します。
添付書類は原則として不要ですが、転職などですでに雇用保険被保険者証が発行されている場合には、回収しなければなりません
新卒社員は手続きの完了後に雇用保険被保険者証が発行されるので、従業員に交付します。
雇用保険についても、以下で事業所の適用条件と加入条件をおさらいしておきましょう。
雇用保険の適用事業所(手続きが必要な事業所)
従業員を1人でも雇用している事業所であれば、原則として雇用保険の適用事業所です。初めて従業員を雇用する際は、「雇用保険適用事業所設置届」をハローワークへ提出します。
雇用保険の加入対象者(手続きが必要な従業員)
雇用保険の加入対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用される見込みがある従業員です。
雇用形態は問わず、パートやアルバイトも条件を満たせば加入申請を行います。
4か月以内の季節業務に従事する人や、31日以上の雇用が見込まれない人などは手続き必要ありません。
参照:『事業主の行う雇用保険の手続き』厚生労働省
参照:『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』厚生労働省

入社手続きにともなう労災保険の届け出
すでに従業員を雇用しており事業所として労災保険に加入している場合は、新入社員の入社手続きのタイミングで、個別の申請は不要です。
労災保険は、従業員を1人でも雇用している事業主に加入が義務づけられています。パートタイム労働者やアルバイトを含め、雇用形態や雇用期間を問わず、すべての従業員が対象です。
初めて従業員を雇用するときだけ、以下の手続きが必要となります。
- 「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出
- 提出期限は、保険関係成立届が雇い入れの日の翌日から10日以内
- 労働保険概算保険料申告書は雇い入れの日の翌日から50日以内。同時に提出することも可能
個人経営の農業・水産業で従業員が常時5人未満の場合や林業で常時労働者を使用せず、年間延使用労働者数が300人以下の場合は、任意加入です。
参照:『労働保険制度』厚生労働省
参照:『労災保険・雇用保険加入に関する手続きの流れ及び必要書類について』東京労働局
労災保険の加入条件については以下で詳しくご確認ください。
入社手続きにともなう住民税・所得税の知識
入社時の税金関連手続きについて、住民税と所得税それぞれの実務的な手順を紹介します。
| 税の種類 | 書類 | 期限 | 提出先 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 住民税 | 特別徴収切替届出書/給与所得者異動届出書 | 入社後すみやかに | 従業員の居住地の市区町村 | 窓口/ 郵送 |
| 所得税 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 最初の給与支払日の前日まで | 会社 | 従業員が記入し、会社へ提 |
住民税に関係する手続き
新入社員が前職で普通徴収をしていた場合は、「特別徴収切替届出書」と本人から回収した普通徴収の納税通知書を、従業員の居住地の市区町村へ提出する必要があります。
前職で特別徴収を行っていた場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」が前職の会社から提出されます。
新卒社員をはじめ、前年に所得がない場合は、翌年の6月から住民税の徴収が始まり、5月末まで徴収はありません。
普通徴収と特別徴収の仕組みについては以下の記事で詳しくご確認いただけます。
所得税に関係する手続き
入社時には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を従業員に求める必要があります。
申告書は、扶養親族の有無にかかわらず、給与所得者全員が提出しなければなりません。会社は申告書の内容に基づいて源泉徴収簿を作成し、毎月の給与から控除する所得税額を決定します。
申告書の提出期限は、最初の給与支払日の前日までです。申告書の提出がないと、給与に扶養控除が適用できないため、確実に回収しましょう。

入社時の雇用保険・社会保険手続きが間に合わない場合
雇用保険・社会保険・税関連の手続きには期限がありますが、万が一遅れてしまっても、適切に対応すれば挽回できる場合があります。
最後に遅れるリスクと対処法を解説していきます。
社会保険手続きが遅れるとどうなる?
社会保険の手続きが遅れると、事業主に対して加入すべき期間の保険料をさかのぼって請求されます。正当な理由がないと判断されると、本来の2倍の保険金額を追徴される可能性もあります。
遅れに気づいたら、取得届の提出と同時に遅延理由書も提出しましょう。
また、保険証が手元にない期間に医療機関を受診する場合は、全額自己負担となります。後日「療養費支給申請書」を提出することで、保険適用分が払い戻されますが、早めに対応するに越したことはありません。
雇用保険手続きが遅れるとどうなる?
雇用保険の手続きが遅れると、事業主に罰金や懲役といった罰則が科される可能性もあります。また、事業主に対してさかのぼって保険料が請求され、場合によっては追徴金が発生することもあります。
万一、手続きが遅れに気づいた時点で、すぐに資格取得届を提出しましょう。
被保険者番号が不明な場合は、雇用保険被保険者証の写しで確認できます。
税金や控除手続きが遅れるとどうなる?
源泉所得税や住民税の手続きが遅れると、給与から控除ができず、後日まとめて控除しなければならなくなります。
担当者に余計な手間がかかるとともに、結果的に手取り額が変動してしまうため、早めに情報を回収しましょう。
とくに扶養控除等申告書の提出が遅れた場合は、控除がない状態で源泉徴収税額が計算されるため、税負担が一時的に増加します。
入社手続きを適切なタイミングで進めることで負担が軽減され、スムーズな給与計算につながります。
入社時の雇用保険・社会保険の手続きは電子化で効率的に(まとめ)
入社時の雇用保険・社会保険の手続きは、期限を守ることが重要です。
手続きの遅れは余計な対応を増やし、必要以上の保険料を請求される事態になりかねません。
電子申請を活用すれば、書類の準備や管理の負担も軽減できます。事前に必要な情報を収集し、電子申請を活用することで、効率的に入社手続きを進めましょう。
入社時の雇用保険・社会保険申請はOne人事[労務]の活用も
One人事[労務]は「e-Gov」と連携し、公的手続きの電子申請を支援する労務管理システムです。
社会保険や雇用保険に関する届け出に対応しています。
専用フォームから従業員が直接情報を入力することで、公的書類の作成時間を短縮できます。
One人事[労務]の活用方法は、無料のオンライン相談にてお尋ねください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、入社手続きの電子化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。お気軽にお申し込みください。
