労働基準法に違反するパターン15選|罰則の内容や対策も解説
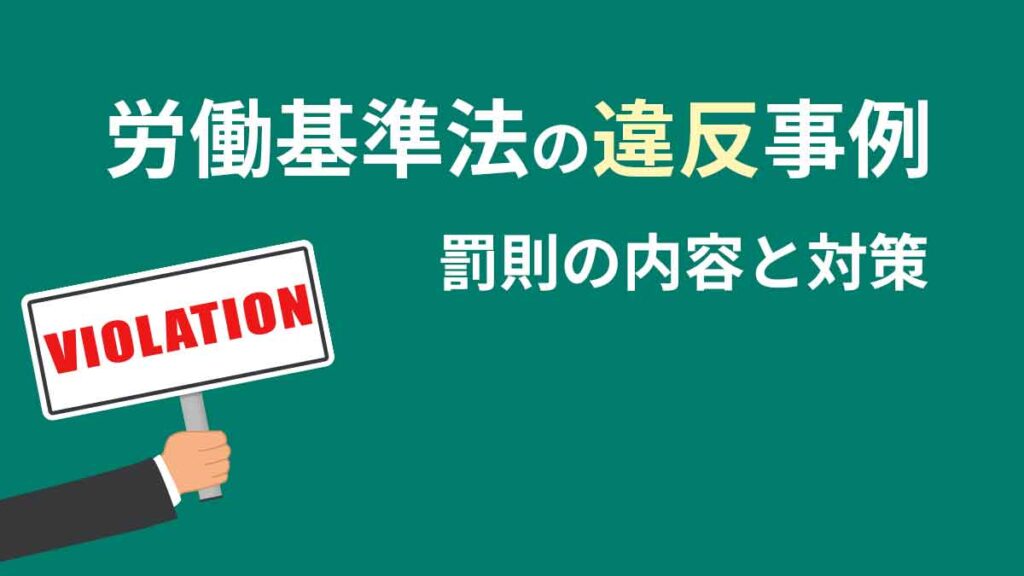
企業は従業員を雇用するにあたって、労働基準法を遵守した仕組みをつくり、運用・管理する義務があります。労働基準法に違反することには多くのリスクがあり、場合によっては罰則を科されることもあるでしょう。本記事では、労働基準法の基本と違反となる具体的な事例を15例ご紹介します。

 目次[表示]
目次[表示]
労働基準法の基本について
労働基準法とは、従業員の労働におけるルールを定めた法律です。労働時間や給与の支給、休日や災害補償など、労働条件としての最低基準が定められています。労働組合法や労働関係調整法とあわせて「労働三法」の一つで、企業と従業員それぞれにとって重要な法律といえます。
労働基準法は1947年の制定以降、複数回の改正が実施されています。常に最新のルールに対応した業務が遂行できるよう、法改正の情報に注意を払いましょう。
労働基準法を守ることは企業の義務
企業には、従業員を雇用するにあたって労働基準法を遵守する義務があります。労働基準法は、当事者の意思に関係なく強制的に適用される「強行法規」の一種であるため、内容を正しく理解し、ルールに従うことが必要です。
違反した場合には罰金や刑事責任の追及、従業員からの損害賠償請求などのリスクが発生する恐れがあります。

労働基準法における違反のパターンと罰則
どのようなケースが労働基準法違反にあたるのか、具体例を交えながら解説します。
1.身分や性別などで差別する
労働基準法第3条・4条により、従業員の社会的身分や国籍、性別などを理由に労働条件を差別的に扱うことは労働基準法違反です。
従業員が女性であることを理由に賃金を低く設定したり、従業員の信条を理由に労働条件に差をつけたりすることは、法律で禁じられています。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される恐れがあるでしょう。
2.従業員の意思に反した労働を強制する
労働基準法第5条により、従業員の意思に反した労働の強制は禁止されています。
暴力行為はもちろん「従わないならクビにする」といって従業員を脅迫し、従業員の意思に反した労働を強制することは労働基準法違反です。違反した場合は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。この強制労働禁止規定違反は、労働基準法上もっとも重い罰則が設けられています。
3.中間搾取(ピンハネ)する
労働基準法第6条により、使用者(事業主)と従業員の間に入り、賃金の一部を中間搾取(ピンハネ)することは禁じられています。
違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。人材派遣会社のように人材紹介および仕事の斡旋を法的に認められている企業の場合は、この限りではありません。
4.違約金などの支払いを強制する
労働基準法第16条により、従業員に違約金の支払いを命じることは禁じられています。
たとえば、契約期間内の退職に違約金を定めたり、損害賠償を予定したりすることは違法です。また、雇用契約書に同様の内容を記載するだけでも、違反と見なされます。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
5.事前予告なしに解雇する
労働基準法第20条により、企業は従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇予告をしなければならないと定められています。もし、30日よりも前に解雇予告ができない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
6.定められた休憩・休日を与えない
労働基準法第34条により、企業は従業員に対して適切な休憩時間を与える義務があります。具体的には、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を付与しなければなりません。
また労働基準法第35条により、企業は従業員に対して「週1日または4週間に4日以上の休日」を与える義務があります。
(休憩)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:『労働基準法』e-Gov法令検索
(休日)第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。ー
引用:『労働基準法』e-Gov法令検索
労働基準法で定められた休憩・休日を与えない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
7.法定労働時間を超えた労働をさせている
労働基準法第32条により、従業員に働かせてもよい時間は1日8時間、週40時間までと定められています。これを法定労働時間といい、従業員にさらに多くの労働を依頼する場合は、労働基準法第36条に基づく「36協定」を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(労働時間)第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
引用:『労働基準法』e-Gov法令検索
36協定の締結なしに法定労働時間を超えた労働をさせた場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
8.残業代を支払わない
労働基準法第37条により、従業員に時間外労働や深夜労働などを依頼した場合、企業は割増率を上乗せした「残業代」を支払わなければなりません。たとえば、時間外労働や深夜労働に対しては通常の25%以上の割増賃金を支給する必要があります。
残業代の支給を拒否した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
9.休業手当を支払わない
労働基準法第26条により、企業側の責任により従業員を休業させる場合、企業は平均賃金の60%以上の休業手当を支給する義務があります。
企業が休業手当の支払いを拒否した場合、30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。ただし、自然災害により出社が不可能な場合は、企業が休業を指示したとしても休業手当の支払い義務は生じません。
10.有給を消化させない
労働基準法第39条により、企業は雇用から6か月が経過し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、10日以上の有給休暇を与える義務があります。継続勤務年数に応じた加算もあるため、従業員それぞれに正しい日数の有給休暇を付与しなければなりません。
従業員に適切な有給休暇を与えなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
11.産前後や育児期間の休暇申請を拒否する
労働基準法第65条、66条、67条により、企業は従業員からの申請に対して、産前産後休暇や育児休暇を付与する義務があります。また本人が希望し、医師が認めた場合を除き、産後8週間以内の女性を働かせることも違法です。
(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
引用:『労働基準法』e-Gov法令検索
違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
12.療養補償・休業補償・障害補償が制定されていない
労働基準法第75条により、従業員が業務上の負傷や疾病によって療養する場合、企業は療養費を負担する義務があります。
違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
13.就業規則の明示・作成を怠っている
労働基準法第15条により、企業は従業員と労働契約を結ぶ際に、労働時間や賃金などの労働条件を明示する義務があります。また、10人以上の従業員を雇用している場合は、労働条件をまとめた就業規則を作成し、従業員に周知しなければなりません。
違反した場合は、30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
14.遺族への補償制度がない
労働基準法第79条により、従業員が業務上死亡した場合、企業は遺族に対して平均賃金の1,000日分を補償する義務があります。
違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
15.18歳未満の未成年・妊娠中の女性を坑内で働かせる
労働基準法第63条、64条の2より、18歳未満の未成年や妊娠中の女性、坑内作業を希望しない産後1年未満の女性を坑内で働かせることは禁じられています。坑内とは、炭坑や鉱坑の内部です。
違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる恐れがあるでしょう。
労働基準法の違反が判明した場合の流れ
従業員からの告発や定期検査によって、労働基準法違反が判明した場合、罰則が科されるまでの流れをご紹介します。
労働基準監督署が調査を実施する
まずは労働基準監督署による立入検査が実施されます。
労働基準監督署の職員が事業所を訪問し、出勤簿やタイムカード、賃金台帳などの資料を確認し、内容をチェックしながら、事実関係を調査します。
立入検査には、訪問の日時を指定されるケースと、事前の約束なしで訪問するケースがあり、いずれも企業側に拒否権はありません。調査を拒否した場合は、30万円以下の罰金を科せられる恐れもあるでしょう。
違反確認後に是正勧告が実施される
立入検査の結果、労働基準法の違反が確認された場合は、企業に対して是正勧告が行われます。その際、労働基準監督署が発行するのが、違反事項とその解消を命じる「是正勧告書」です。企業が違反事項を速やかに改善し、是正勧告書を提出すれば、多くの場合は一旦の終局を迎えます。
しかし、是正勧告後も状況が改善されない場合には、刑事事件として捜査される可能性もあります。
司法処分によって起訴される
実は、労働基準監督署からの是正勧告には法的な強制力がありません。しかし、勧告されたにもかかわらず労働環境が改善されない場合には、刑事事件に移行する恐れがあります。
万が一、刑事事件として扱われることになった場合は、司法処分によって起訴され、企業だけでなく役員や責任者などが送検・起訴されることもあるでしょう。
労働基準法に違反しないための対策
労働基準法を遵守するためには、以下の2つのポイントに注意することが大切です。
- 労働基準法についての理解を深める
- 専門サービスを活用して違反行為を防止する
それぞれのポイントについて解説します。
労働基準法についての理解を深める
法律を遵守するために、まずは法律についての理解を深めることが重要です。担当者は労働基準法についての理解を深め、違反しないための基盤を築く必要があります。
労働基準法は強行法規であるため「知らなかった」「よくわからなかった」では済まされません。各事例を参考にして、法律を遵守するための社内ルール整備や問題の周知徹底をすることが大切です。
専門サービスを活用して違反行動を防止する
規模が大きかったり、人手不足に陥っていたりする企業では、正確な勤怠管理が行き届いていないこともあるかもしれません。
そこでおすすめするのが、専門サービスの活用です。勤怠管理システムをはじめとしたサービスを活用すると、面倒な従業員の勤務状況の把握を効率化できるとともに、法改正にも自動で対応できるため、法律を確実に遵守するための助けとなるはずです。
自社の状況に最適なサービスを導入して、労働基準法違反の防止対策を徹底しましょう。
労働基準法を遵守したルールづくりで、違反を防ぎましょう
従業員の労働条件については、労働基準法に基づくさまざまなルールがあります。労働基準法の遵守は、企業にとっての義務です。法律を深く理解したうえで、違反を防ぐための仕組みづくりを進めましょう。
勤怠管理をより速く正確に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をシンプルにする勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 休憩時間や残業時間を正確に把握できていない
というお悩みを持つ企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。また、有休の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも順次対応してまいります。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
