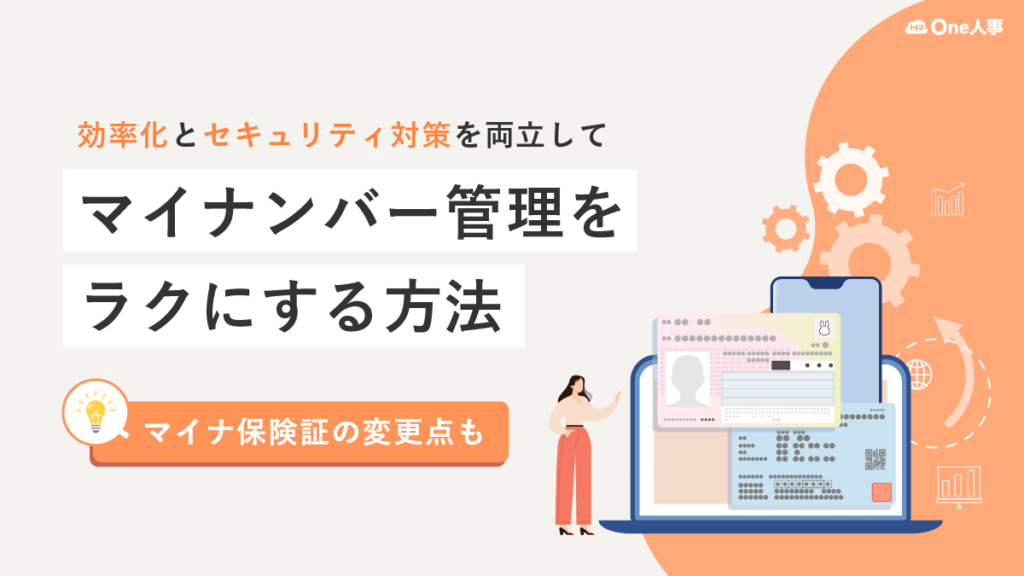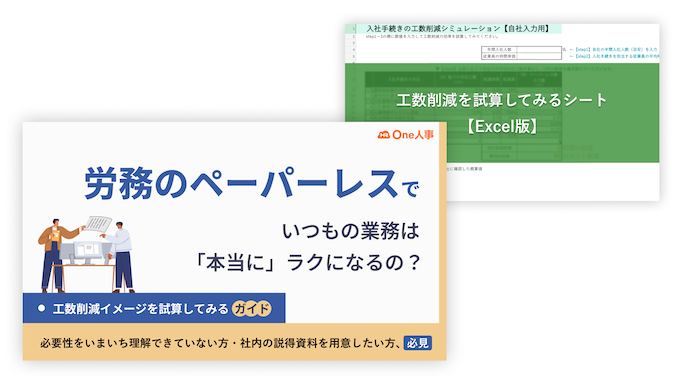人事労務業務を電子化するには|メリットや詳しい手順、導入前に知りたい注意点を解説
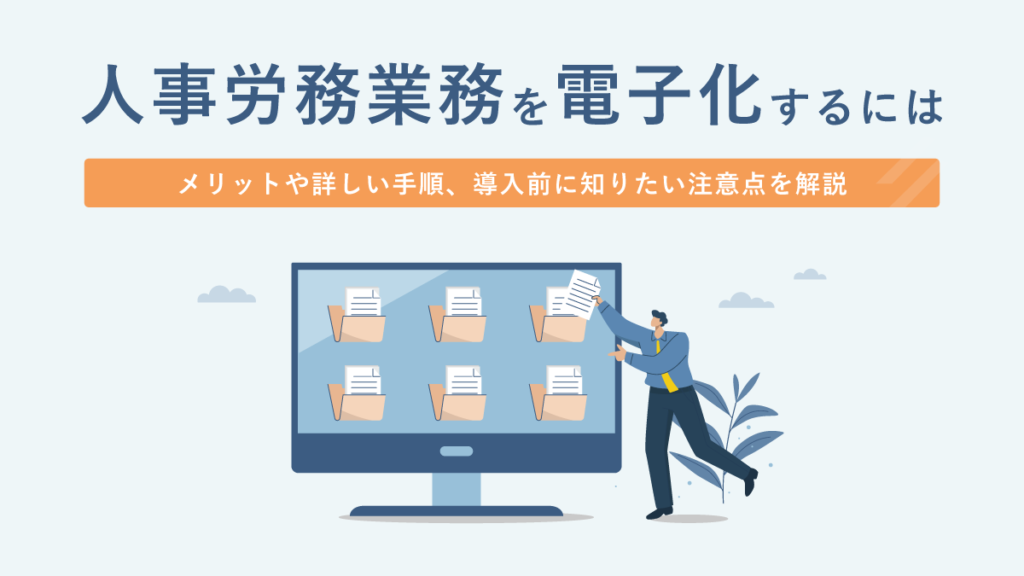
人事労務業務の電子化とは、入社から退職までの一連の手続きや日々の勤怠管理、給与計算の業務をデジタル化し、システムで効率的に管理・運用することです。多くの企業では人事労務業務が広範囲にわたる一方で、いまだに紙での管理や少人数での業務処理に追われています。本来注力すべき人材育成や戦略的な人事施策に時間を割けていますでしょうか。
本記事では、人事労務業務の電子化のメリットや具体的な手順、導入前に知っておきたい注意点について詳しく解説していきます。
→人事労務の電子化を実現「One人事」の資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
人事労務業務の電子化とは?
人事労務業務の電子化とは、従来紙で行っていた人事・労務関連の業務や文書をデジタルデータに変換することです。そして人事情報をシステムで管理・運用し、業務の効率化をはかります。
具体的には採用から退職までの一連の手続きや、日々の勤怠管理、給与計算などを電子的に処理することです。
生産性向上とペーパーレス化などを目的に、人事労務業務の電子化は推進されています。
→人事労務の電子化を実現「One人事」の資料を無料ダウンロード
電子化できる人事労務業務
人事労務の業務は、採用から労務管理、各種申請業務まで幅広くあります。多くは、システムを活用して電子化することで効率化がはかれます。
具体的にどのような人事労務業務が電子化できるのか、確認してみましょう。自社では、以下の業務がまだ紙のままになっていないでしょうか。
| 採用管理 | 応募者情報の管理、面接スケジュール調整 など |
| 労務管理 | 雇用契約の締結、マイナンバー収集・管理、社会保険の届け出 など |
| 勤怠管理 | 残業時間の集計、有給休暇の管理 など |
| 給与計算 | 給与・賞与計算、社会保険料の計算、年末調整、明細発行 など |
| 人材管理 | 目標管理、人事評価、スキル管理 など |
| 各種申請 | 身上異動届、休暇申請、経費精算 など |
もし当てはまるものがあれば、電子化を検討するタイミングかもしれません。
電子化できる労務関係書類
人事労務の業務のなかで、電子化が可能な書類を紹介します。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 源泉徴収票
以上の書類を電子化することで、作業時間や紙の保管コストの削減、書類管理の効率化のメリットがあります。
すべての業務がすぐに電子化できるわけではないので、検討している企業は、社内ルールを踏まえ、まずは電子化に適した書類を選び、スモールスタートしてみるのも一案です。
すでに2019年4月から労働条件通知書の電子交付が認められ、労働者が希望する場合には、メールやSNS、FAXなどの電子媒体での交付が認められています。労働条件を迅速かつ効率的に労働者に通知できるようになりました。
さらに2020年4月に施行された法改正により、人事労務手続きの電子化が、いっそう推進されていくことが予想されています。
人事労務で電子化が義務化されている業務
2020年4月から、特定の法人を対象に社会保険・労働保険の手続きにおいて電子申請が義務化されました。
もしまだ書面で申請している場合は、すぐに対応が必要です。 知らずに手続きを書面ですると、申請が無効になる可能性もあるため注意しましょう。
対象企業と義務化されている主な手続きは以下のとおりです。
| 対象企業 |
|---|
| ・資本金1億円超の法人 ・相互会社(保険業法) ・投資法人 ・特定目的会社 |
※社会保険労務士が手続きを代行する場合は電子申請が必須
| 義務化された主な手続き | ||
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険関係 | 労働保険関係 | 雇用保険関係 |
| ・被保険者報酬月額算定基礎届 ・被保険者報酬月額変更届 ・被保険者賞与支払届 | ・年度更新申告書 ・概算/確定保険料申告書 | ・資格取得/喪失届 ・高年齢雇用継続給付申請 ・育児休業給付申請 |
※2025年1月からは、企業の規模に関係なく労働安全衛生関係の一部手続き(労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告など)について電子申請が義務化されました。ただし、経過措置として、当面の間は電子申請が困難な場合は書面による報告が可能とされています。
電子申請を行わない場合の罰則は現時点では設けられていません。しかし、正しく手続きが行われないと申請自体が無効になる可能性もあります。
絶対に電子申請でないと受理されないのかと思った方も入るかもしれません。例外として電気通信回線の故障や災害などにより電子申請が困難な場合は、従来どおり書面による申請も認められています。
例外に該当する場合以外は、基本的に書面での申請は認められず、電子申請が原則なので、二度手間ややり直しを避けるためにも確認しておきましょう。
参照:『2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。』厚生労働省
人事労務において電子化が進められている理由
日本企業が直面する人材不足や働き方改革への対応において、人事労務業務の電子化は避けて通れない課題です。
電子化に対応していないと、非効率な業務フローが原因で、企業の成長が進まなくなる可能性もあります。では、具体的にどのような理由で人事労務の電子化が推進されているのかを見ていきましょう。
人材情報を人事戦略に活用するため
企業の成長と発展のためには、限られた人材で最大限の成果を上げることが必要です。
人事労務の電子化が進んでいないと、社内でデータが分散して個々の能力を正しく評価できません。その結果、適材適所の人材配置や採用データの分析など、人材情報を戦略的に活用することが難しくなります。
人事労務のデータを電子的に一元管理することで、必要な情報にアクセスできるようになります。
人材のスキルや適性を正確に把握したうえで、人材育成や配置を最適化し、人材活用の精度を高めることが可能です。
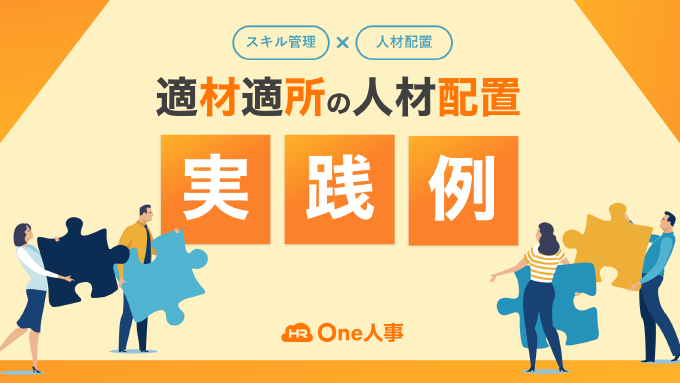
業務を効率化するため
人事労務部門は、採用から教育、評価、労務管理まで幅広い業務を担当しています。
人事労務の電子化が進んでいない企業では、いまだに紙の書類や手作業が多く、日常的な定型業務に追われてしまうのが現状です。
その結果、本来注力したい戦略的な業務に十分な時間を割くことができません。
人事労務の電子化によって業務プロセスを効率化することでミスを減らし、制度設計の見直しなど、より重要度の高い業務に注力できるようになるでしょう。
電子化されたデータをリアルタイムで管理できるため、、意思決定のスピードアップにもつながります。
人事労務業務を電子化するメリット
人事労務業務の電子化は、業務効率化とコスト削減を実現する重要な取り組みです。
「手作業が多く、担当者の負担が大きい」「法改正対応が大変」「テレワークの導入に苦戦している」といった課題がある企業にとって、改善につながります。
具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
ノンコア業務を自動化できる
人事労務のノンコア業務に時間がかかりすぎていませんか。「年末調整や社会保険手続き、勤怠集計に膨大な時間を費やしている…」そんな課題を抱える企業に、人事労務業務の電子化は有用です。
人事労務業務の電子化によって、これまで手作業で行っていた多くの業務を自動化できます。
| 具体例 | |
|---|---|
| 年末調整 | 控除証明書のデータ取得、申告書作成、税額計算まで自動処理 |
| 社会保険手続き | 資格取得・喪失手続きをオンラインで完了し、提出業務を効率化 |
| 勤怠管理 | タイムカードの集計や有給休暇管理をシステムで一元化 |
| 給与計算 | 勤怠データと自動連携し、正確な計算を即時処理 |
手作業を減らすことで人事担当者は、定型的なオペレーション業務に割く時間を減らし、コア業務に集中できるようになります。
法改正に自動対応できる
法改正のたびに手動で社内フォーマットを更新していませんか。
人事労務では、最低賃金の変更や社会保険料率の改定など法改正への対応作業が、忘れたころに発生します。
最新の法律に自動で対応できるシステムが多いため、電子化することで、手作業での修正や確認の負担を大幅に軽減できます。漏れなく法律に準拠した運用が可能です。
| 具体例 | |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 社会保険料率の変更が自動適用され、手動の計算ミスを防止 |
| 給与計算 | 最低賃金改定の影響を自動計算し、給与計算をスムーズに |
法改正への対応漏れによるコンプライアンス違反のリスクを最小限に抑えられるのがメリットです。
多様な働き方を選択できる
テレワークやリモートワーク、フレックスタイム制の勤怠管理に課題はありませんか。
人事労務の電子化によって、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現できます。
| 具体例 | |
|---|---|
| テレワーク | 勤怠打刻や各種申請がオンラインで可能に |
| フレックスタイム・時短勤務 | 労働時間を自動集計し、勤務状況を可視化 |
| モバイル対応 | 外出先からでもスマホで承認作業が可能 |
働き方の選択肢を増やし、従業員満足度の向上にもつながるのは大きなメリットといえるでしょう。
人的ミスを軽減できる
人事労務業務において手入力や転記作業によりミスが発生していませんか。転記ミスや計算ミスが発生すると、給与支払いの遅延や従業員の不満につながります。電子化により計算処理を自動化することで、人的ミスを大幅に減らせます。
| 具体例 | |
|---|---|
| データ入力の自動化 | 転記ミスを防止 |
| 計算処理の自動化 | 給与・社会保険料の計算をミスなく処理 |
| 業務の属人化を防止 | 担当者が不在でも、同じ品質で業務を継続 |
人事労務システムを活用すれば人為的なエラーのリスクを下げ、正確な業務処理が可能になるでしょう。
セキュリティを強化できる
人事労務を電子化する際、セキュリティ対策に不安が残る方もいるかもしれません。給与・個人情報を含む人事データは、適切な管理が求められる重要な情報です。適切なサービスを選定できれば、電子化によって、アナログな方法よりも安全で簡単な情報管理が可能になります。
| 具体例 | |
|---|---|
| IPアドレス制限 | 不正アクセスを防止 |
| 通信の暗号化 | 機密データを安全に送受信 |
| アクセス権限の設定 | 必要な情報にのみアクセス可能 |
セキュリティ対策を強化したい人事担当者こそ、電子化を検討してみることをおすすめします。
人事労務業務を電子化するデメリット
人事労務業務の電子化には多くのメリットがある一方で、導入や運用における課題を考慮する必要があります。
電子化を成功させるためには導入時のコストやシステムに応じたセキュリティ対策、変化に対する対応といった課題を事前に把握しておくことが重要です。
人事労務の電子化における主なデメリットと、対策を解説していきます。
システム導入時にコストがかかる
人事労務を電子化するためのシステムの導入には、まとまった初期投資が必要です。システムの契約費用や購入費用に加え、サーバーやネットワーク環境の構築費用も考慮して見積もりましょう。
従業員数が多い企業では、各事業所への機器やシステムの配置が必要となり、初期費用が高額になる可能性があります。
課題への解決策として、優先度の高い業務から段階的に電子化したり、オンプレミス型より低コストで運用が可能なクラウド型を選択したりする選択肢があります。
システム導入時に利用できる助成金や補助金も検討してみましょう。
長期的に見ると、人件費削減や業務効率化によるコストメリットも大きいため、トータルコストで判断することが重要です。
新しいセキュリティ対策が必要
人事労務の電子化によって、紙の書類管理よりも高度なセキュリティを確保できる一方、運用方法を誤ると新しいリスクへの対策が必要になります。
とくに、システム導入時には、従来の紙ベースの運用とは異なるリスク管理の視点が求められる点に注意が必要です。
| 電子化による新たなリスク |
|---|
| ・ID・パスワードの管理不足による不正アクセス ・サーバー攻撃 ・データ流出 ・内部不正(従業員のデータ持ち出し・誤操作) |
データの暗号化や多要素認証の導入、柔軟にアクセス権限を設定できる電子化システムを選びましょう。
人によってシステムに慣れるまで時間がかかる
人事労務の電子化を進める際、ITリテラシーに個人差がある場合、すぐに効率化が実現するとは限りません。紙ベースの業務から切り替えた直後は、一時的に業務効率が低下する可能性があります。
とくにITに不慣れな従業員が操作に戸惑い、習得に時間がかかることもあります。
導入前は研修を実施して、スキルアップをサポートするなどの準備が必要です。困ったときに役立つマニュアルの準備も欠かせません。
定着するまでのフォローが重要ですが、一度慣れると大幅な業務効率化が期待できます。定着を早めるために、導入前に操作性を確認し、従業員にとって使いやすいシステムを選びましょう。
システム障害が発生する可能性がある
人事労務の電子化でクラウドシステムを採用する場合、インターネット環境に依存するため、接続不良やシステム障害が発生する可能性も否定できません。
ベンダー側のトラブルによってシステムが利用できなくなることもあります。クラウドの利便性を活かしつつ、障害時の代替手段を用意しておくことが重要です。災害時の対応やバックアップ体制を確認し、信頼性の高いサービスを選びましょう。
電子化の定着までにフォローが必要
人事労務を電子化したあと、システムを導入して終わりではなく、運用の継続が課題となります。定着には組織全体での継続的なフォローアップが欠かせません。
導入後にシステムの活用度が低下しないよう、定期的な研修を実施したり、現場の意見を取り入れ、運用方法を改善したりすることが大切です。
とくに操作に不安がある従業員には個別のサポートを提供し、全体の底上げをはかりましょう。
人事労務業務を電子化する手順・ポイント
人事労務業務の電子化を成功させるためには、計画的な導入と運用が重要です。
システムを導入しただけでは十分な効果は得られません。現場の課題整理、適切なシステム選定、定着まで担当者が主導してフォローしましょう。
人事労務の電子化を進めるための5つのステップを解説します。
1.電子化する業務範囲と導入時期を検討する
優先順位の高い業務から人事労務の電子化を進めます。まずは負担が少なく、効果が見えやすい業務から段階的に進めることがポイントです。
たとえば給与明細や社会保険手続きなどは、従業員の負担が少なく、取りかかりやすい領域です。電子化の対象となる従業員の範囲も事前に検討し、必要に応じて紙での対応も残すなど、柔軟な運用体制を検討しましょう。
2.現場の課題を整理する
人事労務の電子化を進める前に、紙での手続きにおける問題点を特定します。「何が問題なのか?」を明確にすることで、電子化の効果最大化につながります。
【よくある非効率な部分】
- 申請書類の承認遅れ
- 書類の紛失
- 管理の煩雑さ
- データの二重入力による時間のロス
- 紙文書を介したコミュニケーションロス
現場の課題を具体的に洗い出し、業務の優先度を決めることで、導入計画を立てられます。
3.運用しやすいシステムを選定する
人事労務業務の電子化を成功させるためには、自社の業務フローに適したシステムを選ぶことが重要です。
システム選定の際、「機能が多いから」「有名だから」ではなく、自社の業務に合っているかどうかを忘れないようにしましょう。
| 検討事項の具体例 | |
|---|---|
| 既存の業務フローとの親和性 | スムーズに移行できるか? |
| 電子申請への対応可能性 | 社会保険・雇用保険の電子申請が可能か? |
| 将来的な法改正への対応力 | システムが自動でアップデートされるか? |
| 従業員の使いやすさ | ITに不慣れな人でも直感的に操作できるか? |
「導入しやすいか」だけでなく、「運用しやすいか」を基準に選びましょう。
4.システム導入後の費用対効果を可視化する
人事労務を電子化したあとは、定期的に効果を数値で把握し、継続的に改善することがポイントです。「どのくらい業務時間が削減されたのか?」システム導入前後の作業時間を数値で把握します。
| 測定するといい指標の例 | |
|---|---|
| 業務時間の削減率 | 作業時間を比較 |
| コスト削減額 | 印刷費・保管スペースの削減額を算出 |
| 従業員満足度 | アンケートやヒアリングで業務改善点を把握 |
従業員にもヒアリングし、現場からのフィードバックを活かしていくことで、運用の最適化を進めます。費用対効果を測定し、電子化のメリットを最大限引き出しましょう。
5.社内周知を徹底する
人事労務の電子化を実現したのに、「現場で活用されていない」という事態を防ぐために、社内周知を徹底することがポイントです。現場がスムーズに活用できる環境を整えましょう。
まずは操作方法や従来の業務フローの変更点をていねいに説明します。
操作手順や申請方法については明確なルールをつくり、全員が統一された方法で活用できるようにする必要もあります。
さらに従業員向けの研修プログラムを体系的に整備し、初期だけでなく、定期的なフォローで、現場に浸透させます。
従業員が安心してシステムを活用できるようにフォロー体制を強化しましょう。
人事労務業務を電子化する際の注意点
人事労務業務の電子化を進める際には、法律の確認やセキュリティ対策、書類の保存要件など、いくつかのポイントに注意が必要です。
- 電子化に適用される法律を確認しておく
- セキュリティ対策が万全なシステムを導入する
- 書類の保存要件を満たしているか確認する
電子化をスムーズに進めるために、注意点に気をつけながら導入を進めましょう。
電子化に適用される法律を確認しておく
人事労務関連書類の電子化には、主に電子帳簿保存法や労働基準法、e-文書法が関係します。
| 主な法律 | 人事書類の電子化にかかわる規定 | |
|---|---|---|
| 電子帳簿保存法(2022年1月の改正) | 税務関係の帳簿や書類を電子データとして保存することを認める法律 | ・労働条件通知書などの人事労務関連書類の電子化を認める ・適正事務処理要件が廃止され、より簡便に電子保存が可能に |
| 電子帳簿保存法(2024年1月の改正) | 電子取引の電子保存が義務化 | |
| 労働基準法の施行規則(2019年4月) | 労基法を具体的に運用するための細かいルールを定めた規則 | ・労働条件通知書の電子交付を認める ・書面だけでなく、FAXや電子メール、SNSなどを通じて労働条件を明示することが可能に |
| e-文書法 | 電子的に作成された文書の法的効力を認める法律 | 契約書や通知書も、紙の文書と同様に法的効力を持つ |
企業は電子データで保存している書類を適切に管理しなければなりません。「労働条件通知書を交付する際は、労働者の同意を得ているか」「電子帳簿保存法に準拠した形式でデータを管理しているか」など、誤った対応がないか確認しましょう。
セキュリティ対策が万全なシステムを導入する
人事労務の電子化に際して、自社のセキュリティ要件を明確に定義し、要件にあてはまるシステム選びが重要です。
初期段階で適切に要件を定義しておくことで、情報漏えいや改ざんなどのリスクを最小限に抑えられます。
とくに重要なセキュリティ対策は以下のとおりです。
| データの暗号化 | データが第三者の手に渡った場合でも内容を読み取れなくなる |
| アクセス権限の管理 | 必要な人だけが、必要なデータにアクセスできるよう設定 |
| バックアップとファイアウォール | データ損失や不正アクセス、外部からの攻撃防止 |
人事異動や退職時は不要になったアクセス権を削除することも忘れずに対応しましょう。
書類の保存要件を満たしているか確認する
人事関連の書類を電子保存するには「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つ要件を満たす必要があります。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 真実性の確保 | ・改ざん防止措置の実施・タイムスタンプの付与・事務処理規程の制定 |
| 可視性の確保 | ・画面・書面での確認機能・検索機能の実装・システム関連文書の備付 |
また、電子化したデータの保存期間や管理ルールも明確に定めます。運用ルールが不明確な場合は、早めに見直しを行いましょう。
人事労務を電子化するなら「One人事」
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。
- ノンコア業務に時間を取られ、やりたい業務に注力できない
- どの業務から電子化すればよいかわからない
- 業務ごとにシステムが散在していて管理が煩雑になっている
以上のような課題がある企業は、まずは気軽に聞けるWeb相談だけでもしてみませんか。
「One人事」の初期費用や気になる操作性については、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
人事労務業務を電子化して業務効率を高めましょう
人事労務業務の電子化は、業務効率の向上だけでなく、人材情報の戦略的活用や働き方改革の推進にも大きく貢献します。
自社に適した電子化の方法を検討し、段階的に導入を進めていくことが重要です。
電子化による業務の効率化で削減できた時間を、人材育成や戦略的な人事施策の立案・実行にあてることで、企業の持続的な成長につなげましょう。