台風時に会社がとるべき対応|出勤命令は違法? 勤怠管理の注意点を解説
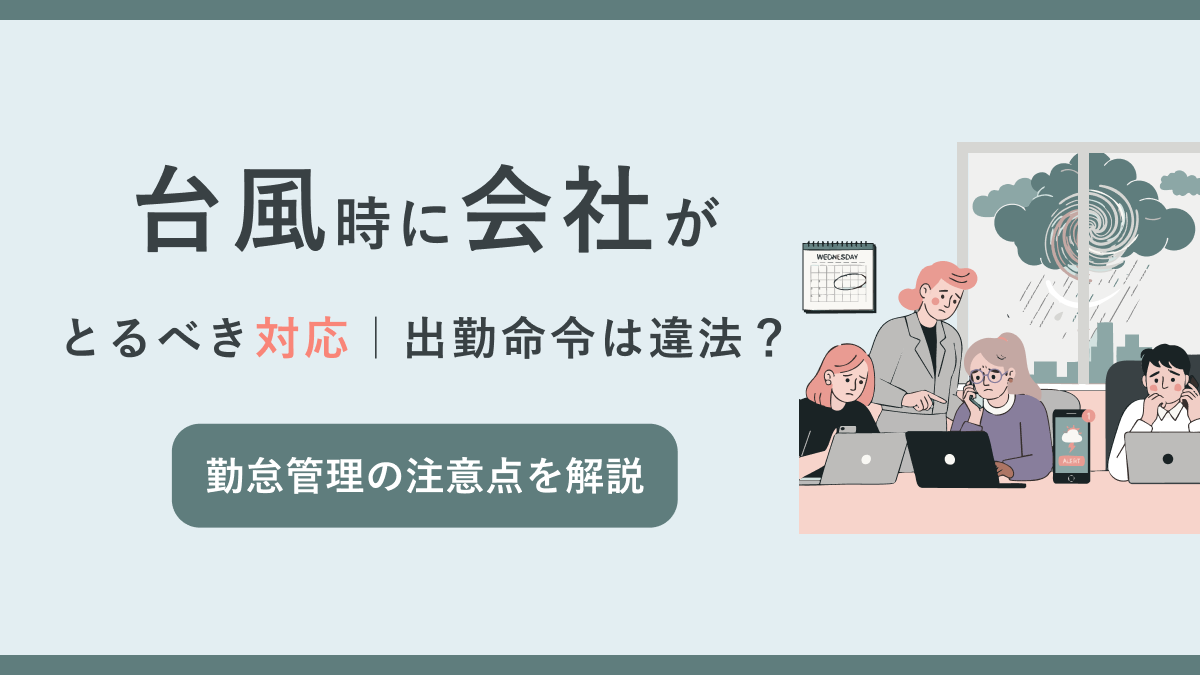
毎年のように日本列島をおそう台風は、企業活動への影響が決して小さくありません。出勤すべきか、自宅待機にするべきか。従業員の安全と事業継続の間で、頭を悩ませる担当者もいるでしょう。
台風接近時に、業務の都合上やむを得ず出勤命令を出すことは、違法なのでしょうか。また、勤怠管理はどのように扱えばよいのでしょうか。
本記事では、台風時に企業がとるべき具体的な対応策や出勤命令の法的な位置づけ、勤怠管理のポイントについて最新の実務と法令をもとに詳しく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
台風の日に出勤させるのは違法?
台風の日に出勤を命じることは、状況によっては違法と判断される可能性があります。
暴風雨や交通機関のマヒが予測されるなかで出勤を強制すると、安全配慮義務違反とみなされるおそれがあります。
労働契約法第5条では、使用者には労働者の生命や健康を守るため、必要な配慮を行う義務があると明記されているためです。
つまり、従業員の安全を軽視した企業の対応は、法的責任を問われるリスクがあるのです。
たとえば、台風接近中に通常どおりの出勤を命じ、従業員が通勤途中に転倒や交通事故にあった場合が該当します。損害賠償請求を受けたり、企業の信用が損なわれたりするケースも少なくありません。
判断を従業員に任せる場合は注意
台風接近時に「出勤は各自の判断で」と、一見柔軟に見える対応にも注意が必要です。判断の基準があいまいなままだと、従業員の間で混乱や不公平感が生じやすくなります。
台風など自然災害時の出勤ルールは、就業規則や災害時マニュアルに明確に定めておきましょう。そして、決めたルールは従業員に周知徹底しておく必要があります。

在宅勤務も検討を
台風などの自然災害に備えて、あらかじめ在宅勤務を制度として整備しておくことは重要です。
通勤リスクを避けながら、業務を止めずに続けられるため、事業継続計画(BCP)の一環として取り入れる企業も増えています。
実際、台風接近時に在宅勤務へ切り替えた企業では、従業員の不安を軽減しつつ、業務も滞りなく継続できたという事例があります。
普段から在宅勤務のルールやIT環境を整備しておくと、 いざというときにも、各自が戸惑うことなく業務を遂行できるでしょう。
台風時の出勤命令がすぐに違法とされるケースは多くありませんが、従業員の安全を守るうえでも、在宅勤務の制度化をおすすめします。
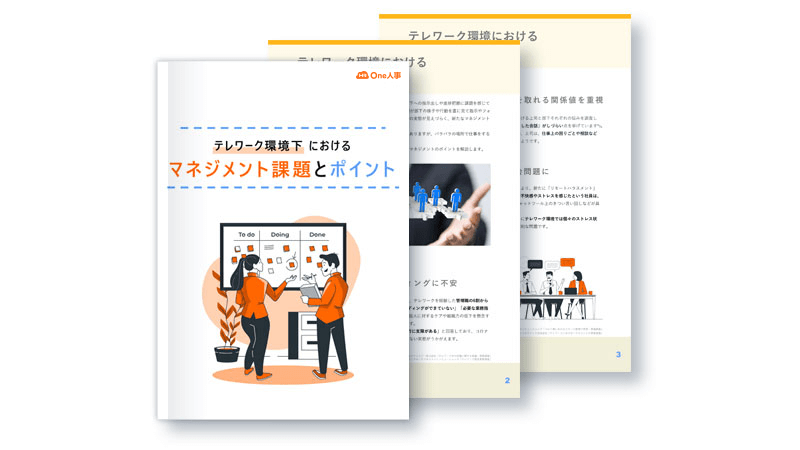
台風の接近に備えて会社がしておきたい対応
台風の接近時、従業員の安全を守りながら事業を停止させないために、平時からの備えが重要です。台風に備えて、企業が講じておきたい5つの対応策を紹介します。
- 就業規則や災害マニュアルを整備する
- 特別休暇の導入を検討する
- 就業時間外の情報伝達手段を定める
- リモートワークを導入する
- BCP(事業継続計画)を策定する
台風接近のニュースが流れた際に「今回は出社させるべきか?」「事業はどう動かすか?」と迷う方も多いでしょう。
従業員の安全と事業の継続を両立させるために、企業として取り組みたい内容を順に解説していきます。
就業規則や災害マニュアルを整備する
台風発生時の混乱を防ぐには、事前にルールを明文化しておく対策が欠かせません。 就業規則や災害マニュアルには、次のような項目を盛り込んでおきましょう。
- 気象警報や交通機関の運休など、出勤可否の判断基準
- 台風の強さに応じた自宅待機、時差出勤、早退、在宅勤務などの対応方針
- 遅刻・早退・欠勤が発生した場合の取り扱い(給与や評価への影響)
たとえば、「台風など自然災害による遅刻や欠勤は正当な理由として扱う」「給与・人事評価には影響しない」といった文言を明記しておくと、従業員も安心して判断できます。
台風時のルールは、マニュアル化し、平時から従業員に周知徹底することが重要です。非常時でも落ち着いて行動できる職場環境が整います。
特別休暇の導入を検討する
台風で通勤が危険な場合、年次有給休暇とは別に「特別休暇」を設けておくと、従業員が安心して安全を優先できます。
とくに、次のような状況を想定しておくと制度設計がしやすくなるでしょう。
- 公共交通機関が全面運休した場合
- 気象警報が発令され、通勤が危険と判断される場合
- 会社が自主的に出勤停止を決定した場合
以上のようなケースでは、あらかじめ「特別休暇として処理する」ことを定めておくと、無理な出勤を避けられます。
取得条件や申請方法は就業規則に明記し、休暇取得時の不公平感が出ないようルール化しておくことが大切です。制度を整えておけば、災害時の判断負担を減らし、現場の混乱も防げます。
就業時間外の情報伝達手段を定める
台風の進路や影響は直前まで変化するため、就業時間外でも確実に情報を伝える手段を決めておく必要があります。
対応にあたっては、以下の3点を明確にしておきましょう。
- 何を伝えるか: 出勤可否、勤務形態、帰宅指示など
- 誰が判断・連絡するか: 担当者、情報を集約する人
- どう伝えるか・方法: メール、社内SNS、電話連絡網など複数手段を併用
手段は1つに限定せず、通信障害や深夜対応も想定しておくのがポイントです。
あわせて、定期的に連絡訓練を実施しておくと、いざというときにも混乱なく、社内で情報伝達ができます。
リモートワークを導入する
台風時の安全確保と業務継続を両立させるために、リモートワークの導入は有効な対策です。
出勤が難しい状況でも、従業員が自宅で業務を行える体制を整えておけば、安心して業務を続けられます。
リモートワークの導入にあたっては、以下の準備が必要です。
- 社外からアクセス可能なパソコンや通信環境の整備
- 社内チャットやビデオ会議などのコミュニケーションツール
- リモート対応時のルール(勤務報告、業務の優先順位、セキュリティ管理など)
テレワークのルールを平時からマニュアル化し、従業員に共有しておくことで、非常時にも円滑に業務連絡や進捗共有を行えます。
制度として整えておけば、災害時の対応力だけでなく、平時の柔軟な働き方にもつながります。
BCPを策定する
台風・地震などの災害に備え、BCP(事業継続計画)を策定しておくことは企業のリスク管理において欠かせません。緊急時でも業務を止めず、被害を最小限に抑えるための体制づくりが目的です。
BCPの策定時は、以下の内容を明確にしておきましょう。
- 指揮命令系統と各担当者の役割分担
- 出勤・休業・連絡判断の基準
- 代替拠点やリモート勤務の活用方針
- 優先的に継続すべき業務と手順
内容は、自社の業種・規模・地域特性にあわせて現実的に設計することがポイントです。
一度策定したあとは、定期的な見直しと訓練の実施により、形骸化を防ぎましょう。
BCPは、非常時に「迷わず動ける」企業をつくるための指針となります。
台風の接近時に会社がとるべき対応
台風の接近時、企業には業務を止めずに従業員の安全を守る対応力が求められます。判断や準備を怠れば、混乱や事故、信頼の低下を招くおそれもあるため、柔軟に順序立てて対応しなければなりません。
ここでは、台風がまさに迫っているときに、企業がとるべき対応策を4つ紹介します。
- 台風情報を収集する
- 業務継続の可否について判断する
- 情報を速やかに共有する
- 個別の状況を踏まえた対応をとる
非常時でも冷静かつ公平に対応できるよう、備えを見直すきっかけとしてください。
1.台風情報を収集する
台風接近への対応は、正確な情報収集から始まります。気象庁や日本気象協会、自治体など信頼できる情報源から、以下の点を継続的に確認しましょう。
- 台風の進路・規模
- 警報や避難情報の有無
- 公共交通機関の運行状況
状況は時間とともに変化するため、複数回に分けて確認し、最新情報をもとに柔軟な対応を検討します。
警報が発令された場合は、出勤ルールの見直しや在宅勤務への切り替えを考えましょう。交通機関の運休が予想される場合は早めに帰宅指示を出し、従業員の安全を最優先に判断することをおすすめします。
現場任せにせず、会社として主体的に集約・発信する体制を整えておきましょう。
2.業務継続の可否について判断する
台風によって事業所や交通インフラに支障が出た場合、企業はすみやかに業務を継続すべきかどうかを判断する必要があります。
以下のような状況が見られる場合は、無理に業務を続けず、休業を検討しましょう。
- 設備や施設に被害が出ている
- 原材料の仕入れや納品に支障がある
- 主要な公共交通機関が運休している
休業を決定する際は、何よりも従業員の安全を最優先に考えましょう。通勤時の危険や現場での二次災害リスクを避けるため、早めの判断が必要です。
必要に応じて、休業手当の支給や特別休暇の付与を検討し、従業員が安心して安全を優先できる環境を整えます。
対応方針は、就業規則やマニュアルにあらかじめ明記し、非常時にも迷わず行動できます。
3.情報をすみやかに共有する
台風接近時に対応方針が決まったら、できるだけ早く全従業員に情報を伝えることが重要です。共有が遅れると、従業員が自己判断で出勤や休業を決めてしまい、職場内で混乱や不公平が起きやすくなります。
メールやチャット、電話など複数の手段を使い分け、確実に情報を届けましょう。従業員からも質問や出勤可否の連絡ができるようにしておくと、状況に応じた柔軟な対応がしやすくなります。
日頃から、情報共有の手段や担当を明確にしておくことで、緊急時にも落ち着いて対応できます。
たとえば、どの手段を誰が使うかを決めておけば、判断後すぐに全員へ伝達でき、現場の混乱を防げるでしょう。
4.個別の状況を踏まえた対応をとる
台風接近時の対応は、従業員ごとの状況を考慮することが重要です。地域や交通手段、家庭事情によって、安全に出勤できるかは異なります。
一律の指示ではなく、以下のような観点から柔軟な対応を心がけましょう。
- 公共交通機関の運休や遅延の影響を受けていないか
- 通勤路の安全が確保されているか
- 自宅での勤務が可能か(IT環境・業務内容の確認)
- 育児・介護など家庭の事情が出勤に影響していないか
とくに出勤が避けられない職種では、交替要員の配置や業務の再割り当てが必要です。
従業員一人ひとりの事情に目を向け、無理のない働き方を選択できるようにすることが、企業への信頼にもつながります。

台風で帰宅指示・自宅待機を出す場合の勤怠管理
台風接近時に従業員へ帰宅指示や自宅待機を命じる場合、勤怠管理と賃金の取り扱いに注意が必要です。対応を誤ると、不公平感やトラブルの原因となるため、勤怠管理においても法的な理解と事前のルール整備が大切です。
帰宅や自宅待機を本人の判断に任せた場合
台風の接近時に「各自の判断で安全を最優先に行動してください」と案内した場合、判断は従業員にゆだねられます。
判断を個人に任せると会社が命じた休業ではないため、ノーワーク・ノーペイの原則により、休業手当の支払い義務は発生しません。
勤怠記録には「会社命令による退勤」か「自己判断による退勤」かを明確に記録しておく必要があります。
判断を完全に従業員に丸投げしてしまうと、現場の混乱や不公平感を招きやすく、安全配慮義務の観点からも望ましくありません。
例として「気象警報発令時は原則として自宅待機」「交通機関が運休した場合は特別休暇を付与」など、具体的な対応方針を明文化しておきましょう。

台風時の休業手当の取り扱い
台風による休業時、賃金の支払い義務は、「会社の判断による休業」と「不可抗力による休業」で異なります。
| 会社の判断による休業(手当支払い必要) | 不可抗力による休業(手当支払い不要) |
|---|---|
| ・台風の影響はあるが、業務継続は可能な状態 ・従業員の安全を考慮し、会社が休業を判断した | ・暴風や災害により会社が被害を受けた ・交通機関が完全に止まり出勤が不可能になった |
会社の判断による休業は、労働基準法第26条に基づき、平均賃金の60%以上の「休業手当」の支払いが必要です。
さらに、会社の故意または過失による休業では、状況によっては民法の規定により、賃金を全額100%支払う必要が生じることがあります。
ただし、就業規則で休業時の取り扱いをあらかじめ定めておけば、賃金全額払いの責任を回避することが可能です。
一方で、会社が最大限の注意を払っても避けられない事態であれば、「不可抗力」として休業手当の支払い義務は生じません。また、従業員が「台風の被害が怖いから休む」と自己判断で欠勤した場合も、賃金・休業手当の支払いは不要です。
台風時の有給休暇における注意点
台風が接近して出勤が困難な状況でも、企業が有給休暇をどのように扱うかは慎重な判断が求められます。有給休暇は本来、従業員がみずからの意思で取得するものであり、会社が一方的に消化させることはできません。
台風時の有給休暇に関する注意点を紹介します。
有給休暇の強制はできない
有給休暇は労働者の権利であり、台風の接近時に取得するかどうかは従業員本人の自由です。 「台風だから今日は有給にして」といった強制的な取得指示は、労働基準法違反となります。
企業ができるのは、あくまで取得を推奨することにとどまり、本人の意思を尊重する必要があります。
従業員が有給休暇を取得しない場合の対応
台風の影響で従業員が有給休暇を使わず欠勤した場合、原則として「欠勤扱い」となります。欠勤であれば、会社に給与の支払い義務はありません。給与の減額や欠勤控除が適用されます。
ただし、会社側が休業を命じた場合は、平均賃金の60%以上の休業手当の支払いが必要です。

まとめ
台風時の出勤や休業について法的な明確な規定はなく、最終的な判断は企業にゆだねられます。だからこそ、従業員の安全を第一に、無理な出勤命令や判断の丸投げは避けたいところです。
対応を迷わないためにも、出勤・休業・有給休暇のルールはあらかじめ定め、就業規則や災害マニュアルに明記し、全従業員へ周知しておきましょう。
休業する場合は、理由や判断主体によって休業手当の支払いが変わるため、慎重に判断し、勤怠管理と労務対応を徹底することが求められます。
