就業規則とは【簡単に】必要な理由や作成義務と要件、労働契約との関係、変更時の注意点
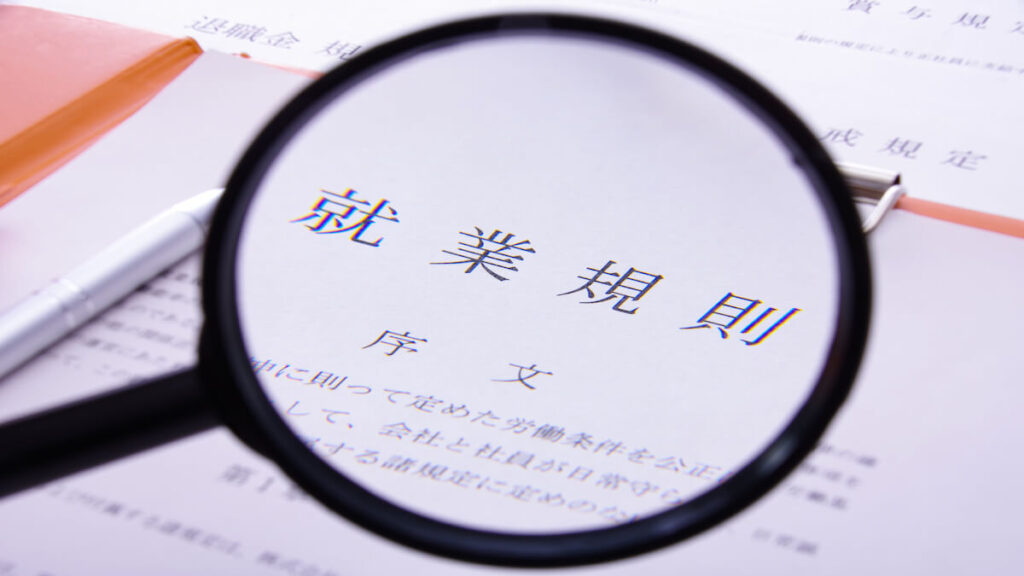
就業規則は、従業員が就業上遵守すべき規律や、労働条件が記載された重要な規則です。法律の範囲内で企業独自のルールを定められるなどメリットも多い就業規則ですが、十分に理解されている方は少ないかもしれません。
本記事では、就業規則の基本から変更する場合の注意点まで詳しく紹介します。就業規則を作成する必要がある方は、ぜひ参考にしてください。
 目次
目次
就業規則とは
就業規則とは、従業員が就業上遵守すべきルールや、労働条件をまとめた規則です。
それぞれの企業における働き方や労働条件などを定めたもので、従業員を常時10人以上雇用している企業には、法律によって作成と届出が義務付けられています。
就業規則は、労使間を規律する根本的な規則を記載しているため、労使間のトラブル防止に役立つ重要なものともいえるでしょう。
なぜ就業規則が必要なのか
就業規則は法律上の作成義務がなくとも、作成すべき理由が存在します。就業規則が必要な4つの理由について解説します。
- 社内の秩序の保持
- 社内トラブル対策
- 企業の社会的責任
- 企業の利益を守る
社内の秩序の保持
就業規則が必要な理由の一つとして挙げられるのが、社内の秩序の保持です。
従業員に対して就業規則を提示することで、守るべき社内ルールが明確になります。その結果、従業員の中でルール遵守が進み、社内の秩序が保たれます。全員が安心して働くためにも、社内秩序の保持は重要といえるでしょう。
社内トラブル対策
就業規則には、解雇基準や命令拒否に対する処罰規定なども定められています。
社内トラブルは、就業規則をもとにして対処できます。たとえば、業務命令に従わない従業員や規律違反を繰り返す従業員がいる場合、拠り所となる規定がなければ適切な対応が取りにくいでしょう。
一方、就業規則があれば、合法的な対処が可能です。
企業の社会的責任
企業の社会的責任も、就業規則を必要とする理由です。企業には、法律を遵守する責任や社会的な責任があります。就業規則でそれらが明確化されることによって、企業は責任を果たしやすくなります。
たとえば昨今問題となっている「セクシュアルハラスメント」や「パワーハラスメント」などに対しても、具体的な罰則を就業規則に定めることで、企業として措置を講じているとみなされるでしょう。
企業の利益を守る
企業の利益を守るためにも、就業規則は必要不可欠です。就業規則に、機密事項の持ち出し制限や退職後の情報持ち出しを禁じる事項を載せておけば、情報漏えいリスクの軽減につながります。
また、企業の利益損失に関連する事項を就業規則で定めておくことで、利益損失の回避が可能です。
就業規則の作成義務について
労働基準法第89条により、条件を満たした企業には就業規則の作成と届出の義務が生じます。具体的には、常時10人以上の労働者を使用する使用者が、義務を負います。
この場合の「常時10人以上」とは、1つの事業所に雇用(所属)している労働者が常態として10人以上いることであり、出勤している人数ではない点に注意が必要です。
労働基準法の第89条、第90条で用いられる「常時10人以上」とは、下記の従業員を含め、当該事業所で使用しているすべての労働者が対象です。
- 正社員
- 臨時的な雇用形態の従業員
- 短期的雇用形態の従業員
- パートタイマー
- アルバイト
ただし、下記の従業員は「常時10人以上」の労働者に含まれません。
- 業務委託の社員
- 派遣労働者
- 繁忙期のみ勤務する臨時職員
勤務中の派遣社員は、派遣元の労働者として「常時10人以上」の労働者にカウントされます。
参照:『労働基準法』 e-Gov法令検索
参照:『就業規則作成・届出に関する FAQ』 厚生労働省
就業規則の作成の必要要件
就業規則を作成する際に必要な要件には何があるのでしょうか。まず、就業規則の作成においては次の2つのルールを守らなければいけません。
- 法律で決まっている最低基準を下回る内容の就業規則は作成できない
- 明文化されていないが、すでに決まっている部分は今の待遇を保証しなければならない
また、就業規則に記載すべき内容として「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」があります。それぞれについて解説します。
絶対的必要記載事項
「絶対的必要記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。内容は次のとおりです。
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項
- 労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由含む)
相対的必要記載事項
「相対的必要記載事項」とは、就業規則において、自社のルールを定める際に記載が必要な事項です。次のような内容が該当します。
- 退職手当
- 臨時の賃金
- 最低賃金額
- 食費や作業用品その他の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 業務外の傷病扶助
- 表彰および制裁の種類
- そのほか従業員すべてに適用される事項
任意的記載事項
法令で定められた事項ではなく、社会通念や公序良俗などを踏まえて各企業で任意に定められる事項が「任意的記載事項」です。たとえば、企業理念や就業規則の解釈・適用範囲、副業の取り扱いなどが挙げられます。
ただし任意であっても、法律で定められた最低基準より内容が低ければ、記載できません。
就業規則と労働契約の関係
就業規則には、労働条件が記載されています。しかし、基本的に就業規則を下回る条件を定めた労働契約は無効です。就業規則は、従業員だけでなく企業側も遵守しなければならず、労働契約においてはさまざまな法令や書類などの関係性をよく理解しておくことが重要です。
類似した書類との相違点
就業規則と類似した契約関係の書類には、雇用契約書や労働条件通知書があります。
雇用契約書
「雇用契約書」は、労使が労働条件について合意したことを証明する書類です。
民法623条の「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」という条文に基づき、労働契約期間や就業する場所、賃金などに関する事項が記載されています。
法律上の作成義務はありませんが、書面で契約書を作成したうえで署名押印し、当事者双方が保管しておくのが一般的です。
労働条件通知書
「労働条件通知書」とは、労働契約に関する期間や賃金など、労働条件に関する事項が記載された書類です。
労働基準法第15条では、使用者が労働者を雇用する際、労働者に対して労働条件を明示することが義務づけられています。これに基づき、明示事項である労働条件を通知するために使用されます。
就業規則を活用するケース
就業規則を活用するケースとして挙げられるのは、次のような場合です。
- 従業員の採用
- 運用方法の確認
- 配置転換
- 出向
- 従業員のトラブル
- 時間外労働や休日出勤
- 遅刻・早退・欠勤などの対処
- 従業員の健康事項
- 休職の取り扱い
従業員側にとっても就業規則の確認は重要です。有給休暇や育児休業などを取得したいとき、退職時などにおいて、規定の確認ができます。
法律に違反した就業規則は無効
労働基準法第92条1項により、法律に違反した就業規則は、法律に違反した部分が無効です。法律に違反した就業規則は労使間トラブルの原因となり、裁判に発展するケースもあります。法律を遵守した就業規則が求められるといえるでしょう。
無効となった就業規則の例
無効となった就業規則の例として、医療法人の事例が挙げられます。この事例では、「前年に3か月以上の育児休暇を取得した従業員については翌年度に昇給させない」という就業規則の規定が争点となり、労働裁判に発展しています。
最高裁判所は、この就業規則が育児・介護休業法第10条「従業員が育児休業をしたことを理由とする不利益な取り扱い」の違反だと指摘し、当該就業規則を無効とし、医療法人に対して賠償を命じました。
就業規則の届け出までの流れ
就業規則の作成から届出までは、次の流れで行うのが一般的です。
- 就業規則案作成
- 過半数代表者からの意見聴取
- 所轄労働基準監督署長へ届け出
- 社内周知
それぞれ解説します。
1.就業規則案作成
絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項、任意的記載事項をふまえ、企業の実態に合わせた就業規則を作成します。その際、厚生労働省のホームページに掲載されている「モデル就業規則」を参考にして作成するのがおすすめです。
2.過半数の従業員からの意見聴取
就業規則を作成・変更する場合、事業場における過半数代表からの意見を聴く必要があります。
また、これらの意見をまとめ、就業規則の提出の際に「意見書」として添付することが義務づけられています。
3.所轄労働基準監督署長へ届け出
就業規則を作成したら、意見書を添えて所轄の労働基準監督署長に届け出を行います。
4.社内周知
就業規則は、労働者への周知が義務づけられています。各事業所の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などを行い、必ず周知しましょう。
就業規則を変更する場合の注意点
次に就業規則を変更する際に注意するべき2つのポイントを紹介します。
- 賃下げの可否について
- 不利益変更する場合の対応法
賃下げの可否について
基本的に、昇給した給与は下げないケースがほとんどですが、業績の悪化などで下げざるを得ない場合もあります。このように、従業員が不利益を受ける就業規則変更を「不利益変更」といいます。
従業員の給与や退職金を下げる場合は従業員の同意が必要となり、同意があれば合法的に給与や退職金を下げることが可能です。就業規則を作成するときは、不利益変更についての明記が重要です。
不利益変更する場合の対応法
就業規則を変更する場合、従業員の過半数を超える代表者からの意見を聴くことが労働基準法にて定められています。とくに労働条件を低下させるケースにおいては、意見を聴くだけではなく同意を得る必要があります。
また、労働契約法においても「使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」とされています。
これらを踏まえ、企業側が行うべき対応は次のとおりです。
- 説明会などを通し、変更内容変更の必要性を十分に説明する
- 従業員と個別の労働契約書を作成して締結する
参考:『労働契約法』 e-Gov法令検索
参考:『労働基準法』 e-Gov法令検索
まとめ
就業規則は、労使間を規律する根本的なルールが記載されており、それぞれの企業における働き方や労働条件などを定めたものです。法律上の作成義務はなくとも、社内秩序の保持や社内トラブル対策、企業の社会的責任、企業の利益保護といった観点から作成が推奨されます。
記載事項として「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」があり、それぞれ内容が異なります。
また、法律に違反した就業規則は無効です。「不利益変更」を行う際には従業員の同意が必要なため、とくに注意を要します。ポイントを押さえて就業規則を作成し、届出を行いましょう。
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。従業員の入退社手続きや年末調整の効率化を実現し、担当者の負担を軽減することで、人材活用の基盤をつくります。気になる費用や操作性は、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。
