年末調整に必要なものとは? 会社・税務署・市町村など提出先別に解説
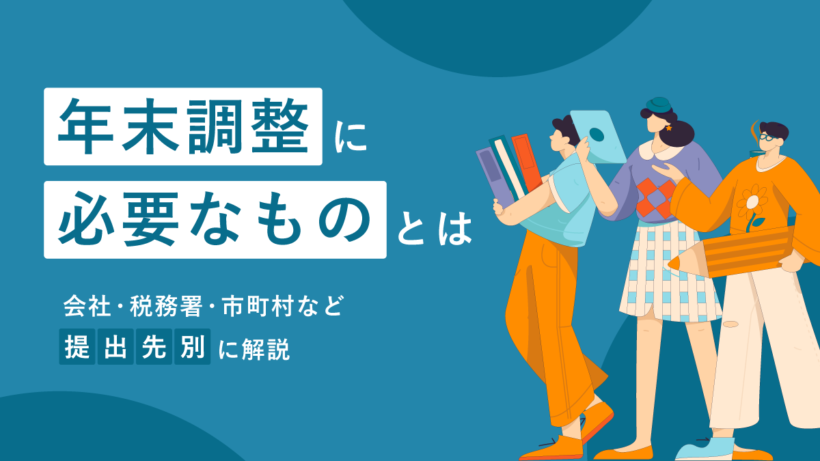
年末調整は、1年間の所得税を正しく計算し直すための大切な業務です。
「毎年やってるのに、何が必要かパッと思い出せない」「提出先ごとに書類を整理するのが地味に面倒」そんな経験はありませんか。年に一度の業務だからこそ、不安がつきまとう方もいるかもしれません。
本記事では、年末調整に必要な書類を提出先別(社内・税務署・市町村)に分類してわかりやすく紹介しています。
▼迷わず効率的に手続きを進めたいと考える担当者の方は、次の資料もぜひご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整の必要書類一覧
年末調整で必要な書類は、提出元や提出先によって大きく次の3つに分類されます。
- 従業員から企業に提出する書類
- 企業から税務署に提出する書類
- 企業から市区町村に提出する書類
具体的に必要な書類は、次のとおりです。
| 提出先 | 書類名 | |
|---|---|---|
| 従業員から企業に提出する書類 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | |
| 保険料控除申告書と控除証明書 | ||
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | ||
| 住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書 ※住宅ローン2年目以降の場合 | ||
| 源泉徴収票※年途中で入社した場合 | ||
| 企業から税務署に提出する書類 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | |
| 源泉徴収票 | ||
| 支払調書 | ||
| 企業から市区町村に提出する書類 | 給与支払報告書(総括表) | |
| 給与支払報告書(個人別明細書) | ||
表で示したように、年末調整の手続きではさまざまな書類を準備する必要があります。提出先によって必要な書類と期日が異なり、早い段階で全体像を把握しなければなりません。
「何を・誰から・いつまでに」集めるのかを早めに整理しておくことで、混乱や再提出の手間を減らせるでしょう。

従業員から企業に提出する書類
まずは、会社が従業員に提出を依頼する書類から確認しておきましょう。従業員に提出してもらう主な書類は、次の5種類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書と控除証明書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書(住宅ローン2年目)
- 源泉徴収票(転職者など)
提出漏れや記入ミスが起こりやすいので、担当者からも働きかけが必要です。それぞれの書類の概要を解説していきます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書とは、各種扶養の対象でないかを確認するための書類です。扶養親族や源泉控除対象配偶者がいない従業員も、提出しなければなりません。
従業員本人の情報に加え、当年の12月31日時点で扶養している親族の情報を記載します。企業は、記載された親族の情報や控除の対象であるかを確認し、年末調整の計算において控除を適用します。
保険料控除申告書と控除証明書
保険料のうち、次の4つは年末調整において控除を受けられます。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 社会保険料
- 小規模企業共済等掛金
保険料控除申告書を用いて、1年間で支払った保険料の総額から控除額を算出します。記載された内容が正しいか判断するために、保険料控除申告書を提出する際は控除証明書を添付するよう従業員に周知しましょう。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
次の控除を申告する従業員は、『基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書』を提出する必要があります。
| 控除の名称 | 適用条件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 最大95万円 |
| 配偶者控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が58万円以下の配偶者がいる | 最大38万円 ※70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は48万円 |
| 配偶者特別控除 | 合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が58万円を超えて133万円以下の配偶者がいる | 最大38万円 |
| 特定親族特別控除(※) | 合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を同じくする年齢19歳以上23歳未満の親族がいる | 最大63万円 |
| 所得金額調整控除 | 年収850万円を超え、次のいずれかの条件に該当する ・本人が特別障害者である ・23歳未満の扶養親族がいる ・同一生計配偶者また扶養親族が特別障害者である | 最大15万円 |
参照:『No.1199 基礎控除』国税庁
参照:『No.1191 配偶者控除』国税庁
参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁
参照:『No.1411 所得金額調整控除』国税庁
※特親族特別控除は、従業員本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下がいる場合に適用されます。ただし、給与所得だけの場合は、給与の収入金額が123万円超188万円以下が要件です。親族は児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。特親族特別控除は令和7年に新設された制度のため、適用漏れがないよう事前に確認しておきましょう。
住宅借入金等特別控除申告書と残高証明書
住宅ローンを利用してマイホームを購入した従業員が提出する書類です。住宅ローンの年末残高合計額から計算された金額を、所得税額から控除できます。
住宅ローンを組んだ初年度は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整による控除申請が可能です。
申告書とあわせて、次の書類が添付されているかを確認しましょう。
- 住宅金融支援機構が発行する融資額残高証明書
- ローンを利用した金融機関が発行する住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
参照:『年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ』国税庁
源泉徴収票
年の途中で中途入社した従業員のように、同年にほかの企業から給与を受け取っていた従業員の年末調整の手続きをする際は、前の職場の源泉徴収票が必要です。
前の職場で給与から税金が天引きされていた場合は、それらを合算して年末調整をしなければなりません。源泉徴収票は、退職後1か月以内に前の職場から受け取れるはずなので、該当する従業員に対しては、なるべく早めに提出してもらうように促しましょう。
▼回収書類のチェックに時間を取られていませんか。回収作業の手間を減らすなら年末調整の電子化がおすすめです。書類の一括チェック機能があるため、紙を目視で確認するよりもラクに確認を完了できます。
→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

企業から税務署に提出する書類
従業員からの書類が集まり計算を終えたら、次は税務署に提出する書類の準備に移ります。
この段階では、法定調書や源泉徴収票など、税務上の報告を目的とした書類が中心です。
担当者としては、「提出が必要なケース」「提出の基準」「どこまで対応すべきか」が気になるところではないでしょうか。
企業が税務署に提出する主な書類は、次のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 源泉徴収票
- 不動産の使用料等の支払調書
- 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
書類によっては提出の要否に基準があるため、条件を整理して紹介していきます。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書を取りまとめる表紙のような役割を持つ書類です。年間給与の合計額や源泉徴収税額、弁護士や税理士などに支払った報酬金額、支払った人数をまとめて記載します。
参照:『令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』国税庁
源泉徴収票
源泉徴収票とは、年末調整の計算が完了した際に、労務担当者が従業員分作成する書類です。それぞれの従業員の年間所得額や控除額の合計、源泉徴収税額などを記載します。
税務署への提出が必要とされている源泉徴収票は、次の2つです。
- 給与の支払金額が一定以上のもの
- 何らかの理由で年末調整をしなかったもの
「給与の支払金額が一定以上のもの」の例として、年間の給与支払金額が500万円を超える従業員や、年間の報酬が150万円を超える役員が挙げられます。
また、「何らかの理由で年末調整をしなかったもの」として、給与などの金額が2,000万円を超える従業員や、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しなかった従業員のうち給与の支払金額が50万円を超える人などが該当します。
参照:『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等』国税庁
支払調書
支払調書とは、弁護士や税理士など、外部機関に支払った報酬が記載された書類です。一定の支払い内容に応じ、法定調書合計表に添付して税務署に提出しなければなりません。
以下に主な支払調書と条件をまとめていますので、自社が該当するかを判断する参考にしてください。
| 支払調書の種類 | 提出条件 |
|---|---|
| 不動産の使用料等の支払調書 | 不動産の地代・家賃、航空機や総トン数20トン以上の船舶の使用料・更新料、権利金などを支払った場合 |
| 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 | 弁護士や税理士などに、源泉徴収の対象となる報酬や料金を支払った場合 |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産やその上に存する権利、航空機や総トン数20トン以上の船舶の売買や貸付けに関して、あっせん手数料を支払った場合 |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 譲り受けた不動産やその上に存する権利、航空機や総トン数20トン以上の船舶の対価を支払った場合 |
参照:『No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等』国税庁
参照:『No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等』国税庁
参照:『No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等』国税庁
参照:『No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等』国税庁
支払調書の提出基準に迷うこともあるかもしれません。今年の支払い実績と照らして、自社にあてはまるかどうか確認してみましょう。

企業から市区町村に提出する書類
税務署への提出と同時並行で、市区町村への必要書類も準備します。従業員が居住する市区町村へ提出するのは、次の2種類の給与支払報告書です。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
どちらも提出期限は翌年の1月31日です。
給与支払報告書とは、従業員の年間給与や控除額などを記載し、翌年度の住民税の金額を決定するために使用します。事業所全体の個人別明細書をまとめた「総括表」と、従業員ごとに給与をまとめた「個人別明細書」の2種類があります。
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(総括表)とは、給与支払報告書の表紙となる書類です。
企業名や企業の所在地、提出先の市区町村に居住する従業員の人数などの情報を記載します。複数の従業員が同じ市区町村に居住している場合は、複数名の個人別明細書に1枚の総括表を添付して提出します。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書)とは、給料・賞与の年間の金額や社会保険料、保険料控除額などの情報を記載する書類です。基本的に、源泉徴収票と同じ内容が記載されます。
市区町村は、企業が提出する給与支払報告書の内容を確認し、従業員の次年度の住民税額を決定します。そのため、年末調整をした翌年の1月31日までに、従業員が居住する市区町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。
年末調整の必要書類を入手する方法
年末調整に必要な書類は、10月下旬〜11月上旬ごろに、税務署から企業宛に郵送されるのが一般的です。早めに準備を進めたい場合は、国税庁の公式ホームページから必要な様式を事前にダウンロードすることも可能です。
ダウンロードにより入手できる書類は次の5種類です。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 特定親族特別控除申告書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 源泉徴収票
そのほかの書類についても、年末調整システムを活用すれば、会社名や従業員情報を入力しておくことで早めに用意できます。また、従業員に提出してもらう必要書類は、システムに過去のデータを蓄積していけるので、簡単な操作で、昨年の情報を引き継いで書類の用意が可能です。
年末調整に必要な書類の多くは、環境さえ整えればWebで簡単に入手・作成・配布ができます。早い段階で準備を始めると、余裕を持ってあわてずに業務を進められるでしょう。

年末調整の必要書類を提出する方法
年末調整で使用する一部の書類は、税務署や市町村に電子データで提出できます。対象となる書類は次のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 従たる給与についての扶養控除等申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 退職所得の受給に関する申告書
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
国税庁が提供する「年調ソフト」を使って作成・提出することが可能です。紙に比べて記入ミスや回収の手間が軽減されるため、利用を検討するのもおすすめです。
税務署に提出する書類の電子保存は、以前まで税務署長からの事前承認が必要でしたが、現在は不要になっています。年末調整においても、デジタルでの提出がさらに進めやすくなっています。
参考:『年末調整手続の電子化に向けた取組について』国税庁
参考:『電子帳簿保存法が改正されました』国税庁
まとめ|年末調整の必要書類を把握してスムーズに手続きを
年末調整では、提出先によって書類の種類も提出期限も異なり、思っている以上に準備項目が多岐にわたります。年末が近づくと通常業務も忙しくなるため、「何を・誰から・いつまでに」集めるかを早めに整理しておくとよいでしょう。
本記事でご紹介した内容を参考に、必要書類を提出先別にリスト化し、従業員への案内や社内チェック体制の準備を進めてみてはいかがでしょうか。
正確な年末調整が完了すれば、翌年の税務対応もスムーズになります。不安なく新年を迎えられるよう、今から着実に準備を進めていきましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
