新卒の年末調整にはアルバイト時代の源泉徴収票が必要?必要書類や注意点を解説
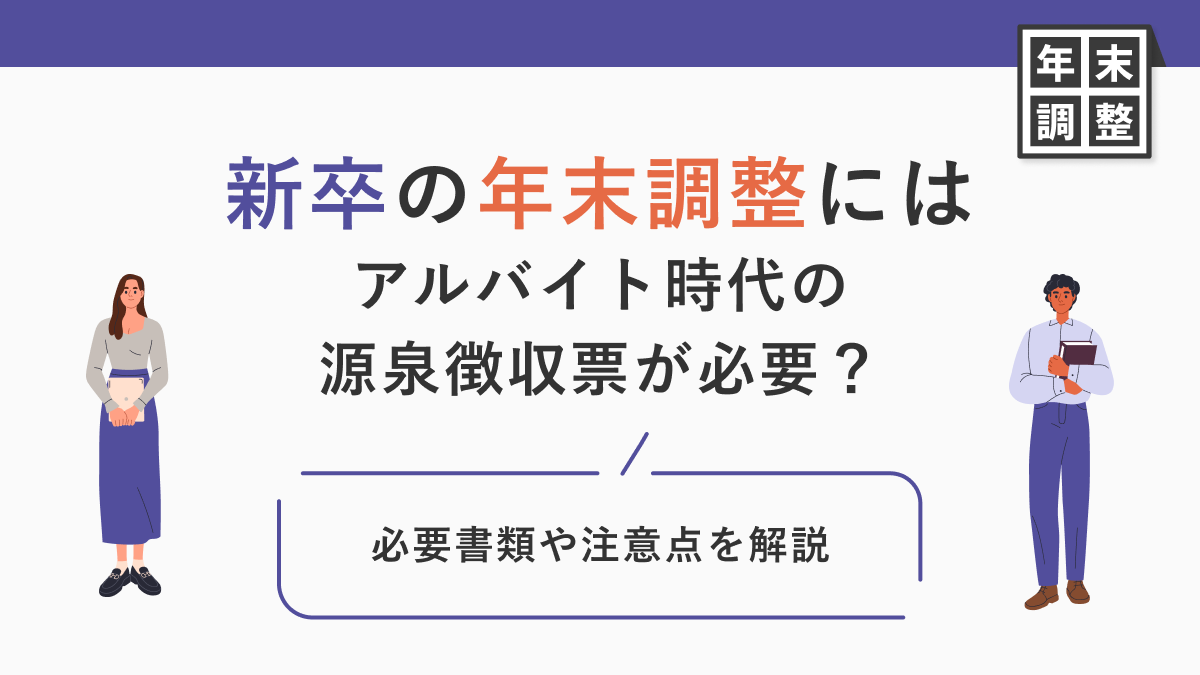
新卒で入社した社員の年末調整では、学生時代のアルバイト収入も年間の申告対象になることをご存知でしょうか。入社前に得た給与所得がある場合、正確な税額計算のために、源泉徴収票の提出が必要です。
「アルバイト先に連絡するのが気まずい」「源泉徴収票を紛失してしまった」といった理由で、必要書類をそろえられないケースもあるかもしれません。しかし処理を行わないと、税金の過不足が発生し、本人に迷惑がかかる可能性もあります。
本記事では、新卒の年末調整で必要となる書類や手続きの流れ、よくあるトラブルの対処法について詳しく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
新卒の年末調整には学生時代の収入も含める
新卒社員の年末調整では、学生時代のアルバイト収入も忘れずに申告する必要があります。年末調整は、1月1日から12月31日までに得たすべての所得が対象です。4月に入社した従業員も、1月から3月までのアルバイト収入があれば、手続きをしなければなりません。
アルバイト先から受け取った源泉徴収票を、会社に提出し、正しく年末調整を行うことが大切です。所得税の過不足を適切に精算することで、税金の還付や追加徴収のトラブルを防げます。
期間中にアルバイトをしていない場合は通常どおり手続きする
入社の前にアルバイト収入がなかった新卒社員の年末調整は、とてもシンプルです。特別な書類を用意する必要もありません。会社から支給された給与だけを対象に、通常どおり手続きを進めましょう。
年末調整は、新卒かどうかにかかわらず、全社員共通で提出する書類があります。具体的には以下の3点です。
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
以上は、新卒に限らず全社員が、入社前のアルバイト経験にかかわらず提出しなければならない書類です。
学生時代にアルバイトをしていなかった場合、当然ながら源泉徴収票の提出は不要です。また、就職の前に自身で保険料を支払っていなければ、保険料控除証明書も必要ありません。
書類を記入する際は、記入漏れや間違いがないように確認しましょう。
新卒でも扶養家族がいる場合や、生命保険料控除などを受ける場合は、該当欄に漏れなく記入してもらう必要があります。該当がない項目は空欄のままでよく、無理に何かを書かせる必要はありません。
▼年末調整の理解をさらに深めたい方は、よくある疑問をまとめた、以下のQ&A資料もご活用ください。

新卒の年末調整で必要な書類
新卒社員の年末調整を行う際には、学生時代の収入の有無にかかわらず、いくつかの書類を提出する必要があります。就職前にアルバイトの経験がある人は、勤務先から受け取った源泉徴収票を忘れずに回収しましょう。
ここでは、新卒社員が提出する基本の3書類と、アルバイト経験に応じて必要な書類について、目的や注意点をわかりやすく解説します。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
年末調整で使う基礎控除申告書は、複数の控除を一括で申告できる便利な書類です。名前が長くて難しく感じますが、1枚で3つの控除をまとめて記入できます。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 特定親族特別控除
- 所得金額調整控除
申告書の基礎控除の欄は、年収が2,500万円以下の人なら全員が記入する必要があります。新卒もほぼ必ず該当すると考えてよいでしょう。給与収入のみの場合、計算は比較的簡単です。
配偶者がいる場合は、配偶者控除等申告書の欄にも記入します。配偶者の年収によって、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかが適用されます。
▼配偶者控除申告書について詳しく知るには、次の記事もご確認ください。
また、特定親族特別控除とは、合計所得金額が58万円超123万円以下である納税者と生計を同一にする配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族がいる場合に適用される令和7年から新設される控除です。該当する場合は、指定の欄に記載が必要です。
▼特定親族特別控除を詳しく知るには、次の記事もご確認ください。
新卒でもその年の給与等の収入金額が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族がいたり、本人または同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者であったりすると、所得金額調整控除も適用されます。
また、その年の「給与所得控除後の給与等」と「公的年金等に係る雑所得」の合計が10万円を超える場合も、所得金額調整控除が適用されます。それぞれに該当する場合は、指定の欄に記載が必要です。
新卒社員で所得金額調整控除に該当する人はまれですが、家庭の事情などを考慮して、念のため確認しておきましょう。
▼年末調整の業務を基礎からおさらいするには、やることチェックリスト付のガイドをご活用ください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
新卒でも配偶者や親、子どもなど、扶養に入れている家族がいる場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入します。家族構成に応じた正しい情報を記入することで、所得税の負担を軽くできます。書類を出さないと、扶養控除が受けられず、税金が高くなるケースもあるので注意が必要です。
参考:『令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』国税庁
給与所得者の保険料控除申告書
もし学生時代や入社後に、以下のような保険料を自分で支払っていた場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」も記入してもらいましょう。
- 生命保険料
- 地震保険料
- 国民年金保険料
書類を提出することで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
保険料控除を受けるためには、保険会社から届く保険料控除証明書が必要です。証明書を手元に準備して、記載されている内容を転記しながら記入すれば、意外と簡単に計算できます。
国民年金の掛金や国民年金基金の掛金、小規模企業共済等掛金については必要な証明書を申告書に添付して提出する必要があります。
毎月の給与から差し引かれている、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、自動で処理されているため、記入不要です。
参考:『令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼所得金額調整控除申告書』国税庁
学生時代の勤務先の源泉徴収票
入社前にアルバイトなどで収入があった場合は、バイト先から受け取った源泉徴収票を提出する必要があります。
年末調整では、1月1日から12月31日までに得たすべての給与所得を合算して税額を決めます。入社前にアルバイト収入があり、源泉徴収されていた場合は、新卒入社の会社に提出し、合算して処理しなければなりません。
源泉徴収票が手元にないという場合は、アルバイト先に再発行を依頼してもらいましょう。会社には源泉徴収票の交付義務があるため、退職後であっても発行してもらえます。
入社前1月から3月の収入がたとえ20万円以下であっても、年末調整は確定申告とは異なり、金額に関係なく提出が必要です。
▼年末調整と確定申告の違いを整理するには、次の記事もご確認ください。
そのほかの書類
年末調整は、関係ないと思っていても、じつは提出が必要な書類もあります。たとえば、新卒社員が学生時代に個人で保険料を支払っていたり、入社前に住宅ローンを組んだりしているケースです。
該当する新卒社員は多くはないかもしれませんが、もしあてはまったら、必要な証明書を忘れずに準備してもらいましょう。
| ケース | 必要な書類 |
|---|---|
| 自分で生命保険料や国民健康保険料に加入し、保険料を支払っていた | 保険料控除証明書/領収書 |
| 学生時代の国民年金を追納した | 控除証明書 |
| 住宅ローン控除を受けている(2年目以降) | 住宅借入金等特別控除申告書/年末残高証明書 |
国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構から届きます。新卒でなくても、学生時代に免除にしていた保険料を追納した場合、証明書の提出を求める必要があります。
国民年金保険料を自分で支払った場合は、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付しましょう。学生時代の国民年金保険料を追納した場合なども、証明書が必要になります。
住宅借入金等特別控除申告書は、税務署から送付されます。1年目は確定申告で調整しますが、2年目以降は会社で処理する点に注意しましょう。年末残高証明書は金融機関から発行される書類です。通常、10月頃から順次発行されるため、手元に届いたら、その前に社内でも案内しておくと安心です。
▼年末調整は税制改正により、毎年少しずつ対応が変わります。2025年度の変更点を知るには、以下の資料もご活用ください。

新入社員が学生時代の源泉徴収票を出さない場合はどうなる?
新入社員が、学生時代のアルバイト収入に関する源泉徴収票を提出しないまま年末調整を迎えると、正確な所得税の計算ができません。
本来受けられるはずの控除が適用されず、本人が税金を多く納めることになったり、あとから税務署から指摘を受けたりするリスクがあります。
源泉徴収票は、本人にとってはもちろんですが、会社としても適切な年末調整を行ううえで欠かせない書類です。
バイト先に連絡しづらい、紛失したといった理由もあるため、対象者には早めに提出の必要性を周知し、未提出時のリスクについても伝えることが大切です。
紛失した場合は再発行を依頼してもらう
新卒社員が「学生時代の源泉徴収票を紛失してしまった」と申し出た場合は、再発行の依頼を本人に促しましょう。
源泉徴収票は、勤務先に電話やメールで請求すれば再発行してもらえる書類です。会社側には交付義務があるため、退職後でも多くは快く対応してもらえることがほとんどです。背景を説明すると、「時間が経っていて連絡しづらい」という本人も安心できるでしょう。
万が一、学生時代のバイト先に発行を断られた場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から会社に指導が入る可能性があります。
期限までに提出できなかった場合は本人が確定申告をする
年末調整の期限までに源泉徴収票がそろわなかった場合、その新卒社員については会社での年末調整ができません。本人に確定申告で対応してもらう必要があります。
確定申告に不慣れな新卒社員には、「申告しないまま放置するリスク」についても念のため伝えておきましょう。
確定申告の期限を過ぎて申告する場合は「期限後申告」となり、延滞税や無申告加算税が発生するかもしれません。延滞税とは期限が過ぎた税金にかかる利息、無申告加算税はペナルティとしての意味がある追加の税負担です。なお、税金が戻ってくる「還付申告」の場合にはペナルティは発生しません。
新卒の年末調整における注意点
新卒社員の年末調整では、学生時代の収入やアルバイトの有無にかかわらず、正確な情報に基づいた手続きが求められます。
「アルバイト収入が20万円以下なら申告不要」と誤解されやすいですが、確定申告のルールに基づくものであり、年末調整にはあてはまりません。
年末調整は1年の全給与所得を合算して計算するため、たとえ金額が少なくても、学生時代に収入がある場合は、源泉徴収票の提出が必要なのです。
また、アルバイトを掛け持ちしていた場合も、すべての勤務先から源泉徴収票を集めてもらうよう案内しましょう。
源泉徴収票を提出しないまま手続きを進めると、税金の過不足や住民税の申告漏れといったトラブルにつながる可能性があります。
とくに新卒社員は「20万円以下なら出さなくていい」と勘違いしやすいため、勘違いを生まないようにていねいに説明しましょう。
新卒1年目から確定申告が必要なケース
新卒社員でも、年末調整だけで税務手続きが完結しない場合があります。
年末調整は原則として会社が所得税の精算を代行するものですが、一部の控除や副業収入などについては、社員本人が確定申告をしなければなりません。具体的には次の3つのケースです。
- 医療費控除を受ける
- 年末調整後に控除が増えた
- 副業やダブルワークをしている
人事側でも把握しておくことで、社員本人への案内漏れや申告忘れを防ぎましょう。
医療費控除を受ける場合
医療費控除は、年末調整では手続きできず、確定申告が必要です。新卒社員であっても、本人や家族の治療費が多くかかった年は、確定申告を行うことで税負担が軽減される可能性があります。
社員から医療費に関する控除の相談があった場合には、確定申告で対応する必要があることを案内しましょう。
▼医療費控除について詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
年末調整後に控除が増えた場合
年末調整が終わったあと、12月31日までに配偶者控除や扶養控除の対象が増えた場合は、控除を受けるために確定申告が必要です。
新卒社員から申し出があった場合は、確定申告の方法と期限を簡単に案内し、控除の取りこぼしがないようにサポートしましょう。
よくあるのは、結婚や出産などのライフイベント、親との同居による配偶者・扶養親族の増加です。
会社での年末調整のやり直しも可能ですが、提出期限が限られているため、確定申告を選択するのが確実でしょう。
また、年末調整時に以下のような申告を忘れた場合も、確定申告で修正できます。
- 扶養親族の追加を忘れた
- 配偶者の退職などにより、控除対象になったのに申告していない
- 子が16歳になり、扶養控除の対象になったことを申告していない
副業やダブルワークをしている場合
新卒社員でも、副業やアルバイトで本業以外の所得が一定額を超える場合は、確定申告が必要です。副収入がある社員に対しては、伝えておくと安心です。
たとえば、副業で30万円の収入があり、経費5万円を除いた所得25万円に対しては確定申告が必要です。ポイントは所得が20万1円以上で申告義務が発生すること。20万ぴったりの副業所得で、確定申告は不要です。
新卒社員が、2か所以上から給与を受け取っている場合、主たる給与でない勤務先の給与収入(額面)が20万円を超えると確定申告が必要になります。いずれも所得ではなく、収入が基準となるため、注意しましょう。
まとめ
新卒社員の年末調整では、入社前のアルバイト収入や保険料の扱いに注意が必要です。たとえ少額でも、1月1日以降の給与所得はすべて申告対象となり、源泉徴収票の提出が求められます。
書類に不備があると、税金の還付が受けられなかったり、追加納税につながることもあります。必要書類の案内は早めに行い、提出漏れがないよう担当者としてチェック体制を整えましょう。
また、書類のやり取りや控除額の確認には多くの手間がかかります。年末調整システムの活用によって、担当者の負担軽減とミス防止がはかれます。業務効率化を進め、確実でスムーズな年末調整を目指しましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

