海外赴任者の年末調整は必要?【ケース別】出国時年末調整についても解説
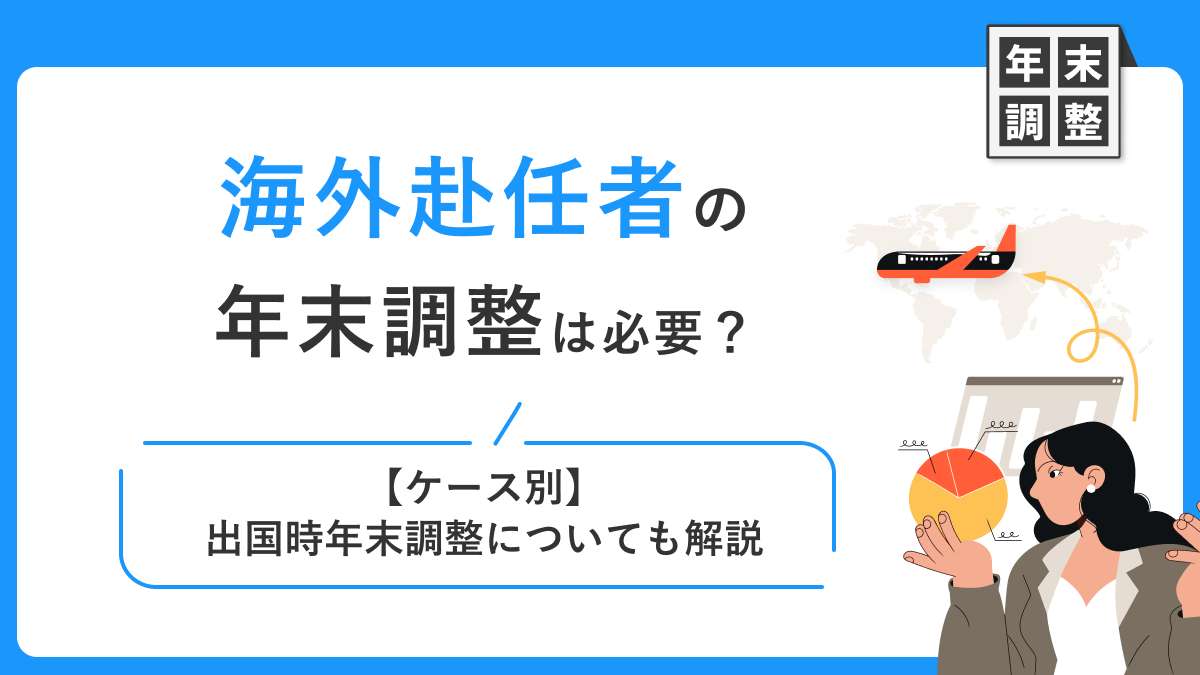
海外赴任者の年末調整で、対応に迷っていませんか。海外支店や現地法人に従業員を赴任させるグローバル企業も多くあるでしょう。
年末調整は基本的に国内の「非居住者」には不要な手続きです。しかし、1年の途中で海外に赴任することになったり、扶養親族が海外にいたりする場合は、特別な処理が必要になります。
本記事では、海外赴任者に関する年末調整の要否や出国時年末調整の流れを、ケースごとに整理しています。さらに扶養親族が海外にいる場合の注意点や、非居住者給与の源泉徴収ルールまでわかりやすく解説していますので、参考にしてください。

 目次[表示]
目次[表示]
海外勤務(駐在)、単身赴任の年末調整は必要?
海外赴任者について年末調整が必要かは、その従業員が「居住者」に該当するかによって異なります。
- 居住者:年末調整が必要
- 非居住者:年末調整が不要
年末調整は、給与から一時的に徴収していた源泉所得税額と、実際の所得税額との差を精算する手続きです。
日本の税制では、日本国内に住所を有する、あるいは現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を居住者と定義します。
海外赴任中であっても、居住者の要件にあてはまる従業員については年末調整が必要です。
反対に、日本国籍を有する従業員であっても、居住者の要件にあてはまらない「非居住者」は年末調整の対象外です。
以下では、海外に拠点を持つ(持っていた)従業員のケース別に、年末調整の要不要を解説します。
参照:『No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整』国税庁
海外転勤後1年に満たない→必要
海外転勤後の期間が1年未満の従業員は、税法上「居住者」として扱われ、年末調整の対象です。居住者である以上、日本国内で支払われる給与は課税対象となります。
ただし、海外転勤後1年に満たない場合でも、次の従業員は年末調整の対象外です。
- 年収が2,000万円を超える従業員(年末調整の代わりに確定申告が必要)
- 災害減免法の規定によって徴収猶予や還付を受けた従業員
海外赴任が短期か長期かの判断は、一般的に赴任の辞令や契約書に記載された期間で判定します。
1年以上の予定で海外赴任した人は所得税法でいう非居住者、1年未満の予定で海外赴任した人は居住者になります。
実際の滞在期間ではなく「予定期間」で判断する点に注意が必要です。
海外転勤後1年以上が経過している→不要
海外勤務が1年以上経過している従業員は「非居住者」とみなされ、年末調整の対象外です。非居住者は日本の年末調整の対象外となり、勤務先で年末調整を行う必要はありません。
ただし、非居住者であっても日本国内源泉所得(例:日本国内の不動産所得など)がある場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
年の途中で海外に出向した→必要
年の途中で海外出向となった場合、出国までに確定した収入については、年末調整が必要です。これは「出国時年末調整」と呼ばれる手続きで、通常の12月の年末調整とは別に、出国日までに臨時で行う年末調整です。
出国が決まった時点で、早めに扶養控除申告書・保険料控除証明書などの必要書類を準備して、提出を依頼することが大切です。
また、出国後に国内勤務期間の給与が支払われた場合、「非居住者に対する国内源泉所得」とみなされ、20.42%の源泉所得税が課されます。
年の途中で海外出向から帰国した場合は必要
年の途中で海外出向から帰国した場合、帰国後から年末までの収入については、年末調整が必要です。
また、海外勤務中の給与であっても、帰国後に日本で支払われた金額については源泉徴収の対象となるため注意が必要です。
帰国後に支払う給与のうち、どの期間の勤務に対する支払いかを明確にし、源泉徴収対象かどうかを判断しましょう。
参照:『No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整』国税庁
海外に居住しながらテレワークをしている→必要
テレワークであっても、海外に生活の拠点を置き、1年以上継続している場合は非居住者と判定されるため、年末調整の対象外です。
所得税に規定される「居住者/非居住者」の判定は、勤務先の所在地ではなく、生活の拠点(住所)がどこにあるかで判定されるためです。
たとえば、家族とともに海外に移り住み、住居や生活費の中心が海外にある状態でリモート勤務を続けているケースは、非居住者と判定されます。
一方で、生活の拠点が日本にあり、短期間だけ海外で働いている場合は、居住者とみなされ年末調整の対象です。
テレワークやワーケーションが一般化するなかで、「居住者」の判定に迷う場合もあるので、住所や生活の本拠をもれなく確認しましょう。

居住者・非居住者の課税所得範囲の違い
住所に基づいて分類される「居住者」と「非居住者」は、課税される所得の範囲が異なります。
また、居住者は日本国籍の有無や、国内に住所または居所を持つ期間に応じて「非永住者」と「非永住者以外」に分類されます。
それぞれの課税所得の範囲をまとめると、以下のとおりです。
| 個人の分類 | 定義 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 | |
|---|---|---|---|---|
| 居住者 | 非永住者 | 居住者のうち、以下の要件に該当する人 ・日本国籍を有さない ・過去10年間に日本国内に住所または居所を有していた期間が合計5年以内 | 課税 | 国内にて支払われたもの、国外から国内へ送金されたものは課税 |
| 非永住者以外 | 非永住者に該当せず、以下のいずれかの要件に該当する人 ・日本国内に住所を有する ・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する | 課税 | 課税 | |
| 非居住者 | 居住者の要件にあてはまらない人 | 課税 | 非課税 | |
国内源泉所得とは日本国内で生じた所得、国外源泉所得とは日本国外で生じた所得のことです。
日本国内で働く従業員のほとんどは、居住者のうち非永住者以外に該当します。非永住者以外の人は、国内・国外問わずすべての源泉所得が課税対象です。
一方、非永住者の場合、課税対象は国内源泉所得と、国外源泉所得のうち「国内にて支払われたもの」と「国外から国内へ送金されたもの」に限られます。そのため、国外で生じ、現地で支払われた所得は課税対象外です。
また、非居住者は国内で生じた所得のみ課税されます。海外赴任者のうち、居住者の要件にあてはまらない従業員も非居住者に該当します。

海外赴任者の出国時年末調整とは?
海外赴任者の出国時年末調整とは、従業員が海外赴任や出向により、年の途中から非居住者となる場合に実施する年末調整です。
通常の年末調整は、当年の12月までにまとめて処理します。しかし、非居住者になった時点以降の給与は、日本では課税されません。
そこで出国日までの給与についてだけ、税金を精算する必要があります。
たとえば、従業員が8月31日に出国して海外赴任するなら、1月1日から8月31日までの給与が年末調整の対象です。
出国時年末調整が必要なのは、以下の2つの要件を満たすケースです。
- 海外勤務の予定が1年以上あり、日本の非居住者になる
- その年の1月1日から出国日までに支払うことが確定した給与が2,000万円以下
出国時年末調整の例
出国時年末調整は、給与や賞与の「支払日」「計算期間」「出国日」の関係によって取り扱いが異なる場合があります。具体的なケースを見てみましょう。
例1:出国後に支払われた給与(計算期間が出国前)
出国日以降に振り込まれる給与であっても、勤務実績がすべて日本国内に属していれば、日本の課税対象となります。非居住者への給与と同様に20.42%の源泉徴収が行われます。
例2:給与計算期間に出国前後が混在する場合
給与計算の対象期間が1か月以内で、居住者だった日と非居住者になった日が混じっているケースでは、給与全体を非課税として扱うのが原則です。つまり、勤務日数に日本国内が含まれていても源泉徴収の対象にならないことがあります。
例3:出国後に支給される賞与(計算期間が長期の場合)
賞与の計算期間が1か月を超えるときは注意が必要です。出国後に支払われても、計算対象に出国前の国内勤務分が含まれる場合、国内勤務に対応する部分は課税対象となり、源泉徴収が必要になります。
出国時年末調整における各種控除
年末調整では、基礎控除をはじめとして各種所得控除(社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除など)を適用します。
出国時年末調整では、出国時の状況に応じて控除の可否を判定されるため注意が必要です。
たとえば、出国時年末調整で、配偶者控除や扶養控除を適用するには、以下のような要件があります。
- 納税者と配偶者・親族が生計を一にしている
- 配偶者や親族の1年間の合計所得金額が各要件の範囲内に収まっている
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない
出国時年末調整では、1年間通しての所得ではなく、出国時点での合計所得金額の見積もりをもとに判定します。ただし、非居住者となる従業員が、納税管理人を選定する場合は、例外です。
納税管理人とは、海外に住む納税義務者に代わって、日本の税務署に対して税務申告や納税手続きを行う代理人のことです。
社会保険料控除の注意点
社会保険料の控除対象となるのは、1月1日から出国日までに支払った保険料です。出国時年末調整を行う際は、従業員に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出してもらい、正しく処理を行いましょう。
親族が海外に居住している場合の年末調整
従業員の親族が海外に住んでいて「非居住者」の要件を満たす場合、扶養控除や配偶者(特別)控除、特定親族特別控除、障害者控除を受けるには、特別な書類の提出が必要です。
具体的には、親族関係書類と送金関係書類の2点です。
| 証明内容 | 例 | |
| 親族関係書類 | 非居住者の親族であること | 戸籍の附票の写し、親族のパスポート、外国政府や自治体の証明書 |
| 送金関係書類 | 親族の生活費や学費を負担していること | 銀行やクレジットカード会社の送金記録、その写し |
親族関係書類とは、非居住者である親族との親族関係を証明する書類です。たとえば、戸籍の附票の写しや親族のパスポートの写し、外国の政府や地方公共団体が発行した書類が該当します。
一方、送金関係書類とは、従業員が非居住者である親族の生活費や教育費を負担していることを証明する書類です。たとえば、金融機関やクレジットカード会社が発行する書類、またはその写しが該当します。
年末調整では、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入して提出してもらいましょう。
【主な記入内容】
- 該当する扶養親族の情報を記入
- あてはまる項目にチェック
- 送金した金額を記入
書類と申告書をそろえることで、非居住者の親族についても控除が適用されます。
海外赴任者の住民税の取り扱い
住民税は、1年間の1月1日時点で日本に住んでいた人に対して課税されます。
海外転勤後1年以上が経過している場合、1月1日時点で海外にいた年については、住民税の課税対象外です。反対に、1月1日時点で日本国内に住所があった年については、住民税が課されます。
一方、海外転勤後の期間が1年未満の場合は居住者とみなされるため、1月1日時点で海外に拠点を移していても、日本で住民税が課されます。
| 1年以上の海外転勤 | 1月1日時点で海外にいる | 非居住者 | 非課税 |
| 1月1日時点で日本にいる | 居住者 | 課税 | |
| 1年未満の海外転勤 | 1月1日時点で海外・日本にいる | 居住者 | 課税 |
たとえば、2025年9月から2026年10月まで海外に赴任する場合、2026年は日本の住民税は課されません。一方、2025年9月から2026年3月まで海外に赴任する場合、赴任期間が1年未満なので住民税が課されます。
| 海外赴任期間 | 居住・非居住 | 課税・非課税 | |
| 2025年9月~2026年10月まで | 1年以上 | 非居住者 | 非課税 |
| 2025年9月~2026年3月まで | 1年未満 | 居住者 | 課税 |
参考:『海外赴任することになったのですが、住民税はどうなりますか。』東村山市
外国籍の従業員の年末調整は?
外国籍の従業員の年末調整についても、日本国籍の従業員と同様に、居住者・非居住者の分類によって扱いが変わります。
- 居住者→課税→年末調整が必要
- 非居住者→非課税→年末調整が不要
日本から海外に赴任した人と同じく、国内の居住期間が1年以上の場合は居住者とみなされ、年末調整が必要です。外国籍の従業員が退職して帰国した場合でも、居住期間によっては年末調整を行わなければなりません。
外国籍の非永住者について
外国籍の従業員が「非永住者」にあたる場合、国外で得た収入のすべてが課税されるわけではありません。日本で支払われた収入と、日本に送金された収入だけが課税の対象です。
- 非永住者→課税(日本で支払われた・日本に送金された収入だけ)→年末調整が必要
外国籍の従業員の扶養親族について
外国籍の従業員が国外に扶養親族がいる場合、日本国籍の従業員と同じく、手続きが必要です。対象の扶養親族を証明する、親族関係書類や送金関係書類を提出するように案内しましょう。
前職が海外勤務だった従業員の年末調整
前職が海外勤務だった従業員は、帰国した従業員や外国籍の従業員と同じ扱いになります。1年以上日本にいる予定であれば居住者となり、居住者となった日以降の給与については年末調整が必要です。
社会保険料控除や生命保険料控除は、居住者となった日以降に払い込んだ金額が対象となります。扶養控除については、通常の年末調整と変わらず、12月31日時点の状況で判定すれば問題ありません。
まとめ|海外赴任者の年末調整は居住期間の長さに注意
日本の税制では、所得税の課税対象を日本国内での居住期間によって判断します。海外赴任した従業員についても、日本での滞在期間が一定以上であれば、年末調整が必要です。
年末調整は、源泉所得税で一時的に徴収した税額と、実際の所得税額との差を精算する手続きです。海外赴任者の取り扱いは複雑に見えますが、基本的な処理の流れは国内勤務者と変わりません。
ビジネスの国際化が進むなかで、海外で働く従業員や、国外に扶養親族を持つ従業員もめずらしくないでしょう。海外赴任者や非居住者に関する年末調整の処理に備えて、課税判定の基準や必要書類を正しく理解しておく必要があります。
また、年末調整を速く正確に処理するには、年末調整に対応したシステムの活用がおすすめです。計算ミスや申告漏れのリスクを減らし、業務全体の効率化を実現します。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数が多くなる業務です。担当者の負担も大きく、課題を抱える企業も少なくありません。公的手続きまで、ミスなく円滑に進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。回収書類は画面上で一覧表示され、申告内容も書類ごとに一括でチェックが可能。書類を一枚一枚確認しなくても、対応漏れの防止に役立ちます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性について、詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

