パートの年末調整書類の書き方は? 気をつけたいケースをあわせて解説
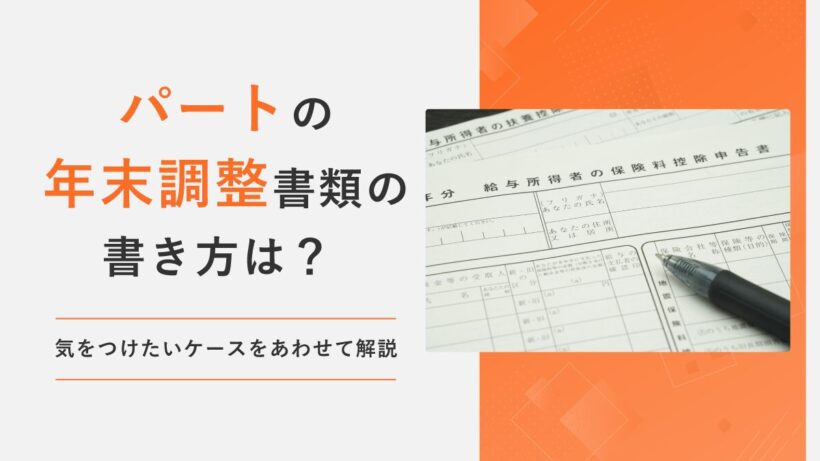
年末調整とは、毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収額と、実際に支払う所得税の差額を精算する手続きです。正社員に限らず、パートとして働く非正規従業員も、年収が一定額を超えるなどの条件がそろえば、年末調整が必要になります。
扶養に入っているから関係ないといった誤解があると、判断を誤ることになるため注意しなければなりません。
本記事では、パート従業員の年末調整書類の書き方をわかりやすく解説します。注意したいポイントや確定申告の手続き方法もあわせて紹介するため、現場での説明対応にもご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整はパートやアルバイトも対象
パートやアルバイトなどのパートタイム労働者も、一定の条件を満たせば年末調整の対象です。家族の扶養に入っていても、自身が給与を受け取っている場合は対象となる可能性があります。
年末調整の対象となるには、まず『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出していることが前提です。そのうえで、12月31日の時点で企業に在籍していること、年間の収入が2,000万円以下であることが条件です。
以下では、パート・アルバイトの従業員が年末調整の対象となる具体的なケースを紹介します。
▼所得税と社会保険では、扶養の意味が異なります。詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。
年収が160万円を超えている(所得税の160万円の壁)
家族の扶養に入っているパート・アルバイトの従業員でも、年収が160万円を超えると年末調整の対象になります。課税所得が発生し、所得税の精算が必要になるためです。
専業主婦(主夫)として扶養に入っていた人が160万円を超える収入を得ると、自分自身が納税義務を負う立場になるのです。
ただし、年収が160万円を下回っていても、次のようなケースでは年末調整が必要となる場合があります。
- 月収が8万8,000円以上となる月が一年に一度でもある
- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している
いずれの場合も、企業側で対象者を確認したうえで、適切に年末調整の手続きを進めていきましょう。
なお、所得税が非課税となる年収額は160万円以下ですが、住民税は自治体によって異なり、年収が約110万円を超えると課税対象となります。
年収が130万円を超えている(社会保険の130万円の壁)
130万円の壁は、納税者の社会保険への加入義務が生じる基準のラインです。パート従業員の年収が130万円を超えると、配偶者や親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。選択肢として、パート先の社会保険に加入する、もしくは自身で国民健康保険や国民年金に加入して、保険料を納めなければなりません。
また、2024年10月以降は、従業員数51人以上の勤務先に勤めるパート従業員で、以下の条件を満たす場合も、「106万円の壁」により社会保険の加入対象となりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上(通勤手当・残業代・賞与などは含まない)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
参照:『パート・アルバイトのみなさま』厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
「130万円の壁」「106万円の壁」はそれぞれ対象となる条件が異なるため、パート従業員の年収や勤務先の状況に応じて、年末調整の対応とあわせて確認が必要です。
▼社会保険の加入条件を知るなら、以下の記事もご確認ください。
▼社会保険の手続きについておさらいしたい方は、次の資料もご活用ください。

パートの年末調整に用いる書類の書き方
パート従業員が年末調整を受ける際は、正社員と同様に書類を提出する必要があります。
書類は毎年決まっていて、基本的には以下の3種類です。
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特別親族等特別控除申告書 等
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
それぞれの書類には役割があり、記入内容も異なります。以下では、パート従業員が提出する場面を想定しながら、実際の記入で迷いやすいポイントや注意点を含めてわかりやすく解説します。
▼年末調整の理解をさらに深めたい方は、よくある疑問をまとめた、以下のQ&A資料もご活用ください。

給与所得者の保険料控除申告書
『給与所得者の保険料控除申告書』は、年末調整の手続きをする際に、当年の生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の保険料控除を申告するための書類です。
申告対象となる保険料控除がない場合は、提出する必要はありません。また、扶養内で働く場合も、原則として提出は不要です。
従業員に給与所得者の保険料控除申告書を提出してもらう際は、必要事項を記載したうえで控除金額を証明する書類を添付するよう伝えましょう。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
年末調整の手続きをする際に、当年の基礎控除や配偶者(特別)控除、所得金額調整控除などを申告するための書類です。
大きく分けて次の4つの項目に分かれています。
- 基本情報(共通)
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申請書特定親族特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
共通する基本情報には、申告者の氏名や住所を記載します。

給与所得者の基礎控除申告書
『給与所得者の基礎控除申告書』は、基礎控除を申告するための書類です。記載する項目は以下のとおりです。
| 給与所得者の基礎控除申告書 |
|---|
| ・給与所得の収入金額 ・給与所得の所得金額 ・給与所得以外の所得の合計額 ・申告者の合計所得金額の見積額 ・控除額の計算と区分 ・基礎控除の額 |
年間の合計所得金額が2,500万円以下の場合は基礎控除が適用されるため、ほとんどの給与所得者は基礎控除申告書に必要事項を記入して勤務先に提出しなければなりません。本年中の給与所得の収入金額や所得金額、合計所得金額の見積額、基礎控除の額などを記載します。
給与所得者の配偶者控除等申請書
『給与所得者の配偶者控除等申請書』は、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象となる場合に記入する項目です。
| 給与所得者の配偶者控除等申請書 |
|---|
| ・配偶者情報 ・給与所得の収入金額 ・給与所得の所得金額 ・給与所得以外の所得の合計額 ・配偶者の合計所得金額の見積額 ・控除額の計算と区分 ・配偶者(特別)控除の額 |
配偶者の情報や配偶者の本年中の合計所得金額の見積額、配偶者控除の額などを記載します。
特定親族特別控除申告書
『特定親族特別控除申請書』は、令和7年から新設された特定親族控除の対象となる場合に記入する項目です。
| 特別親族特別控除申請書 |
|---|
| ・特定親族情報 ・特別特定親族の合計所得金額の見積額 ・特定親族特別控除の額 |
特定親族の情報や特定親族の本年中の合計所得金額の見積額、特定親族特別控除の額などを記載します。
特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が123万円超188万円以下)の人をいいます。
所得金額調整控除申告書
『所得金額調整控除申告書』は、所得金額調整控除を受けるための書類です。記載する項目は次のとおりです。。
| 所得金額調整控除申告書 |
|---|
| ・「要件」欄の該当項目 ・「扶養親族等」または「特別障害者」の必要事項 |
所得金額調整控除には、大きく分けて次の2種類があります。
- 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
- 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
『子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除』は、年末調整で申告が可能です。当年の年収が850万円を超える給与所得者で、本人または配偶者・扶養親族が特別障害者である場合、もしくは23歳未満の扶養親族がいる場合に適用されます。「要件」欄の該当項目へのチェックと、必要事項の記入が必要です。
『給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除』は、従業員自身で確定申告をすることで控除が適用されます。
参照:『令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼所得金額調整控除申告書』国税庁

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、申告者が扶養している配偶者や親族の情報をまとめるための書類です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入する項目は、次のとおりです。
| 基本情報 |
|---|
| ・氏名・個人番号(マイナンバー) ・住所または居所 ・生年月日 ・世帯主の氏名 ・世帯主の申告者との続柄 ・配偶者の有無 |
| 源泉控除対象配偶者 |
|---|
| ・氏名や続柄などの基本情報 ・その年の所得の見積額 ・非居住者の場合は丸印をつける ・住所または居所 ・異動の月日や事由 |
| 控除対象扶養親族 |
|---|
| ・氏名や続柄などの基本情報 ・老人扶養親族または特定扶養親族の項目にチェックを入れる ・その年の所得の見積額 ・非居住者の場合はチェックを入れる ・生計を一にしている場合は丸印をつける ・住所または居所 ・異動の月日や事由 |
| 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生 |
|---|
| ・該当する場合にチェックを入れる ・該当する扶養親族の人数 ・障害者または勤労学生の内容 ・移動の月日や事由 |
| ほかの所得者が控除を受ける扶養親族等 |
|---|
| ・扶養親族の氏名や続柄、生年月日、住所または居所 ・控除を受ける人の氏名や続柄、住所または居所 ・異動の月日や事由 |
| 住民税に関する事項 | |
|---|---|
| 16歳未満の扶養親族 | 退職手当等を有する配偶者・扶養親族 |
| ・氏名や続柄などの基本情報 ・住所または居所 ・控除対象外国外扶養親族かどうか ・その年の所得の見積額 ・異動の月日や事由 | ・氏名や続柄などの基本情報 ・住所または居所 ・非居住者である親族にチェックを入れる ・その年の所得の見積額 ・障害者区分 ・異動の月日や事由 |
参照:『令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼所得金額調整控除申告書』国税庁
参照:『令和7年分扶養控除等(異動)申告書』国税庁
▼年末調整業務の進め方に不安がある方は、次の資料もぜひご活用ください。
パート従業員の年末調整で気をつけたいこと
パート従業員の年末調整は、勤務状況や収入状況に応じた対応が求められるケースもあります。
とくにパートの場合、年内に退職した人や、仕事を掛け持ちしている人、副業をしている人は、通常の手続きとは少し異なるため注意が必要です。
状況に応じた対応ができるよう、年末調整を進める際に注意したいポイントを確認しておきましょう。
12月までにパートを辞めた
年末調整は12月31日時点で在籍している従業員を対象に実施されるため、12月までにパートを辞めた人は原則として対象外です。
退職後に働かない場合は、年末調整は実施されないため、従業員自身で確定申告をする必要があります。
一方で、退職後に新たな職場で働き始めて、12月に勤務したぶんの給料を12月中に受け取る場合は、新しい職場において年末調整が処理されます。
パートを掛け持ちしている
複数の勤務先でパートを掛け持ちしていて、合算した年収が103160万円を超えている場合は、もっとも収入が多い勤務先のみが、年末調整の手続きをしなければなりません。
パート従業員は、給与支払額のもっとも多い勤務先に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出します。
掛け持ち先における給与収入の合計額が20万円を超えている場合は、従業員自身が確定申告をする必要があります。
参照:『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』国税庁
▼掛け持ち社員の年末調整について詳しく知るには、以下の記事もご確認ください。
副業をしている
パート以外の副業で収入を得ていて、副業での年間所得額が20万円を超えている場合は、年末調整とは別に、従業員自身で確定申告をしなければなりません。
確定申告の手続きをする際は、本業の源泉徴収票が必要です。確定申告のときまで、各自で保管するように周知しましょう。
▼副業をしている従業員の年末調整について知るには、次の記事もご確認ください。
確定申告をする方法
年末調整の対象外となるパート従業員は、副業・掛け持ちなどにより確定申告が必要となるケースがあることを紹介してきました。
従業員自身で正しく申告手続きを進められるよう、必要に応じて方法を案内・サポートしてあげるとよいでしょう。
確定申告とは、1年間の所得とそれに応じた税額を計算・申告する手続きです。申告の期日は、例年2月16日から3月15日までとされています。
申告書類は、手書きだけでなく、スマートフォンやパソコンでも作成が可能です。提出方法は、税務署への持参、郵送、もしくはe-Tax(電子申告)から選べます。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、次のとおりです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 国民年金や生命保険などの控除証明書
- マイナンバー/マイナンバーカード
- 振り込みに使う口座情報
確定申告書は、源泉徴収票や控除証明書の内容と照らしあわせながら記入していきます。具体的な書き方は、国税庁のホームページや最寄りの税務署で確認が可能です。
不明点があれば税務署に相談できることや、自治体によっては相談窓口が設けられていることもあるため、従業員へあわせて案内しておくと安心です。
参照:『申告書の記載例』国税庁
まとめ|パート従業員でも要件を満たせば年末調整が必要
パートやアルバイトであっても、一定の要件にあてはまる従業員は年末調整の対象になります。自社のパート従業員が要件を満たすかどうかを判断し、必要な書類を正しく提出できるようサポートすることが重要です。
本記事で紹介した書類の書き方や注意点を参考に、雇用形態に関係なく、スムーズに年末調整を進めていきましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

