年末調整の未済の意味とは? 源泉徴収票の見分け方や確定申告のやり方を解説
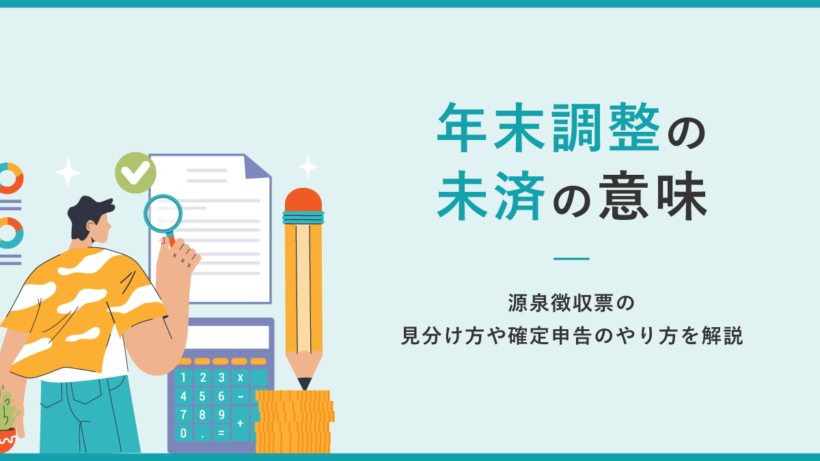
年末調整の未済とは、年末調整の手続きが済んでいない状態のことです。
年末調整は、月々の給与から源泉徴収した概算の所得税額と、本来の所得税額の過不足を調整する重要な手続きです。年末調整は雇用形態に関係なく行われるため、ほとんどすべての従業員が対象となりますが、一部のケースで「未済」の状況が発生します。
本記事では、年末調整の未済の概要や、未済として処理する代表的なケースについて解説します。源泉徴収票での見分け方や確定申告の基本的な流れも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整の未済の意味
年末調整の未済とは、年末調整が完了していないことです。
たとえば、年の途中で退職して当年中の最後の給与が支給されない従業員については、当年の年末調整ができないため未済として処理されます。また、担当者は必要に応じて「年調未済」と記載された源泉徴収票を発行します。
年末調整が未済で処理される場合
年末調整が未済として処理される主なケースは、次の4つです。
- 年収が2,000万円を超える
- 住宅ローン控除を受ける初年度
- 自社以外に本業の勤務先がある
- 年の途中で退職した

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。
年収が2,000万円を超える
年間の収入が2,000万円を超える従業員は、年末調整の対象外であり、未済として処理されます。従業員は自分で確定申告を手配しなければなりません。
住宅ローン控除を受ける初年度
住宅ローン控除を受ける初年度は、年末調整は未済として処理します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入し、一定の要件を満たす場合に受けられる控除です。2年目以降は年末調整で処理されますが、初年度だけは従業員本人による確定申告が必要です。
▼年末調整における住宅ローン控除の扱いについて知るには、次の記事もご確認ください。
自社以外に本業の勤務先がある
本業以外の勤務先では年末調整は行われないため、未済という扱いになります。
アルバイトやパート、副業などで複数の勤務先で働いている場合、年末調整が行われるのは1つの企業のみです。基本的にはもっとも収入が多い勤務先が「本業」として位置づけられ、本業の勤務先にて年末調整が行われます。
本業以外の収入については、従業員本人による確定申告が必要です。
▼副業をしている従業員の年末調整について知るには、次の記事もご確認ください。
年の途中で退職した
年の途中で退職した従業員については、年末調整は行われず、未済扱いとなります。年末調整の対象となるのは、当年の12月31日時点で在籍している予定の従業員であるためです。
年の途中で退職した従業員が同年内に転職した場合は、転職先で年末調整が実施されます。一方、同年内に転職しない場合は、従業員本人による確定申告が必要です。
ただし、12月退職で12月に給与の支払いがある場合は、年末調整が実施されます。
年末調整の未済を源泉徴収票で見分ける方法
年末調整が未済であっても、源泉徴収票は給与の支払いがあった全員に発行されます。会社が年末調整を終えると、従業員の収入額や給与所得控除額などの情報が記載された源泉徴収票が交付されます。
源泉徴収票を確認すれば、従業員本人も自分が未済扱いとなっているかチェックすることが可能です。具体的には、次の4点を確認することで見分けられます。
- 摘要欄に「年調未済」と記載されている
- 「所得控除の額の合計額」などが空欄である
- 乙欄にチェックが入っている
- 摘要欄に「普通徴収」と書かれている
それぞれ、以下で詳しく解説しましょう。
摘要欄に「年調未済」と記載されている
年末調整をしていない場合は、摘要欄に「年調未済」と記載されるケースがあります。ただし、未済の表記は必須ではなく、会社によっては摘要欄にとくに何も記載しない場合もあるでしょう。
基本的には会社のルールに沿っていれば問題ありませんが、摘要欄に記載したほうが年末調整が実施されていないことを明らかにしやすくなります。

「所得控除の額の合計額」などが空欄である
年末調整が未済ということは、年末調整における各種計算もしていないということです。そのため、年末調整が未済の源泉徴収票は、「扶養控除」や「生命保険料控除」など多くの項目が空欄の状態で発行されています。
なかでも「所得控除の額の合計額」の項目を見れば、年末調整が実施されたかどうかは一目瞭然です。年末調整ではほとんどすべての従業員に「基礎控除」が適用されるため、項目が空欄ということは、年末調整が未済であることを意味します。
乙欄にチェックが入っている
源泉徴収税額表にある甲・乙・丙のチェック欄は、『源泉徴収税額表』における税区分をあらわすものです。
- 甲欄:給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合の税区分
- 乙欄:給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない場合の税区分
- 丙欄:主に日雇賃金に適用する税区分
源泉徴収税額表とは、従業員の給与から源泉徴収する所得税額を計算するための速算表です。源泉徴収税額表は甲欄・乙欄・丙欄で構成され、それぞれの従業員があてはまる欄を使用します。
また、年末調整は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出した従業員に対して処理する決まりとなっています。そのため、源泉徴収票の乙欄にチェックが入っているということは、「申告書が提出されていない=年末調整の対象外」であることを意味するのです。
たとえば、複数の勤務先で働く従業員は、年末調整を受ける勤務先にのみ給与所得者の扶養控除等申告書を提出します。申告書の提出を受けた勤務先では甲欄、それ以外の勤務先では乙欄を使用して源泉徴収を行います。
摘要欄に「普通徴収」と書かれている
年末調整が未済の場合は、摘要欄に「普通徴収」と記載されているケースがあります。
普通徴収とは、住民税の納付方法をあらわす言葉です。通常、従業員の住民税は毎月の給与から天引きし、会社が代わりに納付する「特別徴収」が採用されています。所得税の源泉徴収義務がある事業者には、住民税を特別徴収して納付する義務もあります。
一方、普通徴収とは、住民税を納税者本人が納付する方法です。通常は自営業者やフリーランスなど給与所得のない人が利用する制度ですが、年の途中に退職して同年内に転職しない従業員については、特別徴収から普通徴収に切り替わります。
ただし、普通徴収と書かれていても、年末調整を実施しているケースもありますので注意が必要です。
▼源泉徴収票は電子配布がおすすめ。年末調整の電子化により、計算結果を自動で反映できるとともに、手渡しによる配布コストを削減できます。
→源泉徴収票の電子配布でスムーズに|One人事[労務]の特長

年末調整の未済時の対応・確定申告のやり方
年収が2,000万円以上の従業員や、住宅ローン控除を受ける初年度など、年末調整が未済になっている場合は本人が確定申告をする必要があります。やり方は通常の確定申告と同様で、基本的な流れは次のとおりです。
- 確定申告に必要な書類をそろえる
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を税務署に提出する
- 所得税の納付または還付
確定申告に必要な書類のなかには、会社が発行した源泉徴収票も含まれます。年末調整が未済の源泉徴収票は多くの項目が空欄ですが、確定申告に必要な情報が多く記載されているため、会社は確実に発行しましょう。従業員から紛失の連絡を受けた場合は、すみやかに対応することも大切です。
なお、従業員が複数の勤務先で働いている場合は、本業の会社で年末調整を受け、未済分は確定申告をします。副業分を申告せずにいると追徴課税が適用され、税負担が増すおそれもあります。
また、年の途中で退職し、年内に再就職しない場合は確定申告が必要です。一方、年の途中で退職しても、同年内に新しい職場で働き始めた場合は、転職先で年末調整を受けられます。
年末調整の未済を放置するとどうなる?
年末調整の未済のままだと、所得税や住民税の計算に必要な控除が適用されず、従業員が本来より多くの税金を支払ってしまうリスクがあります。
所得税の計算では、次のような控除が適用されません。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除 など
▼その他控除一覧を確認するにはこちら
過払いとなるのは所得税だけでなく、所得や所得控除などに基づいて計算される住民税も同じです。
給与所得には基本給だけでなく、時間外手当や休日手当、通勤費なども含まれます。源泉徴収では、年間を通じた概算で所得税を差し引いているため、手当の有無で税額にずれが生じています。
つまり、年末調整の未済を放置すると、概算金額との差によっても、本来より多く所得税を多く払いすぎてしまう可能性があるのです。
反対に、本来追加で支払うべき税金があった場合も、年末調整が未済のまま放置されていると、追徴課税や延滞金などのペナルティが発生するおそれがあります。
そのため、意図しない年末調整の未済は放置せず、適切に対応しなければなりません。
まとめ|年末調整の未済=年末調整が完了していない状態
年末調整の未済とは、年末調整の手続きが済んでいない状態のことです。会社によっては、年末調整が未済の場合、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載するケースもあるでしょう。そのほか、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄が空欄であったり、乙欄にチェックが入っていたりと、従業員にも分かりやすいサインがあります。
しかし、従業員が源泉徴収票の見方や未済について理解していないケースも少なくありません。年末調整の未済を放置すると、税金の還付を受けられなかったり、追徴課税が適用されたりと、従業員に不利益が生じてしまいます。
年末調整が未済の場合は、意味や必要な対応について従業員に説明できるようにしておくと安心でしょう。
年末調整を電子化|One人事[労務]
年末調整は煩雑で作業工数も多く、担当者の業務負担が増してしまいます。
業務負担を軽減し、ミスなく円滑に進めるには、年末調整の電子化がおすすめです。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までを半自動化することで、効率的な年末調整業務を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料よりご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

