ESGの取り組み事例とは? 注目される背景やSDGsとの違いを解説

ESGとは、企業の持続可能性を評価する3つの視点を指しています。昨今の企業経営では、安定した利益の確保だけでなく、社会的な視点での取り組みがますます重視されるようになっています。
本記事では、ESGの定義や企業が取り組むメリット、取り組み事例、ESG投資の種類を紹介します。
持続可能性(サステナビリティ)を意識した経営に移行したいとお考えの方は、ぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
ESGとは何か
まずはESGの定義やESGに投資することの意味など概要についてご説明します。
ESGの定義
ESGは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を取った言葉です。近年、企業の経営において、この3つの観点からの配慮が必要だという考え方が広がっています。
| ESGの取り組み例 | |
|---|---|
| Environment(環境)への配慮 | 温室効果ガスの削減、再生可能エネルギーの利用、廃棄物の適切な処理など |
| Social(社会)への配慮 | 人権の保護、男女平等、多様性(ダイバーシティ)の尊重、ワークライフバランスの実現など |
| Governance(企業統治) | 法令(コンプライアンス)の遵守、情報開示、権利の保護、内部監査など |
過去に多くの企業が自社の利益を追求する経営を続けてきた結果、さまざまな社会課題が生まれてきました。
だからこそ、長期的な発展を続けていくために、この3つを守っていくことが重要なのです。そのため、ESGは企業が社会に負う義務であり責任ともいえます。
ESG投資
これまで企業と投資家による経済活動は、売上や利益などにつながるかどうかが重視されてきました。
しかし、環境・社会・企業統治に対して投資することで、長期的な利益が見込めると考えられるようになっています。これがESG投資という考え方です。
ESG投資が広がり始めたのには、1つの大きなきっかけがあります。それは2006年に国際連合事務総長のコフィー・アナン氏が、PRI(国連責任投資原則)を提唱したことです。
PRIは各国の金融業界に共通するガイドラインで、機関投資家に対してESGの観点を持つように促しました。
この影響で世界の投資家がESGに配慮した企業への投資を強化し始め、企業側もESGを重視するようになっていきます。
2015年に日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRI(国連責任投資原則)に署名したことから、日本国内でもESG投資が注目され始めました。

ESGが注目されている背景
世界的にESGが注目されている背景には、どのような要因があるのかを解説します。
持続可能性(サステナビリティ)の重視
ESGが注目されてきた背景にあるのが、持続可能性(サステナビリティ)という概念です。
この概念が普及していったきっかけは、1987年に環境と開発に関する世界委員会が公表した報告書「Our Common Future」の中心的な考え方として、「持続可能な開発(Sustainable Development)」が取り上げられたことだとされています。
1980年頃から世界中で環境問題や社会問題が深刻化し、対策が求められ始めました。
そして世界では、経済的な成長と環境保全は反発するものではなく、共存できるものだと考えるようになります。
将来にわたって経済発展を続けられるよう、長期的な影響を考えて社会や環境と共存していくために、配慮しなければならないとされたのが「持続可能性(サステナビリティ)」です。
これが、ESG、CSR、SDGsなどの考え方につながっています。
ESGと企業の社会的な責任(CSR)の違い
ESGと同じように企業が重視するようになった言葉としてCSRがあります。
CSRは「Corporate Social Responsibility」の略で、「企業の社会的責任」という意味です。
世界中で環境や人権問題への関心が高まるとともに、企業が自社の利益だけ優先することなく社会に対しての責任を果たしているか厳しく見られるようになりました。
その責任に応えるための活動をCSR活動といいます。
具体的には、社会問題の解決につながる事業の促進、文化的なイベントへの後援、従業員による植林・清掃などボランティア活動などが例として挙げられます。
ESGが長期的な利益を見越した投資家の目線が含まれているのに対して、CSRはあくまで企業が社会的な責任を果たすための考えです。
どちらかといえば、CSRは利益を社会に還元していく意味合いが強いです。
とはいえ内容的には重なる部分も多く、CSRもESGも一つの流れのなかで注目を集めていると考えてよいでしょう。
ESGとSDGsとの違い
「SDGs」とは「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発目標」という意味です。
2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
目標は、貧困をなくそう、飢餓をゼロに、など17のゴール・169のターゲットから構成されています。
近年、非常に大きな注目を集めていて、SDGsに取り組む企業は世界で急速に増えているため、SDGsという言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
日本でも、経団連が行動憲章を改訂して「Society 5.0の実現を通じたSDGs(持続可能な開発目標)の達成」を組み込んだことにより、民間企業に浸透し始めています。
ESGと異なる点としては、SDGsは基本的には国連や政府が中心となって進めるものだということです。E
SGはあくまで民間企業が主体の考え方となっています。しかし、SDGsの盛り上がりが、ESGの普及にも影響を与えていると考えられるでしょう。

ESGによる企業のメリット
ESGを経営に取り入れることで、企業にもたらされるメリットをご紹介します。
投資家からの評価の獲得
ESG投資という言葉があるように、その企業がESGに取り組んでいるかどうかは、投資家にとって重要な判断材料になっています。
反対に、ESGに取り組んでいないと将来的に成長していく見込みが薄いと判断され、投資の対象から外されてしまう可能性があるのです。
投資ファンドのなかには、持続可能なビジネスをやっている企業にしか投資しないという方針を示しているところもあります。
ESGへの取り組みで直接的な利益を得られることは少なく、どうしても最初はコストになってしまうでしょう。
しかし、それによって投資家からの評価と注目を集められれば、将来的に資金として回収できるかもしれません。
ステークホルダーとの関係性の強化
ESGに取り組むことで、投資家だけでなく、従業員や取引先、地域社会など、あらゆるステークホルダー(自社に関係する存在)とのつながりを強くできます。
たとえば、職場における多様性を尊重したり、ワークライフバランスを実現したりすれば、それによって従業員の自社への愛着が強くなり、生産性が向上するでしょう。
法令(コンプライアンス)の遵守や権利の保護を徹底すれば、取引先からの信用が厚くなり、商談がスムーズに進むはずです。
企業の経営はステークホルダーの協力がなければ成り立ちません。
ESGへの取り組みは、ステークホルダーとの良好な関係性を築くという意味も持っています。
社会的信用とブランド力の向上
ESGへの取り組みを社外に公表すれば、社会的な信用を得ることも可能です。
近年は消費者も環境問題や社会問題への関心が高まっています。
そのため、ESGへの配慮が他社との差別化要素やブランド価値につながるのです。製品やサービスがコモディティ化(均一化)していることから、ESGは消費者に選ばれるための重要な要素の一つになってきています。
採用においても同様です。企業が社会に貢献しているかを重視する求職者が増えているといわれています。
待遇だけでは他社との差別化がしにくく、なかなか優秀な人材を採用できません。
ESGへの投資は採用への効果も見込める貴重な手段だと考えられます。
ESG投資は長期的な目線でメリットを考える
設備や人材への投資とは異なり、ESGの取り組みから直接的な利益を得ることは難しいです。そのため短期的な視点で捉えると、どうしてもコストとして考えられてしまいます。
しかし、ESGの取り組みによって積み重ねた信頼やステークホルダーとの関係性は、将来的に間接的な利益として還ってくる可能性があります。
い方でESGに全く関心を示していないことで、事業の継続が難しくなったり、社会的な信用を失ってしまったりするリスクもあります。
自分たちの会社がESGに取り組むべきかを検討するなら、長期的な目線でどういったメリットが想定されて、どのようなリスクが想定されるか考えるとよいでしょう。
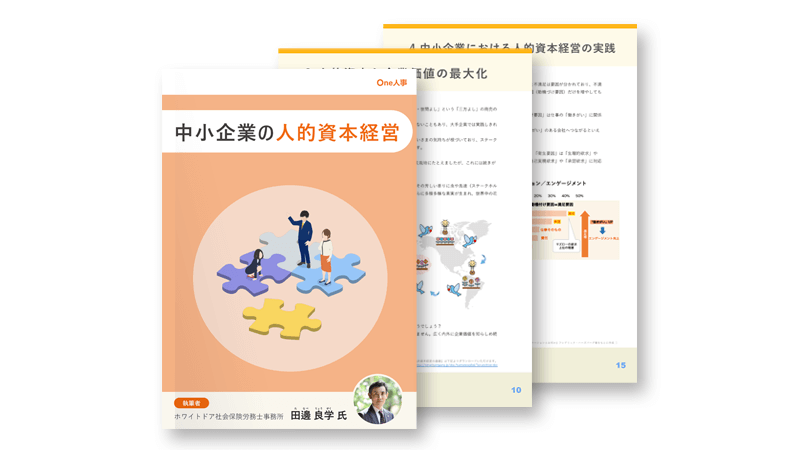
ESGの取り組み、施策の事例
実際にESGに取り組んでいる企業の事例を、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)、それぞれの観点から紹介します。
Environment(環境)の取り組み・施策の事例
製造業はESGのなかでも、とくに環境への取り組みを重視していることが多いです。
たとえば大手複合機メーカーでは大量印刷による紙資源の消費と向き合い、必要な時に必要な分だけ印刷して廃棄を減らせるプリンタを開発しました。
大手日用品メーカーでは、環境への負荷に配慮して、製品ボトルに使用されているプラスチックをすべて再生プラスチックに変更しています。
不動産会社が、断熱効果の向上や太陽光発電の利用などによって環境に優しいマンションづくりを進めるのも、ESGへの取り組みといえるでしょう。
製品の原材料や生産プロセス、性能などを見直すことによって、環境問題に貢献できる可能性があります。
一方で、無形の商品やサービスを扱う企業の場合は環境問題に直接アプローチしにくく、従業員による清掃や植林ボランティアなどビジネスとの親和性が低くなりやすいです。
そのため環境への配慮は3つのなかだと、優先度としては高くないかもしれません。
Social(社会)の取り組み・施策の事例
社会への取り組みは業種を問わず、あらゆる企業が当事者になります。
たとえば大手グループのIT企業では、自社での安全な作業環境やテレワーク環境の整備などに加えて、出張でのプログラミング授業、大学への非常勤講師の派遣や奨学金の提供など将来を担うIT人材の育成にも取り組んでいます。
有名製菓メーカーが将来的な原料供給の安定化を目指して、チョコレートの売上1個につき1円をカカオの原産国に寄付し、農家の技術向上や教育環境の整備に投資しているという事例もあります。
とある金融系の企業では、外国の方に向けたATMの多言語化、耳の不自由な方に向けた音声ガイダンスサービスなどに力を入れています。
その他の企業では、ステークホルダーの人権尊重、男女平等・女性活躍の推進、多様性(ダイバーシティ)の確保、長時間労働の是正などを経営方針として掲げている企業が多いようです。

Governance(企業統治)の取り組み・施策の事例
大手家電メーカーでは、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、知的財産マネジメント、ブランドマネジメントという4つの観点で企業統治の体制をつくり、その方針を企業のホームページでも公開しています。
大手商社では、取締役会の1/3を社外取締役に、ガバナンス・報酬委員会・指名委員会は過半数を社外の人員で構成するなど、独立した客観的な視点からの監督を受け、意思決定を透明化することをESGへの取り組みの一つとしていました。
郵便事業を営む有名グループ企業のように、グループ全体でコーポレートガバナンスの体制を構築し、リスクをまとめて管理しているケースもあります。
東証一部に上場している企業は、コーポレートガバナンス・コードに従うことが求められます。
一方で企業統治を意識する必要があるのは大企業だけではありません。
法令(コンプライアンス)の遵守、公平で透明性の高い意思決定、権利の保護などは、企業規模によらず意識したい要素といえるでしょう。
ESG投資7つの種類
ESG投資の手法には7つの種類があります。投資家目線での考え方ですが、どういった基準で投資先が選ばれるのかを知っておくと、企業にとってもメリットがあるでしょう。
ネガティブ・スクリーニング
ネガティブ・スクリーニングは、環境に悪影響を与える、社会的倫理に反するなど、ESGの考え方に反する企業を投資先から排除する手法です。
古くから行われてきた原始的な手法で、現在も多く使われています。
具体的には、タバコ、アルコール、ギャンブル、武器製造、ポルノなどの事業が対象となることが多いです。
国際規範スクリーニング
国際規範スクリーニングは、国連や国際労働機関などが定める基準を満たしていない企業を、投資先から除外する手法です。
ネガティブスクリーニングと考え方としては似ていますが、事業内容は問いません。
具体的な内容は基準とする規範にもよりますが、児童労働、汚職、動物実験、化石燃料の使用などがチェックされます。
ポジティブ・スクリーニング/ベスト・イン・クラス
ポジティブ・スクリーニングは、ESGへの取り組みに対する評価が高い企業を投資先に選ぶ手法です。
ネガティブ・スクリーニングとは反対の考え方ともいえます。
企業が公開している情報や、外部機関によるESG指数(格づけ)を参考にする場合が多いです。
ベストインクラスとは、そうした基準に照らしあわせて各業種のなかで、もっとも評価が高い企業に投資する手法です。
サステナビリティ・テーマ投資
サステナビリティ・テーマ投資は、ESGに関わるテーマで事業を行っている企業に投資する手法です。
具体的には、再生可能エネルギーの利用法の開発、持続可能な農業、汚染・廃棄物の処理を助ける製品、貧困の解消や女性の活躍推進につながるサービスなどです。
近年は、企業や自治体が環境問題の解決に必要な資金を調達するための債券「グリーンボンド」なども注目を集めています。
インパクト・コミュニティ投資
インパクト・コミュニティ投資は、企業のESGに対する取り組みが、どれくらい影響力を持っているかによって投資先を判断する手法です。
社会や環境などへの影響力を重視する手法はインパクト投資、地域社会への影響を重視する手法はコミュニティ投資と呼ばれます。
インパクト・コミュニティ投資では、たとえば再生可能エネルギーの活用に取り組んでいる企業の場合、「温室効果ガスの排出量が何%削減できたのか」などの数値で、影響力を判断しています。
ESGインテグレーション
ESGインテグレーションは、従来のやり方で重視してきた財務情報とESGの取り組みに対する評価のバランスを見て、総合的に判断する投資手法です。
ただESGに取り組んでいるだけではなく、ちゃんと会社として利益が出ている企業を投資先に選定します。
むしろESGに対する取り組みが社会や環境にどんな影響を与えるかよりも、将来的な利益やリスク回避にどうつながるかを重点的に検討して投資先を選定する傾向が強いです。
エンゲージメント・議決権行使
エンゲージメント・議決権行使は、株主になることで企業に対してESGへの取り組みを促す投資手法です。
現状の取り組みを評価するのではなく、今後どう変えていくかという視点で企業を選定するため、ほかの手法とは考え方が異なります。
ESGへの取り組みを促す方法は、経営層とのコミュニケーション、情報開示の要求、株主総会での意見や議決権の行使などです。
結果として、企業の活動に変化が見られない場合は、投資先から外すこともあります。
まとめ|企業がESGに積極的に取り組むには?
ESGは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の頭文字を取った言葉です。
企業経営では、3つの観点を意識して取り組む考え方が広がっています。
現在は大企業を中心に進んでいますが、今後は中小企業でも意識しておかないと思わぬリスクを招く可能性も否定できません。
しかし、業種や企業規模によって取り組むべきESGの課題はさまざまです。
ステークホルダーとの関係構築や法令順守、情報開示は多くの企業で実践しやすい分野です。一方、環境問題への取り組みは業種によっては効果的な方法を見つけにくい場合もあります。
だからこそ、長期的な視点で自社の経営にどれだけ影響を与えるかを考え、優先順位をつけて進めていくことが大切です。
