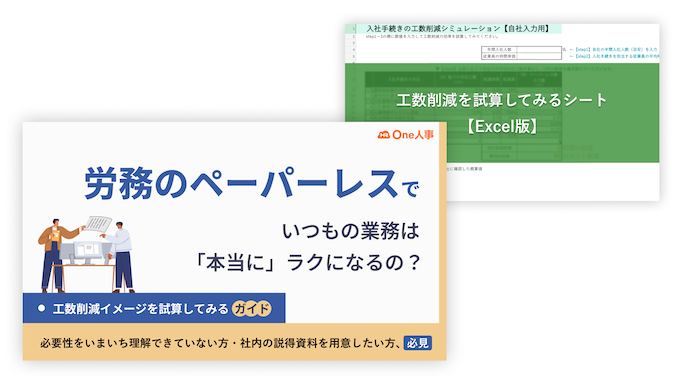サイロ化とは? 意味や原因、企業における課題、解消方法を解説
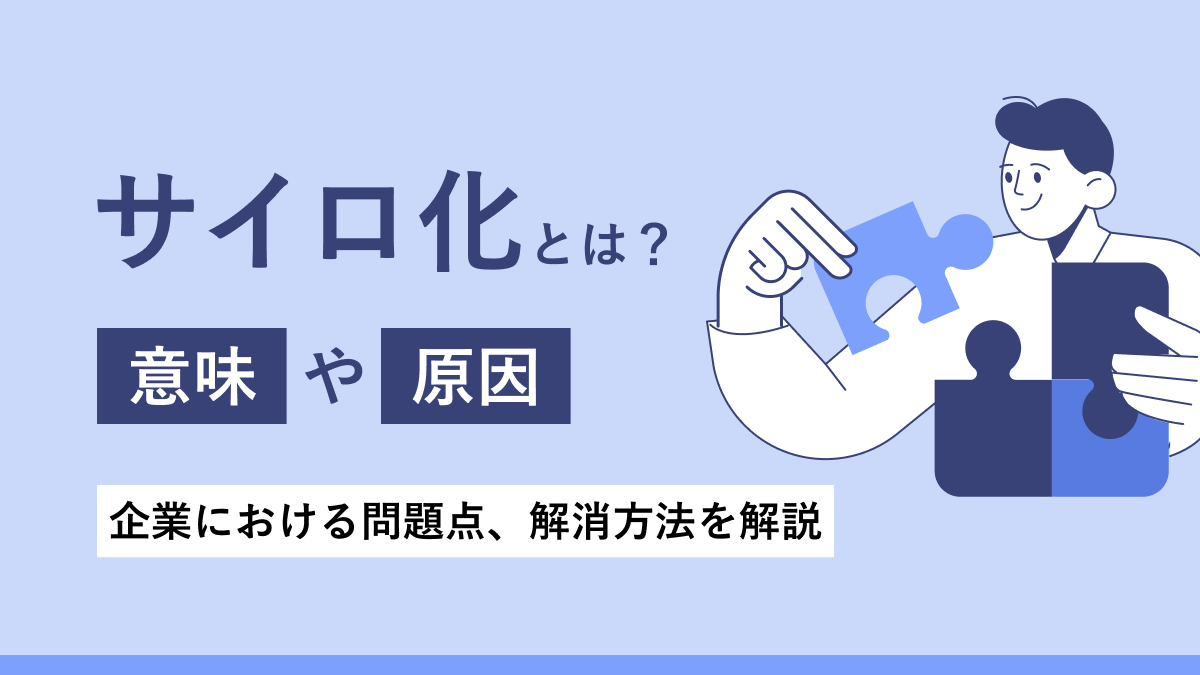
「サイロ化」とは各種データや管理システムがバラバラに分かれて孤立し、全体で情報共有がしにくくなることを意味します。部門間の連携がさまたげ、結果として業務効率や顧客満足度の低下を招くため、しばしば企業の課題として浮上しています。
サイロ化を放置すれば、競争力が低下し、新たなビジネスの機会を逃すリスクもあるのです。
本記事では、サイロ化の意味や種類と発生原因を紹介します。さらに、企業で起こりやすい課題や、解消に向けた具体的な方法、取り組むことで得られるメリットも解説していきます。
→人事のサイロ化を防ぐ|ワンストップ人事労務システムの資料を見てみる

 目次[表示]
目次[表示]
サイロ化とは? 意味・語源と種類を解説
サイロ化の意味とは、情報や業務の流れが組織やシステム内で分断され、全社的な連携が取れなくなる状態です。
サイロ化の語源は、農業で使う「サイロ(貯蔵庫)」に由来します。サイロは独立したタンクで、穀物などの内容物が混ざらないように保管する設計になっています。
サイロの仕組みが、企業のなかで部門や情報が孤立している様子の比喩として使われるようになりました。
組織のサイロ化
組織のサイロ化とは、部署や部門がそれぞれ独立しすぎて、横のつながりが弱い状態です。
たとえば、営業部門が集めた顧客の声を、開発部門に十分に共有できないことがあります。
結果的に、顧客の期待を反映した製品が生まれず、競合に遅れを取ってしまうかもしれません。
また、部門間で「情報は自分たちだけのもの」という意識が強いと、連携不足が進み、対立や不信感が生じることもあります。そうなると、チームの士気が下がり、業務効率まで悪化しかねません。
複数の国や地域に拠点を持つ企業では、距離や文化の違いから情報の断絶がさらに深刻化するケースもあるようです。
システムのサイロ化
システムのサイロ化は、各部門が異なるシステムを使用し、相互の連携が取れていない状態を意味します。
たとえば、販売管理と生産管理のシステムがそれぞれ独立して稼働している場合、リアルタイムに情報をやり取りできません。販売データと生産計画がずれ、在庫の過不足や納期遅れのリスクが高まります。
バラバラのシステムを統合するには、追加の開発費やデータの変換作業が必要です。コストも時間もかかるという問題が生じてしまいます。
データのサイロ化
データのサイロ化は、部門やシステムごとにデータが分散管理され、全社的に一元化されていない状態です。
たとえば、営業・マーケティング・カスタマーサポートの各部門が、それぞれ独自に顧客データを管理しているケースです。
分断があると、同じ顧客に対して部門ごとにサービス対応に統一性がなく、一貫した顧客体験を提供できません。
また、全体のデータを統合して分析するには膨大な労力がかかります。意思決定のスピードが落ち、チャンスを逃すリスクも高まります。

サイロ化が起こる原因
サイロ化が進む背景には、組織構造やシステム運用方法など、さまざまな要因が絡みあっています。サイロ化が進んでしまう主な原因を具体的に見ていきましょう。
原因を理解し、根本的な対処に取りかかることで、解消に向けた対策が立てられます。「自分の組織にもあてはまるかも」と思いながら読んでみてください。
縦割りの組織構造
縦割りの組織構造は、サイロ化が生じる代表的な原因の1つです。
縦割りの組織では、各部門がそれぞれの役割や目標に専念します。そのため部門間の連携や助け合いが軽視されがちです。
たとえば、製造部門がコスト削減を重視している一方で、営業部門が高品質な製品を求めることが多いです。考えの違いがきっかけで、互いに意見が対立し、協力が難しくなることがあります。
結果として、顧客ニーズを反映した製品が生まれにくくなるのです。
さらに、組織内でのコミュニケーション不足や部門間の競争意識も、サイロ化を助長します。とくに企業文化が「情報の独占」をよしとする傾向にある場合、ますます情報共有が制限され、組織全体のパフォーマンスが低下してしまうでしょう。
システムやアプリケーションの連携不足
システムやアプリケーションの連携不足も、サイロ化を生む大きな原因です。
多くの企業では、特定の目的や部門の要件に応じて、それぞれ独自のシステムやアプリケーションを導入しています。
しかし、システム間で十分にデータ連携ができていないと、情報が分断され、一元管理できなくなってしまいます。
たとえば、CRM(顧客関係管理システム)とERP(基幹業務システム)が連携していない場合、顧客データや売り上げ情報をまとめて把握できず、顧客対応の質が低下する可能性があります。
システム同士の連携不足は、導入時に長期的な視点が欠けていたり、異なるベンダーのシステムを部分最適で組みあわせたりした場合に発生しやすい問題です。
部署や拠点ごとに最適化されたシステムの導入
部署や拠点ごとに「自分たちにあうシステムを選ぼう」と最適化を進める動きはめずらしくありません。しかし、行き過ぎると、全社的にはかえって非効率を生み、サイロ化の原因となります。
たとえば、ある拠点だけ独自の在庫管理システムを採用したものの、ほかの拠点とデータの互換性を持たない場合、在庫情報を統合して分析できません。
結果として、全体の在庫を正確に把握できず、追加の確認や手作業が必要になるのです。
とくに大規模な企業やグローバル企業で、問題が起こりやすく、管理コストの増加やデータ精度の低下を招きます。

独立採算制の導入
独立採算制の導入は、サイロ化を引き起こす原因になりやすいです。
独立採算制の企業では、各部門が自分たちの収益とコストの責任を負うため、全社的な連携よりも自部門の利益を優先する傾向があります。
たとえば、販売部門が自部門の利益を最大化するために過剰な受注を獲得したとします。すると、生産部門は急な計画変更や納期の調整に追われ、大きく混乱してしまうでしょう。
結果として、他部門との情報共有や共同作業がおろそかになり、サイロ化が進行するのです。
サイロ化による5つの課題
サイロ化が企業にもたらす影響は、決して小さくありません。業務効率が落ちるだけでなく、経営の判断が鈍り、顧客からの信頼を失うきっかけにもなります。すでに兆しがあらわれていませんか。
ここからは、サイロ化が引き起こす代表的な5つの課題を確認していきます。
- 意思決定のスピードが遅れる
- データを活用しづらい
- 作業効率や生産性を向上しづらい
- 余計なコストがかかる
- 顧客満足度の低下を招く
1. 意思決定のスピードが遅れる
サイロ化によって情報が分断されていると、経営やプロジェクトの意思決定に必要なデータを集めるまでに時間がかかるのが課題です。
営業部門と製造部門が異なるシステムを使用している場合、営業データと生産データを統合する作業に手間がかかり、リアルタイムな意思決定が難しくなるでしょう。
遅れは、迅速な対応が求められる市場の変化や競合他社の動きに対する柔軟性を損ない、企業の競争力を低下させる可能性があります。
また、判断に必要なデータの整合性が取れず、誤った判断を下してしまうリスクも高まります。
2. データを活用しづらい
サイロ化が進むと、ビッグデータやデータドリブン戦略を活用するのが難しくなります。
マーケティング部門が顧客購買データを所有していても、データが他部門に共有されていなければ、販売戦略や製品開発に反映させることは困難です。
また、データの形式や保存場所が異なる場合、統一して活用するための時間とリソースが必要となり、データの持つ価値が減少してしまいます。
結果として、新たな市場機会や顧客ニーズの洞察を逃してしまうのです。

3. 作業効率や生産性を向上しづらい
サイロ化された組織では、同じ情報が複数の場所で重複管理されることがめずらしくありません。
各部門がそれぞれ独自の顧客情報を管理し、同じデータを複数回入力する手間が発生しています。
そのためデータ整合性を確認したり、ミスの修正を修正したりするだけで多くの時間がかかります。 本来注力すべき重要な業務に、リソースを十分割けなくなるでしょう。
非効率な作業が生産性の低下につながり、最終的には全社的なコスト増加や成長の機会損失にもつながっていきます。
4. 余計なコストがかかる
サイロ化が進むと、各部門が独自のシステムやツールを導入するため、ライセンス費用や運用コストが重複することがよくあります。
分断されたシステムを統合するには、外部のコンサルタントや開発者を雇う必要があるため、コストも増えるでしょう。
異なるシステム間でデータを移行したり連携したりする作業にも、多額の追加費用が発生します。かけたコストのわりに、得られる効果が限られてしまうのが大きな課題です。
5. 顧客満足度の低下を招く
サイロ化は、顧客対応にも悪い影響が懸念されます。
カスタマーサポートの担当者が顧客の過去の購入履歴や問い合わせ内容にアクセスできないと、顧客のニーズに即した適切な対応ができません。
また、営業部門とサポート部門がバラバラの情報をもとに対応してしまうと、顧客に対して一貫性のない説明をしてしまいます。「この会社は連携がとれていない」と思われ、信頼を失う原因になるでしょう。
結果として、リピート購入が減ったり、ブランドイメージが低下したりするおそれがあります。
サイロ化を解消するメリット
サイロ化を解消すると、企業は大きな変化を実感できます。
日々の業務がスムーズに回り、情報の価値を最大限に活かせるようになるのはもちろん、組織全体のスピードや柔軟性も向上するでしょう。業務効率の改善から新しいビジネスチャンスの創出まで、得られるメリットは想像以上に幅広いものです。
サイロ化を解消することで具体的にどのような効果が期待できるのか、3つのメリットを紹介します。
業務を効率化できる
サイロ化を解消することで、業務プロセス全体を見直し、効率化をはかることが可能です。
分断されていた情報を1つのデータベースにまとめることで、作業のムダや重複をなくせるためです。
全社で共通のデータベースを導入すれば、部門間の情報共有がスムーズになります。データ入力や集計も自動化され、時間と人的リソースを削減できます。
従業員が本来の業務に集中できる環境を整えることで、生産性が向上するでしょう。
適切な経営判断につながる
サイロ化をなくすことは、経営の意思決定を支える力になります。
統合された正確なデータに基づいて判断できるため、迅速で的確な対応が可能になるためです。
販売データや顧客情報を一元管理すれば、市場の動きを正しく分析できます。需要予測や施策立案もスピーディーに行えるでしょう。
サイロ化の解消で、経営の柔軟性や競争力を強化できる点が大きなメリットです。
企業のデータ価値が高まる
サイロ化を解消すると、データの活用価値が高まります。
全社の情報を一元管理することでデータ同士の関連性を分析しやすくなるためです。
AIやBIツールで統合データを解析すれば、顧客の購買傾向を把握したり、新しいビジネスチャンスを見つけたりできます。
データ活用が進むことで、よりパーソナライズされたサービスを提供できるようになり、企業全体の成長を後押しします。
▼人的資本情報の開示が求められる昨今では、企業の人事データはとても価値のあるものとして認められています。人事データの価値を知るには、以下の資料もご活用ください。

サイロ化を解消する方法
サイロ化の課題やメリットを理解できたところで、「どこから手をつければいいのかわからない」と悩む方も多いはずです。
サイロ化を解消するための方法を3ステップで紹介します。
- データを統合する
- 部門間の垣根を超えたコミュニケーションを促進する
- 従業員の理解を促す
サイロ化を本気で解消するには、データやシステムを統合するだけでは不十分です。目に見える仕組みの改善だけでなく、従業員一人ひとりの意識を変え、部門同士が助け合う風土を育てることも欠かせません。
データを統合する
サイロ化を解消するためには、まず分断されたデータを統合し、一元管理する環境を構築します。
たとえば、データウェアハウス(DWH)やクラウドプラットフォームを活用する方法があります。
異なるシステム間でデータ形式をそろえれば、全社でリアルタイムに情報を共有できるでしょう。
また、CDP(Customer Data Platform)を導入することで、顧客データを統合し、マーケティングや営業活動に活用する企業も増えています。

部門間の垣根を超えたコミュニケーションを促進する
サイロ化を防ぐには、部門同士のコミュニケーションを活性化することも重要です。
情報共有の習慣が根づかない限り、仕組みだけ整えてもすぐに形骸化するおそれがあるためです。
具体的には、ジョブローテーションやクロスファンクショナルチームを導入する方法があります。他部門の仕事や課題への理解が深まり、横断的なプロジェクトも円滑に進むでしょう。
さらに、社内イベントやワークショップを定期的に開催し、従業員同士の交流を促進することも効果的です。
継続的な取り組みが、部門の壁をなくし、オープンな情報共有の文化につながります。
従業員の理解を促す
サイロ化を根本から解消するには、従業員全員の理解と協力が欠かせません。
全員が共通の目標として意識を持っていなければ、どんな対策も一時的な取り組みで終わってしまいます。
まずはサイロ化が生むリスクや解消の必要性を共有しましょう。成果をわかりやすく見せることで、プロジェクトへのモチベーションを高められます。
サイロ化の解消プロジェクトは、組織全体の行動を変えるきっかけとなります。
人事情報のサイロ化を解消するには?
人事情報のサイロ化に悩む企業は少なくありません。勤怠管理、給与計算、人材管理をそれぞれ別々のシステムで運用していると、データを活かしきれず、同じ情報を何度も入力する手間が発生してしまいます。
「One人事」は、労務・勤怠・給与・タレントマネジメントを1つにまとめて管理できる人事労務システムです。 データの分断をなくし、サイロ化を防ぐ組織づくりを支援します。
詳しい活用例は、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務のお悩みに沿った資料を無料でダウンロードしていただけます。人事領域で業務改善に取り組む担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
まとめ|サイロ化の解消で競争力を高める
サイロ化は、企業の成長や競争力を阻害する深刻な課題です。情報や業務が分断された状態を放置すれば、業務効率や顧客満足度の低下を引き起こし、やがてビジネス全体に影響をおよぼします。
サイロ化対策を計画し、段階的に実行することで、情報を最大限に活用し、組織の一体感を高めることが可能です。そして業務のスピードが上がり、意思決定が正確になり、顧客への価値提供も向上するでしょう。
変化の激しいビジネス環境で競争力を維持するために、サイロ化の解消に向けて動き出してみてはいかがでしょうか。