給与所得者の特定支出控除とは?対象の支出や企業に求められる対応を解説
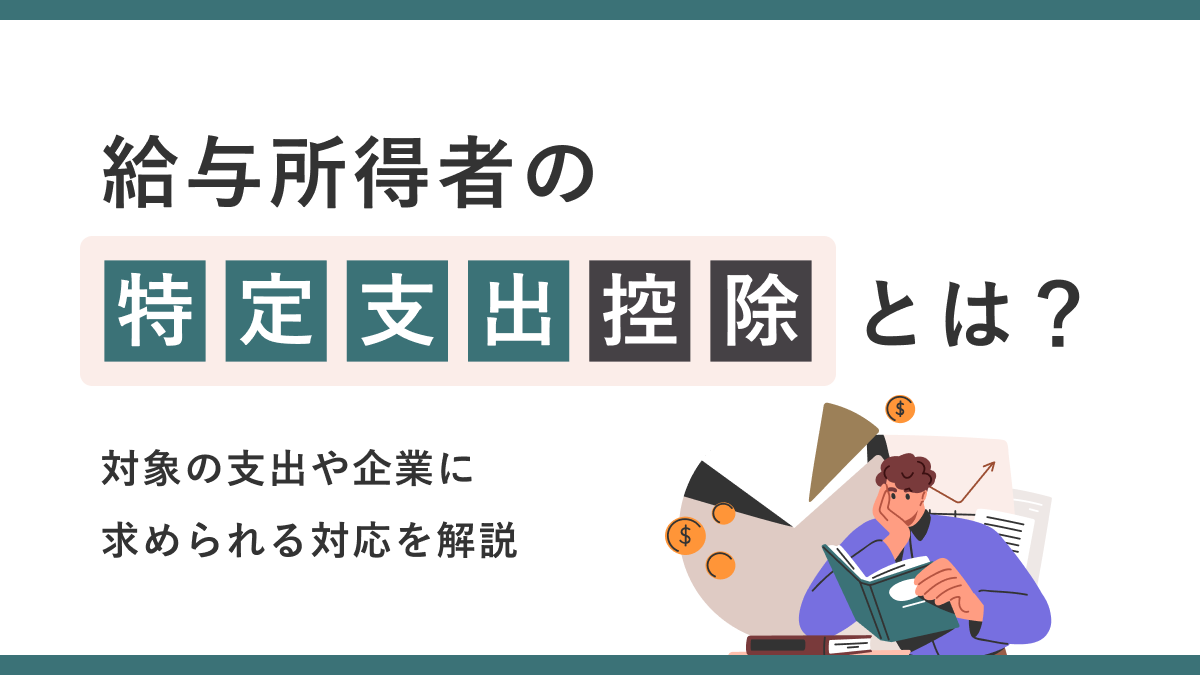
所得控除の一種に、給与所得者の特定支出控除があります。特定支出控除は該当者が限られるうえ、年末調整では処理しないため、担当者でもあまりよく知らないという人は多いでしょう。
しかし、特定支出控除の申告では、企業に「特定支出控除に該当するか・しないか」の判断が求められます。企業の担当者は、特定支出控除について理解を深め、必要な手続きを滞りなく済ませなければなりません。
本記事では、給与所得者の特定支出控除について、該当する費用の種類や企業に求められる対応などを詳しく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
給与所得者の特定支出控除とは?
給与所得者の特定支出控除(以下、特定支出控除)とは、従業員が業務にかかる費用を多く負担した場合に適用される制度です。
資格取得にかかった費用や、営業で必要なスーツ代について、税金で控除できたらいいと思ったことはありませんか。
特定支出控除は7種類の特定支出について、1年間の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える部分の金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引けます。
そのほかの所得控除と同様、所得金額が少なくなるため従業員の税負担を抑えることが可能です。
以前は要件が厳しかったため利用者は少数でしたが、範囲拡大や適用判定の見直しにより多くの人が利用できるようになりました。
特定支出の種類
特定支出に該当するものは、次の7種類と定められています。
- 通勤費
- 職務上の旅費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 勤務必要経費
それぞれの支出の範囲や条件について、以下で詳しく解説します。
通勤費
通勤に使う交通費を従業員が自分で支払っている場合や、支給される通勤費を超える場合は、特定支出とみなされます。電車やバスなどの公共交通機関の運賃および料金だけでなく、自動車通勤に使用するガソリン代なども対象です。
正社員には通勤費を支給する企業が多いため、パートや派遣スタッフなどで交通費を自分で支払っているようなケースが想定されます。
職務上の旅費
出張のように、普段の勤務地を離れて職務を遂行するために必要な旅費のうち、従業員本人が支払ったものは特定支出として認められます。
ただし、交通手段や経路を総合的に判断し、無駄のない最適な移動ルートであることを確認しなければなりません。
転居費
引越しが必要な勤務地への異動によって発生した転居費用のうち、従業員個人が支払った金額は特定支出に該当します。
人事異動にともなう転居費用は企業が負担するケースが大半ですが、転居にともなう燃料費やホテルへの宿泊費、梱包材料の購入費用なども対象になります。転居にかかった費用を従業員個人が支払っている場合は、特定支出として計上が可能です。
研修費
業務に求められる知識・スキルを習得するための研修費用のうち、従業員個人が支出した金額は特定支出として計上できます。ただし、スキルアップのための研修をすべて計上できるわけではなく、あくまで業務に直接的にかかわる講座のみが対象です。
また、グループ研修だけでなく、キャリアコンサルタントによる職業相談を利用するための費用も含まれます。研修会場へ行くための交通費も含まれますが、経路や期間などを踏まえて総合的に判断する必要があります。
資格取得費
業務上必要な資格の取得費用も、特定支出として計上が可能です。たとえば、以下のような資格が対象です。
- 簿記
- 自動車免許
- 医師免許
- 弁護士資格
そのほか、経営に活かすためにMBAを取得する場合などの、大学院の学費も計上できます。
ただし、計上できるのは支払い済みの学費のうち、その年1年間の学費のみです。たとえば、2年分の学費を一括で入金している場合も、計上できるのは1年分となります。
帰宅旅費
単身赴任のように、自宅とは別の住居で暮らしている場合、帰省にかかる費用は特定支出として計上できます。
週末や長期休暇に、単身赴任先から家族のもとへ帰る際の公共交通機関の運賃などが対象です。たとえば新幹線代や飛行機代のほか、自動車のガソリン代・高速料金なども含まれます。
回数や金額に上限が設けられているわけではありませんが、常識の範囲内で「家族との生活拠点に戻る費用」が認められます。観光や娯楽を目的とした旅行費用は対象外です。
勤務必要経費
業務を遂行するうえで必要とされる費用は「勤務必要経費」にまとめられています。大きく分けて「図書費」「衣服費」「交通費や接待費など」が特定支出として認められます。
図書費
担当業務に直接的に関係する専門書や専門誌などの購入費用です。
会計担当なら税制改正に関する専門書、営業担当なら業界のマーケットレポート、建築デザイン職なら写真集などが対象と考えられます。
趣味的な書籍や一般的な雑誌は認められません。
衣服費
会社が着用を指定している衣服の購入費用です。典型的には「スーツ着用が必須の営業職」のスーツ代や、制服を自費で購入する場合が、特定支出とみなされます。普段着としても利用する予定の衣服や装飾品は対象外です。
交際費や接待費など
職務上必要な交際にかかる費用です。得意先との接待のための飲食費や、得意先へのお中元・お歳暮代などが該当します。
一方で、社内の親睦会の費用や、同僚や部下への慶弔費などは、「業務上必要」とは認められないため控除の対象外です。
特定支出控除の計算方法
特定支出控除について、「実際にどれだけ節税できるのか」と気になる人もいるでしょう。
特定支出控除の計算はシンプルで、次の3つのステップで行います。
- 年収に応じた基準額を計算する
- 特定支出控除にできるか確認する
- 控除額に所得税率を乗じる
各ステップの具体的な計算方法を確認していきます。
1.年収に応じた基準額を計算する
特定支出控除を適用する条件は、業務にかかる支出が給与所得控除の半分を超えることです。そのため、まずは従業員それぞれの収入金額に応じた給与所得控除額を確認する必要があります。
給与所得控除は、給与などの収入金額に応じて以下のとおり定められています。
| 給与などの収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162万5,000円まで | 65万円(※) |
| 162万5,001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万1円以上 | 195万円(上限) |
(※)令和7年度(2025年度)税制改正により、給与所得控除の最低保障額が65万円に変更
出典:『No.1410 給与所得控除』国税庁
参照:『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』国税庁
たとえば、年収500万円の従業員の場合、給与所得控除は500万円×20%+44万円=144万円です。つまり、業務にかかる支出が半分の72万円を超える場合に、特定支出控除の対象となります。
2.特定支出控除にできるか確認する
次に、従業員の業務にかかる支出額を把握し、特定支出控除にできるかを確認します。
年収500万円の従業員の場合、特定支出が100万円なら100万円-72万円=28万円を特定支出として申告が可能です。
一方、特定支出が50万円だった場合、基準である72万円を下回るので控除はできません。
3.控除額に所得税率を乗じる
控除額の28万円に所得税率を乗じると、実際に所得税額から差し引かれる金額を計算できます。
所得税率は、課税所得金額に応じて以下のとおり定められています。
| 課税所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
たとえば、年収500万円から各種所得控除後に10%の所得税率が適用される場合、「28万円×10%=2万8,000円」の節税になる計算です。
特定支出控除を適用するために必要な手続き
特定支出控除を適用するためには、所定の手続きが必要です。制度の概要がわかったところで、実際の申請方法が気になる人もいるでしょう。
特定支出控除は年末調整では処理できないため、確定申告と企業からの証明書が必要になります。ここからは、従業員個人が特定支出控除を申請する方法や、企業に求められる対応について解説します。
特定支出控除は確定申告で申請する
配偶者控除や扶養控除などの所得控除とは異なり、特定支出控除は年末調整で処理できません。従業員が特定支出控除を受けるためには、本人が確定申告をする必要があります。
確定申告で、提出する書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 特定支出を支払った証明となる領収書やレシートなど
- 特定支出に関する証明書
- 特定支出に関する明細書
確定申告書には、特定支出のための記入欄は設けられていません。代わりに「所得金額等」の給与欄に、給与所得控除などと一緒に特定支出控除を差し引いた金額を記入します。
特定支出控除を受けたい場合は、通常は確定申告が不要な会社員にも申告手続きが求められます。従業員が直前であわてずに済むよう、手続きについておおまかに案内しておくと親切です。
企業は特定支出に関する証明書を発行する
企業は、特定支出控除に関する証明書を発行する必要があります。従業員が確定申告の際に提出する大切な書類なので、遅れることなく処理することが大切です。
証明書は、従業員が企業に証明の依頼書を提出し、企業がその内容を証明するという形式で発行されます。従業員から証明の依頼書を受け取ったら、特定支出に該当することを確認したうえで必要事項を記入しましょう。
特定支出に該当するか、該当しないかの判断に迷うときは、税理士などに相談するのもおすすめです。
「研修費」と「資格取得費」に限っては、国家資格キャリアコンサルタントによる証明があれば、企業による証明の代わりとして利用できます。
特定支出控除について企業が注意したいポイント
特定支出控除について企業がとくに注意したい点は、以下の2つです。
- 通常どおり年末調整を済ませる
- 証明書の様式に気をつける
特定支出控除は従業員が確定申告で申請する制度ですが、企業側にも重要な役割があります。対応を誤ると、従業員が控除を受けられなかったり、申告がやり直しになったりするリスクも考えられるため、ポイントを1つずつ確認していきましょう。
通常どおり年末調整を済ませる
特定支出控除を受けるために従業員が確定申告をする場合でも、年末調整は通常どおり行う必要があります。
確定申告の際には、特定支出に関する証明書のほか、源泉徴収票も必要です。年末調整を済ませないと源泉徴収票を発行できないので、ほかの従業員と同様に手続きを済ませましょう。
証明書の様式に気をつける
特定支出に関する証明書は、通勤費や研修費など、費用の種類ごとに様式が定められています。費用の種類によって記載内容が異なるので、従業員が正しい様式を使用しているか確認しましょう。
証明書の様式は、国税庁のホームページからダウンロードができます。
まとめ|特定支出控除を理解し、確実な対応を
特定支出控除とは、自己負担した仕事の費用を、税金計算から差し引ける所得控除制度です。
資格取得費や単身赴任の帰省費など、従業員にとっては負担軽減につながります。
特定支出控除は従業員本人が申告するものですが、企業にも証明書の内容確認や必要事項の記入などの対応が求められます。
企業にとって重要なポイントは、特定支出控除の対象になるか、ならないかを判断することです。迷ったときは担当者や部署内だけで判断せず、税理士などの専門家に相談しましょう。
従業員が確定申告で特定支出控除を申告する場合でも、年末調整は通常どおり必要です。煩雑な年末調整業務を効率化するなら、便利なシステムの活用も検討してみましょう。人事労務の自動化が進めば、担当者の負担軽減やミスの防止につながります。
年末調整の控除計算をミスなく|One人事[給与]
One人事[給与]は、ミスができない年末調整の計算をはじめ、給与計算の自動化を助けるクラウド給与計算システムです。
One人事[労務]との連携により、書類の回収から一貫してシステム上で完結できます。制度改正にもスムーズに対応でき、繁忙期の担当者の負担を減らせるでしょう。
One人事[給与]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ労務管理の効率化のヒントになるお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。ぜひお気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
