年末調整の還付金を計算する手順とは【具体例でシミュレーション】平均額や発生条件も解説
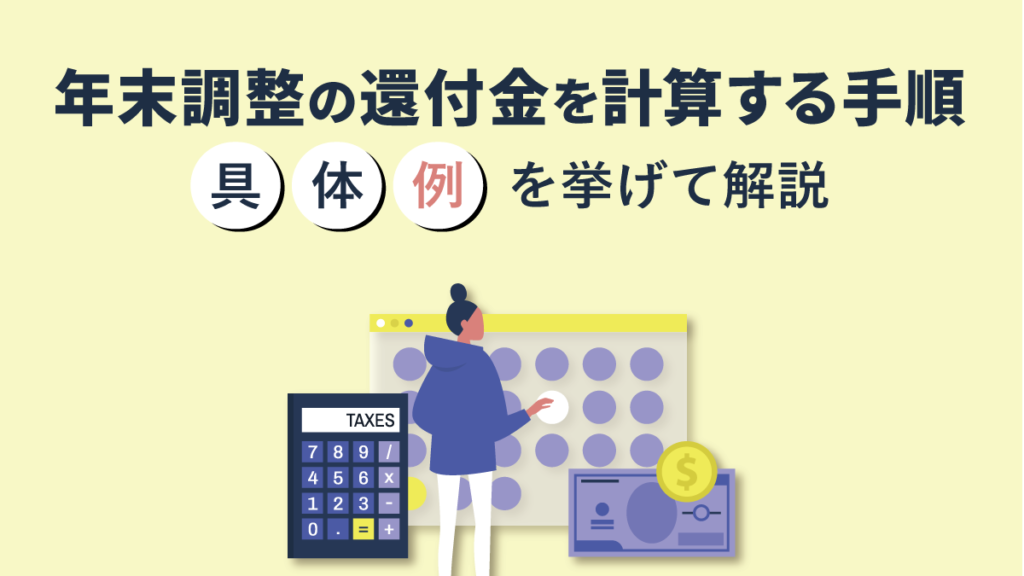
年末調整の還付金とは、毎月の給与から引かれていた所得税が実際の税額より多かった場合に、払い戻される金銭(差額)です。計算方法や発生条件が複雑で、完全には理解できていない人もいるかもしれません。
本記事では、年末調整の還付金について、具体的な手順をシミュレーションしてわかりやすく解説します。
年末調整の還付金を計算する手順を、具体例を用いてシミュレーションし、わかりやすく解説します。また平均的な還付金額や還付金が発生する条件、必要な書類、計算に必要な控除項目などポイントも紹介します。
→年末調整の計算を効率化|「One人事」資料を無料ダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整の還付金が発生する条件
年末調整の還付金とは、毎月の給与から差し引かれていた源泉徴収額が、実際に徴収すべき取得税額を上回っていた場合に、払いすぎた分を従業員に戻すお金を意味します。
給与からは各種社会保険料や所得税が差し引か(源泉徴収さ)れていますが、所得税額は1年間の所得に基づいて確定するため、毎月の源泉徴収は概算です。
1年間の所得が正式に決定するタイミングで、正確な所得税額を算出し、概算金額との差額を精算する仕組みが年末調整です。
還付金の受け取りではなく追加徴収になることもある
年末調整の還付金が発生するのは、あくまでも源泉徴収額が実際の所得税額を上回った場合です。
多くの従業員が当てはまりますが、反対に源泉徴収額よりも実際の所得税額が大きい場合は、対象の従業員から不足分を追加で徴収する必要があります。
たとえば、以下のようなケースでは追加徴収が発生する可能性があります。
- 年の途中で従業員の扶養から抜ける家族がいた
- 年の途中で収入が大きく変わった
- 賞与の金額が毎月の給与の合計金額よりも多かった

年末調整の還付金の計算に影響する控除
そもそも年末調整で還付金が発生するのは、毎月の給与に各種「所得控除」が適用されているためです。
所得控除とは、所得から一定額を差し引く制度です。所得税は所得に基づいて計算されるため、所得から一定額が差し引かれると、当然ながら所得税額も低くなります。
たとえば、以下の控除項目があります。
| 控除項目 | 詳細 |
|---|---|
| 給与所得控除 | 給与収入の金額に応じて適用される控除 |
| 扶養控除 | 従業員に所得税法上の扶養親族がいる場合に適用される控除 |
| 配偶者控除 | 従業員に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される控除。 |
| 保険料等控除 | 健康保険・厚生年金保険などの社会保険料や、生命保険・地震保険・個人年金保険などの各種保険料の支払い額に応じた控除。 |
| 住宅借入金等特別控除 | 従業員が住宅ローンを組み、住宅の購入または増改築工事をした場合に適用される控除。 |
| ひとり親控除 | 従業員がシングルマザーまたはシングルファザーの場合に適用される控除。 |
| 寡婦(寡夫)控除 | ひとり親控除に該当せず、配偶者との離婚または死別後に婚姻していない、一定の要件を満たす人に適用される控除。 |
| 特定親族特別控除 | 令和7年から新設。納税者と生計を同一にする配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下である場合に適用される控除。 |
参照:『No.1410 給与所得控除』『No.1180 扶養控除』『No.1191 配偶者控除』『No.1171 ひとり親控除』『No.1170 寡婦控除』国税庁

年末調整の還付金の計算に必要な書類
年末調整の還付金を計算するためには、所得控除の対象となることや所得控除の金額を確認できる以下の書類が必要です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 生命保険や地震保険などの控除証明書
- 扶養親族の国民年金や国民健康保険などの控除証明書(従業員が保険料を支払っている場合)
- 住宅ローンの年末残高を確認できる書類
また、従業員の当年1年間(1月〜12月)の給与がわかる資料も用意しましょう。
年末調整の還付金の計算手順
年末調整の還付金を計算する基本の手順を5つのステップに分けて解説します。
- 1年間の給与総額を合計
- 給与所得額を算出
- 課税所得金額を算出(2から所得控除を引く)
- 3に税率を掛けて所得税額を確定
- 還付金を算出(4と源泉徴収税額を比較)

1.1年間の給与総額を合計
まずは従業員の1年間の給与総額を計算しましょう。毎月の給与だけでなく、賞与も含めて計算します。12月分の給与は未払いの状態なので、概算の金額を用います。
2.給与所得額を算出
次に給与総額から給与所得控除を差し引いて、給与所得額を算出しましょう。
2020年分以降の給与所得控除は以下のとおりです。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 650,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 650,000円 |
| 1,800,001円から1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
3.課税所得金額を算出(2から所得控除を引く)
次に2で算出した給与所得額から、各種所得控除を差し引きます。
従業員からの申告書類や添付書類をチェックし、記載された情報に基づいて所得控除を適用しましょう。
4.3に税率を掛けて所得税額を確定
日本では累進課税制が採用されているため、課税所得金額が大きくなるほど、税率も高くなります。また所得税額からは課税所得額に応じた控除額を差し引くことが可能です。
課税所得額ごとの税率と控除額の関係をまとめると、以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

5.還付金を算出(4と源泉徴収税額を比較)
最後に、4で算出した所得税額と、源泉徴収税額の差額を計算しましょう。源泉徴収税額の方が多い場合は、差額分を従業員に支給します。
年末調整の還付金額の計算をシミュレーションすると?
ここからは具体例を挙げながら、年末調整の還付金の計算をシミュレーションしていきます。本記事では、以下の例をもとに考えてみましょう。
| 【シミュレーションに使う例】Aさん | |
|---|---|
| 年間給与額 | 4,400,000円 |
| 年間賞与額 | 1,100,000円 |
| 年間社会保険料 | 803,000円 |
| 年間源泉所得税額 | 137,500円 |
| 生命保険料控除 | 50,000円 |
| 住宅ローン控除額(住宅ローン残高3,000万円、控除率0.7%) | 210,000円 |
| 扶養配偶者 | 1名 |
まずAさんの1年間の給与総額は、4,400,000円+1,100,000円=5,500,000円です。給与所得控除の表に当てはめると、Aさんの給与所得は「3,600,001円から6,600,000円まで」に該当するため、給与所得控除は以下のとおりです。
| 所得控除 |
|---|
| 5,500,000円×20%+440,000円=1,540,000円 |
給与所得控除後の所得は以下のとおり計算できます。
| 給与所得控除後の所得 |
|---|
| 5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円 |
次に各種控除を適用します。Aさんに適用される控除は、以下のとおりです。
| Aさんに適用される控除 | |
|---|---|
| 基礎控除 | 630,000円 |
| 扶養控除(配偶者控除) | 380,000円 |
| 社会保険料控除 | 803,000円 |
| 生命保険料控除 | 50,000円 |
控除額を合計すると、「630,000円+380,000円+803,000円+50,000円=1,863,000円」となります。先ほど計算した給与所得控除後の所得から、各種控除の合計額を差し引きましょう。
| 課税所得金額 |
|---|
| 3,960,000円-1,863,000円=2,097,000円 |
以上のようにAさんの課税所得金額は2,097,000円と計算できました。
ここからはAさんの所得税額を計算していきます。
課税所得金額が3,299,000円までの場合、所得税率は10%、控除額は97,500円です。Aさんの所得税額は以下のとおりです。
| 所得税額 |
|---|
| 2,097,000円×10%-97,500円=112,200円 |
次に住宅ローン控除を適用します。Aさんの所得税額から住宅ローン控除額を差し引くと、以下のとおりです。
| 住宅ローン控除後の所得税額 |
|---|
| 112,200円-210,000円=0円 |
控除額が所得税額を超えるため、税額は0円になります。
最後に、先ほど計算した所得税額と、源泉徴収税額の差額を計算しましょう。
Aさんの給与に対する年間源泉所得税額は137,500円でした。実際の所得税額は0円なので「本来の所得税額<源泉徴収税額」となり、還付金が発生します。還付金の金額は以下のとおりです。
| 還付金額 |
|---|
| 137,500円-0円=137,500円 |
年末調整の還付金額をエクセルで計算する方法
年末調整の還付金額をエクセルで計算したい場合は、国税庁が提供している『年末調整計算シート』を用いると便利です。
ただしエクセルでの管理は手入力が必要なため手間がかかり、入力ミスによる計算間違えが起こる可能性もあります。年末調整手続きの効率を高めるなら、年末調整システムの活用も視野に入れましょう。

年末調整の還付金の平均は計算できる?
還付金の平均額は公表されていませんが、国税庁が公表している「源泉所得税および復興特別所得税の還付金の合計」と「年末調整を受けた給与所得者の人数」の数値を用いて、おおよその金額を推定できます。
源泉所得税および復興特別所得税の還付金(約2兆5,429億円)を、年末調整を行った1年を通じて勤務した給与所得者と年末調整を行った1年未満勤続者の合計人数(約5,265万人)で割り算すると、還付金の平均額は約48,298円となります。
参照:『第148回 国税庁統計年報 令和4年度版』国税庁
参照: 『令和4年分 民間給与実態統計調査』国税庁
年末調整の還付金が戻る時期
年末調整の結果、還付金が発生した場合は、12月の給与とあわせて支給するのが一般的です。
ただし、明確な決まりがあるわけではないため、1月の給与とともに支給したり、給与とは別に支給したりする会社もあります。
年末調整の還付金の計算をラクにするには?
従業員の年間の所得税額を計算した結果、「本来の所得税額<源泉徴収税額」となった場合は還付金が発生します。必要な情報や基本的な計算手順を理解していれば、還付金の具体的な金額をシミュレーションすることが可能です。
還付金を計算するためには、従業員の給与や控除額を正しく把握する必要があります。アナログ管理や手入力・手計算では人的ミスが発生しやすいため、年末調整システムの導入を検討をおすすめします。
年末調整を効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、年末調整のペーパーレス化を実現するクラウドシステムです。入社手続きやマイナンバー管理も含め、多岐にわたる労務処理の効率化を支援いたします。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |


