休憩中の外出禁止ルールは違法?自由利用の原則と制限が認められるケースを紹介
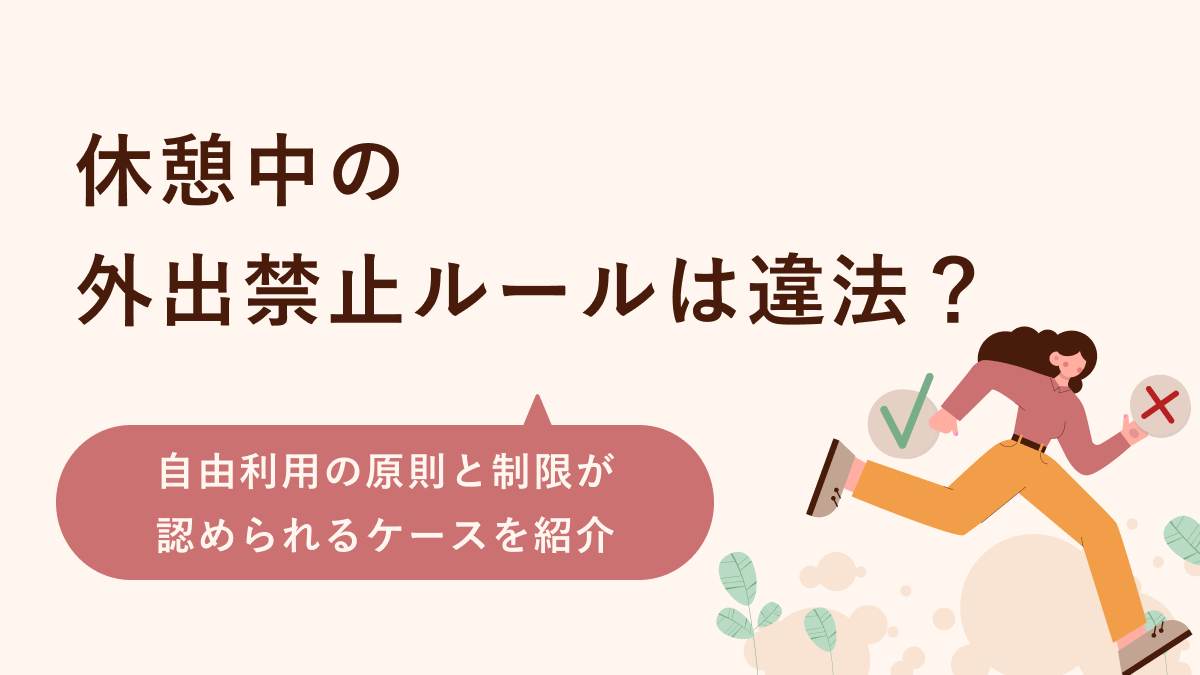
「休憩時間中は外出禁止」というルールを会社で設けていませんか。
労働基準法では、休憩時間は労働者が自由に利用できると定められており、原則として外出を禁止できません。ただし、すべての外出制限が違法なのではなく、業務の性質や職場環境によっては、一定の制限が認められることもあります。
本記事では、休憩時間の法的な原則と外出制限が許される条件や具体例、制度を運用するうえでの注意点を解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
休憩時間を外出禁止にするのは違法
会社によっては「休憩中は外出禁止」といったルールが暗黙の了解になっている職場もあるかもしれません。しかし、休憩中の外出禁止ルールは、労働基準法における「休憩の自由利用の原則」に違反する可能性があります。
同法第34条3項には「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と明確に規定されているためです。
そもそも休憩時間は、従業員が労働から完全に解放され、自由に過ごせる時間として保障された、大切な権利です。ただ作業を中断するだけの時間ではありません。
休憩中の過ごし方は本人に委ねられ、基本的に企業が干渉できないのです。そのため外出を「一律に」禁止することは原則として認められていません。
ただし企業側には、職場の規律を維持したいという意図もあるでしょう。そこで例外的に「一定の条件下」で外出に制限を設けることも可能とされています。
休憩中の外出を許可制とするのは可能
休憩時間中の外出を許可制にすることは、条件によっては違法にならない場合もあります。
行政解釈によれば「事業場内で自由に休息できる環境があれば、外出について所属長の許可を求めることは必ずしも違法というわけではない」とされているためです。
参照:『労働基準法関係通達』
重要なのは「事業場内で自由に休息できる」という条件です。会社内に快適な休憩室や食堂があり、外出しなくても十分にリフレッシュできる環境を整えていることが前提となります。
とはいえ実務上、外出を不許可にするのは難しいのではないでしょうか。現実的な対応としては、「許可制」ではなく「届出制」にとどめるのが望ましいとされています。休憩の届出制なら、会社は従業員の居場所を把握できる一方で、個人の自由も尊重されるでしょう。
休憩時間の届出制を導入する場合は、就業規則への明記が必要です。たとえば「社員は休憩時間中に事業場から外出する場合は、事前に所属長に届け出て承認を得ること」と規定します。
ただし「承認」は形式的な手続きにとどまり、合理的な理由がない限り、不承認にはできません。
休憩中に業務を与えて外出させないのは違法
休憩時間中に業務を与え、外出できない状態にしてしまうことは、労働基準法違反です。
休憩とは、労働から完全に解放された時間でなければならないため、以下のような状況は「休憩時間」とは認められません。
- お店に従業員が1人しかいなくて、休憩中でもお客さんが来たら対応しなければならない
- 休憩中でも電話対応を求められたり、レジが混んできたら応援に呼ばれたりする
以上のような状況では、本当の意味で休憩は取れていませんよね。たとえ形式上、休憩とされていても、実態は手待ち時間とみなされます。
手待ち時間とは、いつでも業務に対応できる状態で待機している時間のことです。手待ち時間は労働時間とみなされ、本来なら賃金が発生します。
つまり、休憩中に業務を課したり、外出できない状態にしたりすることは、「休憩」として成立していないということです。企業側は、完全な休憩が取れる環境を整えなければなりません。
休憩時間の3原則
労働基準法では、休憩時間に関して以下の「3つの原則」が定められています。いずれも労働者の健康と権利を守るための重要な考え方です。
- 途中付与の原則:休憩は労働時間の途中に与えなければならない
- 一斉付与の原則:原則として、同じ事業場の労働者には同じ時間に休憩を与えなければならない
- 自由利用の原則:休憩時間中は労働者が自由に時間を使えるようにしなければならない
一部例外が認められている原則もあるため、詳細を確認していきましょう。
途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中で与えなければならないという原則です。連続した仕事による心身の疲労を回復するという、休憩本来の目的に基づいています。
たとえば、8時間労働の場合には「4時間働く → 1時間休憩 → 残り4時間働く」といった取り方が典型例です。労働時間の途中に休憩を置くことで、従業員は無理なくリズムを整えながら働けます。
一方で、勤務開始直後や終了直前に休憩を取らせる運用はどうでしょうか。これでは途中での疲労回復にならず、休憩時間として認められません。
途中付与の原則は、例外が一切認められていないのが特徴です。どのような業種や職場であっても、必ず労働時間の途中に休憩を設ける必要があります。
なお、休憩時間を複数回に分割して与えることは可能です。例として1時間の休憩を30分ずつ2回に分けて与えられます。ただし、あまりに細かく分割するなど、実質的に休憩として機能しない運用は認められません。

一斉付与の原則
休憩時間は原則として、事業場にいる全従業員が一斉に取らなければなりません。一斉とは、派遣労働者も含め、同じ場所で働く人たち全員が同時に休憩に入ることを想定しています。
とはいえ一斉に休憩を取るのが難しい職場もあるでしょう。たとえば、次のような業種では例外が認められています。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融業(例:銀行)
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業(例:病院)
- 接客娯楽業(例:飲食店)
- 官公署などの公共サービスにかかわる業種
以上のような業種では、従業員が一斉に休憩をとってしまうと、業務が停止してしまうため、交替制など柔軟な対応が認められているのです。
上記の業種に該当しない場合でも、労使間で労使協定を締結すれば、一斉付与の原則を除外できます。労使協定には、「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「その労働者に対する休憩の与え方」を定める必要があります。
自由利用の原則
労働基準法では「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。自由とは、単に作業に従事しないだけの手待ち時間とは異なります。労働者が仕事から完全に解放され、自分の意思で好きなように過ごせる時間です。
休憩時間の自由利用の原則からすると、休憩中の行動に、企業が過剰に干渉することはできません。従業員は休憩時間中に会社の外に出て、食事や買い物、銀行での用事など、私的な活動が行える権利があります。「ちょっとコンビニに行ってきます」も「銀行で手続きをしてきます」も、基本的には自由です。
ただし、企業秩序の維持や業務への支障を防ぐために、最低限の制限が認められる可能性もあります。行政解釈により「事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を害さない限り差し支えない」とされているためです。
休憩制限のポイントは、ルールが「必要最小限」であり、かつ休憩の目的を損なわないことです。

休憩の自由利用の原則に違反した場合のペナルティ
休憩時間に関する労働基準法の規定に違反した場合、企業には厳しいペナルティが科されます。
労働基準法は労働者の健康と権利を守る「強行法規」です。当事者間で「自社ではこの運用で問題ないよね」と合意があっても、違反を免れることはできません。
休憩時間の自由利用の原則に違反した場合、具体的にどのような罰則が科され、企業にはどのような責任が生じるのでしょうか。
労働基準法第119条に基づいて、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。決して軽い処罰ではありません。
▼ほかにも労働基準法には休憩に関するさまざまなルールがあります。罰則や注意点を確認するなら以下の記事もご確認ください。
休憩中でも認められる行動制限【具体例】
休憩時間は原則として、労働者が自由に利用できる時間で、外出を制限することはできません。しかし、企業秩序の維持や業務への影響を考慮し、一定の制限が認められる場合があります。主な例は以下のとおりです。
- 制服・社員証を着用したままの外出
- 休憩場所の限定
- 飲酒・喫煙禁止
- 政治活動の禁止
- デスクでの仮眠や食事の禁止
- 社内備品の私的利用の制限
休憩時間の自由利用の原則と、企業の規律保持の必要性とのバランスをどう取るかが重要です。以下では企業が従業員を制限できる行動例と、それぞれにおける留意点を詳しく見ていきましょう。
制服・社員証を着用したままの外出
休憩中に、企業名やロゴが入った制服やネームプレートを着用したままの外出を禁止している企業は少なくありません。
制服姿で不適切な場所に出入りしたり、マナーに反する行動をとったりすると、会社全体の信用にかかわるおそれがあるためです。
ただし「制服のまま外出禁止」というルールを設ける場合、十分な着替え時間を確保しましょう。実質的に休憩時間が短くならないよう、配慮する必要があります。
企業のイメージを守りながら、労働者の休憩権も尊重するバランスが大切です。

休憩場所の限定
食品工場や研究施設など、特殊な作業環境では、休憩中の外出に制限をかけるケースもあります。
作業着の着脱に手間がかかるなど、休憩のたびに着替えるのが非効率であったり、衛生・安全管理上の理由から外部との接触を避ける必要があるためです。
外出を制限する場合は、休憩場所が「しっかり休める環境」であることが前提となります。休憩室が狭くて座る場所がない、騒音がうるさいといった環境では、十分にリフレッシュできません。
従業員が安心して休めるよう、外に出られない代わりに、快適な休憩室を用意しましょう。
飲酒・喫煙禁止
休憩時間中の飲酒や喫煙について制限を課すことは、安全管理責任や品質保持の観点、そして社会通念上から見ても、合理的な対応といえます。
飲酒は判断力の低下を招くため、全面的に禁止している企業が一般的です。飲酒運転の危険性はもちろんのこと、たとえ車を運転する業務でなくても、休憩後に酒気を帯びた状態で勤務に戻るのは問題です。就業規則に違反者への懲戒処分を定めることも、適切な対応といえるでしょう。
喫煙についても、対面の接客業や食品関連の業務では、においや顧客への印象を理由に制限する企業もあります。
ただし、全面禁止は喫煙者の権利を過度に制限する可能性があるため、適切な喫煙場所の設置など、代替措置を講じましょう。
政治活動の禁止
休憩中に選挙ビラの配布など、職場内で政治活動を禁止するのは、一般的に認められています。
最高裁判所の判例でも、「企業秩序を維持するために就業規則で政治活動を禁止するのは合理的」とされています。社内で政治的な対立や混乱を招く可能性があるからです。
また、休憩時間中の政治的な発言が、ほかの従業員の自由利用を妨げるおそれもあります。
政治活動の自由は憲法で保障された権利ですが、職場という共同体では、一定の制限が合理的と判断される場合もあるのです。みんなが気持ちよく働ける環境を目指しましょう。
デスクでの仮眠や食事の禁止
事務所内の共有スペースでは、来客対応や業務への支障を避けるため、休憩中のデスクでの仮眠や飲食を禁止できる可能性があります。
とくに、来客が多い営業所や受付を兼ねるスペースでは、企業イメージや清潔感の維持といった理由から、一定の制限には合理性があるといえるでしょう。
会社は休憩時間中であっても、事務所の設備や施設に対して管理権限を持っています。職場環境の維持という観点から利用方法にルールを設けることが可能です。
ただし、短時間の仮眠など、周囲に配慮したうえで業務に支障をきたさない範囲であれば黙認している企業もあります。
一律に禁止することは、「休憩は労働者が自由に利用できる時間」とする労働基準法の趣旨に反するおそれもあるため、配慮が必要です。
休憩中の仮眠に制限をする場合は、代替となる仮眠室や休憩スペースを整備しましょう。
社内備品の私的利用の制限
業務用パソコンの私的利用は、休憩中であっても制限することが可能です。
私的な利用によってウイルス感染などのセキュリティリスクが高まり、会社のネットワーク全体に被害がおよぶ可能性があるからです。
また、従業員は勤務時間中に職務に専念する「職務専念義務」を負っています。休憩時間中であっても「勤務中」にあたるため、業務と無関係な行為は制限の対象とする場合もあります。
たとえば、休憩中に業務用パソコンで私的にインターネットを閲覧する行為は、情報漏えいやマルウェア感染のリスクがあります。会社の備品を私的に使用する行為についても、車両など高額な物品は、窃盗や横領とみなされる可能性も否定できません。
リスクを防ぐためにも、企業が休憩中の備品使用に一定の制限を設けるのは妥当な対応といえるでしょう。

休憩時間の過ごし方を制限する場合の注意点
休憩時間の自由利用の原則に、制限を設ける際は注意が必要です。手続きが不十分で、合理性に欠けると、法令違反に問われたり、労使間でトラブルが生じたりするリスクがあります。
ここでは、休憩時間の制限をルールとして運用するために、おさえておきたい2つのポイントを解説します。
- 就業規則に明記する
- 合理的な理由が求められる
就業規則に明記する
休憩時間の過ごし方に制限を設ける場合、内容を就業規則に明確に記載しなければなりません。就業規則は労働条件の基本を示す文書です。あいまいな運用や口頭指示では、トラブルの原因になります。
休憩制限に関して記載したい主な項目は以下のとおりです。
- 休憩時間の長さと取得タイミング
- 休憩時間中の外出に関するルール(届出制か許可制か)
- 休憩場所の指定がある場合はその内容
- 休憩時間中の禁止行為(飲酒など)
- 違反した場合の取扱い
休憩時間中の外出に一定の制限をする場合は、例として以下のように記載します。
| 社員は休憩時間中に事業場より外出しようとする場合は、事前に所属長に届け出て、承認を得なければならない |
労働者の権利を不当に制限するような表現は避け、必要性と合理性に基づいた内容にしましょう。また、承認は形式的なルールです。合理的な理由なく、不承認はできないと理解しておく必要があります。
また、就業規則に記載しただけでは不十分です。従業員への周知徹底も法的要件となります。以下のような方法で周知をはかりましょう。
- 事業場の見やすい場所への掲示
- 社内イントラネットへの掲載
- 書面またはPDFによる配布と説明
合理的な理由が求められる
休憩中の外出制限には、誰が見ても納得できる「合理的な理由」が必要です。「許可制が違法でないから」「念のため」他社もそうしているから」では、合理的とはいえません。
従業員に説明できない制限は、信頼を損ねるおそれがあります。合理的と判断される理由の例は以下のとおりです。
| 緊急時対応が求められる職種 | 医療従事者や消防士など、緊急事態に即時対応する必要がある業務では、休憩中の外出制限にも合理性があります。 |
| セキュリティ上の制限が必要な職場 | 機密情報を扱う部署や、入退場に厳しい管理が必要な施設では、安全確保を理由に制限が設けられることがあります。 |
| 作業効率を下げないための配慮 | 工場などで作業着の着脱を頻繁に行う必要がある場合、休憩のたびに外出させるのは非効率です。職場環境に応じた合理的判断といえます。 |
| 企業イメージの保護 | 従業員が制服を着たまま特定の場所へ出入りした結果、企業イメージを損なうおそれがある場合も、制限の根拠となります。 |
必要に応じて従業員と対話の場を設け、ルールの背景や目的を共有することも、トラブルを未然に防ぐポイントです。
まとめ
休憩時間中の外出を一律に禁止することは、労働基準法第34条に定められた「自由利用の原則」に反するおそれがあります。
ただし、事業場内に十分な休憩環境があり、業務上の合理的な理由がある場合は、外出に届出や許可を求めることも一定の条件で認められるでしょう。
実務では、不許可とする運用は避け、届け出制とするのが現実的です。制限を設ける際は、就業規則への明記と従業員への周知、そして「なぜ必要なのか」を説明できる合理性が不可欠です。
労働者の権利を守りつつ、職場秩序も保てるよう、実態に即したルールづくりを進めましょう。
休憩時間の管理も効率化|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、休憩時間の管理を含む、従業員の勤怠管理をシンプルにする勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 休憩時間や残業時間を正確に把握できていない
以上のような課題がある企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
