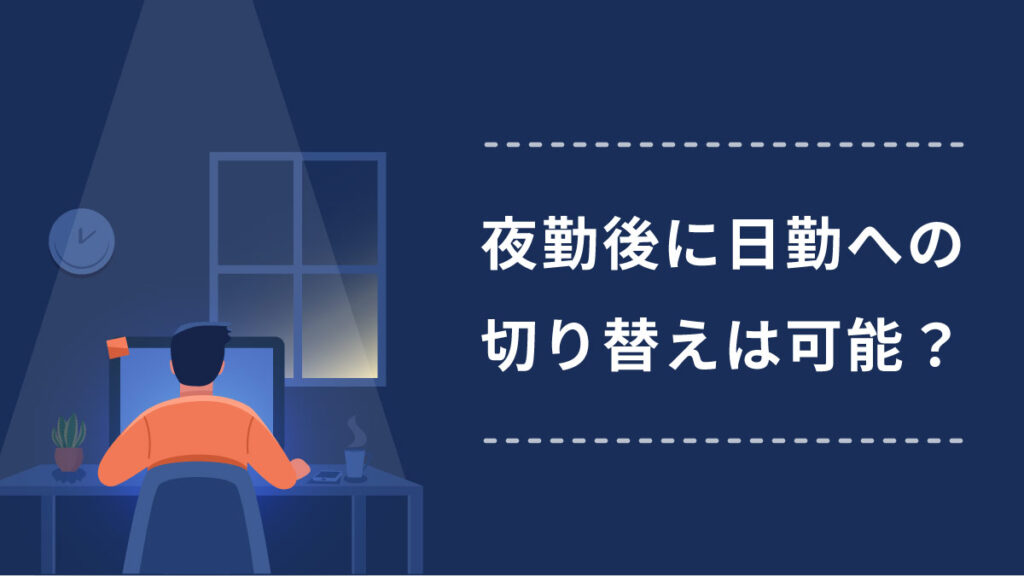連続勤務の上限は何日? 7連勤は違法? 労働基準法における罰則や例外、リスクを解説

企業によっては、繁忙期や少子高齢化にともなう人手不足などにより、従業員に連続勤務をさせてしまう状況もあるでしょう。しかし、労働基準法は無制限の連続勤務を許しているわけではありません。連続勤務は従業員の心身の健康に悪影響を及ぼす恐れがあるため、適切なペースで休日を与えるように努める必要があります。
本記事では、連続勤務の基本的なルールや例外、法律に違反した場合の罰則などについて解説します。上限日数を超えないための具体的な対策も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
 目次
目次
労働基準法上で連続勤務の上限は何日まで? 7連勤は違法?
労働基準法の規定を踏まえると、連続勤務の上限は原則として最大で12日です。つまり、7連勤は違法とは判断されません。
同法第35条によると、企業は従業員に対して必ず週に一度の休日を与えることが義務づけられています。 この週に一度の休日を「法定休日」といいます。
法定休日は決まった曜日である必要はありません。たとえば、日曜日を週の起算日とすると、週1回の休日を確保したうえで、以下のような12連勤も認められます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 2週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 |
このように、週の初めの日曜日に休み、その後月曜から2週目の金曜日まで勤務、2週目の土曜日に休みを設定すると、法律の範囲内で最大の連続勤務が可能です。
連続勤務日数が12日未満でも、週1回以上の休日を与えていなければ、労働基準法違反と判断されます。たとえば、以下のような例です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 |
| 2週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |

有給休暇は連続勤務日数に含まれる?
従業員が有給休暇を取得しても、連続勤務の日数はリセットされません。給与が支給される有給休暇は、法律上は勤務日に含まれるためです。
たとえば、以下の出勤例の場合でも、連続勤務の日数は12日と数えられます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 有給休暇 (出勤日) |
| 2週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 |
有給休暇の取得により、連続での「実労働」日数が途絶えたとしても、少なくとも週1回の休日を付与する必要があります。
連続勤務日数は月またぎでもカウントされる?
連続勤務の上限日数は、月末から翌月初めにかけて勤務が続いても、リセットされずに連続して数えられます。法的には、日数の数え方について月またぎに関する特別ルールが設けられていません。
そのため、企業は通常、週単位で連続勤務日数を管理し、適切に週1日以上の休日を設定することが求められます。
連続勤務上限にあたらない3つの例外
連続勤務日数の上限は原則として12日間です。しかし、以下のようなケースは例外とされています。
- 36協定の範囲内の場合
- 変形休日制の場合
- 管理監督者の場合
それぞれの例外における取り決めや注意点について、詳しく解説しましょう。
36協定の範囲内の場合
連続勤務の上限日数は、36(サブロク)協定の範囲内であれば、例外が認められます。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使間の取り決めです。法定労働時間を超える労働や、休日労働をさせるために労使間で合意したルールを指します。
36協定で取り決めれば「少なくとも週1回の休日を与える」「労働時間の上限は1日8時間/・週40時間まで」といったルールを超過した労働を命じても、違法性を問われることはありません。
ただし、36協定にも上限規制が設けられており、法定労働時間を超えた労働時間は「月45時間/年360時間」までと定められています。
度を越した連続勤務は、従業員の心身の健康に悪影響を及ぼしかねません。36協定の範囲内であっても、連続勤務日数は最大12日程度を目安とするのが望ましいでしょう。
変形休日制の場合
変形休日制を採用している職種や部署では、連続勤務の基本の上限日数について例外的な考え方が採用されています。
変形休日制とは、「4週間を通じて4日以上の休日」を設定する制度です。業務の特性上、労働基準法第35条で定める「少なくとも週1回以上の休日」を与えるのが難しい業種において適用が認められています。
変形休日制では、4週間(28日間)の最初と最後の2日ずつを休日とすると、最大24日間の連続勤務も可能です。
24日連続勤務の例
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 休日 | 休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 2週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 3週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
| 4週目 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 | 休日 |
また、月をまたいで、1か月目の第1週目月曜から木曜までを4連休、2か月目の第4週木曜から日曜を4連休にすることで、理論上は48連勤も可能です。ただし、48日は現実的な連勤日数ではなく、理論上可能だからといって採用してよい働き方とはいえないでしょう。
変形休日制を導入するためには、就業規則への明記が必要です。ただし、従業員の心身の健康を守ることを考えると、連続勤務日数はできるだけ短縮するのが望ましいといえます。
管理監督者の場合
「労働者」とは法的な立場が異なる管理監督者は、連続勤務日数が12日を超えても違法性はないとされています。労働基準法で定めている労働時間や休憩、休日に関するルールの適用が除外されているためです。
ただし、管理監督者は、肩書きではなく実態で判断されます。認められる条件は厳しく、「管理職」と名乗っているからといって、必ずしも「管理監督者」であるとは限りません。
厚生労働省の行政解釈では、管理監督者を「労働条件の決定や、そのほかの労務管理について経営者と一体的な立場にある者」としています。規制を免れる目的のみで設定された役職では「名ばかり管理職」と判断され、連続勤務の上限の例外は適用されないと考えてよいでしょう。
連続勤務日数の上限を超えたときの罰則
連続勤務日数の上限を超えて従業員を働かせることは、労働基準法第35条に違反します。
第35条に違反した場合の罰則については、同法の第119条に「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す」と定められています。
連続勤務日数の上限に関する違反行為が認められても、まずは労働基準監督署から改善の指導を受けるケースが一般的です。それでも改善が見られない企業に対しては、第119条の規定に沿って罰則が科せられる恐れがあります。
連続勤務日数の上限を超えるリスク
連続勤務の上限日数を超えるリスクは、労働基準監督署からの改善指導や、労働基準法違反による罰則だけではありません。従業員を連続で働かせすぎると、以下のようなリスクが発生する恐れがあります。
- 従業員の健康に悪影響を及ぼす
- 生産性が低下する
従業員の健康に悪影響を及ぼす
過度な連続勤務は、従業員の健康に悪影響を及ぼします。休日を与えられないことで疲労が蓄積され、肉体的・精神的な不調を引き起こすリスクが高まるでしょう。
高ストレスな状態が続くことで、最悪の場合、うつ病を発症する原因にもなりかねません。
生産性が低下する
連続勤務により休みなく働く日々が続くと、肉体や脳に疲労が蓄積され、生産性が低下してしまいます。効率が下がることで普段よりも作業に時間がかかり、さらに労働時間が長引くという悪循環に陥ってしまうこともあるでしょう。
集中力も欠如して、普段ではしないようなミスを起こしてしまう可能性もあります。作業の内容によっては労災事故を引き起こす恐れもあり、企業の対外的なイメージや社会的な信頼の低下にもつながりかねません。
連続勤務日数の上限を超えないための対策
連続勤務日数の上限超過を防止するには、以下の4つの対策が考えられます。
- 人材不足を解消する
- 勤務日数を正確に把握する
- 勤務間インターバルを導入する
- 勤怠管理システムを導入する
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
人材不足を解消する
過度な連続勤務を防止するためには、人材不足の解消に向けた対策を打つことが大切です。人的リソースが不足すると、従業員1人あたりの業務量が増え、十分な休日を与えられなくなります。
従業員の連続勤務が続いている状況であれば、新たな人材の採用を含めた人員体制の見直しをはかるとよいでしょう。また、業務フローを見直し、人材が不足している部分を把握することも重要です。
勤務間インターバルを導入する
過度な連続勤務の防止策の一つとして、勤務間インターバル制度の導入も挙げられます。
勤務間インターバルとは、勤務終了後、翌日の勤務開始までに一定以上の休息時間を設ける制度です。従業員の生活時間や睡眠時間を確保する目的で運用されています。
勤務間インターバル制度の導入は、2019年より企業の努力義務とされました。
インターバルを確保する仕組みは企業によりさまざまです。たとえば以下のような方法が考えられるでしょう。
- 一定時刻以降の残業と、翌日の始業以前の勤務を禁止する
- 終業時間が遅くなったときは、翌日の始業時間を通常よりも繰り下げる
あくまでも努力義務ですが、勤務間インターバル制度の導入は、過度な連続勤務の防止につながります。従業員の健康やワークライフバランスを守るために、検討してみてもよいでしょう。
参照:『勤務間インターバル制度とは』働き方・休み方改善ポータルサイト
勤務日数を正確に把握する
連続勤務を防止する対策として、従業員の勤務日数を正確に把握できる体制を整備する必要があります。勤務日数の管理がいい加減になると、意図せず連続勤務日数の上限を超過してしまうことも考えられます。
企業と従業員が互いに、勤務日数のルールについて共通の認識を持っておくことも重要です。まずは本人に自身の勤務日数を正しく把握してもらうことが、働きすぎの防止につながるでしょう。
勤怠管理システムを導入する
勤務日数の管理を徹底するために、勤怠管理システムの導入もおすすめです。従業員一人ひとりの勤怠情報をより正確に把握できるとともに、長時間労働の是正や過度な連続勤務の防止につながります。
勤怠管理システムの中には、法律で定められた労働時間や連続勤務日数の上限を超過しそうな場合に、警告アラートを設定できるサービスもあります。勤怠情報を手作業で管理している企業では、担当者の負担が軽減できるでしょう。

過度な連続勤務を避け、従業員の健康を保護
労働基準法第35条の規定により、原則として連続勤務日数の上限は12日間までと解釈できます。同規定に基づいて、企業は従業員に、少なくとも週1日以上の休日を与えなければなりません。
注意したいのは有給休暇の扱いです。有休は給与が発生する休日なので、勤務日として扱い、連続勤務のカウントに含まれます。
連続勤務日数の上限を超過して従業員を働かせた企業は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
たとえ罰則を免れたとしても、過度な連続勤務は従業員の心身の健康を害し、労働生産性の低下や労災事故の発生も招きかねません。
本記事で紹介した対策を参考に、過度な連続勤務を防ぐ仕組みを整えましょう。
勤務日数を正しく把握するなら|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤務日数の管理を自動化する勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
というお悩みを持つ企業を支援しております。アラート機能により、不注意による違反の見落としを防ぐこともできます。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |