管理職の残業時間に規制はある? 100時間を超えられる? 深夜の扱いや管理監督者との違いも解説
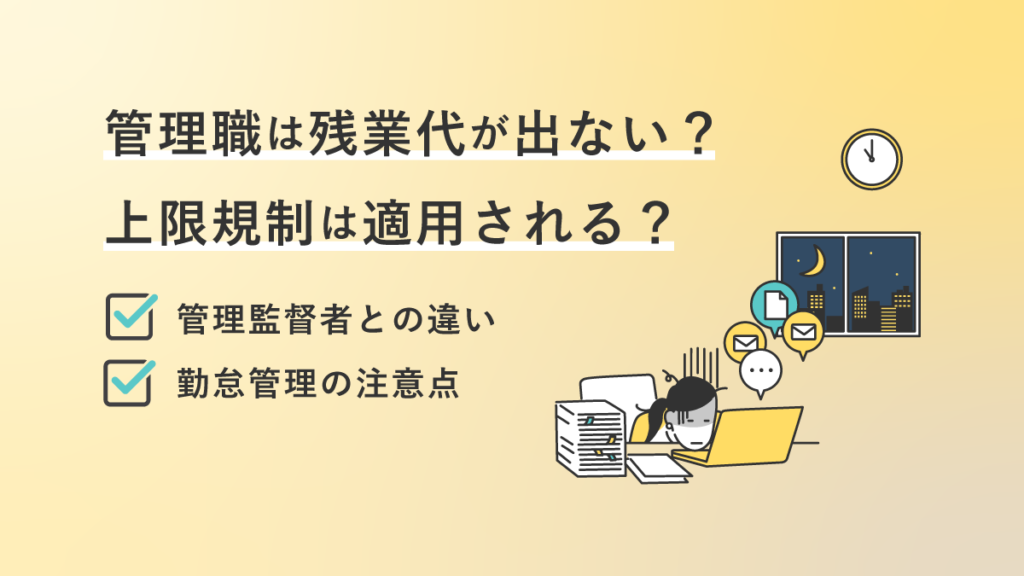
一般的に管理職は残業時の割増賃金の対象になりません。ただし一定の役職以上を指す「管理職」というだけで無制限に残業をさせてもよいわけではありません。
たとえば「管理職の残業は無制限」「100時間を超えても問題ない」と思っていませんか。
本記事では、労働基準法における管理職の残業規制を解説し、管理者と一般的な管理職の違いについても整理します。経営層や人事担当者はもちろん、管理職自身もぜひ参考にしてください。
▼残業管理の基本を確認したい方は以下の記事もご確認ください。
残業管理の方法とは【誰の仕事?】目的・必要性と課題、エクセルを活用した法も簡単に解説

 目次[表示]
目次[表示]
管理監督者は残業の上限規制が適用されない
一般的に管理職は、労働時間や残業に関する規制が適用されないと考えられています。そのため「管理職が残業しても割増手当は支払われない」と考える人もいるでしょう。
管理職が残業規制から外れるのは労働基準法で定められた「管理監督者」に該当する場合のみです。役職名が「管理職」でも、管理監督者に該当しなければ、法律で定められた残業時間の上限規制が適用されます。
「管理職」といっても無条件で規制の対象外になるわけではなく、管理監督者に該当するかどうかで対応が異なります。違いを理解せずに「管理職だから残業は無制限」と認識してしまうと、企業にとってもリスクを負うことになるため注意しましょう。

時間外労働の上限規制とは
労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、週40時間と規定しています。企業が従業員に法定労働時間を超える時間外労働をさせる場合、36協定を締結したうえで、割増賃金を支払う義務があります。時間外労働(残業)にも上限規制があり、原則として「月45時間、年360時間まで」が限度です。
ただし、臨時的・特別な事情により、労使の合意があれば、「36協定の特別条項」を結ぶことで、基本の上限を超えることが可能です。
36協定の特別条項を締結していても、さらに上限があり、以下のとおり決められています。
- 時間外労働が年720時間以内である
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満である
- 時間外労働と休⽇労働の合計について「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が、すべて1か⽉当たり80時間以内である
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回以内
上限規制に違反した場合、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。時間外労働(残業)には細かなルールがあり、企業は適切に労働時間を管理することが重要です。
▼上限規制について詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
「管理監督者」と「管理職」の違い
「管理職」と一言でいっても、労働基準法で定める「管理監督者」と、企業内での役職としての「管理職」には違いがあります。管理監督者は、経営層に近い立場で重要な職務を担い、意思決定や労務管理にも関与して働く存在です。また、労働基準法の保護規制(残業・休日労働・休憩の規制)を受けるかどうかという点も異なります。
| 管理監督者 | 一般的な管理職 | |
|---|---|---|
| 残業規制 | なし(労働基準法適用除外) | あり(労働基準法適用) |
| 残業代 | なし | 時間外労働に対してあり |
| 労働時間の裁量 | 自由 | 会社の指示にしたがっている |
| 職務・権限 | 経営層に近い、重要な意思決定権を持つ | 一定の管理能力が認められ責任を負う |
| 待遇 | 高め | 役職手当などがつく場合も。一般労働者より高め |
参照:『しっかりマスター労働基準法ー管理監督者編ー』厚生労働省
以下でそれぞれの定義を確認し、違いを整理していきましょう。
労働基準法における「管理監督者」
管理監督者とは、労働基準法で「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」と定義されています。
具体的には、以下のような経営者層に近い権限を持ち、みずから就業時間を決めて勤務する従業員です。
| 判断項目 | 詳細 | 例 |
|---|---|---|
| 職務内容 | 経営に関する重要な職務を担っている | 経営判断や人事権を持つ |
| 責任と権限 | 経営者に近い責任と権限を持っている | ・部門の最終意思決定権を持つ ・重要な判断を下す |
| 勤務形態(働き方) | 自分の裁量で働き方を決められる | ・出退勤が自由 ・勤務時間を指示されない ・休日でも対応を求められる |
| 賃金などの待遇 | 給与や賞与、報酬体系においてふさわしい待遇を受ける | 一般の労働者と比べて明らかに優遇 |
以上の4つを満たさないと、「管理監督者」として認められないでしょう。管理監督者に該当する場合、残業時間の上限は適用されず、残業代も支給されません。
参照:『労働基準法第41条』e-Gov法令検索
参照:『労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために』厚生労働省
一般的に「管理職」と呼ばれる存在
一般的に広く使われる管理職とは、企業のなかで一定以上の役職を指す言葉です。例として係長・課長が挙げられます。業務上の管理責任を持つものの、経営者に近い権限と裁量があるとはいえず、労働基準法上の「管理監督者」には該当しないケースも少なくありません。
役職名が「管理職」でも、「管理監督者」の条件に当てはまらなければ、残業代は支払われます。
管理監督者は役職名ではなく実態に応じて判断
管理監督者かどうかは、実態に応じて総合的に判断されます。
企業のなかで、管理監督者の要件をすべて満たした状態で働いている場合は、管理監督者とみなされます。反対に、管理監督者の要件を満たしていない場合は管理監督者として認められません。
たとえば、管理職に就く人が、業務に関する決定権や判断権がなく、さらに上司に確認しなければならないような場合は、管理監督者とはいえません。

管理職に残業代が出るケースと出ないケース
管理職に残業代が出るケースと出ないケースについて解説します。
名前だけの管理職は残業代が支給される
残業代が支給されるのは、労働基準法における管理監督者の要件を満たさないものの、「管理職」と呼ばれている人です。会社での呼び方ではなく、所定労働時間や就業時間にしたがって働いているなど実態で判断されます。
「管理職」と呼ばれるすべての人が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するわけではありません。 会社が「管理職」としている場合でも、労働基準法で定めた管理監督者の条件を満たしていない場合は、通常の労働者と同じ扱いになります。
管理監督者には残業代が支給されない
管理職と呼ばれる人のなかで、残業代が支給されないのは「管理監督者」に該当する人です。 管理者は、経営層に近い立場で重要な職務を担うため、労働時間の制限を受けず、必要に応じて長時間労働もあります。 法律上、時間外労働(残業)という概念が適用されず、残業代も支払われません。その代わり職務や責任の重さを考慮して、一般の労働者とは明らかによい待遇差を受けているのです。
▼残業代について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
管理職の残業が100時間を超えたらどうなる?
管理職(管理監督者)には労働時間の制限がないため、仮に月100時間の残業をしても、理論上は問題になりません。しかし、長時間労働は過重労働のリスクを高めます。時間外労働の上限規制を受けられないため、過労死ラインに達するような働き方が見過ごされてしまう傾向にあります。
2019年4月以降、企業には管理監督者の勤労怠管理が義務化されました。管理監督の労働時間を正しく把握し、長時間労働による健康被害を防ぐためです。
企業は管理監督者の労働時間を正しく記録し、過重労働を防ぐ対応が必要になります。
参照:『客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました』出雲労働基準監督署
80時間を超えた場合はどうなる?
100時間の一歩手前である80時間超の残業時間も、健康リスクが高まる重要な基準として設定されています。
管理職も含め、残業時間が月80時間を超えた従業員には、安全配慮義務の観点から、産業医による面接指導を実施しなければなりません。
明らかに長時間労働が続いている従業員に対しては、業務負担の調整や労働時間の見直しなど、具体的な改善策を検討しましょう。
参照:『長時間労働者への医師による面接指導制度について』厚生労働省

管理職でも労働時間は把握しなければならない
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働基準法や労働安全衛生法が改正されました。以前までは「把握するのが望ましい」程度だった管理職(管理監督者)の労働時間に対する勤怠管理が、義務化されたのです。
また、働き方改革の推進により、一般従業員の時間外労働が制限されたことで、管理監督者が部下の業務をカバーし、長時間労働を強いられるのではないかと懸念されています。
一般の従業員や管理監督者ではない管理職の残業時間が月100時間を超えると、原則として違法です。代表者や管理者に対して6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、法人に対して30万円以下の罰金が科される可能性があります。
管理監督者は規制の対象外ですが、100時間を超えるような残業が続けば、健康障害のリスクが高まり、最悪の場合は過労死の可能性を引き上げます。
残業時間を正確に管理していないと、安全配慮義務違反を問われるため、管理監督者の働き方も適切に管理できるよう体制を見直しましょう。
参照:『労働安全衛生法』e-Gov法令検索
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
▼労働時間の管理方法に不安がある方は以下の資料もご活用ください。

管理職でも深夜手当や有給休暇は適用される
管理監督者の場合、労働時間や休日のルールは適用されませんが、一部対象になるルールもあります。管理監督者が対象になるルールについて紹介します。
管理監督者は深夜手当の支給対象
管理監督者であっても、労働基準法第37条により、22時から翌5時までの深夜勤務に対しては割増賃金が支給されます。深夜労働には25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
労働基準法では、通常の労働と深夜帯の労働を区別してルールを設けています。管理監督者が適用されない「労働時間、休憩及び休日に関する規定」に、深夜の労働に関する規定は盛り込まれておらず例外です。
万一、管理監督者が22時以降に働いているにもかかわらず、割増賃金が支給されていないと、法律違反として問題になるため注意が必要です。
管理監督者でも年次有給休暇の扱いは同じ
管理監督者は休日出勤の制限を受けませんが、年次有給休暇が一般従業員と同様に取得できます。取得の条件は以下のとおりです。
- 雇用されてから6か月以上経過
- 全労働日の8割以上の出勤率
▼有給休暇には細かな付与ルールがいくつかあります。ルールや付与タイミングを確認するには以下の資料をぜひご活用ください。

管理職の残業にかかわる注意点
管理職の残業には、企業側も管理職自身にも注意したいポイントがあります。 とくに「管理監督者」として扱われる場合、残業規制が適用されないため、働き方や企業のルール整備が重要です。
自己の裁量で働く場合は注意する
管理者は、労働時間のルールが適用されず、自分の裁量で働く時間を決められます。しかし、自由だからといって、遅い時間から出勤したり、遅刻早退を繰り返したりするような働き方は避けるべきです。
周囲との連携が取れない働き方が続くと、業務に支障をきたすだけでなく、信頼を損ねる原因にもなります。企業は、管理監督者が経営層と同様に重要な責任を担う立場であることを認識し、責任ある行動を求めましょう。
就業規則で管理監督者について規定する
管理者かどうかは、実際の業務内容や責任の範囲に基づいて判断されます。しかし、誰が(もしくは自分が)管理監督者に該当するか否かを正しく認識できていない企業もあるのではないでしょうか。
管理監督者の定義は、就業規則で明確にすることが重要です。規定により、役職者自身や周囲も管理監督の範囲を正しく理解できるようになります。残業代の支払いをめぐるトラブルを回避するためにも、企業はルールを整備し、組織内で周知徹底する必要があります。
名ばかり管理職の未払い残業代に注意する
本来は残業代の支払い対象となる労働者が、現状にそぐわないまま管理監督者として扱われることで、適正な残業代が支払われないケースが問題となっています。
実態が管理監督者でない人に、時間外労働に対する残業代が支払われていなかった場合、過去3年にさかのぼって未払い残業代を請求される可能性があります。
このような問題は、労務トラブルに発展し、裁判で争われた事例もあるため、注意しなければなりません。賃金が一般従業員より高いため、請求額も高額になる事例が多くあります。
参照:『労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために』厚生労働省
管理職の残業時間を適切に管理する方法
管理職を含めた、従業員の残業時間を適切に把握するための勤怠管理方法を紹介します。
- 自己申告してもらう
- タイムカードで管理する
- パソコンの使用記録を確認する
- 勤怠管理システムを導入する
自己申告してもらう
エクセルや出勤簿などを用いて、管理職みずから勤怠状況を申告してもらう方法です。エクセルファイルであらかじめ設定しておけば、労働時間や休憩時間を入力するだけで自動的に集計でき、コストをかけず勤怠管理を実施できます。
ただし、自己申告による勤怠管理は、客観的な労働管理の記録としては認められないため注意しましょう。
タイムカードで管理する
タイムカードによる勤怠管理は、比較的導入コストやランニングコストを抑えられる方法といえます。利用方法もシンプルで、誰でも悩まず使えるうえにメンテナンスが不要なため、管理も容易です。
ただし、基本的にタイムカードはオフィスに設置され、出社と退社のタイミングを記録するものです。リモートワークや出張などで社外に従業員がいる場合、正確な労働時間の把握が難しいでしょう。
打刻漏れや不正打刻のリスクも否定できず、管理体制の整備が必要です。さらに、手動での集計作業が発生し、手間と時間がかかることがデメリットといえます。
パソコンの使用記録を確認する
パソコンの使用記録を活用して勤怠管理をする方法もあります。とくに、パソコンでの作業が主な職種には、実際の労働時間を正確に把握できるメリットがあります。
パソコンのログに基づく勤怠管理は、客観的な記録に基づくため、正確性が高く、打刻漏れの心配がありません。不正申告の防止にも効果が期待できます。
ただし、休憩時間の把握が難しい点に注意が必要です。また、外回りの多い職種や複数の拠点で事業を展開する企業にとっては、リアルタイムでの勤怠管理が困難なことがデメリットです。
勤怠管理システムを導入する
管理職を含め従業員の労働時間を正確に管理したい場合は、勤怠管理システムの活用をおすすめします。
一般的な勤怠管理システムに備わっている機能は以下のとおりです。
- 出退勤時間の打刻
- 労働時間の集計
- 残業申請
- 休暇申請
- 残業時間の把握
- 給与計算との連携など
勤怠管理システムを活用することで、管理職の労働時間をリアルタイムで正確に把握できます。管理監督者や従業員の長時間労働を防ぐためにも管理体制の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

多くの勤怠管理システムには、生体認証や特定の端末でしか打刻できない機能が搭載されているため、不正打刻や不正申請の防止にも役立ちます。また、給与計算システムなどほかのシステムと連携できるサービスもあり、効率的な運用が可能です。
自社に必要な機能と予算を総合的に考慮し、最適なシステムを選びましょう。

まとめ
管理職(管理監督者)には基本的に「残業」という概念がありません。労働基準法において、自分の裁量で働けることが規定されているからです。
一般的に「管理職」という言葉は一定以上の役割職を指す言葉として使われますが、労働基準法でいう管理職は「管理監督者」のことを指します。
管理監督者かどうかは、実際の勤務時間に基づき、以下の基準を満たしているかで判断されます。
- 経営にかかわる重要な職務を担い
- 決定権を持つ
- 自由な勤務形態
- 管理監督者としてふさわしい待遇
基準を満たしていないのに残業代が支払われていない場合、従業員とのトラブルにつながります。過去の未払い分を請求されるケースもあるため、企業は以下の点に注意が必要です。
- 管理者の定義を明確にする
- 管理者に該当しない従業員には適正な残業代を支払う
適切な労務管理を行うことで、トラブルを回避しましょう。
労働時間の管理を適正化|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、管理監督者を含む従業員の労働時間管理の適正化を支援するサービスです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
さまざまな課題がある企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
